| 浜岡原発5号機の復水器配管損傷の原因は?(2011年5月21日) |
| 福島第一原発の方はあまり大きな動きが無いのですが、 海洋への放射性物質流出のうち、 半減期の短い放射性ヨウ素は、沖合いにおいては検出されなくなりつつあります。 これは、だいぶヨウ素が安定物質に変わったからだと思います。 放射性セシウムの方はまだ検出されていますが、 量は少しずつ減っています。 セシウムの半減期は長いのですが、半減期まで全く安定物質に変わらないわけではないので、 徐々にこちらも安定物質に向かっているのだと思います。 〜〜〜〜〜 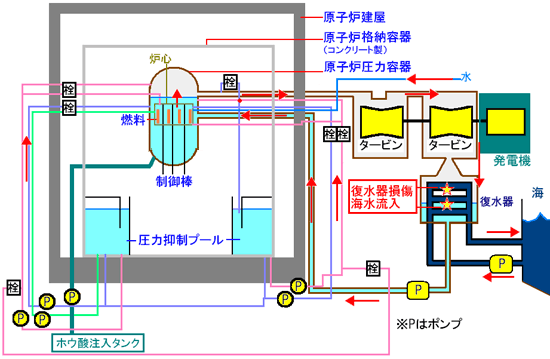 ・・・で、今回は福島第一原発ではなく、浜岡原発5号機の方です。 浜岡原発5号機の停止時に大量の海水が原子炉配管に流れ込んだ問題は、 私の予想通り復水器の損傷が原因でした。 図では復水器の横の配管を簡略化して3本で描いていますが、 実際この横の配管は沢山あり、そのうち20本程度が損傷したようです。 5号機は2005年に出来たばかりの原子炉で、 他の1〜4号機で使っているあの悪名高いゼネラルエレクトリック社規格のマークI型ではなく、 格納容器自体をコンクリート製にして、 中の圧力容器も頑丈にした最新の沸騰水型軽水炉です。 その最新の5号機の復水器配管が老朽化しているとは考えにくいのですが、 停止以前から金属疲労を起こしていた可能性があります。 特に近くに落ちていた、 配管に溶接されていた金属製のキャップは金属疲労が激しかったのだと思います。 その金属疲労が飽和点を超えて破壊してしまった原因が、原子炉稼働の停止だと思います。 原子炉炉心の燃料に制御棒を差し込み、中性子の飛散を抑えると、 急激に復水器の温度と蒸気の圧力が下がり、配管の金属が収縮して破壊されるのです。 中部電力の見立てでは、 金属性キャップが脱落してそれが配管に当たって損傷したかもしれないとのことです。 その場合、考えられるのが金属キャップの溶接不良です。 そうなると、別の所でも溶接不良箇所もありえるので、早急な点検が必要だと思います。 |
| 先の見えない復興と原発事故収束(2011年5月19日) |
| 逐次この日記を書いてますが、 政府菅内閣の震災復興、原発事故対応の酷さには怒りを通り越して絶望感さえ感じます。 18日、菅首相は「電力会社の地域独占解消と発送電の分離」を提案しました。 言葉が悪いですが、本当に「馬鹿クソ首相」と罵声を浴びせたくなります。 そんなことは震災復興、原発事故収束が済んだ後で考えれば良いのであって、 今、菅内閣がすべきことは違うだろうと言いたいです。 思いつきでなんでもポンポン発言するのはやめていただきたいと思います。 こんな政府菅内閣の状態じゃ、 震災復興も原発事故収束も先が見えずに不安になるばかりです。 震災復興に関しても、識者と同調して、エコタウン、首都機能移転、三陸の国立公園化、 大規模区画整理による近未来都市造成、高速道路や高速鉄道の充実等々、 本当に一部の人間の利権渦巻く夢みたいな妄想ばかりで、現実的な復興策は殆ど皆無です。 その妄想を無理に実現しようとすると余計な国費が費やされ、 それは何れ、「消費税増税」と言う形で国民に負担が跳ね返ってきます。 つまり、何にせよ今の内閣では消費税増税が国民のためにならないと言う事です。 特に被災地の方は増税やTPP参加で負担を強いられた挙句、 復興もなかなか進まないと言う、二重、三重の苦しみを味わう事になります。 被災地の方が望んでいるのはエコタウンや首都機能移転とかではなく、 元通りの平穏な生活なのです。 菅首相が本気で支持率回復を考えているのなら、 役に立たない閣僚やブレーンを切り捨て、被災者の意見を取り入れて復興策を考える事です。 (少なくとも、与謝野氏や内閣府経済社会総合研究所所長は 即時に更迭してもらいたいものです。 彼らは国民を不幸にすることしか考えていない我利我利亡者です。) さすがに菅内閣の足元と政官財報学の癒着体制を見透かす有権者も増えつつあり、 復興のための消費税増税に反対する方の率は確実に上がっています。 (しかも各新聞社の世論調査は消費税増税賛成の数値を10〜20%割り増しにしている。) メディアや財界が盛んに主張するTPP参加にも論理に矛盾があり、 読売新聞の例で言うと、「内向き(国内生産)から外向き(外国進出)へ」とか言いながら、 「TPP参加で国内産業の空洞化を阻止」と相対することを恥ずかしげも無く言っています。 日頃、論理が矛盾する事はよくありますが、 それは正論ではない事象をはぐらかすため、 余計な大義名分を付け加えて(方便)世論誘導をするからそうなるのです。 私は菅首相に批判的ですが、TPP参加先送りの判断に関しては正しいと思います。 今、TPPに参加すると間違いなく日本と言う国家は滅んでしまいます。 日本を大事に思うなら、 メディアや財界人は今まで緩い社会で育んだ、 「腐った考え」を捨て去った方が良いと思います。 |
| 福島第一原発2、3号機も同じ燃料全溶融か?(2011年5月17日) |
| 原子力安全委員会の推定発表によると、 やはり、2号機、3号機も「1号機と同じように炉心の燃料がほぼ溶融していると思われる。」 とのことです。 このことは東電も、保安院も、政府も、 事故後早い段階からある程度知っていたのですが、 あえて発表しなかったのだと思います。 (これは、水位上昇がしないこと、地下坑の高濃度汚染水、 INES事故レベルのいきなりの引き上げなど、 説明が不可解で辻褄があっていないことで容易に推定出来ます。) 国民にショックを与えないためとは言え、 事実隠しをすると、各専門家の対策案も間違ってしまいますし、 世界各国の日本への不信感を増長させてしまいます。 もう、済んでしまったことは元に戻せないので、今後は正確な発表をお願いしたいところです。 なお、現況は以下の通りです。 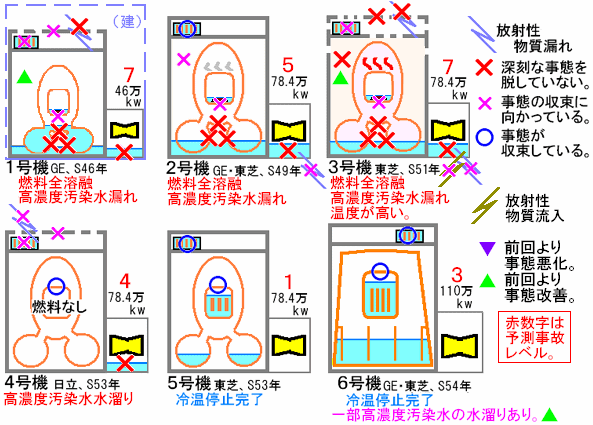 |
| 福島第一原発1号機の全燃料溶融(2011年5月16日) |
| 福島原発1号機の炉心燃料全溶融について、 東電及び保安院の正式な推定報告がありました。 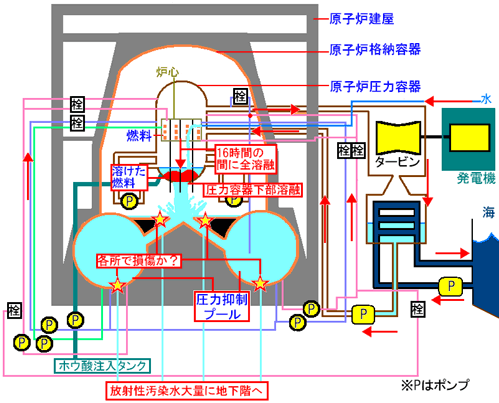 既に各メディアで報道されている通り、 地震から16時間以内に燃料がほぼ全部溶融し、 溶けた熱い燃料が格納容器下部や圧力容器を溶かして損傷させ、 そこから放射性物質の入った高濃度汚染水が地下階に流れたと言う事です。 しかし、私は最初から最悪な事態が予想されていたので、 初期に政府やメディアが盛んに言っていた「不安を煽る」ことを書いてきましたが、 まあ、「その通りになりました」ということで、 弊サイトのこのページを継続してご覧になられていた方は、 特に驚かれていないと思います。 逆に今まで注水しても全然水位が増えていなかった原因が特定出来たので、 はっきりした対策が取れると思います。 なお、今回は1号機に限っていますが、2号機も3号機も水位は増えてなく、 地下坑に大量の高濃度の放射性汚染水があるので、 1号機と同じ状況になっていると思います。 〜〜〜〜〜 炉心溶融のキーポイントになった時間は、地震発生後5時間前後だったようで、 そこまでの時間と、それから全溶融になるまでの時間が今後の責任問題になると思います。 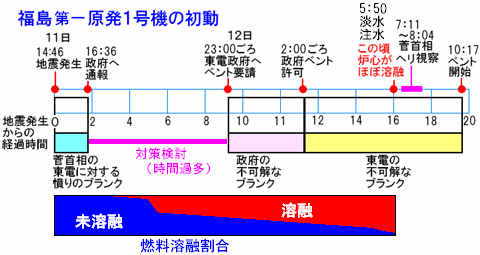 上の図は地震発生からベント開始までを時系列に並べた表ですが、 説明するまでもなく責任の所在ははっきりしています。 「ブランク」と書いた時間と、対策検討時間超過がそのまま人災部分になったわけです。 ただ、菅首相が東電幹部を恫喝したブランクは、 緊急事態の原因調査時間を差し引くと、僅かなブランクでここは致し方ないと思います。 問題は東電が政府にベント許可を要請するまでにかかった時間と、 政府がベントを容認するまでのブランクです。 ここだけで11時間要していて、ここまででほとんど炉心の燃料は溶融してしまいました。 対策検討は「不測の事態」とは言え、災害による原発対策マニュアルがあったわけで、 ここで8時間近く使うのは「慎重ゆえに事態を悪化させた」と言わざるを得ません。 そして、東電のベント許可要請から政府は会議を開き、許可の決定を出したわけですが、 そもそも「会議」と言うものを正式にやる必要があったのか疑問です。 緊急事態な訳だし、政府菅内閣は原発に詳しい訳ではないので(菅首相は詳しいらしい?)、 東電の要請に判子を押すだけで済んだ筈です。 そして、その許可からベント開始まで8時間以上かかっています。 この東電のブランクは表向きは「ベントの蓋が思うように開かなかった」 と言うことになっていますが、菅首相のヘリ視察が絡んでいたとみて間違いないと思います。 そんなことから人災部分の責任は東電と政府菅内閣にあると言えます。 ただ、問題は東電が責任を認めているのに対し、 政府菅内閣は東電に大部分の責任を押し付けていることです。 (最近一部責任を認めたが、菅首相のヘリ視察や対策遅れは言及されていない。) ここをはき違えて「東電悪い、菅首相は偉い。」 などの間違った評価をするととんでもないことになります。 なお、ちょこっと書いておきますが、浜岡原発5号機の停止の際、 原子炉に行く水に海水が混じっていたと言う事です。 これが大事にならなければ良いのですが・・・。復水器の損傷などが考えられるので、 楽観は禁物です。 |
| 両陛下と政官財報学の落差/1号機の炉心は?/発電の重要なポイント (2011年5月13日) |
| 天皇皇后両陛下はお体の調子が悪い中、 毎週のように被災地をご訪問されています。 被災地の方にとって、両陛下のご訪問は復興の励みになると思います。 一生懸命な両陛下のこの光景をみると、菅首相始め各閣僚、 腐敗臭さえする内閣府経済社会総合研究所所長、 その他政官財報学の無責任さ、情けなさには辟易します。 なんでこんな政官財報学癒着の社会構造になってしまったのか、 我々は考え直す必要があると思います。 そして、この社会構造がなかなか脱せない不景気の原因だと気付くべきです。 |
| 13日の各メディアに福島第一原発1号機の炉心が完全に溶融していて、 水位は燃料域よりかなり下だったと言うニュースが出ていました。 ・・・が、これについて特に東電も保安院も正式な発表は今現在ありません。 どうやらメディアの記者が保安院の言葉尻をとって拡大解釈したようで、 まだ憶測の域を脱していないようです。 しかし、東電も保安院も炉心溶融は想定済みで、 最悪、全部溶融して圧力容器底面に溜まってもあとは冷えるだけなので、 特にそれ自体でどうこうと言う事はないと思います。 ただ、その溶融した燃料によって圧力容器や格納容器が損傷している場合は、 放射性物質もれ拡大のおそれが出るので、そこのところを注意深く見守る必要があります。 なお、現在は下図の通りで、特に大きな変化はありません。 3号機の方は注水量を増やしたため、少しずつ温度が下がっている一方、 スクリーン(ポンプ室流入口前のゴミ取り金網) から地下坑を通って汚染水が逆流しているようです。 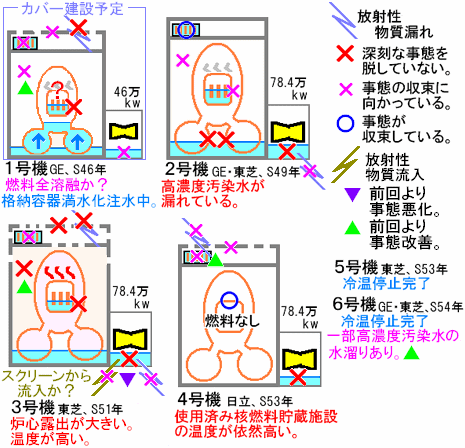 |
| さて、連日に渡って太陽光発電や風力発電の現実、 発電電気は蓄えられないことを書いてきました。 私は決して次世代クリーンエネルギーに反対しているわけでもないし、 原子力発電に賛成しているわけでもありません。 ただ、「次世代クリーンエネルギーではまだまだ原子力発電の穴埋めにはならない」 と言う現実を知っておく必要があるのと、 抜本的に電力不足、エネルギー資源問題を短期的に考えるのには、 「政治家も我々国民も視点が間違っている」と言う事を言いたいのです。 何故、このことを強調するかと言うと、菅首相のエネルギー政策見直しや、 エコタウン計画には全く具体性がなく、 しかも何れもどれくらい時間がかかるのかわからないし、エコ効果も分からないからです。 今は兎に角復興優先であり、 そのためには電力不足を早急に解決しなければならないのです。 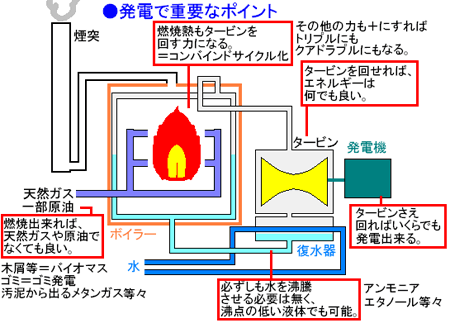 発電に関する誤解や無知が、間違ったエネルギー策の考えになってしまいます。 上の図は発電で重要なポイントとして火力発電を例に図示しています。 先ず、火力発電も原子力発電も水を沸騰させてその蒸気をタービンに当てて回転させ、 それと同軸上に繋がれた発電機が回転する事によって発電する仕組みとなっています。 火力と原子力の違いは水を沸騰させる熱の発生方法だけです。 また、水力はタービンがランナ(水車)、風力はタービンがブレード(風車)に変わっただけで、 それと同軸上に繋がった発電機を回して発電するところは火力や原子力と一緒です。 それから考えられるエネルギー策として、 先ず、タービンさえ回れば水を沸騰させる必要が無いと言うことです。 つまり、タービンを回すエネルギーは何でもよく、最悪人力で回しても良いのです。 また、液体を使うにしても、必ずしも水ではなく、もっと沸点の低い液体でも可能です。 沸点の低い液体ならそれだけ沸騰に要する熱エネルギーを減らすことが出来ます。 ただ、これらの液体は危険を伴うもの(爆発、発火したり毒性があったり)が多いのと、 水ほどどこにでもある液体でもないので、あまり使われてこなかったのですが、 原子力の危険性を考えればはるかに安全だと思います。 また、液体を沸騰するために燃焼させるものは、今主流の液化天然ガス(LNG)や、 前まで主流だった原油でなくても良く、燃焼さえすれば何でも良いのです。 例えばバイオマス発電の場合、木屑等を燃やし、その熱で水を沸騰させて発電しています。 バイオマス発電の場合、ダイオキシンなどの別の問題の対策が必要になりますが、 一つの考えとして有効になっています。 また、面白いものとして、ミドリムシを大量に培養させ、 それを燃やして発電する方法も考え出されています。 そして、一番実用化されていて、短期的な解決になるのは、 火力発電所のコンバインドサイクル化です。 燃焼空気と沸騰蒸気の両方の力でタービンを回すことにより、 エネルギー効率が上がります。エネルギー効率が上がれば同じ燃料の量でも、 発電出力をアップする事が出来ます。 東京電力は計画的にコンバインドサイクル化を進めていますが、 まだまだ一部の火力発電所の一部の炉に留まっているので、これは推進するべきです。 もっと言えば、復水器に流れる水の力でもタービン(ランナ)を回せば、 ダブルコンバインドがトリプルコンバインドにもなりえるわけで、 発想を転換すればもっとエネルギー効率を上げることが出来ます。 なお、発電機自体は老朽化しない限り無限大に発電出来ます。 これを知らなかったり、誤解している方が多く、 間違った省エネに走ってしまう原因となっています。 つまり、電気の消費自体を押さえる事が省エネでは無い(節電にはなるが)と言うことです。 (発電所やエネルギー方法が健全なら電気はどんどん使っても良いのです。) これを一人ひとり理解すれば、もっと有効なエネルギー策が出来るのではないかと思います。 |
| 発電電力は直接蓄えられないと言う現実(2011年5月13日) |
| よくテレビを見ていると、事情を知らないコメンテータなどが、 なんで発電電気を蓄えておく事が出来ないんだ!と怒りながらおっしゃる方がいます。 でも、本当に発電電力は直接蓄える事が出来ないのです。 意外と一般の方に知られていないのは、 「家庭で使われている交流電気はコンデンサに蓄えておく事が出来ない」ことです。 直流電気の場合、コンデンサに電気を流すとコンデンサの両面に電荷が貯まって、 コンデンサの充電限界(静電容量)まで電気を保存しておく事が出来ます。 しかし、交流電気の場合はコンデンサに電気を流して充電してもすぐ放電してしまい、 実質電気が流れているようになってしまうので、蓄えられないのです。 そのため、コンデンサに電気を蓄えるためには交流電気を直流電気にする必要があります。 (なお、充電式乾電池、充電式懐中電灯、デジカメバッテリー等は直流電気で、 充電器において交流電気を直流電気に変換しています。) 家庭用の些細な電気ならAC-DCアダプター(ただし、交流に戻せない) で対応出来るのですが、 発電所の電気となると、 コンデンサ以外に直流に変換する整流器かコンバータが必要になります。 (発電電気は交流電気のため) コンバータはGTOサイリスタかIGBTを沢山使用しているので、 導入するとそれだけコストがかかります。 結局、電気を貯めておくのに、 見かけ上、電気を水に変えて保存する揚水式発電など大掛かりなことになるのは、 交流電気が直接蓄えられないからです。 「じゃあ、最初から直流電気で発電すれば良いじゃないか?」 と思われる方がいらっしゃると思いますが、 直流は簡単に電圧を上げたり下げたりすることが出来ないのです。 直流電気を高圧で送電した場合、各変電所では電圧を下げるために変圧器ではなく、 沢山の抵抗か、GTOサイリスタやIGBTのチョッパ装置が必要になり、 これもコスト増になってしまいます。 (しかも、抵抗やチョッパ装置は著しい電力損失を伴います。 =コンデンサの蓄電メリットが相殺されてしまいます。 また、かといって、低圧で送電すると送電ロスが発生します。) つまり、直流送電は実用的ではなく、 使われているのは、一部の海峡送電線などの長距離送電線だけです。 なお、弊サイトの電線のページをご覧になられている方は、 「変電所にコンデンサがあるじゃないか!」とおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、 このコンデンサは電気を蓄えるためにあるのではなく、 電圧低下、電力損失を防ぐため(力率改善のため)にあるものです。 |