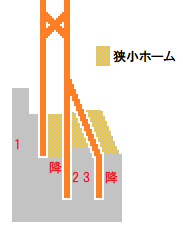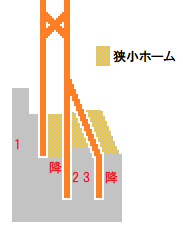|

古社寺を訪ねて・叡電叡山本線1
叡山電鉄は嵐電の項で書いた通り、
えちぜん鉄道とともに元々は京福電気鉄道の路線でした。
そのため、車両の規格は京福電気鉄道(嵐電)の嵐山本線等と同じで、
軌間1435ミリ、電圧600Vになっています。
(えちぜん鉄道の軌間は1067ミリです。)
叡電叡山本線は大正14年に京都電燈が開通させた路線で、
昭和2年に京都電燈子会社の鞍馬電気鉄道に経営を移した後、
昭和17年に京都電燈から分離独立して出来た、
京福電気鉄道に吸収合併されました。
しばらくは京福電気鉄道の路線として存在していたのですが、
昭和40年代後半から昭和50年代前半に京都市電が廃止され、
接続する鉄道路線が無くなると、乗客が激減しはじめ、
経営は瞬く間に苦しくなりました。
昭和60年に京福電気鉄道は経営再建のため、
子会社の叡山電鉄を設立し、
翌年に叡山本線と鞍馬線を叡山電鉄に移行させました。
平成元年に京阪電気鉄道鴨東線が出町柳駅まで開通すると、
利用客が再び増え始めました。
その頃から叡山電鉄は京福電気鉄道より京阪電気鉄道との結びつきが強くなり、
徐々に京福電気鉄道の持っていた叡山電鉄の株を京阪電気鉄道が取得しはじめ、
現在は京阪電気鉄道の完全子会社になっています。
叡山電鉄のうち、
出町柳駅~八瀬比叡山口駅間5.6㎞は叡山本線ですが、
出町柳駅~宝ヶ池駅間は鞍馬線の電車も乗り入れています。
01(E01)、出町柳(でまちやなぎ)Demachi-Yanagi

京阪電気鉄道の出町柳駅は地下にあるのですが、
叡山電鉄の出町柳駅は地上にあります。
京福電気鉄道(嵐電)の四条大宮駅と異なり、
京阪のホームとは地下通路で繋がっており、
雨の日に傘を差す必要はありません。
京都市電時代は最寄りの賀茂大橋電停が通り一つ分ズレた位置にあったため、
あまり便利ではありませんでした。
そのため、市電からの乗り換えは次の元田中駅の方が多かったようです。
なお、出町柳駅は、高野川、鴨川を挟んだ向かいにある「出町」と、
出町柳駅のある付近の地名、「柳元(柳の辻)」を合成して出来た合成駅名です。

ホームは4面3線で、3線とも乗降分離可能になっています。
そう書くとそこそこのターミナルな印象を受けるのですが、
狭い敷地に無理矢理そのような配線をしているため、
元田中駅寄りはホームがかなり狭いです。
狭いホームを乗車ホームにすると乗車客であふれかえってしまうため、
特に狭くて長いホームは降車専用ホームにしています。
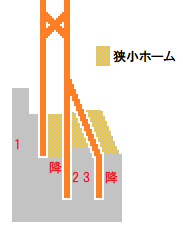
3線のうち西側の1線は単行しか止められません。
そのため、単行運転主流の八瀬比叡山口駅方面の列車が主に使っています。
あとの2線は2両編成の停車が可能ですが、
なるべくホームの狭い部分にかからないよう、
単行列車はホームの広い車止め寄りに停車します。

元田中駅寄りは点字ブロックが1列しか配列出来ない狭さです。
西側の1線は元々は2両編成の停車が可能でしたが、
ホーム拡幅のため、車止め寄り1両分を埋め込みました。

出町柳駅を出発します。

シーサスクロッシングを過ぎます。

道路に沿って右カーブです。

御蔭通りと交差します。

細かいアップダウンが繰り返されます。

家が建て込んでくると元田中駅です。
02(E02)、元田中(もとたなか)Moto-Tanaka

相対式2線の駅ですが、
東大路通を挟んで出町柳駅寄りに八瀬比叡山口駅・鞍馬駅行きホーム、
茶山駅寄りに出町柳駅行きホームがあります。
駅直ぐ南東に田中神社があります。
京都市電があった頃は、東大路通に叡電前電停があり、
同市電との乗り換えが便利な駅でした。
また、一時期はこの駅から山端駅(現・宝ヶ池駅)まで京都市電が乗り入れていました。

左カーブを曲がります。

両側道路に挟まれています。

左手は養徳小学校です。
03(E03)、茶山(ちゃやま)Chayama

相対式2線の駅です。
付近は住宅密集地です。

マンションの中を走ります。

住宅地の風景に似合わない展望列車「きらら」がすれ違います。

北大路通と交差します。
そして、すぐに白川疎水を渡ります。

右手が一乗寺公園になります。

下り勾配になると、一乗寺駅です。
古社寺を訪ねて・叡電叡山本線2へ
川柳五七新電車のページ3Fへ戻る
川柳五七新電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|