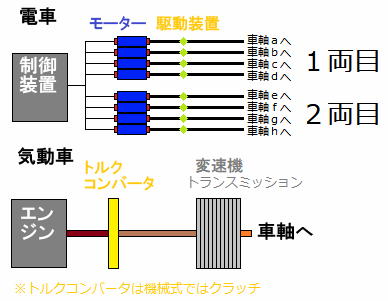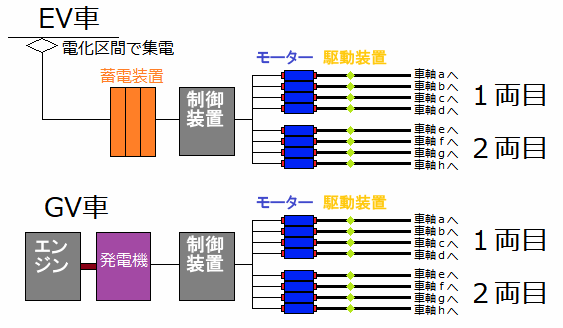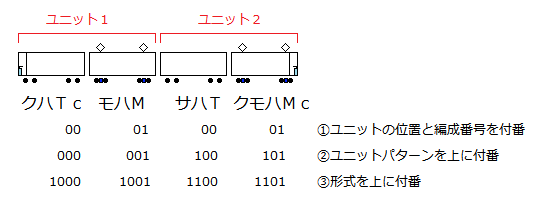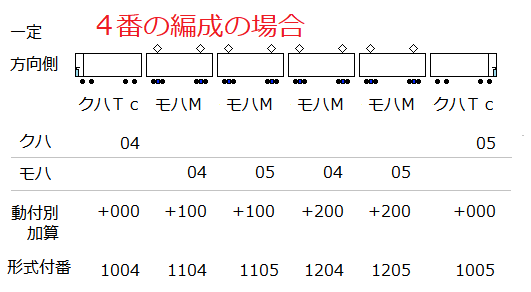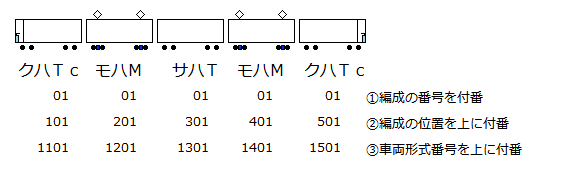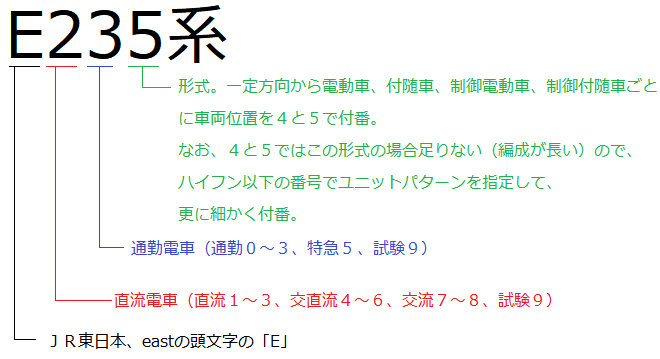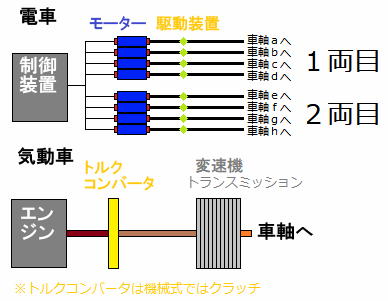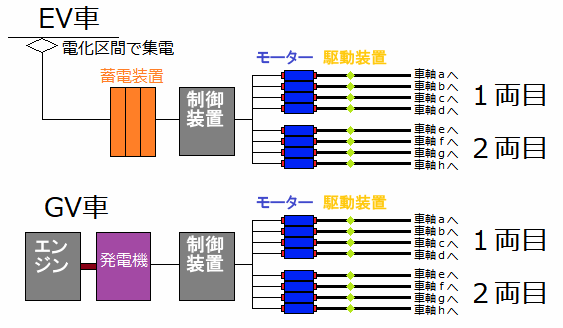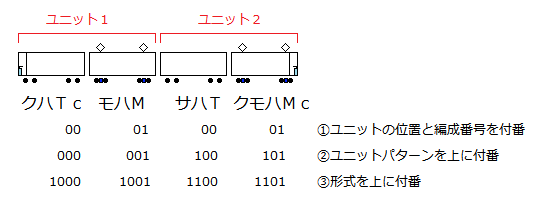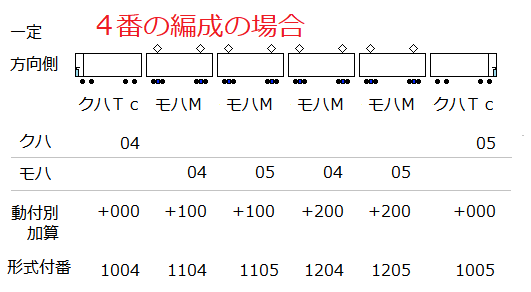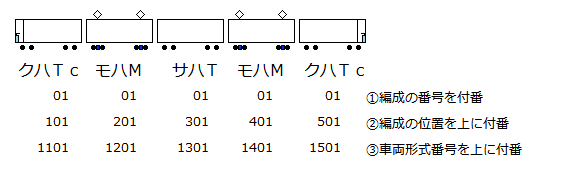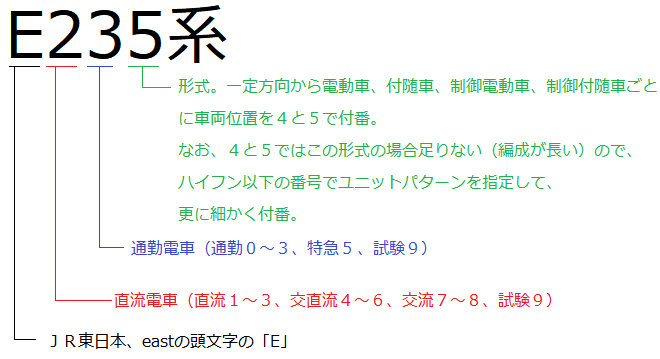電車の車両形式って何!?その1
初心者鉄道ファンや、全く鉄道に興味の無い方でも必ず疑問に思うことがあり、
よく訪ねられることがあります。
それは、「電車に『モハ』とか『クハ』とか書かれているけど、
これって何?」と言うものです。
これは車両の記号ですが、
じつはこれを丁寧に説明すると、かなり複雑で、
分かりにくかったりします。
(特に鉄道に興味の無い方はちんぷんかんぷんだと思います。)
そして、その車両記号に続いて、車両番号が表示されるのですが、
これも、各社で付番法則がまちまちで、
一元的に説明するのが困難です。
なお、車両記号と車両番号を総称して、
車両形式と言います。
1、電車の車両記号
電車は2両編成以上になると、ユニット(組み合わせ)を組むことになります。
そのユニットは固定されており、
間違った車両でユニットを組んでしまうと、
全く電車が動かなくなってしまいます。
例えば、モーターのある車両とモーターの無い車両を組むところを、
モーターの無い車両2両で組んでしまうと、
動かないことになります。
また、モーターのある車両で組んでも、
運転台がない車両だけで組んだら、
やはり動かせないことになります。
それを防止するためにあるのが、
電車の記号です。

この例の場合、正しいユニットの組み合わせは、
「クハ+モハ+サハ+クモハ」×2ユニット(本)です。
電車の場合、側面から見るとそれぞれの違いが分かりにくいので、
車両記号が無いと組み間違いを起こす可能性があります。
組み間違いをすると、全くモーターが無かったり、
運転台が無かったり、あっても運転台が逆になってしまうこともあります。
これを防止するために車両記号とその組み合わせを設定しておきます。
現在は車両記号を廃止し、
車両番号でユニットの組み合わせが分かるようにしている鉄道会社もあります。
この場合、編成は固定編成が前提になります。
(固定編成で無くても出来なくはないのですが、
車両番号の区分が複雑になり、
覚えにくくなるため、適切とは言えません。)
1−1、電動車
電動車とはモーターが搭載されている車両のことで、
モーター(当時はモートルと言っていた)の「モ」を取り、
「モ」という記号で表します。
最近はmotor(モーター)の頭文字である「M」を取り、
「M車」と言う言い方をするのが一般的です。
モーターは「駆動装置って何!?」で書いた通り、
台車と一体化して取り付けられており、
ボギー車なら基本的に1両あたり4台のモーターが搭載されています。
しかし、1台車の2車軸のうち、
1車軸しかモーターの歯車と組み合わせていない車両は、
1両あたり2台のモーターと言うことになります。
その場合でも「モ」と言う記号を使います。
1−2、付随車
付随車とはモーターが全く搭載されていなく、
運転台も搭載されていない車両のことを言います。
記号は「サ」が使われていますが、
これは語源がはっきりしていません。
ただ、有力説は「まっさら」の「さ」から来たと言う説です。
(「はさまる」の「さ」説もあります。)
(車両記号は戦前からあったので、
語源がはっきりしていないものも多い。)
「M車」と同じように、trailer(トレーラー)の頭文字である「T」を取り、
「T車」と言う言い方をします。
昔は機関車で客車牽引をしていたので、
沢山の付随車がありました。
それが、電車に置き換わった際、電動車が増えたため、
付随車がかなり減りました。
それは、電車では動力を分散するため、
各車両にモーターを搭載していたからです。
しかし、最近はVVVFインバータにより、
高出力三相交流モーターが主流になったため、
付随車が再び増えつつあります。
なお、ユニット上、編成の短い車両は当然ながら付随車が無い場合もあります。
1−3、制御電動車
電動車の中でも運転台が付いている車両は、
制御電動車として区別されます。
記号は「クモ」が使われます。
「クモ」のうち「モ」は電動車と同じモーターから来ていますが、
「ク」の方は、駆動の「ク」説と、コントロールの「ク」説の二通りがあります。
先ほどから言っている通り、
やはりアルファベットでも表記されており、
motorの「M」と、control(コントロール)の「c」を合わせ、
「Mc車」と言われています。
なお、「Mc車」は「MC車」ではなく、
「c」は小文字で表記します。
これは英文法の問題では無く、
「c」は細分形式に当たるからです。
1−4、制御付随車
運転台があっても、モーターの搭載していない車両があります。
それを制御付随車と言い、
「ク」と言う記号が使われます。
「ク」の語源は制御電動車で述べたとおりです。
ただ、面白いのは、「クサ」とかにしていないところです。
ただ、アルファベット表記の場合は、
trailerとcontrolを合わせて、
「Tc車」と言っています。
1−5、電動車総称
鉄道会社によっては、
「モ」と「クモ」を電動車からとった「デ」で表記することがあります。
〜〜〜〜〜
なお、電動車比率を見る上で、
●M▲Tと言う言い方をします。
例えば10両編成で電動車+制御電動車が6両、
付随車+制御付随車が4両の場合、
6M4Tと言います。
2、気動車の車両記号
電車の場合、制御装置によってトルク調整がなされ、
制御装置とモーターは電気的回路で接続されています。
そのことから、1台の制御装置で数両分(数台分)のモーターを制御出来るので、
逆に言うとユニットが重要だと言えます。
気動車の場合は、
変速機(トランスミッション)によりトルク調整がされるのですが、
エンジンと変速機はトルクコンバータにより物理的に接続されているので、
1台エンジン〜1個の変速機が基本となり、
1台のエンジンで他の車両の変速機に接続することはありません。
また、編成も電車程長くはないので、
ユニットはさほど重要ではありません。
そのため、気動車の場合一元的に「キ」と言う車両記号が使われています。
なお、気動車は現在、重油を使っているのですが、
昔はガソリンや軽油を使った気動車もありました。
ガソリンや軽油を使った気動車は、
「ケ」と言う車両記号を使っていたところもありました。
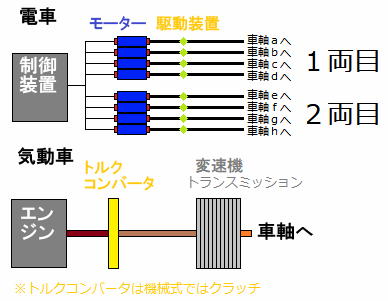
この図では電車が一つの制御装置で、
8台のモーターを動かす場合の例です。
この場合、1つの制御装置で2両が関連します。
気動車はエンジンからトルクコンバータを経て、
変速機に繋がっています。
これは1軸線上の物理的な接続のため、
複数両関係することはありません。
余談ですが、日本の気動車は液体式変速が主流で、
エンジンと変速機の回転の噛み合わせはクラッチでなく、
トルクコンバータと言う、二つの羽の間でオイルを流すことで、
回転を伝えるものになっています。
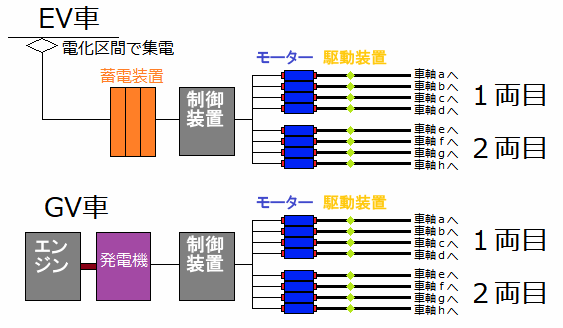
なお、最近はハイブリッド車(HB車)や蓄電池電車(EV車)、
ディーゼル発電電車(GV車)など、
非電化区間を走る車両がディーゼル車のみで無くなりつつあり、
「キ」と言う記号は使われなくなりつつあります。
なお、EV車、GV車は何れもモーターで電車を動かすため、
形式等は電車に準じています。
3、車両等級
車両には主に内装面で等級付けがされています。
例えばJR東日本の新幹線では、
普通車(自由席+指定席)、グリーン車、
グランクラス車と言った具合に分かれています。
これを車両の等級(グレード)と言い、
昔から区別されていました。
基本的には一等車から三等車に区分され、
一等車には「イ」、二等車には「ロ」、三等車には「ハ」と、
イロハ方式になっています。
現在、一等車該当は殆ど無く、
二等車はグリーン車、三等車は普通車とされています。
なお、「二等車がグリーン車」と定義しているところから、
各社の一般民鉄特急は回転リクライニングシート車でも、
「普通車」とされてしまいます。
そのため、普通車しか存在しない鉄道会社も多く、
車両等級を省略する会社もあります。
また、JR東日本の中距離列車のように、
普通電車の中にグリーン車を組み込んでいる車両は、
これがボックスシートや転換クロスシート並のシートであっても、
グリーン車(二等車)扱いになってしまうと言う矛盾もあります。
なお、車両等級は先の車両記号と組み合わせて使われることが多く、
例えば電動車で普通車の車両は「モハ」と表示されます。
先に書いたJR東日本の新幹線のグランクラス車は「イ」に当たるのですが、
新幹線は車両記号を使用していないので、
「モイ」とか「クイ」とかを見ることが出来ません。
4、車両番号
車両記号や車両等級の後につけられるのが、
車両番号で、1両1両に付番されています。
この番号は各社、各形式付番の仕方がまちまちで、
ここで全部を説明することは出来ませんが、
付け方には一定の法則があります。
基本的には車両記号が分からなくても、
正しい車両のユニットで組めるような付番になっています。
なお、以下の付番例はあくまでも例であり、
付番方法は各社で微妙に異なります。
4−1、ユニット付番
昔の車両形式だと、ユニットごとに分けて付番する場合が多いです。
これは車両記号の組み合わせを忘れても、
車両番号だけで組み合わせが分かるようにするという、
バックアップ的な目的があります。
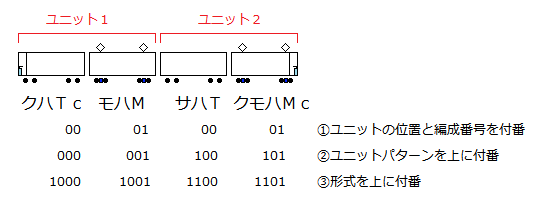
上の図の例のように、二つのユニットで4両編成1本が形成されている場合、
まず、ユニットと一定方向側(路線によって異なる。)からの編成位置関係で
編成番号を付番します。
上の図が最初の編成だった場合、
「00+01+00+01」と付番します。
なお、二番目の編成だった場合は、
「02+03+02+03」になり、三番目の編成だった場合は、
「04+05+04+05」・・・と、なります。
次に、ユニットパターンを考えます。
この場合、「クハ+モハ」のパターンと、「サハ+クモハ」のパターンの二通りがあります。
前者のパターンをパターン「0」とし、後者のパターンをパターン「1」とします。
これを百の位に付番します。
さらに千の位には形式番号を付番します。
4−2、電動車、付随車別付番
電動車、付随車、制御電動車、制御付随車別に分けて付番する方法です。
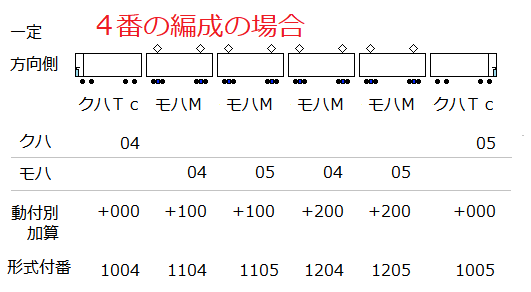
上の図のような電動車と制御付随車で成り立っている6両編成を例にします。
この編成が4番編成の場合、
一定方向側(路線によって異なる。)から電動車、
制御付随車別に04、05と付番します。
(この例の場合は編成番号と編成番号+1ですが、
編成番号-1と編成番号の場合もあります。)
なお、この編成では電動車が4両あるため、
04と05だけでは足りないのですが、
その場合はもう一度04、05と付番します。
次に制御付随車に+000、前の電動車のユニットに+100,
後ろの電動車のユニットに+200を加算します。
(加算方法などは各社で異なります。
また、加算で無くハイフン以下で表示する場合もあります)
最後に形式番号を千の位に付番します。
4−3、固定編成付番
編成の組み替えが頻繁にあった昔と異なり、
現在は編成が固定されている固定編成が多くなっています。
固定された長編成をいくつかのユニットに分けて付番すると
かなり分かりにくくなってしまうため、
固定編成用の付番をして数字の並び=編成の構成が分かるようにしています。
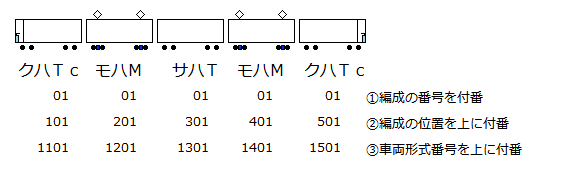
固定編成は細かいユニットに分けず、
1固定編成を1ユニットととして付番します。
上の図の5両編成の例の場合、
この編成パターンに他のパターンが無い場合、
一の位と十の位に編成番号を付番します。
百の位に一定方向側(路線によって異なる。)からの編成位置を付番します。
そして、千の位に形式番号を付番します。
上記の例の場合、5両編成で良いのですが、
10両編成以上だとどうかと言うと、
10両目は「0」、11両目は「A」、12両目は「B」・・・と、
言った具合に付番すること場合や、
インフレ形式の場合、千の位も使って編成位置番号を付番することがあります。
(この場合、形式は万の位を使う)
また、編成パターンが複数ある場合も、
適宜、千の位を使って編成パターンを付番することがあります。
4−4、ハイフン付番
車両形式に多くの意味合いを持たせた場合や、
形式の位を低く設定した場合、
形式の後にハイフン「―」を入れて、
車両番号を付番している鉄道会社や形式があります。
ハイフンの後ろはユニット付番方式、固定編成付番方式の両方があり、
鉄道会社や形式によって異なります。
国鉄〜JR(形式設定を引き継いだ場合のみ)の場合、
形式自体を三桁で表す慣習があり、
百の位に直流、交流、交直流別、
十の位に使途、一の位に電動車、付随車、制御電動車、制御付随車ごとの、
一定方向側からの車両位置を表しています。
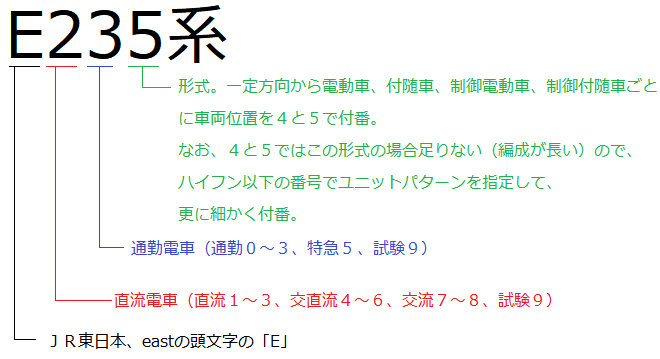
2022年現在、JR山手線で主力として走っているE235系の場合、
頭にJR東日本のeastの頭文字「E」を付けていること以外は、
旧国鉄の形式付番に準じています。
百の位の2は直流電車を表していて、
直流は1〜3番、交直流は4〜6番、交流は7〜8番としています。
十の位の3は通勤電車を表していて、
通勤電車は0〜3、特急電車は5になっています。
ここは国鉄と少し異なっています。
(国鉄時代は通勤電車が0〜2、急行電車が5〜7、特急電車が8になっていました。)
そして、一の位の5はその電車の形式で、
車両番号を表す際は、
一定方向側から電動車、付随車、制御電動車、制御付随車ごとに、
形式数-1と形式数で表すのが慣例となっています。
そのため、電車の形式数は必ず奇数になります。
しかし、この付番で車両番号を表すと、
E235系の場合、E234とE235しか使えないので、
ハイフン以下のユニットパターンで更に細分化しています。
5、車両形式
車両形式は車両ごとのタイプを言います。
基本的には車両番号ごとに区切られていて、
千の位や万の位ごとに形式を変えている鉄道会社は、
●000系とか▲0000系として一括りにします。
なお、「系」は「形」、「型」と表記する鉄道会社もあり、
読みも「けい」や「がた」とまちまちです。
なお、先からの付番方式から考えると、
形式は1000系の場合、
「いちぜろぜろぜろけい」と言うのが正しいです。
しかし、一般の方々などは全くその読みになじみが無いため、
鉄道会社も「せんけい」とアナウンスしているのが殆どです。
上で紹介したE235系も「いーにさんごけい」ですが、
「いーにひゃくさんじゅうごけい」とアナウンスしています。
つまりは、内部用語と一般用語との違いと考えておけば良く、
わざわざこれは「せんけい」ではなく「いちぜろぜろぜろけいだ!!」
なんて訂正する必要はありません。
(そんなことをわざわざ訂正したがるから鉄道ファンは嫌われる・・・。)
6、形式番号のインフレ
鉄道会社はそれぞれどんどん新型車両を導入し、
どんどん新車両形式を付けていくと、
何れは形式に付ける数字が足りなくなってしまいます。
その時、行う方法が以下の4つです。
6−1、若返り付番
過去にあった車両形式番号を再利用する方法です。
ただし、この場合、その形式の車両が完全に全廃していることが条件です。
例として、東急電鉄が田園都市線用に新型車両を導入した際、
既に9000系まで型式番号を使っていたため、
あの青ガエルで有名だった、5000系と同じ型式番号に戻したことは有名な話です。
その縁からか、5000系を旧5000系カラーにした列車も運転されました。
6−2、全く新しい形式付番方法に変更
これもよくある方式で、
0▲系とかE●系とか、今までに無い新しい形式付番に変える場合があります。
これは、古い形式が残っていて、
若返り形式の付番が困難な場合によく使われます。
東京メトロの前身の営団地下鉄が0▲系を一時期導入していたのが有名です。
西武鉄道のラビューは、本来で言えば50000系で付番したかったのですが、
その番号は既に使っており、100000系ではさすがに桁が多いため、
丁度創業100周年(武蔵野鉄道から)だったことから、
100をひっくり返し、あらたな一歩を踏み出すと言うことで、
001系という新しい付番がされました。
6−3、構わずインフレ付番
桁数を考えずインフレ付番を続ける方式です。
さすがに今のところ万の位で止まっていますが、
どこかのハイパーインフレの国家の通貨のように、
1000000000000系とかもあり得ます。
もしくはわざと、ハイパーインフレ付番にして、
「日本一(世界一)桁数の多い形式。」として売り出すところもあるかもしれません。
6−4、同じ型式番号の使い回し
形式の桁数が少ないJRなどでよくやる方式で、
全くタイプが異なっても、●▲■系◇☆◎番台と言う表記で、
元の形式を流用し続けることがあります。
有名どころではJR東海の700系新幹線電車で、
700系の他、N700系、N700系A、N700系Sと、アルファベットを付け加えることで、
同じ形式を長期にわたり長々と使い続けています。
電車の車両形式って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|