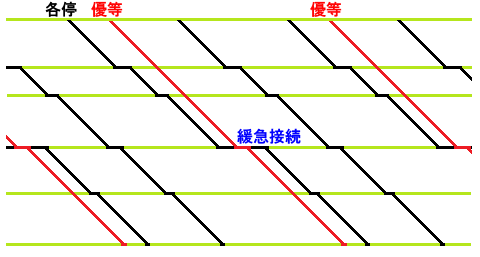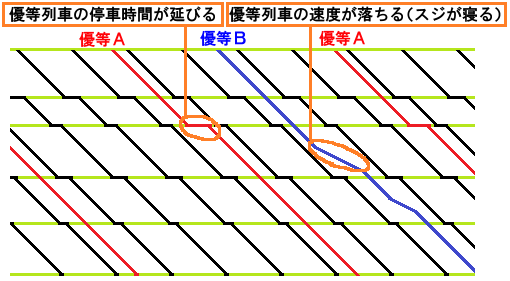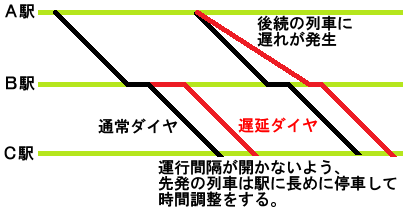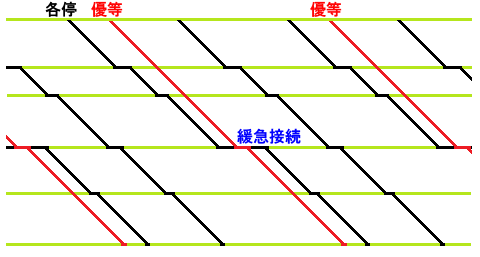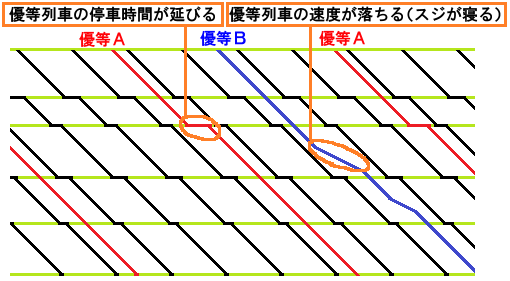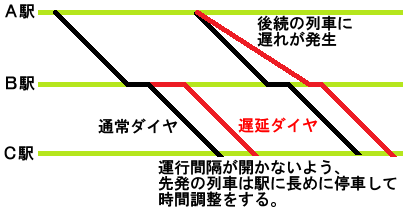電車の運行工程って何!?その2
5、緩急接続
優等列車が走る路線は、
適度に各駅停車と同一ホームで乗り換えられる駅に停車して、
相互の乗り換えをしやすくする必要があります。
このことを緩急接続、または、緩急結合と言います。
緩急接続が可能な駅は前回の停車施設で書いた、
通過線にホームのある通過式ホームなどに限られます。
それ以外の場合は、先行の各駅停車を途中の駅どまりにして、
引き上げ線に入った後、後行の優等列車をその駅に停車させることにより、
間接的に緩急接続させる方法があります。
または、緩急接続が出来ない通過式ホーム駅の前の駅で優等列車を停車させ
通過式ホーム駅で追い越す先行の各駅停車からの乗客を受ける方法もあります。
設備不足で距離も短く、全体的にそこそこの利用客のある路線は、
後の項で述べる平行ダイヤにして、
単に各駅停車の合間に優等列車を挟んだだけの路線もあります。
この場合、一見優等列車の運転意味が無いように思えるのですが、
混雑の均一化や効率運用など様々な理由が背景にあるため、
そのような優等列車でも運転されています。
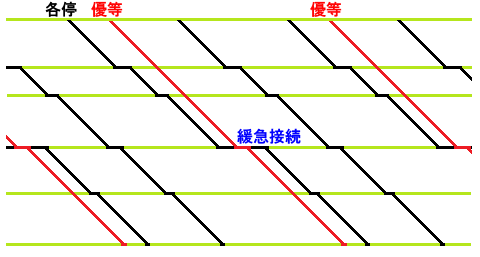
緩急接続を行う場合、
先行の各駅停車が副本線(待避線)にて駅停車したあと、
後行の優等列車が本線(通過線)に停車します。
そして、優等列車を先に発車させた後、
各駅停車が発車します。
なお、通過線にホームのない通過式ホームは、
単に各駅停車を優等列車が追い越して
先行、後行が入れ替わるだけなのですが、
無駄に停車駅を増やしたくない場合は、
緩急接続を考慮しない場合があります。
特にターミナルに近い駅は、
各駅停車からの乗り換え客で優等列車が過度に混まないよう、
また、各駅停車が空気輸送にならないよう、
緩急接続をあえて避ける場合があります。
6、パターンダイヤ
ダイヤはその路線の設備によって複雑に変化するのですが、
出来る限り、周期的に繰り返されるダイヤの方が利用客にとって分かりやすいし、
混雑も平均化出来ます。
そのため、新幹線や通勤路線のディタイムでは
周期的に繰り返されるダイヤになっています。
このダイヤをパターンダイヤと言います。
パターンダイヤにすると、いつも利用している乗客はいちいち時刻表を見なくても、
感覚的に列車の来る時間が分かるようになります。

上の図の駅時刻表では、
平日は11時から15時まで、
休日は10時から16時までパターン化されています。
厳密に言えば、早朝深夜とパターンが切り替わる時間帯、
そして平日朝ラッシュ時以外は
概ねそれぞれの時間帯に合わせたパターンダイヤになっています。
なお、休日のディタイムは時間帯によらず利用客が平均化しているので、
パターンダイヤの時間帯が長くなる傾向があります。
一方、平日は9時、10時台でも通勤通学客がいるため、
ある程度本数を確保しているのと、
夕方以降利用客が再び増えるため、
ディタイムのパターンダイヤ時間帯は短くなっています。
平日ダイヤの欠点は、ラッシュ時に沢山の車両がいるのに対し、
ディタイムはあまり車両が必要でないことです。
それぞれの路線の用意する車両数は
平日朝ラッシュ時のピークを基準にしなければならず、
朝のピークの本数が多ければ多いほど車両が必要になります。
しかし、僅かの時間帯のために多くの車両を用意するのは
鉄道会社にとって効率的ではないため、
時差通勤を呼びかけて混雑の分散化を促しています。
7、過密区間のダイヤ
通勤路線の朝ラッシュ時は多くの列車を走らせて、
多くの乗客を捌きます。
しかし、1閉塞区間に入れる列車は原則1列車に限られるため、
あまりに列車の本数を多くすると、
「列車の渋滞」が起きて、とりわけ優等列車はノロノロ運転になります。
改善策は複々線化して緩急分離することですが、
工事に時間がかかるのと、建設費用も莫大になるため、
そう簡単には出来ません。
そのため、応急処置として一般的に使われるダイヤが、平行ダイヤと千鳥式ダイヤです。
なお、特別車両を使う優等列車は、停車時間が伸びて他の列車の障害となるため、
このダイヤを使う過密な時間帯を外してその前後に多く設定するようにしています。
7−1、平行(並行)ダイヤ
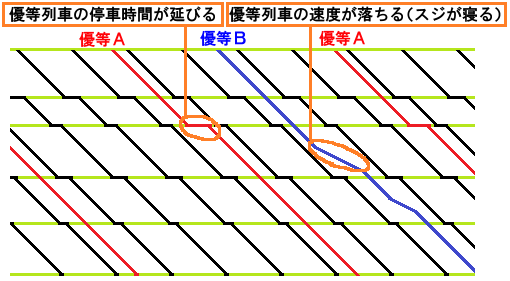
平行ダイヤは最も本数の多い区間を優等、緩行関係なく、
ダイヤグラムのスジをほぼ平行にするダイヤです。
つまり、列車毎の時間差を無くして列車の本数を増やす方法です。
こうすることにより、各駅停車から優等列車に乗り換える乗客を抑えることが出来、
優等列車の混雑を減らし、かつ、列車の間隔も平均的になります。
しかし、優等列車は「ただ駅に停車しない(停止信号で駅で停車してもドアが開かない)」状態となり、
各駅停車と所要時間が変わらなくなる欠点があります。
各駅停車と所要時間が変わらないようにする方法は、
駅の停車時間を延ばしたり、スジを寝かせてノロノロ運転にすることですが、
優等列車利用客にとってはストレス以外の何物でもありません。
なお、都心に近い駅ほど利用客が多い路線は、
これを割り切って、この区間の列車をすべて各駅停車にする場合があります。
東急田園都市線の準急や東京メトロ東西線の通勤快速はこの例に当てはまります。
サービス的には両者ともダウンになるのですが、
乗客の心理は所要時間の速さでなく、「スピードが速い」ことに心地よさを感じるので、
駅の停車数が増えても、ノロノロ運転がなければ速く感じる傾向があります。
7−2、千鳥式ダイヤ

千鳥式ダイヤ(または千鳥式運転)も例の鉄道アナリスト、
川島令三氏が名付けたらしいです。
そのため、川島教の信者の鉄道ファンはこのダイヤを称賛する傾向があります。
アンチ川島の鉄道ファンは別の用語を使いたいのですが代替用語がなく、
このダイヤを採用している阪神や西武も公式に「千鳥式ダイヤ」と言っているので、
仕方なく「千鳥式ダイヤ」と言っています。
千鳥式の由来は千鳥のようにとまったり動いたりすることで、
優等列車の停車駅を固定せず、
優等列車ごとに停車駅をずらして、
全体的に本数の平均化とスピードアップを図るものです。
このダイヤの利点はその他にもいろいろあり、
各駅に優等列車が均等に停車するため、
緩急接続駅の混雑緩和が出来ること、
各駅の列車本数が増えること、
停車駅をずらした優等列車同士で間隔をぎりぎりまで詰めることが出来ることです。
そのため、途中のどの駅も平均的に利用客が多い場合、有効なダイヤと言えます。
欠点は言うまでもなく種別が増えてしまうこと、
停車駅に規則性がないため、
停車駅を覚えるのに苦労することが挙げられます。
そのため、このダイヤは原則、
いつも同じ時間帯の同じ人が利用する通勤時間帯に限られます。
また、JRの特急や新幹線は、
同じ種別でも旅客のニーズや乗務員の都合に合わせて
停車駅を変えることが多いので、
時刻表で調べないと停車駅が分からない場合が多いです。
JRは元々日本国有鉄道だったため、
利用客に分かりやすくするよう、
停車駅を極力揃えようと言う発想はあまりないため(特にJR東日本)、
混乱の元になることがあります。
特に新幹線は運行管理システムに頼りすぎているため、
ダイヤが乱れると収束困難になってしまうことが多いです。
なお、千鳥式ダイヤは阪神と西武で採用していると書きましたが、
発祥は阪神の方で、西武は野球ダイヤの研究のため阪神に社員を研修に行かせた時、
一緒にこのダイヤ方法も持ち帰ったことにより、
混雑の激しい池袋線で採用するに至りました。
8、回復運転
何かの拍子でダイヤが乱れた場合、
ダイヤを調整する回復運転が実施されます。

回復運転の方法は二つで、
まず、遅れが発生した場合、駅の停車時間を所定より短くすることです。
ただ、乗客はそんなことに関係なく停車時間はある程度あると思っているので、
乗客の乗降を早く促す必要があります。
一般的には発車メロディを早く鳴らしたり、
「降りたら列車から離れてください。」と放送したり、
「停車時間が過ぎています。」と放送します。
次にとる方法が運転速度を通常より速くすることです。
勿論、回復運転のためのスピードアップは安全の範囲内で、
通常は正常ダイヤの設定運転速度を遅めにして、
回復運転はあまりにダイヤが乱れない限り、
そこそこ速い速度で運転すれば回復するように出来ています。
回復ダイヤに対し、遅めに設定している正常ダイヤを「余裕ダイヤ」と言い、
JR東日本など関東の鉄道では一般的に通勤時間帯に遅れることが多いので、
正常ダイヤを余裕ダイヤで設定することが多いです。
一方、JR西日本など関西の鉄道はあまり余裕ダイヤを設定しない傾向があります。
その結果起きた悲惨な事故がJR福知山線の脱線転覆事故です。
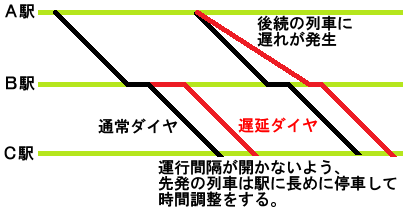
また、後続の列車が遅れた場合、
先発列車との間隔が広がってしまいます。
そうすると、その広がった時間分の利用客が後続の列車に乗るため、
列車の駅停車時間が伸びてしまい、更に遅れが広がってしまいます。
そのため、先発の列車は停車時間を伸ばして時間調整をし、
遅れた後発列車に乗客が不必要に乗らないようにする策をとることがあります。

遅延が大きく、回復運転では遅れを取り戻せない場合は、
間引き運転を行います。
上の図のように列車1本分の遅延が発生した場合、
本来の折り返し運用の列車は運転中止にして、
後続の折り返し列車運用にスライドして帳尻を合わせます。
スライドした列車分後続の列車の運用があぶれるため、
途中で運転打ち切りにして折り返したり、
運転自体を中止にします。
かつて、JR中央線の東京駅での平日ラッシュ時は、
毎日のように1〜3本の列車が間引かれて消えていたらしいです。
9、増解結運用
途中で利用断面が大きく下がる駅(段落ち駅)では、
基本的に一部の列車を折り返し運用にしてその先の運転本数を減らすのですが、
全体的にあまり本数を多くしたくない場合は、
列車の基本編成に付属編成を増結し、
利用断面が下がる駅で付属編成を外して
その先は基本編成で走らせる場合があります。

上の図のように、一時間当たりの輸送能力を段落ち駅まで30両にして、
そこから先を20両にする場合、
10両編成を3本運転して、そのうち1本を段落ち駅で折り返すのが一般的です。
しかし、15両編成を2本運転して、
段落ち駅で5両切り離して、そこから先は10両で運転しても、
一時間当たりの輸送能力は1本折り返しと同じになります。
しかし、この場合のメリットは乗客側にとっては殆どなく、
むしろ増解結をする段落ち駅で無駄な増解結作業で停車時間が延び、
トータルでの所要時間も延びるだけでなく、
利用客がある程度ある区間でも本数がそこそこにしか設定されなく、
利便性が落ちます。
この運用のメリットは鉄道会社側にあり、
3本運用だと運転士と車掌が6人必要なのに対し、
2本の増解結運用だと4人で済むので、人件費がその分削減出来ます。
JR東日本は国鉄時代の悪い慣習を今でも引き継いでいるので、
中距離列車でこういった運用を未だに行っています。
増解結をする付属編成を引き上げ線と逆側(ターミナル側)に連結すれば、
増解結駅での停車時間を少なく出来るのですが、
JR東日本はこれも国鉄時代からの悪い慣習を引き継いでいて、
乗務員の無駄な移動を少なくするため、
引き上げ線側に付属編成を連結することが多い(湘南新宿ラインは除く)です。
そのため、解結の場合は付属編成が引き上げ線に入るまで
基本編成が発車出来ないし、
増結の場合は付属編成が引き上げ線から出てくるまで
基本編成は停車していなければならなくなります。
民鉄の場合、元々長い編成が運転出来る設備がないので、
こういった運用は少なく、
増解結を頻繁に行っている京急も本数を減らす目的ではなく、
むしろ、多方面に運用を効率よく分散させるために行っているので、
乗客側にとっても乗り換えが少なくなるなどのメリットがあります。
電車の車両形式って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|