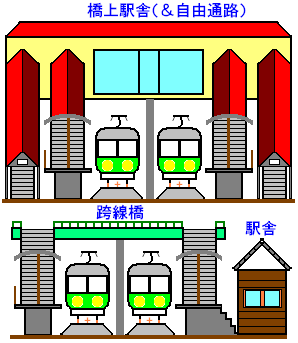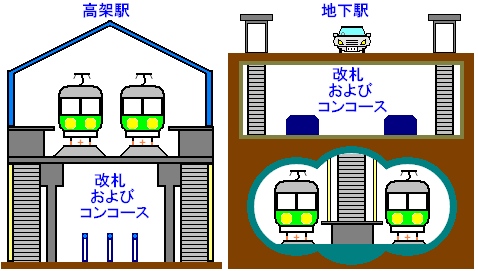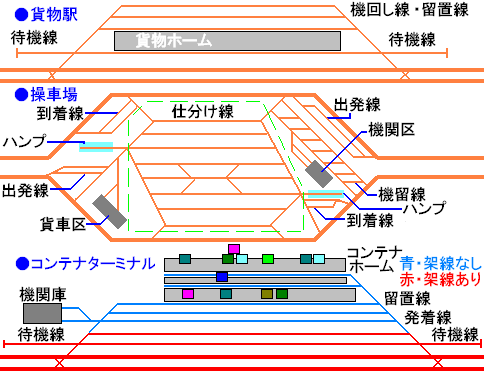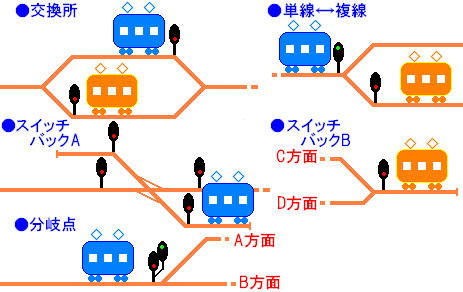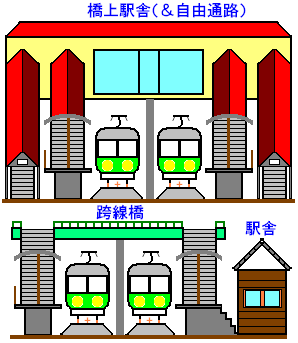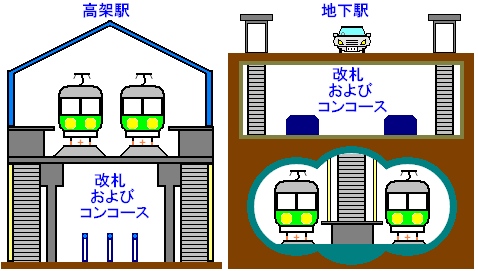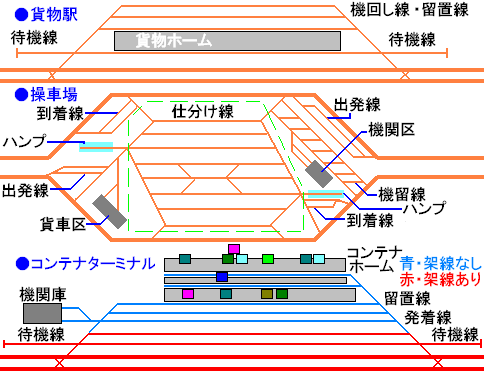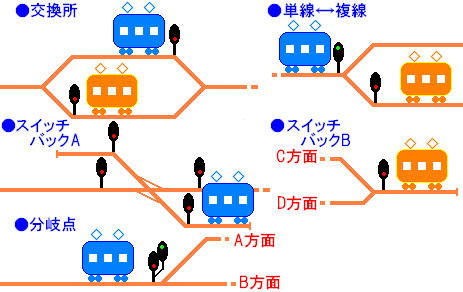電車の停車施設って何!?その2
3、旅客駅
鉄道ファンでなくてもご存知の一般的な「駅」で、乗客が乗り降りします。
大きなターミナル駅もあれば、ホームだけの簡素な駅まで様々あります。
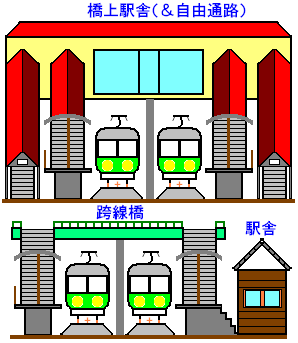
地上駅の場合、駅舎などの配置で駅の構造を分ける事が出来ます。
橋上駅舎は線路の上に駅舎を設ける駅で、
通勤路線では一般的になっています。
この方式にすると、駅舎の用地の確保が少なくて済む(ほぼ線路用地だけで済む)他、
構内踏切などが不要になるので安全性が増します。
また、駅の出口が複数ある場合でも改札口を集約出来る利点もあります。
橋上駅舎を利用して改札外に通路を造れば、
東西、南北の移動が自由に出来ます。
欠点はホームと駅舎に必ず階段が入ってしまうことです。
そのため、ある程度利用客のある駅は、
エスカレータやエレベータなどを設ける必要があります。
最近は改札内に色々店舗を設ける
「エキナカ」方式を採用する鉄道会社も増えています。
エキナカの場合、鉄道会社に店舗料が入る他、
店側にとっても鉄道利用客が嫌でも店の前を通るので、
多くの集客が期待出来ます。
また、乗客にとってもある程度の列車待ちがある場合、
時間つぶしも出来るし、
列車待ち時間を買い物時間に有効に使うことが出来るので、
特に時間に忙しないサラリーマンにとっては便利です。
ただ、エキナカを採用する場合、
ある程度時間超過になっても改札が閉まらないよう、
制限時間を長くする必要があります。
エキナカにかなり力を入れているJR東日本は、
重複や途中下車が無ければ近郊区間の経路自由制度があるので、
元々制限時間は無いに等しく、
あまりに時間を逸脱しない限り、駅員に呼び止められることはありません。
逆に運賃の異なる経路が複数あり、どうしても不正乗車防止のため、
短い時間制限を設けなければならない鉄道会社線などは、
エキナカを造りにくい状況になっています。
ただ、時間制限は元々切符乗車の「キセル」防止のためにあるもので、
ICカード主流の現在ではあまり意味が無く、
重複乗車や迂回乗車、乗車券面逸脱乗車などは悪質な鉄道ファンや、
どうしてもシートに座りたくてわざと折り返し乗車する客でない限りやらないので、
(一般の乗客は早く目的地に着きたい為、
一番速くて安くて短い経路を選ぶので)
京成電鉄のように経路別に運賃が異なり、
かつ、速い方が高額運賃の場合(京成本線&成田スカイアクセス)を除いては、
時間制限を設ける意味合いは殆ど無くなりつつあるので、
エキナカもそれに伴い増えていくと思います。
〜〜〜〜〜
一方、橋上駅舎を設けない場合は、
ホームが複数ある駅に限り、
跨線橋または構内踏切を設けます。
駅舎とホームが同一面である場合は、
階段ののぼりおりが無いか若しくは少なくて済みます。
また、橋上駅舎より駅舎の建設費を抑えることが出来ます。
欠点は駅の出口が複数ある場合、
それぞれの出口に駅舎を設けなければならない欠点がある他、
駅舎の用地が必要になることです。
主要駅は駅舎をそれなりに大きくする必要があるので、
駅舎の用地はかなり確保しなければなりません。
また、構内踏切が残っている駅は、
乗降客の安全を確認する必要がある他、
構内踏切側の線は踏切を渡っている乗客のため、
発車時間を調整する必要が出てしまう欠点もあります。
利点、欠点を考慮すると、この方式は比較的ローカル線に向いていると言えます。
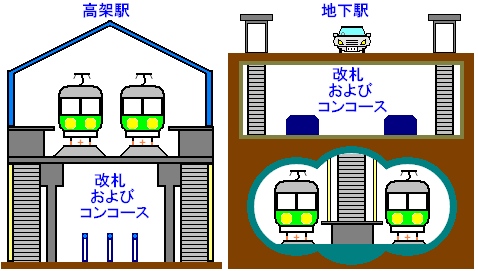
最近は線路用地の有効利用や、踏切を廃止して道路交通の円滑化を図るため、
立体交差駅も増えています。
立体交差駅は複雑に路線が交差している乗換駅で無い限り、
階段はのぼりだけかくだりだけで済みます。
なお、立体交差駅は高架駅と地下駅に分かれています。
高架駅はホームのある高架下に改札口を設けられるので、
用地を有効利用出来ます。
また、高架下は他にも付属店舗などを造る事が出来ます。
地下駅の場合、通常はホームの上に改札・コンコース階を設けます。
そのため、地下鉄のように複数の地下路線がある場合は、
このコンコース階を広くする必要があるので、建設費が高騰します。
また、列車の遅延や運転見合わせの時乗り換え客の混雑を防ぐため、
態と乗り換え通路を長くしている駅もあります。
古い地下鉄は相対式のホームがある階に改札を設け、
改札・コンコース階を設けない駅もあります。
その場合、上下(AB)線ホームを繋ぐ通路を造らない限り、
地上から降りる階段を間違えて、別方面のホームの改札を入ってしまい、
取り返しのつかないことになることもあります。
4、貨物駅
貨物駅は貨物の衰退に伴い数が減っています。
しかし、トラック輸送は多方面に・少量で・短距離の輸送には向いているのですが、
一方向に大量かつ長距離輸送する場合は、
それだけトラックとその運転手が必要になり、コストもかかってしまいます。
そのため、そういった貨物輸送は鉄道が有利と言え、
全国各地に路線網があるJR線では貨物輸送が今でも多く行なわれています。
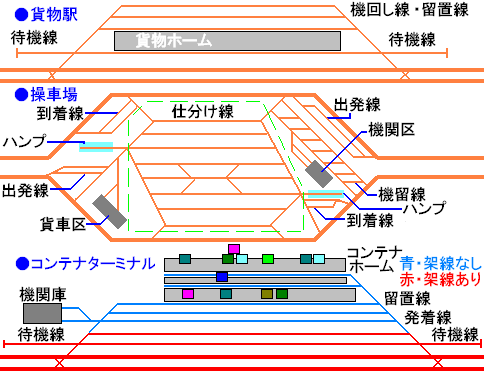
貨物駅の場合、貨物を載せるホーム、または積み込み施設があるのですが、
その他に機回し線が必要になります。
これは、貨物列車が基本的に機関車牽引だからです(一部、貨物電車もありますが)。
また、多くの貨物列車が設定されている場合は、
貨車や機関車の留置線も設けられます。
電化路線の場合、
架線が荷物の積み込みの邪魔になる場合があるので、
貨物駅のホーム部分は架線を張らず、
専用のディーゼル(またはバッテリー)機関車、動車で
この部分だけ牽引する駅もあります。
こういった機関車に付け替える作業を「入れ替え」と言い、
入れ替え用の機関車や動車は入替機関車、入替動車と言います。
また、カタカナではスイッチャーと呼ばれています。
操車場は貨物を乗せた貨車を操縦して仕分けるところなのですが、
最近は一方向集約貨物やコンテナ貨物が主流になっているので、
操車場の数は減りつつあります。
とは言え、石油などの液体や危険物など、
専用の貨車が必要な貨物列車も多くあるので、
全く無くなる事はありません。
操車場を設ける理由は「貨物は歩いて乗り換えが出来ない。」ことです。
そのため、操車場において、
今まで牽引されていた貨物列車の編成から、
それぞれの別方面へ行く貨物列車の編成に付け替えます。
付け替え方は貨物列車の編成をバラして手押しで貨車を押して、
それぞれの仕分け線に入れるという原始的な方法もありますが、
今は貨車をリモコン操縦することが一般的になっています。
また、一時期はハンプと言う上り坂に機関車で牽引し、
仕分け線の分岐器を切り替えた後、貨車を繋ぐ連結を切って、
貨車を慣性の法則で坂を転がし、それぞれの仕分け線に入れると言う、
「突放(とっぽう)」と言うのも行なわれていました。
しかし、現在は突放を行う事により積荷が崩れたり破損したりするリスクがある他、
作業員が貨車と貨車の間に挟まれたり、
突然動き出した貨車にはねられると言う危険性があるので、現在は禁止されています。
コンテナターミナルは、
「コンテナ」と言う荷物の入った大きい函をコンテナ台車に載せたり降ろしたり、
別のコンテナ台車に載せ変えたりするところです。
コンテナはクレーンで吊り上げてコンテナの台車に載せるのが一般的なので、
電化路線でもコンテナホーム部分は架線を張らず、
専用のディーゼル機関車で牽引します。
しかし、最近はそれも時間とコストがかかるので、
架線があってもコンテナが載せられるフォークリフトや、
低床ホームを導入しているところもあります。
5、信号場(信号所)
線路の分岐や列車の交換(行き違い)などにより、
列車が停車することがある所を信号場(鉄道会社によっては信号所)と言います。
信号場は基本的に乗客も貨物も扱っていません。
一見、複線の閉塞区間と同じように見えるのですが、
複線閉塞区間と異なるのは、
信号場部分の閉塞信号は場内と出発になっていることです。
また、乗務員が入れ替わることがある信号場は、
乗務員専用のプラットホームを設けます。
信号場の信号は地上、車上の区別が無く、
車上信号でも列車交換や分岐などがある場合は信号場を設けます(例は少ないですが)。
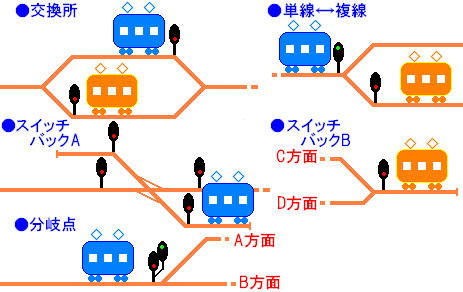
信号場を設ける理由は多種多様にあるのですが、
一番一般的なのは、単線路線で駅のないところに列車の交換設備を設ける場合です。
どちらかの列車をこの信号場の信号で停車させなければ、
当然、反対側の列車と正面衝突してしまうので、
場内信号と出発信号が設けられています。
この交換所の信号が複合的要因で作動せず、
正面衝突という悲惨な事故が平成3年、信楽高原鉄道で起きました。
なので、「たかが交換所」と馬鹿にするのはご法度で、
運転士やCTCの職員はダイヤを正確に把握する必要があります。
単線から複線、複線から単線に切り替わるところにも信号場が設けられます。
基本的理由は先の交換所と同じで、
主に複線から単線に進入する列車が反対側から来る列車と正面衝突しないように、
信号場が設けられます。
スイッチバックや折り返しで駅を設けないところも信号場になっています。
連続急勾配でのぼりきれない場合、
山をジグザグ登る場合、採用する事があります。
分岐点は基本的には信号場になっているのですが、
路線によっては両分岐路線とも閉塞を同一にして
信号場を設けない場合があります。
分岐点で分岐方向に行く列車は、
どの線に進入するべきかを現示する信号機があり、
合流方向に行く列車は、
合流先の線路に進入出来るかどうかの出発信号があります。
6、分界点
運行管理も線路施設管理もしている第一種鉄道事業会社同士の境界は、
乗務員の交代などの便利さなどから、駅または、信号場にします。
しかし、運行管理が第二種鉄道事業の路線で、
線路施設管理の第三種鉄道事業同士の境界がある場合、
第二種の運行の境界と、第三種の施設管理の境界が一致しないところが殆どです。
その場合、第三種鉄道事業同士の境界には駅も信号場もありません。
そういったところを分界点と言い、
分界点には管理区分を表す分界標柱が線路脇に設置されている他、
レールには区分用の継ぎ目を設け、電化路線は架線のセクションを設けて、
管理区分の明確化を図っています。
最近の路線は運行コスト、施設管理コストを削減するため、
上下分離にするところが多く、今後、こういった分界点が増えると思います。
なお、第一種鉄道事業会社同士でも、
施設管理等の問題で分界点を設ける場合があります。
主な分界点
成田高速鉄道アクセス〜成田空港高速鉄道
(成田湯川〜空港第2ビル間)第二種は京成電鉄。
JR宇都宮線〜東武日光線(栗橋駅構内)JR管理側に乗務員交代設備あり。
JR貨物〜西武池袋線(所沢〜新秋津間)
JR側は新秋津駅構内扱いで営業キロは無い。
JR御殿場線〜小田急小田原線(渋沢〜松田間の連絡線)
乗務員交代はJR松田駅で行う。
筑豊電気鉄道(熊西〜萩原間)黒崎駅前側は第三種が西日本鉄道。
などなど・・・。
電車の運行工程って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|