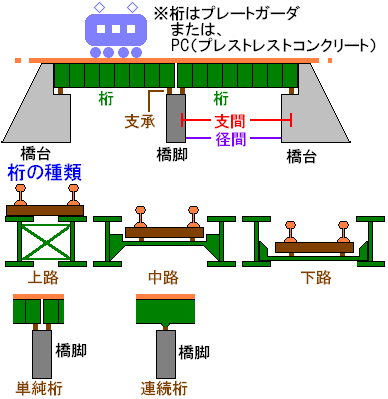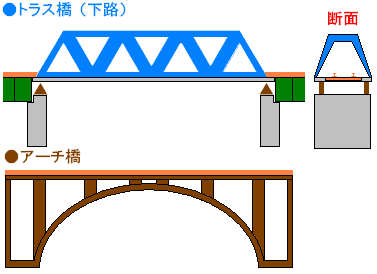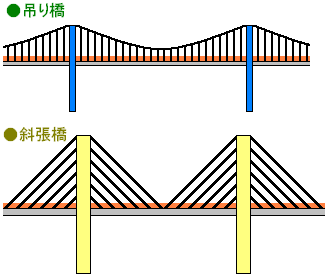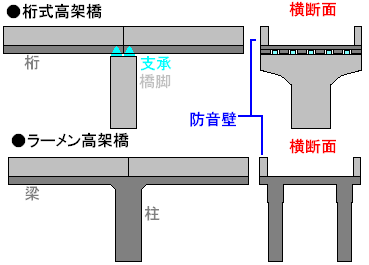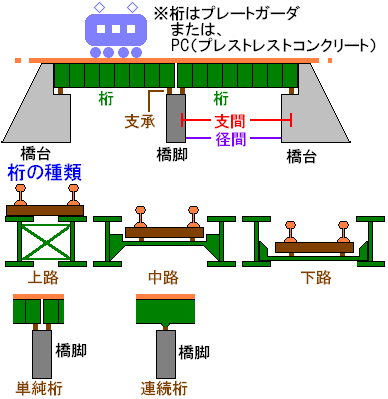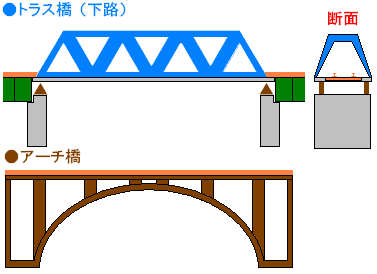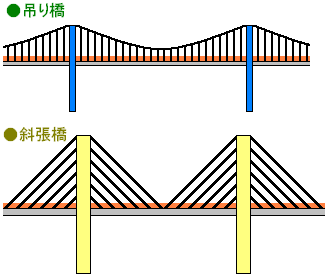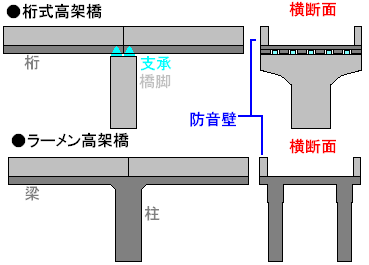電車の土木構造って何!?その1
地上は平坦ではなく、
山(丘)があったり、川(谷)があったりします。
また、踏切が存在する事によって、
道路の渋滞が恒常化しているところもあります。
そのため、各所に橋やトンネル(隧道)を造り、
山や川を越えたり、道路と線路を立体交差化したりしています。
そんな橋やトンネルを土木構造物と言い、
色々な土木工法を駆使してそれらは造られています。
1、橋梁
橋梁と言っても、色々な種類があります。
最もメジャーなのは、プレートガーダ橋やトラス橋です。
最近は土木技術の発展により、吊り橋や斜張橋も登場しています。
なお、橋梁の「梁」の字は常用漢字外漢字なので、
「橋りょう」と書くこともあります。
1−1、短支間桁橋
桁橋は河川等の両端にある橋台と橋台、
または、橋台と橋脚、橋脚と橋脚に桁を渡して、
その上に線路を敷く方法です。
なお、橋脚は流木がひっかかるのを防止するためと、
河川の流れで橋脚の沈下やずれが起きるのを防止するため、
基本的に河川の流れに平行にして設けます。
通常は橋梁の長さを短くするため、
河川に対し直角に渡るコースを採用するので、
橋脚の向きとまくらぎの向きは一致します。
しかし、河川に対して斜めで渡るコースになる場合は、
橋脚の向きとまくらぎの向きが一致せず、
橋脚に接続した架線柱に取り付けるビームも
まくらぎと平行になっていない場合があります。
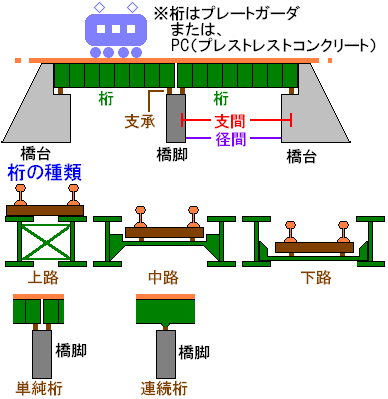
支間(桁を支える支承と支承の間)の短い桁橋は比較的構造が簡単で、
架け替えも用地に余裕があれば、
新しい桁をスライドさせることにより、
短時間で架け替え出来るので、
小さい河川の交差や道路の交差によく使われます。
桁は構造的にはプレートガーダという鋼板・鋼材を組み合わせたもの、
または、PC(プレストレストコンクリート)が使われます。
プレートガーダは通常、単に「ガーダ(girder)」と言いますが、
鉄道ファンや技術者によって「ガーダー」「ガダー」「ガータ」「ガーター」「ガター」「カダー」と、
言い方が異なります。
また、一般の方は「ガード」(「○○線のガード下」「池袋のびっくりガード」等)
と言っているので、
一般向け表示は「ガード」としています。
まあ、外来語なので、特に正式な言い方は決まってなく、
鉄道しか趣味の無い方に起こりがちな、
「これはガードでなくガーダだ」と言うナンセンスな指摘をするべきではありません。
プレートガーダはPC桁に比べて軽量で、
建設コストが安く、建設期間も短く済むので、
大型クレーンが無かった時代には長い橋梁にも普通に使われていました。
ただ、欠点もあり、
一つは鋼板で造っているので、
錆どめ目的に定期的に塗装を塗りなおす必要があります。
また、もう一つにプレートガーダ橋は列車が通過するとものすごい騒音を出します。
これは、プレートガーダ自体の振動による騒音原因の他、
橋梁部分に吸音効果のあるバラストが無く、
プレートガーダの上に直接まくらぎを載せているからです。
だからと言って、無理にバラストを置くと、
バラストの重みでプレートガーダが変形してしまいます。
(消音砕石程度の細かくて軽いものならある程度可能)
それに、上路式の場合、床板が基本的に無いので、
バラストの敷きようもありません。
そのため、短い橋梁を除いて最近はPC桁が主流になり、
長大なプレートガータ橋は架け替えなどで減っています。
一方、PC桁の場合、重くて建設コストがかかると言う欠点があります。
ただ、ある程度工場でパーツを造っておいて、
現場では極力組み立て工事だけで済むようにしています。
なお、PC桁はプレートガーダ橋に比べて頑丈な上、
バラストを敷くことも出来るので、騒音低減が出来ます。
〜〜〜〜〜
桁には色々種類があり、
線路位置で分類すると、上路、中路、下路があります。
上路は桁の上に直接まくらぎが置けるので、構造が簡単になります。
また、桁の高さ分フルに橋台や橋脚の高さを低くする事が出来ます。
しかし、安定感でみると中路や下路に劣ります。
上路の桁橋で脱線した場合、
それを押さえるのは護輪軌条か脱線防止ガード(線路施設の項参照)だけなので、
強風で横転事故を起こした場合、最悪列車が橋から落ちてしまいます。
昭和61年には国鉄山陰本線(現・JR山陰本線)の
余部橋梁(現在はエクストラドーズド型の新橋に架け替え済み)で、
強風により回送列車が脱線、橋梁下に転落し、
丁度下にあった水産加工工場の従業員がお亡くなりになると言う
痛ましい事故がありました。
橋梁は大抵河川に架かっている事が多く、
河川は特に風が強いため、
脱線のリスクが高くなっています。
そのため、現在上路タイプはやむを得ない場合以外、採用されていません。
中路や下路は上路に比べると構造が複雑になりますが、
脱線してもプレートガーダやPCで列車の転落を防止する事が出来ます。
桁を側面から見た場合の分類は大きく分けて単純桁と連続桁があります。
単純桁は支間ごとに桁が分かれていて、
橋脚は双方の桁を支承(橋脚と桁を接続する器具)で支持します。
連続桁は橋梁全体が一つの桁で繋がっていて、
橋脚の支えは1箇所で済み、地震による落橋も低減出来ます。
連続桁にした方が支承の接続作業が短く済みますが、
長い連続桁の橋梁を造る場合は、
橋脚と桁のずれ誤差を無くす精密な計算が必要になります。
また、大型クレーンの導入など大掛かりな工事になります。
折衷的なものとして、径間の真ん中にヒンジと言う段のある切れ目を2ヶ所設け、
その間を吊り桁で結ぶと言う、ゲルバー桁の採用もあります。
ゲルバー桁はそれぞれの橋脚がそれぞれ異なった沈下をしても、
ヒンジ部分がそれにあわせてたわむので、追従出来る利点があります。
〜〜〜〜〜
なお、最近の支承は
地震や列車通過時の振動を吸収出来る構造になっています。
1−2、長支間桁橋
プレートガータの桁橋は橋梁が長くなると
どうしても橋脚の基数が多くなってしまいます。
橋脚は流れている川に設置するものなので、
その基数が多くなるほど工事期間が長くなってしまい、
建設コストもかかってしまいます。
そこで、採用されるのが長い橋脚間(径間)でも大丈夫な、
強度強化された長い支間の桁橋です。
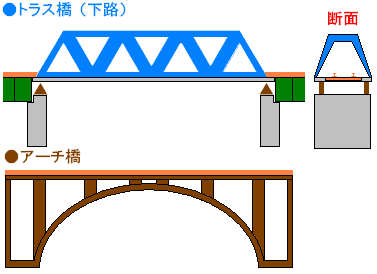
トラス橋は上弦材、下弦材を斜材(何れも鋼材またはPC)で三角状に組んだ桁橋です。
トラス橋は頑丈なため、径間を長くし、橋脚の基数を減らすことが出来ます。
また、鋼材トラスは軽量なので、部材の運搬組み立てが楽に出来ます。
また、副次的な利点として、下路タイプのトラス橋は、
列車が脱線しても、トラス桁が支えになり、橋梁下への落下を防ぐ事が出来ます。
昭和53年に営団地下鉄東西線(現・東京メトロ東西線)で起きた、
荒川・中川橋梁脱線事故は、
トラス桁があったため、橋梁下の河川に列車が転落するのを防ぐ事が出来、
幸いけが人だけで済みました。
アーチ橋は桁(これも鋼材またはPC)がアーチ状になった桁橋です。
アーチと言う構造は上からの圧力に強いため、
やはり、橋脚の数を減らすことが出来ます。
かつては長支間の橋梁に多く採用されていましたが、
トラス橋が普及すると、そちらの方が建設コスト、建設労力共に削減出来るので、
次第に採用例が減ってきました。
しかし、アーチ橋は見た目が美しいので、
近年は環境一体化デザインの目的であえてアーチ橋を採用する場合があります。
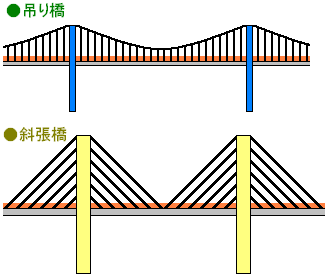
吊り橋はご存知の通り、ワイヤーで桁を吊って支える方式で、
海峡などかなり長くて海底が深く、
なかなか適切な径間で橋脚設置が出来ない場合に採用されます。
代表的なのはJR本四備讃線(瀬戸大橋線)です。
ただ、吊り橋には重大な欠点があります。
それは、列車が通過すると桁が大きくたわんでしまうことです。
その時、レールに何も対策をしていないと、
橋梁の両端のレール、または継目が橋の中心側に引っ張られて破損してしまいます。
そのため、橋梁の両端には緩衝桁及び、伸縮継目が必要になります。
それと、橋梁のたわみ回数が多くなると、
橋を構成している部品や部材が急速に劣化していきます。
そうすると、最悪橋梁の崩壊に繋がってしまいます。
瀬戸大橋開通時に建設技術者は
「100年は大丈夫だろう。」とTVで言っていましたが、
本当に100年持つのかどうかは分かりませんし、列車の車両の重さ、
ダイヤなども影響してくるので、
将来的にはまた大きな架け替え工事をする必要が出るかもしれません。
斜張橋(コンクリートで包んでロープを強くしたのは斜版橋)は、
塔から斜めのロープで桁を吊る方式です。
吊り橋に比べると太いロープが必要になりますが、
ロープの本数が減り、ロープ接続部品を減らすことが出来ます。
ただ、吊り橋と同じくたわむ欠点があるので、
ロープ角度を45度に緩くして、桁をPCでがっちり固め、塔でも桁をしっかり支えた、
エクストラドーズド橋が開発され、
今、ブームなのかあちこちの橋梁でこのエクストラドーズド橋が採用されています。
2、高架橋
最近は道路と線路の立体交差化が都市部を中心に行われていて、
鉄道線が高架化されることも多くなっています。
鉄道の高架橋の種類も色々あるのですが、
よく使われるのが桁式高架橋とラーメン高架橋です。
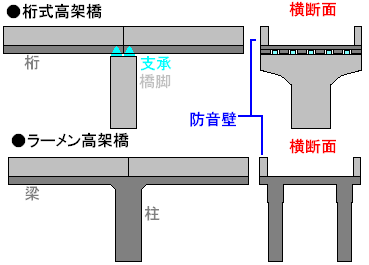
高架橋のうち、桁式高架橋は桁式橋梁と同じように、
橋台、橋脚が桁を支承で支える構造になっています。
桁の裏面は溝になっていて、
その溝に支承が入るようになっています。
溝と支承には若干の空間があり、
地震が起きた場合、振動を吸収するはたらきがあります。
桁式高架橋の場合、土質の違いで地盤の沈下が起きても、
ある程度まで対応出来る利点があります。
また、橋脚は重力式やT式など、比較的重たくて頑丈なものが使われます。
一体化されていない分、自由度が利くので、
定間隔で橋脚が設置出来ないところ(道路交差部分等)では、
桁式高架橋が使われます。
一方、ラーメン高架橋は名前から何だか麺料理を想像してしまいます。
しかし、麺料理のラーメンとは全く関係なく、ドイツ語のrahmenから来ています。
「ラーメン」は「骨組み」と言ったような意味合いです。
ラーメン高架橋は柱や梁などの各部材を頑丈に鉄筋溶接、
コンクリート接着などで剛結して造ります。
そのため、柱と梁の間には桁式高架橋のように支承はありません。
また、桁式高架橋のように完成時に継目になる部分が無く、
各々が強固に繋がっているので、
膨張縮小、荷重の変化などを考慮して設計しないと、
経年劣化で高架橋にヒビが入ったりします。
ラーメン高架橋は桁式高架橋より建設の手間がかからないのですが、
採用される箇所は、
地盤が単調で、柱の間隔が一定に出来るところが多いようです。
ラーメン高架橋は地震に強いと言われていますが、
これは少し?です。
地震に強いのはちゃんとした構造計算の元で設計されたものを、
設計通りに建設したものに限ります。
高度経済成長期に建設した高架橋は
結構、設計を逸脱した手抜き工事が多かったので、
コンクリートのクラックやジャンカ部分から水が浸み込み、
中の鉄筋が錆びているところも多いです。
そのような状態の高架橋が地震に遭うと、
柱と梁を結ぶ鉄筋が切れて梁の落下になりやすく、
また、柱も細いので、横揺れが強い地震だと折れやすくなります。
これを回避するため、
柱に鋼板を巻きつけて補強する工事があちこちで行なわれています。
〜〜〜〜〜〜
高架橋は都市部の住宅地に建設する事が多いので、
桁や梁の両側には防音壁が設けられています。
電車の土木構造って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|