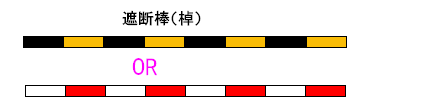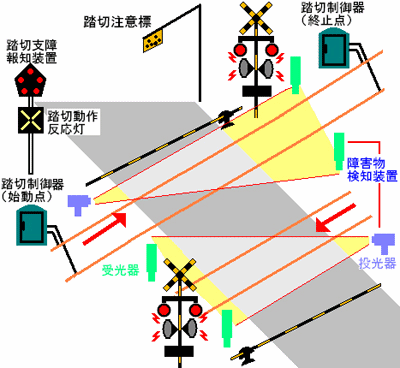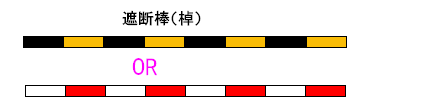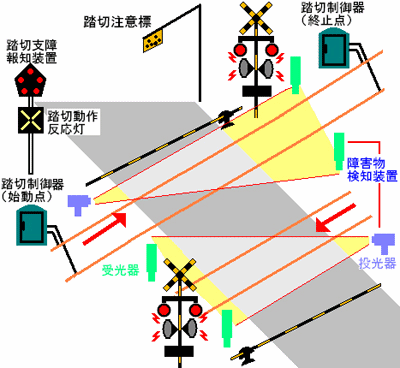電車の踏切施設って何!?
鉄道の線路と道路が続く限り、
どこかで双方が交差する箇所が生じます。
その場合の交差は2通りあり、
線路と道路が同じ高さ(平面)で交差する平面交差、
線路か道路のどちらかが上か下を越して(パス)交差する立体交差があります。
路面電車の併用軌道を除く普通鉄道の平面交差は、
一般的に「踏切」と言います。
新規に造られる路線は立体交差が多く、
既存の路線も立体交差化が進んでいるのですが、
現実的にすべての平面交差を立体交差にするのは不可能なので、
今でも踏切は各所に存在しています。
1、列車優先
路面電車の併用軌道区間の道路の交差は、
道路交通信号に従いますが、
それを除く平面交差の箇所では「列車が優先」になります。
自動車派の方は「何で列車が優先なのか?」と疑問に思われるのですが、
それは自動車と異なり、列車は信号が変わっても急には停車出来ないからです。
例として時速90キロメートル走行で考えると、
自動車は100メートルあればなんとか停車出来ますが、
列車は(車両性能にも異なりますが)400メートル程度必要になります。
(なお、「列車は600メートル以内で停車出来る走行速度」と言う規定は
削除されています。)
一方、路面電車は出しても時速40キロメートルと言う低速走行なのと、
自動空気ブレーキで高減速度なので、
道路信号の変化にも何とか対応出来ます。
それでも、列車の位置によって信号の変化を調整するシステムがなされています。
2、踏切の分類
踏切は第1種から第4種の4つに分類されます。

先ず、第1種はオーソドックスな踏切で、警報機、遮断機がある踏切です。
第1種は甲乙の二通りがあり、
甲の方は完全な自動踏切で、
乙の方は踏切警手が手動で操作するものです。
また、時間帯によって自動、手動を切り替える踏切もあります。
この場合、列車の密度の多い時間帯は少しでも遮断時間を短くするため手動にし、
それ以外の時間帯は自動にする所が殆どです。
しかし、手動踏切は踏切警手などの係員が遮断を失念し、
人身事故を起こしてしまう危険性があります。
事実、平成17年には東武伊勢崎線の竹ノ塚駅前の踏切で、
係員の操作失念による死傷事故が起こりました。
そのため、手動踏切は廃止の方向に向かっています。
第2種踏切は周囲の通行が多い時間帯に限って使われる踏切ですが、
最近はあまり見かけません。
第3種踏切は警報機のみで遮断機がない踏切です。
また、第4種踏切は警報機、遮断機、何れもない踏切です。
第4種踏切はローカル線を中心に多く残っているのですが、
警報も何もならず、遮断もされないので、
自動車や自転車、歩行者が知らずに進入してしまい、
列車にはねられる事故が多く起こっています。
(実は弊サイト作者も危うくはねられそうになったことがあります。)
ただ、第4種踏切を第1種踏切に変えるのにはかなりの費用がかかり、
かと言って、第4種踏切を廃止してしまうと、
その踏切の利用者は別の踏切まで迂回しなければならないと言う不便が発生するので、
完全に無くす事は困難になっています。
なお、第4種踏切がある区間は運転士が警笛を鳴らして注意喚起をします。
(ただ、警笛騒音問題で見通しの悪い区間に限っている路線もあります。)
第3種踏切は耳の不自由な方にとっては危険ですが、
第4種踏切同様、
なかなか第1種踏切切り替えや廃止が出来ない状況になっています。
3、遮断機
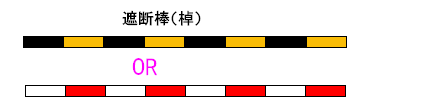
遮断機は遮断棒(遮断棹【かん】とも言う)を
電動、圧縮空気、または手動で操作する機械です。
かつて遮断棒は竹を使っていたのですが、
長期間使うと腐食するのと、折れやすいので、
現在はアルミ、FRP(ガラス繊維強化プラスチック)を使うのが一般的になっています。
FRPは釣竿で使っているものと同じ材質で、
私の父が釣具メーカーに勤めていた頃は、
遮断棒の製造も行なっていました。
基本的に遮断棒は黄色と黒のストライプにするよう定められていますが、
視認性(特に夜間)を考慮すると、
黄色と黒のストライプより赤と白のストライプの方が良い事が分かったので、
都市部の交通の多い踏切を中心に、
赤と白のストライプの遮断棒に交換されつつあります。
4、警報機

警報機は第1種〜第3種踏切に必ずある、おなじみの装置です。
日本の道路は左側通行なので、
警報機は踏切方向に向かって左側に設置されています。
まあ、「説明しなくても分かっている」と言う方が殆どだと思いますが、
一応説明いたします。
警報機はクロスマーク、警報灯、警報音発生器、進行方向指示器、
踏切故障表示器、踏切支障報知器がセットになっていますが、
レイアウトは路線、警報機製造会社、踏切状況により異なります。
ただ、遮断機の支持ポールとクロスマークなどの塗装は、
黄色と黒のストライプにするよう定められています。
列車が近付くと先ずこの警報機が作動し、
その後、遮断機が閉まります。
クロスマーク(Xマークとも言う)は一番目立つ上部に取り付けます。
日本人は「×」を見ると「禁止」とか「止まれ」と言うことを自然的に認識するので、
ここは注意しなければならないことが分かります。
警報灯は赤色2灯で、2灯が交互に点滅します。
警報音発生器はおなじみの「カンカン」音を出す装置で、
昔は本当に鐘(ゴング)で「カンカン」音を出していたのですが、
現在は電子音が一般的になっています。
なお、「カンカン」の音は警報音発生器製造メーカーや鉄道会社の方針などにより、
微妙に異なります。
進行方向指示器は踏切によって無い所がありますが、
歩行者や自動車の運転手などに列車がどちらから来るか知らせるためにあります。
特に、複線で両方向から列車が来る場合、
片方の列車が通過した後、
「もう列車が通過した。」と思って
うっかり歩行者や自動車が踏切内に入って大事故を起こさないよう、
この装置であらかじめ知らせておく必要があります。
なお、踏切付近で列車がすれ違う場合、
後から踏切を通過する列車は警笛を鳴らす路線がありますが、
通勤路線の特に朝ラッシュ時の本数の多い時間帯は警笛を鳴らす場面が多くなり、
線路付近の住民からの騒音による苦情も多いので、
最近は警笛を鳴らさない路線が多くなっています。
特に空気ホーンは電子ホーンに比べて音がうるさいので、
自粛する傾向があります。
なので、歩行者や自動車の運転手は進行方向指示器をよく確認する必要があります。
踏切故障表示器は文字通り、
踏切が故障している時に「こしょう(故障)」と表示されるもので、
普段は非表示か「一旦停止」などの注意喚起が表示されています。
なお、この故障表示器はかつて、
踏切が故障していなくても、
30分以上連続して作動していた場合に「こしょう」表示されるようになっていました。
歩行者などが「警報機の故障かぁ。」と思って踏切内に入ってしまい、
列車にはねられ、死傷事故を起こす事が度々起きたので、
現在は表示されないものに交換されつつあります。
踏切支障報知器は踏切内に人や自動車が立ち往生してしまった場合、
この報知器のボタンを押すと、
踏切支障報知装置と言う信号が点灯し、
列車の運転席には警報がなります。
この場合、運転士は列車をすみやかに停車させるので、
事故を未然に防ぐ事が出来ます。
5、踏切制御装置
列車が近付くと警報機が作動し、遮断機が閉まるわけですが、
列車が近づいている事を感知し、
警報機や遮断機を作動させるシステムが踏切制御装置です。
最近の踏切制御装置は、
踏切支障報知装置やATS、ATCなどの保安装置とも連係しているものがあります。
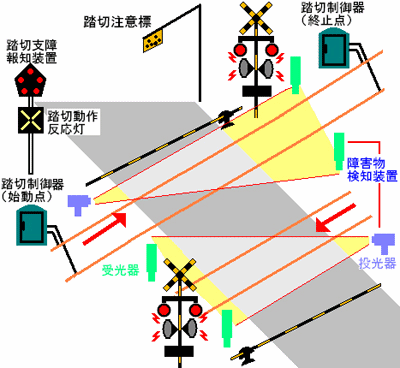
踏切の制御方式は点制御と連続制御の2つがあります。
点制御の場合、
踏切制御器(始動点)の所のレールに30メートル程度の軌道回路を設け、
列車がそこを通過すると、
車輪の車軸を通り双方レールの軌道回路が短絡し、接続用継電器に電気が流れます。
継電器に電気が流れると、継電器は警報機や遮断機の回路を接続させ、
それらを作動させます。
列車が踏切を通過した後、踏切制御器(終止点)を通過すると、
始動点と同じ原理で開放用継電器に電気が流れ、
継電器は警報機や遮断機の回路を開放し、
それらの作動を止めます。
連続制御は警報機や遮断機が作動する範囲のレールに可聴周波を流し、
その範囲に列車が入って回路が短絡すると、
警報機と遮断機が作動します。
また、列車の種別によって
警報機と遮断機の作動時間を変える機能も付けることが出来、
速い列車は作動時間を早く、遅い列車は作動時間を遅くすることが出来ます。
その他、保安装置として、
障害物検知装置があります。
障害物検知装置は踏切の左右に投光器と受光器を設け、
遮断機遮断時に投光器から
レーザや赤外線(超音波のタイプもあります)などを発光させます。
投光器からのレーザや赤外線が受光器にそのまま入れば、
障害物が無いのですが、
踏切内に人や自動車などが立ち往生すると、レーザや赤外線が遮断され、
受光器にそれらが入らないので、
踏切支障報知装置が作動し、列車の運転士に踏切支障を伝えます。
先ほど書きました通り、
踏切支障報知装置は踏切支障報知器のボタンを押した時も作動するのですが、
いざ、踏切支障報知装置が作動した場合は、
その信号が回転するように交互に点灯します。
踏切動作反応灯は、
運転士に踏切の警報機や遮断機が
しっかり作動しているかどうかを知らせるものです。
図では×タイプの信号になっていますが、
鉄道会社によって1灯タイプや2灯交互点灯タイプがあります。
何れも、警報機や遮断機が作動すると点灯するようになっています。
踏切注意標は踏切の存在を知らせると共に、
過積載のダンプカーなどが鉄道架線に荷物をひっかけないよう、
制限高の表示もされています。
踏切注意標はポールに取り付けるタイプの他、
カテナリー(架線より若干低い)のようにしたスパン線に取り付けるタイプがあります。
電車の土木構造って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|