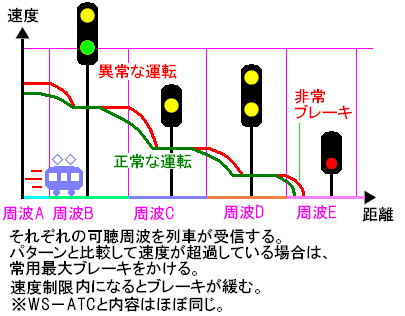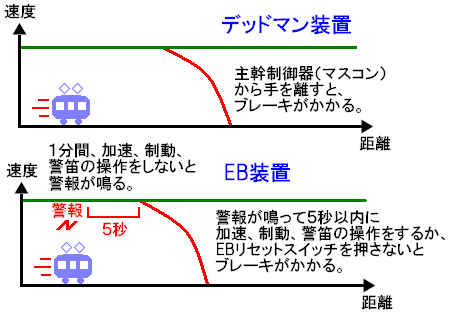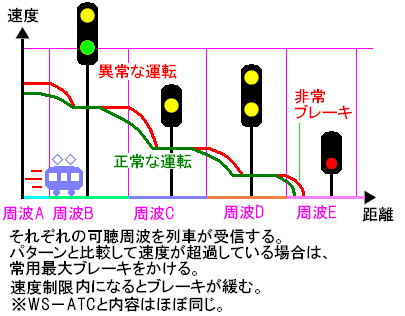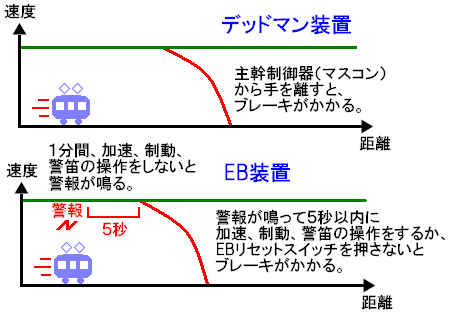電車の保安装置って何!?その2
3、自動列車制御装置の種類
3-1、WS-ATC・AF軌道回路式ATS
WS-ATCとAF軌道回路式ATSは殆ど同じ保安装置です。
WS-ATCはATCの初期タイプで、
当時の考えでは、
停止信号手前で確実に止めるATSに対し、
ATCはその機能プラス、信号現示の速度制限まで自動的に速度を落とし、
速度制限以下になったら自動的にブレーキを緩めるのが、
ATCとされていました。
AF軌道回路式ATSは、「ATSを改良進化させたら、
WS-ATCと同じになってしまいました。」と言うもので、
これによりATSとATCの区別が形骸化されました。
要は、保安対策を突き詰めると結局同じところに辿り着くと言う訳です。
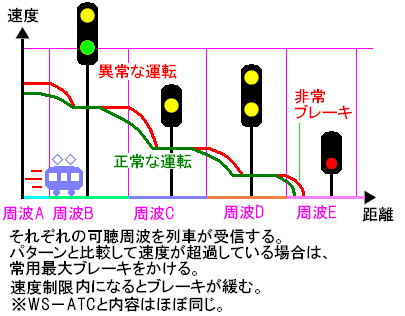
WS-ATCとAF軌道回路式ATSは、
レールに可聴周波(AF・Audio Frequency)を流します。
先の閉塞区間の信号現示が今走っている閉塞区間の現示と異なる場合、
この可聴周波が変化します。
列車側はこの可聴周波の変化をキャッチし、
先の閉塞区間の速度制限まで速度を落とす、減速パターンを計算します。
この減速パターンよりスピードオーバーしている時は、
常用最大ブレーキまたは、非常ブレーキがかかるようになっています。
減速パターン以下の速度に落ちたら、自動的にブレーキを緩めます。
(初期タイプはその機能が無い場合があります。)
3-2、CS-ATC
地上信号機のカラーは緑、黄、赤とその表示の組み合わせで現示するわけですが、
その表示出来るパターンには限度があります。
・・・かと言って地上信号に「制限時速45㎞」などの具体的な速度制限表示をしても、
非常に視認がしにくく、
新幹線などの高速列車や視通の悪い地下鉄では
見落としてしまう可能性が高くなります。
そこで、従来の地上信号をやめて車上信号にしたのが、
CS-ATCです。
CS-ATCの速度制限表示は運転席の速度計の周りにある車内信号機が行い、
色ではなく、具体的な速度制限の数値を表示します。

基本的な仕組みはWS-ATCと全く同じで、
異なるのは、車上信号のため、細かく速度制限が設定されていることです。
また、速度照査や線路状況を判定する論理機能が強化・統合されています。
WS-ATCと同じく、
先の閉塞区間の信号現示が今走っている閉塞区間の現示と異なる場合、
可聴周波が変化します。
列車はその可聴周波の変化をキャッチして減速パターンを計算し、
それよりスピードオーバーしている場合は、常用最大ブレーキをかけます。
そして、速度が速度制限以下になったら、ブレーキが緩む仕組みです。
少し前の鉄道関連の書籍だと必ず、
「CS-ATCは機械優先のシステムです。」と言う書き方がされているのですが、
現在、この表現は不適切だとされています。
・・・と、言うのは、
CS-ATCの場合、減速をすべて機械優先・・・つまり機械任せにすると、
常に常用最大ブレーキがかかることになるからです。
いきなり常用最大ブレーキがかかったり、それから緩んだりすると、
乗客は慣性の法則で強く体が引っ張られて不快感を感じます。
それを避けるには、車内信号機が予告現示(信号が点滅)している間に、
運転士があらかじめ弱いブレーキをかけて
速度を落としておく方法をとることになるのですが、
とある鉄道会社の運転士は、加速が終わったらハンドルから手を離し、
ボケーと椅子に座って、減速はATC任せと言う酷い運転をする者がいます。
当然、そういう運転では、
常用最大ブレーキがいきなりかかったり緩んだりするので乗り心地が悪いし、
線路に異常があった場合、とっさに非常ブレーキもかけられません。
なので、基本的に保安装置と運転士の運転は双方のバックアップであり、
機械優先、人優先と言うことはありえません。
CS-ATCは常用最大ブレーキが常にかかると言う欠点以外にも、
地上、車上どちらも装置が大掛かりになってしまうと言う欠点があります。
これは、速度制限ごとに異なる可聴周波を用意しなければならないからです。
車上装置は乗務員室だけでなく、
客室の一部までその装置が占有するほど大きいので、
それだけ乗客定員も下がる事になります。
CS-ATCは結構欠点も多いので、
その欠点を克服するため、今はデジタルATCが主流になっています。
3-3、デジタルATC(D-ATC・何とかS-ATC)
CS-ATCは速度制限に応じて可聴周波が必要になるため、
速度制限の現示を細かくすればするほど装置が大きくなってしまうし、
使える周波数にも限界があります。
そこで、ATC信号をデジタル符号化して、
少ない可聴周波で大容量のデータが送信出来る、
デジタルATCが開発されました。

デジタルATCの場合、多くのデータが送信出来るので、
速度現示を極めて細かく設定出来ます。
そのため、従来のように閉塞区間を必ずしも固定する必要がなくなり、
先行の列車の位置によって的確な間隔を保てる速度現示が可能になりました。
CS-ATCは現示信号まで速度を落とす減速パターンが計算されるのですが、
基本的に前の列車に追突や衝突しない位置で停止出来れば良いので、
デジタルATCは前の列車と的確な間隔で停止出来るような減速パターンを計算します。
そのため、信号現示毎の「ブレーキがかかったり緩んだりの繰り返し」が少なくなり、
ダイヤ面、エネルギー面両面で運転ロスが削減されます。
ブレーキパターンも常用最大ブレーキだけでなく、
車両の性能と線路状況(勾配、カーブなど)に合わせて、
ブレーキ段階を決めるので乗り心地が向上します。
そして、CS-ATCに比べてはるかに装置を小型化出来るメリットがあります。
ただ、CS-ATCからデジタルATCに変えるには、
地上側も車上側も大規模な工事が必要となるため、
しばらくはCS-ATCが残存する事になると思います。
4、定位置停止支援装置
列車の運転で一番難しいのは、
所定の位置にピタッと止めることです。
これは列車のブレーキの減速度は自動車に比べてかなり低いからです。
最近は駅ホームにホームドアやホームゲートを設けることが多く、
その場合、列車のドアとホームドア・ホームゲートの扉の位置が合うよう、
停車位置の許容誤差はたった数十センチだけになっています。
そのため、許容誤差内に止めるのには非常に高度な運転技術が必要になります。
そこで、登場するのが
定位置停止支援装置(TASC=Train Automatic Stopping Controller)で、
許容誤差内に停車出来るよう、停車パターンを計算し、
許容誤差内に停車出来ないおそれがある場合は、
自動的にブレーキをかける装置です。
なお、TASCを最初に導入したのは、
東京メトロ(当時・営団地下鉄)銀座線(平成5年投入)なのですが、
当時の営団の社内事情からあまりこれを宣伝しなかったので、
東急池上線(平成10年投入)が最初だと思っている方が少なくなかったりします。

TASCの場合、停止位置手前にいくつかの地上子を設けます。
地上子から停止位置までの距離データを受信した列車は、
停止位置までの停車パターンを照査し、
そのパターンより速度が超えている場合は、
自動的にブレーキをかけます。
5、自動列車運転装置
自動列車運転装置は英語でAutomatic Train Operation deviceと書くので、
略してATOと言っています。
ATOはATCやTASCの上乗せで付加する装置で、
ATCやTASCの減速関与だけでなく、
加速関与もするようにしたのがATOです。
つまり、完全自動運転な訳で、
運転士が出発確認ボタンを押すと、
ATC信号現示速度まで加速し、
そこから先、ATC信号の指示に沿って加速や減速、惰性走行をします。
そして、駅の停車はTASCの機能を使います。
なお、出発確認ボタンは二つあり、それを同時に押すことにより、
列車は発車します。
出発確認ボタンが二つあるのは、
何かの拍子で運転士の体などが出発確認ボタンにぶつかって、
誤発車するのを防止するためです。
ATO運転中、運転士は緊急停止ボタンに手を沿え、
緊急時にすかさず停車出来るよう、備えています。
運転パターンは正常ダイヤ時モードとダイヤ遅延時モードがあるのですが、
著しくダイヤが乱れている場合、ATOでは対処出来ないので、
マニュアル運転(手動運転)になります。
また、地上を走る路線は天候によって微妙な操作が必要になる場合があるので、
状況に応じてマニュアル運転に切り替える事があります。
それ以外でも、運転士の技術維持のため、
ATO区間でも定期的にマニュアル運転をするよう定められています。
6、デッドマン装置・EB装置
運転士も生身の人間な訳で、
運転中、病気等で意識を失ったり、
最悪の場合はお亡くなりになってしまう場合があります。
その場合、何もバックアップ装置がないと、
列車の暴走になってしまい、大事故に繋がってしまいます。
そこで設けられているのが、デッドマン装置やEB装置で、
それらの装置は「運転士に異常がある」と判定したら、
即座に列車を停止させる仕組みになっています。
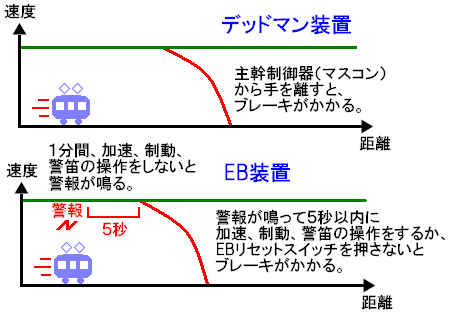
デッドマン装置は
字のごとく「死人装置」(分かりやすいけど表現がダイレクト過ぎる・・・。)です。
デッドマン装置搭載車の主幹制御器(マスコン)にはばねが入っていて、
通常は上に跳ね上がっています。
運転士が正常な状態の時は、
その主幹制御器を下に押しながら運転操作をします。
運転士に何か異常があると主幹制御器を押す力が弱まるか、手を離すかするので、
ばねにより上に跳ね上がります。
そうなった場合、即座にブレーキがかかるようになっています。
ただ、デッドマン装置はワンハンドルの列車には搭載出来ないのと、
絶えず主幹制御器を下に押していないといけないので、
EB(Emergency Brake device)装置を導入する路線が多くなっています。
EB装置搭載車は走行中、
1分間加速、制動(ブレーキ)、警笛などの操作をしないとブザーが鳴ります。
ブザーが鳴った場合、5秒以内に加速、制動、警笛の操作をするか、
EBリセットスイッチを押さないと、ブレーキがかかるようになっています。
大都市近郊の通勤路線は駅間距離も短いし、
列車密度が高く、絶えず加速、制動を繰り返しているので、
EB装置のブザー音を聞く事はあまり無いのですが、
郊外路線やローカル線に乗ると、
定期的に運転席から「プー」とか「ピー」とか言う音がいきなりするので分かります。
おまけコラム
速度制限は時速20㎞、40㎞、70㎞ではなく、
時速25㎞、45㎞、75㎞と、時速○5㎞と設定する事が多いのですが、
これは、一の位が0の速度だとアナログ速度計で見た場合、
時速表示の数字と針が被って見難いからです。
電車の踏切施設って何!?へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|