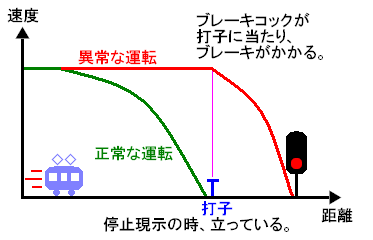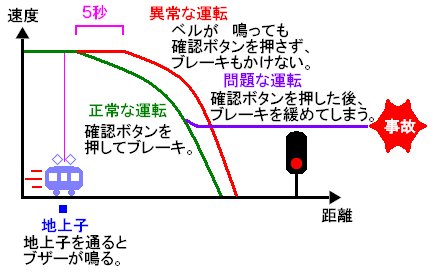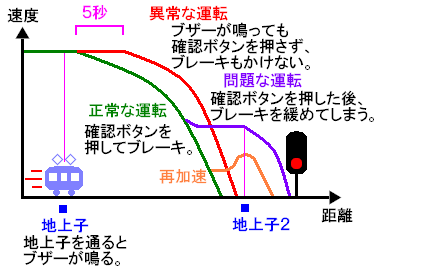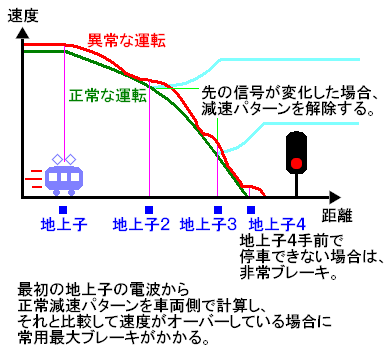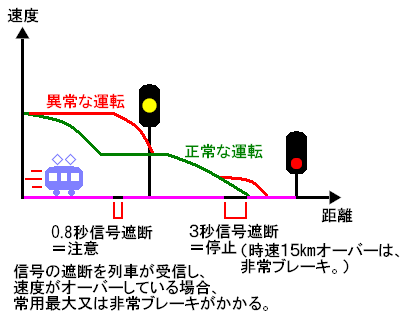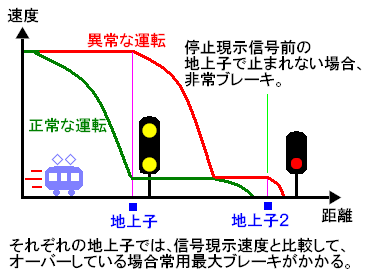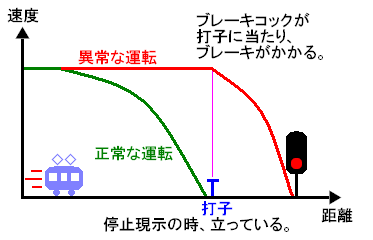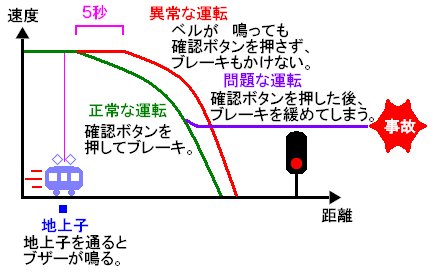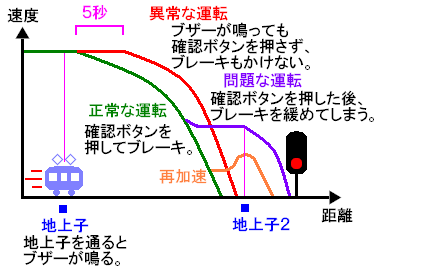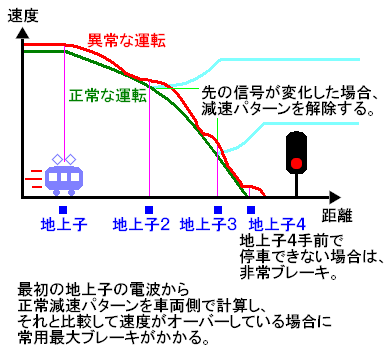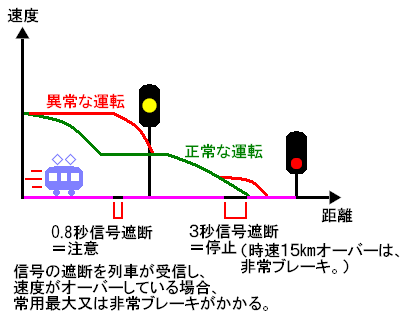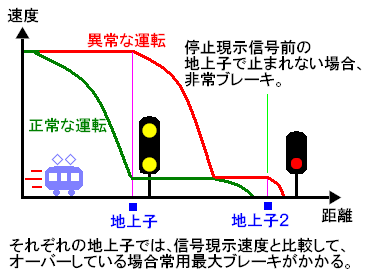電車の保安装置って何!?その1
列車の運転士も人間な訳で、
うっかり信号を見落とす可能性があります。
また、運転中、何かしらのトラブル(病気等)で
運転士が運転出来ない状況になる可能性もあります。
そんな列車がそのまま入ってはいけない閉塞区間に入ってしまうと、
追突や衝突などの大事故を起こしてしまう可能性が高くなってしまいます。
それを防止するためにあるのが保安装置です。
1、自動列車停止装置と自動列車制御装置
保安装置には自動列車停止装置と自動列車制御装置があります。
前者は英語で書くとAutomatic Train Stopなので、略してATS、
後者は英語で書くとAutomatic Train Controlなので、
略してATCと一般的に言っています。
ATSは赤信号の閉塞区間に入りそうになったら、
確実に列車を停止させる装置です。
ATCは赤信号の閉塞区間に入りそうになったら確実に列車を停止させるだけでなく、
信号現示や線路状況によって列車の速度を自動的に落とす装置です。
しかし、ATSもATCも改良に改良を重ねた結果、
双方の違いが殆ど無くなってしまい、区分けが形骸化しています。
(欧米では「ATP」と一まとめにしています。)
平成っ子の鉄道ファンはATSが地上信号、
ATCが車上信号だと勘違いしている人が結構いるかと思います。
ATSでも車上信号にすることは可能ですし、
初期のATCである、WS-ATCは地上信号でした。
つまり、地上信号、車上信号はATS、ATCに関係なく、
細かく速度指示をする場合、
または地下鉄や新幹線など地上の信号の視認が困難な場合は、
車上信号を使います。
ただ、相対的にATCの方が速度指示が細かいので、
車上信号が採用されることが多いです。
2、自動列車停止装置の種類
2-1、打子式ATS
打子式ATSは一番原始的でかつ機械的なATS装置で、
赤信号の閉塞区間に入りそうになったら、
打子でブレーキコックを解除させて強制的にブレーキをかける方式です。
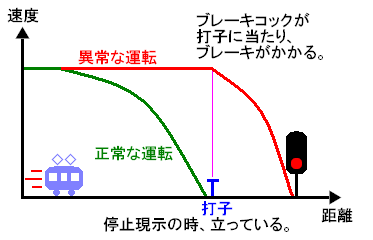
打子式ATSは、信号機の前に打子と言う叩き棒をレール脇に設けます。
進行現示の時はこの打子が寝ているのですが、
停止現示になると打子が立ち上がります。
列車が信号を無視してそのまま赤信号の閉塞区間に入ろうとすると、
打子がブレーキコックに当たり、弁が解放されます。
そうするとブレーキ管の圧縮空気がどんどん漏れるので、
非常ブレーキがかかる仕組みです。
(何で圧縮空気を抜くとブレーキがかかるのかは、
空気制動の項の自動空気制動をご覧下さい。)
打子式ATSは列車を停止させるだけで、細かい速度制御は出来ませんが、
構造が簡単で保守が楽であり、
簡単ゆえに丈夫で長持ちするし、
物理的に確実に停止出来るので信用性もあります。
そのため、現在でも専用線、モノレールなどで使用されていて、
一部の地下鉄路線ではつい最近までこのATSが使われていました。
また、ATSの仕組みを説明する時は、
メインに使われていなくてもこの打子式ATSの説明を載せるのがセオリーになっています。
2-2、ATS-S
保安装置に関しては地下鉄で積極的に導入されましたが、
国鉄は予算の都合で先延ばしにされ、
なかなか採用されませんでした。
そんな昭和37年、常磐線の三河島~南千住間で、
貨物列車と旅客列車が接触し、旅客列車が脱線して、
しかも、脱線した列車に反対方向の列車が衝突して、
死者160人が出ると言う悲惨な事故が起きてしまいました。
さすがに保安装置の必要性を痛感した国鉄は、
ATSの導入に踏み切りました。
その時導入されたATS方式がATS-Sです。
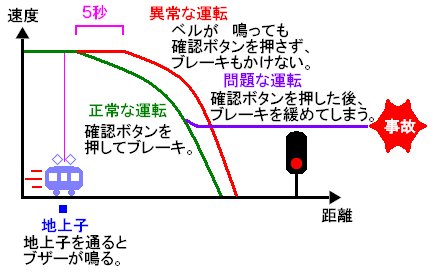
ATS-Sは信号機のかなり手前に地上子と言う電波発信装置を設けます。
列車が地上子を通り過ぎると、
先の閉塞区間に入れない(停止現示)場合、警報ベルが鳴ります。
この警報ベルが鳴ったら、
運転士は5秒以内に確認ボタンを押してブレーキ操作をします。
運転士に何かトラブルが起きている場合、確認ボタンを押せないので、
異常運転と判断され、自動的に非常ブレーキをかけて列車を停止させます。
ATS-Sの警報ベルは最初けたたましくジリリ・・・!と鳴っていますが、
確認ボタンを押してピタっと鳴らなくなると、
その後運転士が失念する可能性があるので、
一応停車するまで、キンコンキンコンと言う音が鳴ります。
ただ、キンコンキンコンと鳴っている時はもう手遅れで、
その後異常運転をしても非常ブレーキがかからず、
入ってはいけない閉塞区間に入ってしまい、
大事故を起こしてしまう可能性があります。
それでもこのATSを使い続けた結果、
国鉄のJR化直後の昭和63年に、
中央緩行線の東中野駅で列車の追突事故を起こしてしまいました。
2-3、改良型ATS-S
ATS-Sは上記のような問題があるため、
その問題を改善したのが、改良型ATS-Sです。
JRの会社によって「ATS-S何とか」と言う名称を付けています。
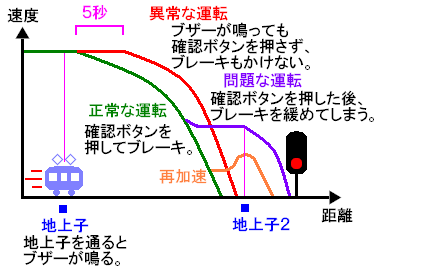
改良型ATS-Sは従来の地上子の他に、もう一つ地上子を信号手前に設け、
この地上子手前で列車が停止出来ない場合、
この地上子から電波を受信し、
即時に非常ブレーキをかけます。
たとえ、運転士が確認ボタンを押した後、
ブレーキを緩めたり再加速をしたりして、
入ってはいけない閉塞区間に入ろうとしても、
確実に列車を停止させることが出来ます。
なお、双方の地上子の電波の周波数が同じだと、
信号を混同してしまうので、
周波数は異なるものを使っています。
(最初が130キロヘルツ、信号手前が123キロヘルツ)
また、車両側にタイマーを搭載し、
2点間の通過時間を計算(速度=距離÷時間)し、
スピードオーバーかどうかを判定する機能(これを速度照査と言います。)
を追加している路線もあります。
この場合、各々の信号現示の速度制限やカーブの制限速度と比較して、
スピードオーバーしている場合は、自動的にブレーキをかけて速度を落とします。
なお、JR福知山線(宝塚線)の脱線事故が起きた時、
同線ではまだこの速度照査機能が無かったため、
事故の一原因になったと言われています。
2-4、ATS-P
ATS-Sは速度照査機能を付加すると地上子が沢山必要になる欠点があり、
また、正常運転時でも先の閉塞区間に進入出来ない場合、
警報ベルがなってうるさいので、
その点を改良したのがATS-Pです。
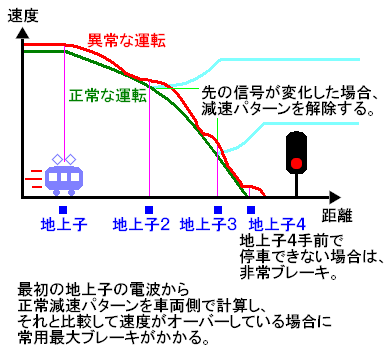
最初に通る地上子から情報電波
(信号の速度制限、またはカーブの制限速度、停止までの距離)を送信し、
それを車両が受信します。
車両は電波を受けた後、正常減速運転パターンを計算し、
そのパターンより速度がオーバーしている時のみ、
常用最大ブレーキをかけて確実に停止させます。
(ただし、信号手前の地上子の前で停車出来ない場合は非常ブレーキ。)
この方式にすれば、正常運転時は自動的にブレーキがかからず、
警報ベルも鳴らない(パターン区間進入予告の単打ベルのみ)ので、静かになります。
また、ATS-Sで速度照査機能を付加すると、
速度照査をする毎に地上子が必要になってしまいますが、
ATS-Pは、減速パターンを計算する点のみ地上子を設置すればよいので、
地上子の数を減らす事が出来ます。
また、先の閉塞区間の信号現示が「停止」から「進行」に変化した場合は、
次に通る地上子の電波を受信する事により、
減速パターンを解除することが出来ます。
言い換えれば減速パターン計算と減速パターン解除の点が荒いATCと同じで、
ATCに比べて地上側も車上側も設置コストが安いので、
そんなに高密度で運転しない区間は、
保安装置をATCにした区間でもわざわざATS-Pに更新した路線もあります。
2-5、商用周波軌道回路式ATS
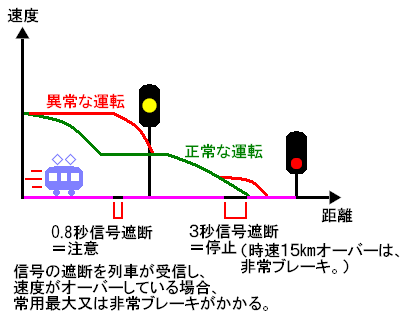
レールに商用周波数(東日本は50ヘルツ、西日本は60ヘルツ)の信号を流します。
信号機現示によって異なる長さの時間、レールの信号電気を停電させます。
列車はその信号電気の停電をキャッチして、
注意現示の場合のスピードオーバーは常用最大ブレーキ、
停止現示の場合は非常ブレーキをかけます。
この方式の場合、0.8秒停電が注意(時速45㎞制限)、
3秒停電が停止と決められているのですが、
それ以外の停電パターンは決められていないため、
(色々、細かい時間差で停電パターンを設定してしまうと、
列車が誤判断する可能性があります。)
細かい速度制限を設定出来ない欠点があります。
細かい指示をする場合は信号をデジタル化する必要があります。
2-6、多変周連続速度照査式ATS
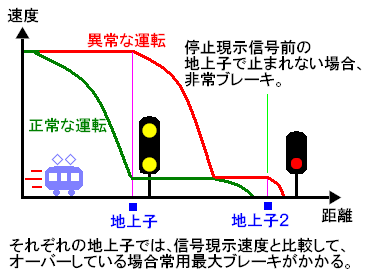
各々の信号機の前に地上子を設置し、
信号の現示によって異なる周波数の電波を送信します。
列車側がその電波を受信し、
信号の速度制限よりスピードオーバーしている場合は、
常用最大ブレーキがかかる仕組みです。
信号が変化した場合は、
次の信号の地上子を通過することによってクリアします。
電車の保安装置って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|