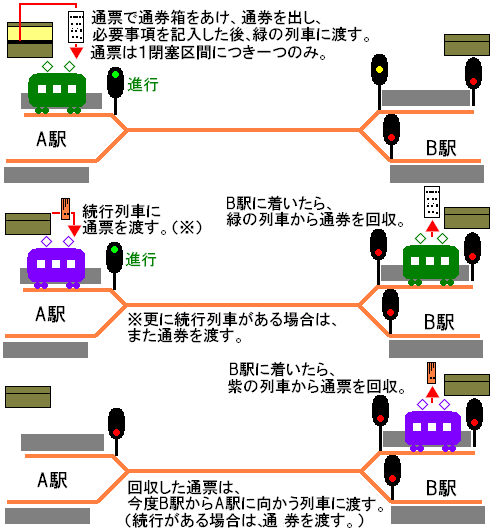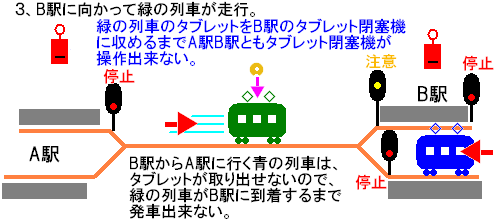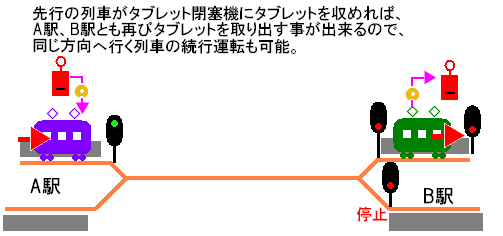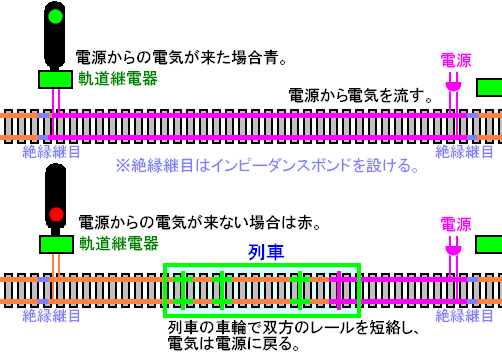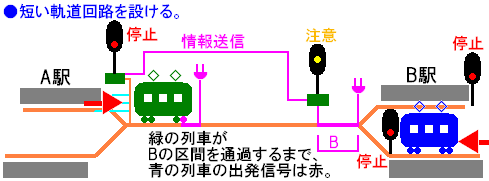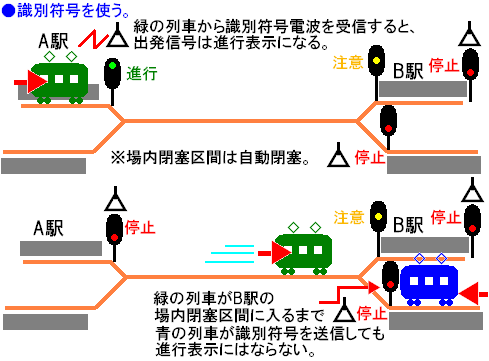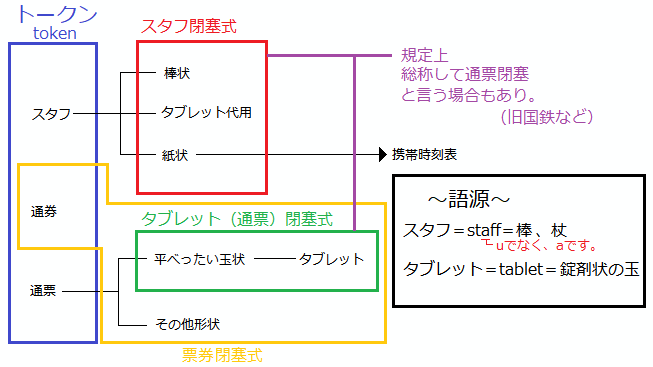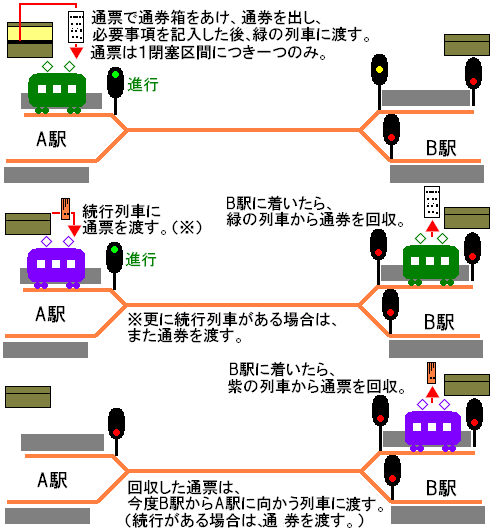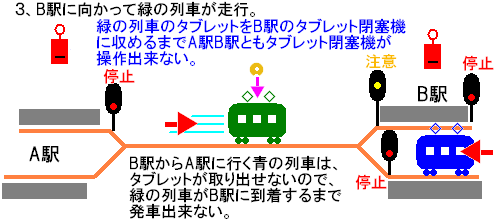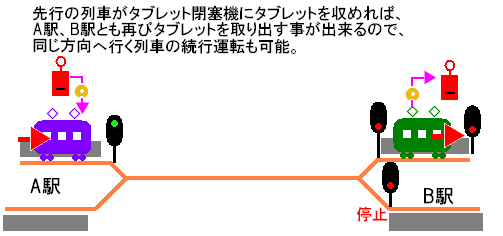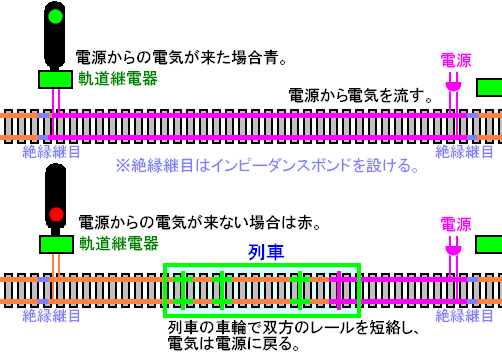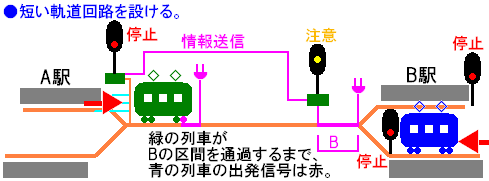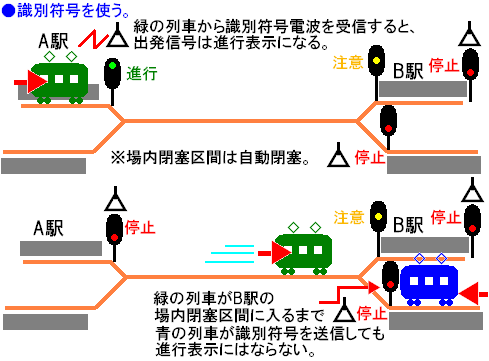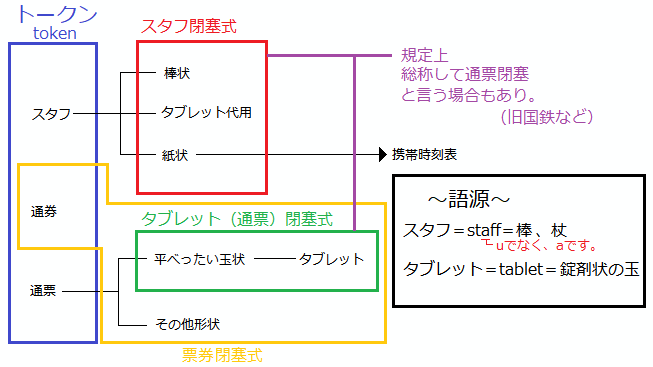電車の閉塞区間って何!?その2
3、非自動閉塞方式
閉塞方式には自動閉塞式と非自動閉塞式があります。
最近は殆ど自動閉塞式になっていますが、
本数が少ないローカル線などは、
設備を簡素化するために非自動閉塞方式を採用している路線があります。
3−1、スタフ閉塞方式
「スタフ」とは日本語で「棒」と言う意味で、
1閉塞区間につき1本しかない棒を使うことで、
1閉塞区間に走ることが出来る列車を1列車に限定すると言う、
極めて単純な閉塞方式です。

スタフ閉塞区間の場合、
1閉塞区間に1本しかないスタフを持っている列車のみ、
そのスタフの閉塞区間に入れるようにしたものです。
なので、運転士や駅員の人為的な過失がない限り、
スタフを持っている列車以外がその閉塞区間に進入することはありません。
なお、スタフは基本的にそのまま「棒」を使うのが基本ですが、
スタフ閉塞区間と票券閉塞区間、タブレット閉塞区間が隣接する場合、
いちいちスタフ閉塞用の棒を用意するのも面倒なので、
票券やタブレットで代用することがあります。
スタフ閉塞方式は極めて簡単で、
自動閉塞のような保守コストも殆どかからないのですが、
スタフが1本しかないと言うのが欠点で、
スタフが戻ってこない限り後続の列車を走らせることが出来ません。
そのため、上り下り列車を交互に走らせなければならないなど、
ダイヤ上の制約が出てしまいます。
しかし、上の図のような最終交換可能駅から先は終点も含めて1線しかなく、
行って戻ってくる1列車しか走りようがない閉塞区間は、
設備投資や保守コストを減らすため、
今でもスタフ閉塞方式を採用しているところがあります。
3−2、票券閉塞方式
スタフ閉塞式の場合、上り下り列車を交互に走らせなければならず、
同じ方向の続行運転が出来ません。
そのスタフ閉塞方式の問題点を補った方式が票券閉塞方式です。
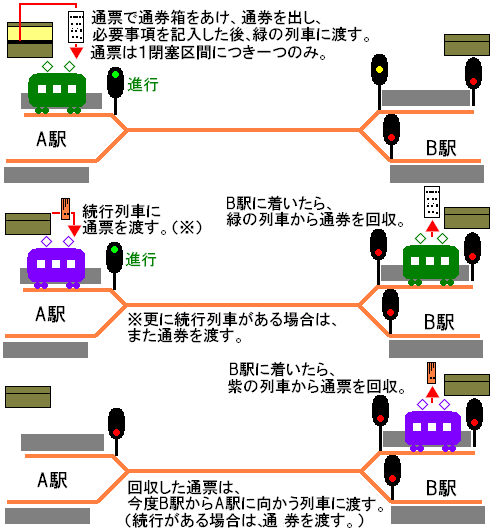
票券閉塞方式の場合、駅間閉塞区間の両端の駅に、
それぞれ、複数枚通券が入った通券箱を用意します。
通券箱は1閉塞区間に1つしかない通票でのみ開けることが出来ます。
続行運転がある場合、
出発駅の駅係員が通票で通券箱を開け、通券を取り出します。
その通券に必要事項を記入した後、
一番先に発車する列車の運転士に渡します。
通券を受け取った後、運転士は次の駅に向けて列車を発車します。
一方、次の駅側は通票が無いので、通券箱が開けられません。
そのため、次の駅側から列車を発車させることは出来ないので、
反対方向の列車がその閉塞区間に入ってしまう事は
人為的過失がない限りありません。
先行列車が次の駅に到着した後、
次の駅の係員は出発駅に先行列車が到着した事を連絡します。
そうしたら、出発駅側は後続の列車にも同じように通券を渡していくのですが、
続行運転が途切れる最後の列車には通券でなく通票を渡し、
次の駅側に通票をまわします。
次の駅側はその通票を持った列車が到着する事によって、
やっと通券箱が開けられるようになり、
反対方向の列車を走らせることが出来るようになります。
勿論、続行運転しない時は通券箱を開けず、
通票をスタフ閉塞のスタフのように使えばよいだけです。
票券閉塞は続行運転が出来るメリットがある他、
上下線で別の通券箱と通票を用意すれば複線でも使えるメリットもあるのですが、
通券に必要事項を記入する事務作業が煩雑になる欠点がある他、
通票と通券を間違えて渡したり、
使用済み通券を使用済み処理せず再利用すると言う、
人為的事故が起こりやすい欠点があります。
3−3、タブレット(通票)閉塞方式
タブレットは日本語で錠剤とか玉っころとか言う意味で、
1閉塞区間に一つしか取り出せない玉っころを使うことによって、
1閉塞区間に入る列車を1列車に限定する方式です。
タブレット閉塞方式はタブレット閉塞機と言う機械を使うので、
人為的事故をカバーすることが出来ます。

上の図で緑の列車がA駅からB駅に向けて出発したい場合、
A駅B駅双方の駅係員は連絡を取り合いながら
タブレット閉塞機と言う機械を同時に操作して、
A駅〜B駅間用のタブレットをA駅のタブレット閉塞機から1個だけ取り出します。
タブレット閉塞機にはいくつかA駅〜B駅間用のタブレットが入っているのですが、
取り出したタブレットをA駅またはB駅のタブレット閉塞機に収めるまで、
タブレット閉塞機を操作しても次のタブレットは取り出せません。

A駅のタブレット閉塞機からA駅〜B駅間用のタブレットを取り出したら、
緑の列車の運転士にそのタブレットを渡すのですが、
いかんせん小さい玉っころなので、落として無くす可能性が十分に考えられるため、
キャリアと言う肩掛けの収納部分にタブレットを収納してから運転士に渡します。
タブレットが収められたキャリアを運転士が受け取った後、
B駅に向かって緑の列車は発車します。
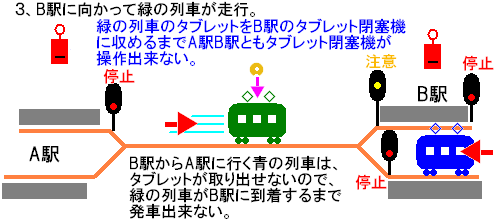
緑の列車がB駅に到着するまで、A駅もB駅もタブレットは取り出せないので、
A駅B駅間には上り下りとも緑の列車以外の列車が走ることはありません。
緑の列車がB駅に到着したら、タブレットをタブレット閉塞機に収めます。
そうしてやっと再びタブレット閉塞機を操作してタブレットが取り出せるようになるので、
反対方向の列車を走らせることが出来ます。
ただ、反対方向の列車の発車時刻に余裕が無い場合は、
緑の列車が持ってきたタブレットとキャリアを
そのまま反対方向の列車の運転士に渡します。
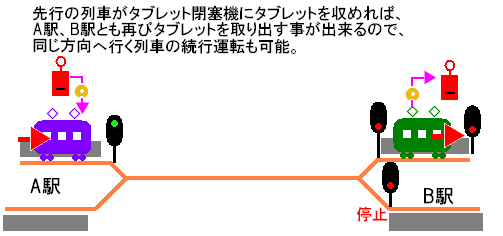
同じ方向の続行運転がある場合、
先行の列車が次の駅に到着した後、
先行列車が持っていたタブレットをタブレット閉塞機に収めて、
A駅B駅が再びタブレット閉塞機を操作すれば、
A駅から後続列車に渡すタブレットを取り出すことが出来ます。
タブレット閉塞方式は非自動閉塞方式の中では、
完全版と言えるものなのですが、欠点もあります。
先ず、通過列車の問題があります。
通過列車はいちいち駅に停車して、
駅員に前の区間のタブレットとキャリアを渡して、
次の区間のタブレットとキャリアを受け取る余裕は
無い(通過列車の意味が無い!?)ので、
駅ホームの進入側に受け器と言う、螺旋状に渦巻いている柱、
出発側にキャリアを取り付ける
腕(キャリアを取ると腕が下にさがる)のある授け器の柱を設けて、
駅進入時に運転士が列車を動かしたまま、
受け器に前の区間のタブレットが収められたキャリアを輪投げのように投げ込み、
そのあと窓から腕を前方に出して、
授け器から次の区間のタブレットが収められたキャリアを取ります。
(列車によっては車両側に授受用のキャッチ金具がある場合があります。)
駅構内は速度を落としているとは言え、
列車を動かしたままキャリアの授受を行なうのは非常に危険で、
慣れないとキャリアの授受に失敗して
軌道上にキャリアを落としてしまう可能性があります。
もう一つの欠点にタブレット閉塞機の操作に時間がかかり、
その間は他の駅務が全く出来ない欠点(しかも、閉塞区間両側の駅とも)があります。
昔はおおらかだったので、駅員がタブレット閉塞機の操作で券売業務が出来なくても、
客はそれが終わるまで待っていたのですが、
今は「客をほったらかして内部業務を行なっている!!」
という「お客さまの声」に繋がってしまう(客は全然事情を理解していないため)ので、
駅員が一人の駅は集中してタブレット閉塞機の操作が出来なくなってしまいました。
また、本来無人駅でもおかしくないような駅でも、
停車場であるばかりに駅員を配置しておかなければならず、
人件費もかかってしまいます。
そのため、貨物専用路線などを除くと、
タブレット閉塞方式は殆ど自動閉塞方式に変えられ、今では殆ど見られません。
4、自動閉塞方式
複線は駅間でも細かく閉塞区間が分けられていて、
とても駅の作業だけで閉塞区間の管理は出来ません。
そこで、登場するのが自動閉塞方式です。
単線の路線も非自動閉塞方式に携わる駅員の人件費を削減するため、
自動閉塞の採用が当たり前になっています。
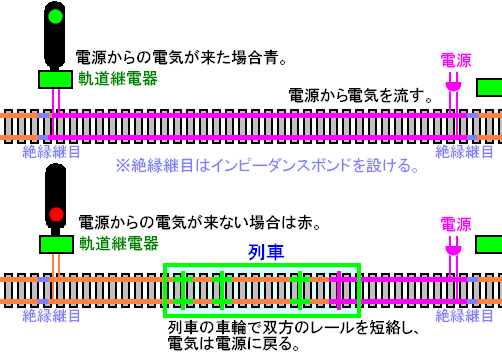
自動閉塞方式は閉塞区間の端から端まで左右双方のレールに電気を流し、
電気が端から端まで届いているか否かで
列車が閉塞区間内にあるかどうかを判定しています。
閉塞区間の入口に軌道継電器(軌道リレー)、出口に電源を設け、
電源側から軌道継電器に向けて電気をレールに流します。
(電気は直流電化区間の場合、
商用周波数=東日本50ヘルツ/西日本60ヘルツの交流電気、
交流電化区間の場合は帰線電流と混じらないようにするため、
25〜30ヘルツの周波数の交流電気を一般的に使っています。)
閉塞区間内に列車がない場合は軌道継電器まで電気が流れるので、
信号は「進行」現示(車上式は運転席の計器表示)をします。
一方、閉塞区間内に列車がある場合は、
列車の輪軸が左右双方のレールを短絡するため、
電気は輪軸を通って電源側に戻ってしまいます。
軌道継電器に電気が流れなくなると、信号の現示は「停止」になります。
この方式は閉塞区間に列車があるかどうかだけでなく、
レールが破損した場合も電気が軌道継電器に流れなくなるので、
レール破損による脱線事故を未然に防ぐ事が出来ます。
5、特殊自動閉塞方式
単線の場合も基本的には上の自動閉塞方式を使いますが、
駅間は交換所がない限り基本的に1閉塞区間なので、
列車が駅を発車して駅間閉塞区間に入った事さえ分かれば、
その駅間閉塞区間の端から端までの長い距離に電気を流す必要は無いので、
特殊自動閉塞方式が採用される場合があります。
5−1、軌道回路検知式特殊自動閉塞方式
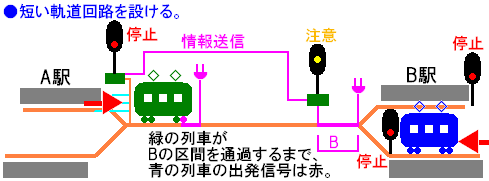
特殊自動閉塞方式には色々種類がありますが、
自動閉塞方式の基本である、レールに電気を流す方法を使うならば、
閉塞区間の入口と出口に短い距離の軌道回路を設けます。
閉塞区間の入口の軌道回路区間で列車が通り、
軌道継電器に電気が流れなくなったら、
その閉塞区間に入ったと言う判定になり、
出発信号は「停止」になります。
そして、その列車が閉塞区間出口にある軌道回路区間を通り過ぎるまで、
出発信号機は「停止」現示のままになります。
なお、この方式でも、
場内閉塞区間は通常通りすべて軌道回路の自動閉塞を使います。
5−2、電子識別符号式特殊自動閉塞方式
赤字ローカル線など、もっと設備を簡素化したい場合は、
電子識別符号を使う場合があります。
鉄道ファン内では一般的に「電子閉塞」と言っているものです。
電子識別符号方式は、場内閉塞区間はすべて軌道回路の自動閉塞にさせて、
駅間の閉塞区間だけ電子識別符号を使って、
その駅間閉塞区間の軌道回路を省略するものです。
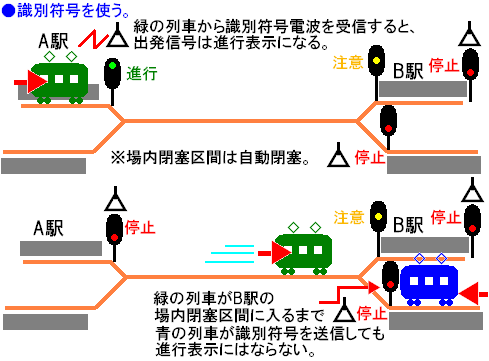
駅間の閉塞区間に入る前に運転士が閉塞区間の受信機に識別符号電波を送り、
その列車が駅間の閉塞区間に入る事を記憶させ、
出発駅の出発信号を「進行」表示させます。
そうすると、その列車が次の駅の場内閉塞区間に入るまで、
他の列車がその駅間の閉塞区間に入るために識別符号電波を送っても、
「進行」表示になりません。
なので、その閉塞区間に他の列車が入る事を防止する事が出来ます。
運転士が携帯している札状時刻表の「スタフ」とスタフ閉塞の「スタフ」
スタフと言うと、運転士が携帯している、
札状の時刻表を思い浮かべる方が多いと思います。
実は、スタフ閉塞の「スタフ」も、
札状時刻表の「スタフ」も元々は同じもの(staff/棒)から来ています。
両者の「スタフ」や「タブレット(通票)」は総称して「トークン」と呼ばれます。
トークンと言うと今でこそ認証パスワードに使用されている方もいるので、
薄々意味合いはお分かりになると思いますが、
通行許可証と言う意味です。
通行許可証で最初に使われたのが棒で、
それが「スタフ」の語源になりました。
通行許可証の棒は先端に運行区間が表示されていて、
その区間は走行して良いと言う意味合いがあります。
それが、紙になったのが、
今の札状時刻表の「スタフ」の最初という訳です。
ただ、現在、鉄道ファンでも混乱してしまう原因になっているのは、
自動閉塞化するにつれ、
紙の「スタフ」は単に運転士の携帯する時刻表になってしまったことです。
{staff(棒)かstuff(手回り品)か分からなくなる原因。}
そのため、スタフ閉塞を考えるときは、
札状時刻表の「スタフ」はまず別に置いといてから(別物として)考え、
あとから語源を遡る方がわかりやすいと思います。
スタフやタブレットに関しては、複雑な上、歴史上の経緯から誤解も多く、
鉄道ファン同士での激しい言い争い(炎上に近い)が絶えません。
しかし、その論争を私が拝見したところ、
決して双方とも間違ったことは言っていないのです。
大体は一部事象だけを見ていることによる、意見のズレや勘違いが殆どです。
そんな訳で、鉄道ファン同士仲良くなるよう、
わかりやすく下表にまとめました。
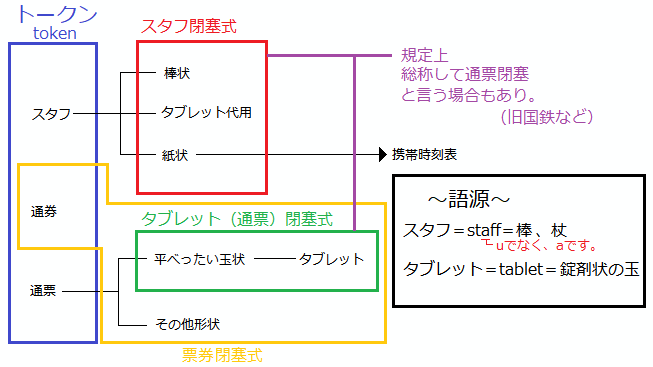
電車の保安装置って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|