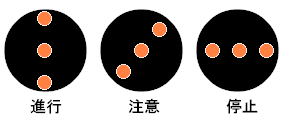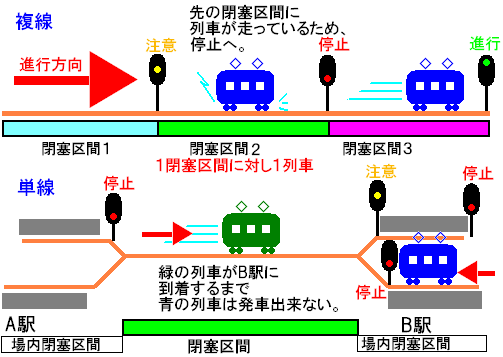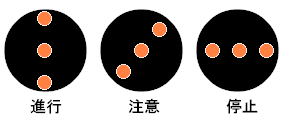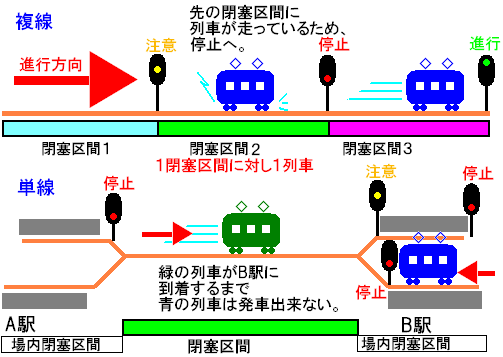電車の閉塞区間って何!?その1
交通標語に「車は急には停まれない。」と言うものがあるのですが、
鉄道車両に関しては、自動車よりもっと急に停まれません。
勿論、技術的には自動車並みの減速度にすることは可能なのですが、
そうすると、
立っている乗客が慣性の法則で進行方向に飛ばされて大怪我してしまいます。
そのため、鉄道車両の減速度は極めて低くしており、
運転士が前を走っている列車に気付いてブレーキをかけても間に合わず、
追突や正面衝突をしてしまうおそれがあります。
それを防止する方法として考え出されたのが、
閉塞(へいそく)区間と言うものです。
閉塞区間とは、駅構内及び、駅間を細かい区間に分けて、
その区間に入る列車の数を1列車に制限する事により、
追突、正面衝突事故を防ぐものです。
なお、閉塞の「塞」の字は常用漢字外漢字なので、
一般的には「閉そく」と書きます。
1、鉄道の信号機
鉄道の信号機は道路交通の信号機とは意味合いが異なっています。
そのため、道路交通の信号機とは切り離して考えるのが基本です。
前、ちょろっと書きましたが、鉄道の信号機は「青信号」とは言わず、
「緑信号」と言います。
そのため、アルファベットも「green」の「G」表示になっています。
鉄道の信号機は基本的に速度制限を表すもので、
「走ってよい」とか「注意しろ」とか「停まれ」とか言う
漠然なものを示すものではありません。
なお、鉄道において「信号無視」は大事故に繋がるので、
厳格に守らなければなりません。

鉄道信号は地上信号と車上信号の2つがあります。
ここでは、とりあえず地上信号の説明をしますが、
車上信号も考え方は同じです(次回の保安装置の項で詳しく説明)。
基本的には地上信号を採用するのですが、
列車の密度が高かったり、速度が速かったりする場合は、
沢山の信号表示パターンが必要になるため、
車上信号にすることがあります。
地上信号は二灯式から六灯式まであり、
多く表示をする必要がある信号ほど信号灯の数が多くなっています。
一番の基本は三灯式で、緑、黄、赤の3色がそれぞれ1灯あるものです。
で、先ず、緑信号ですが、
これは「進行」を表すものです。
しかし、「進行」と言う言葉は便宜的に付けているもので、
この信号にならないと進行出来ない訳ではありません。
また、「進行」だからと言って無制限に速度が出せるわけではなく、
その路線の最高運転速度または、制限速度以下で走らなければなりません。
なお、「進行」も速度制限があり、路線によって異なりますが、
概ね時速115キロメートル〜125キロメートルに設定されています。
大体の路線はその速度以下で走っているので、あまり気にならないのですが、
それ以上で走る路線は更に「高速進行」と言う表示を設ける場合があります。
次に黄信号ですが、これは「注意」を表すものです。
確かに「注意」現示(信号表示すること)は
「注意しよう」と言う意味合いがありますが、
この現示になった場合は、
指定速度制限以下に必ず落とさなければなりません。
これも路線によって異なりますが、
概ね時速45キロメートル〜55キロメートルに設定されています。
ただ、「進行」と「注意」の速度制限にはかなり開きがあり、
閉塞区間(この後説明します。)が短く、速い速度で走る路線の場合、
「進行」からいきなり「注意」になっても速度が落としきれない場合があります。
それを防止するため、「進行」と「注意」の間に「減速」を設ける場合があります。
「減速」は黄と緑の同時点灯で、
(2灯同時に点灯させる場合は、
視認性を上げるため、必ず2灯分間隔を開けて点灯させるようにする。)
概ね時速65キロメートル〜75キロメートルに設定されています。
それでも、「進行」で時速120キロメートルで走っている場合、
「減速」が時速75キロメートル設定でも時速45キロメートルの開きがあるため、
(速度が速いほど速度が落ちるまでの距離〜制動距離が長くなる。
そのため、高速域では制動距離を多く取らなければならない。)
「減速」の予告的に黄と緑を点滅させる、「抑速」を設ける路線もあります。
赤信号は道路交通の赤信号と同じく「停止」を表すのです。
「注意」と「停止」の間も時速45キロメートル程度の開きがあるため、
閉塞区間が短い路線は、間に「警戒」と言う黄の2灯表示を設けています。
警戒は概ね時速25キロメートル〜35キロメートルに設定されています。
〜〜〜〜〜
当たり前ですが、
信号機の速度制限と制限速度区間が被っている場合は、
速度の低い方を優先します。
例えば、制限速度時速25キロメートルの区間で、
信号機が「注意」現示になっていても、時速25キロメートル以下に落とします。
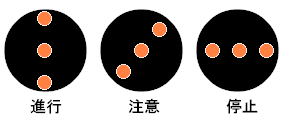
なお、カーブ区間などで通常の信号が視認しにくい場合は、
中継信号と言う信号を適宜設けます。
中継信号はこの先の信号表示を予告するものです。
なお、中継信号が縦1列点灯になっている場合は「進行」、
斜めは「注意(減速・警戒含む)」、横は「停止」をそれぞれ表しています。
2、閉塞区間とは
閉塞区間とは冒頭で申し上げました通り、
駅構内(交換所も含む)及び、駅間を細かい区間に分け、
その区間を走る列車を1本に限定する事ですが、
複線(複々線も含む)と単線では若干考え方が異なります。
なお、複数の閉塞区間に1列車がまたがることは可能で、
大都市圏の通勤路線ではよくあります。
その場合、
またがった閉塞区間双方ともその列車以外の列車を進入させることは出来ません。
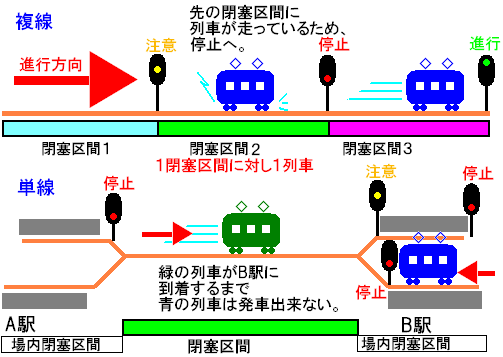
複線の場合、上下線は別の線路を走っているため、
起終点駅構内や折り返し駅構内を除くと、
正面衝突と言うことは、
運転士がいきなり列車をバックさせると言う暴挙に出たり、
脱線事故が起きたりしない限りありえません。
そのため、複線区間は追突防止のために閉塞区間が設けられています。
閉塞区間の間隔は列車密度(運転本数)が高いほど、
駅間距離が長いほど、
または、列車速度が速いほど細かく分けられています。
駅構内や交換所の場合は「場内閉塞区間」と言い、
駅間の閉塞区間と分けられています。
この「駅」と言うものが曲者で、
ここで言う「駅」は停車場のことで、停留場のことではありません。
停留場は駅間の閉塞区間の一部に入ります。
そう書くと、「停車場と停留場の違いは何だ!?」と言うことになってしまうのですが、
その答えが「停留場は場内閉塞区間を設けていない所です。」
と言ういつまでも解決しない回答になってしまいます。
まあ、完全とは言えませんが、停車場と停留場の見分け方は、
その駅構内で線路の分岐があるかどうか、起終点か中間駅かどうかで判断します。
中間の駅構内において分岐等が全くない駅は、「停留場」である場合が多いです。
(目の肥えた鉄道ファンの方々は、場内信号の有無で判断出来るようです。)
場内閉塞区間は、進入側に場内信号機、出発側に出発信号機があり、
場内が広い場合は、場内、出発信号機が多くなります。
場内信号機は進入列車の場内における進入予定の線に
他の列車がないかどうかを表示したもので、
進入予定の線にまだ他の列車がある場合は、場内信号は「停止」現示になります。
(場内信号が複数ある場合は、
他の列車の停車している場内閉塞区間までの数に応じて、
「注意」や「警戒」現示をします。)
出発信号機は出発列車が駅間閉塞区間、
または、駅間閉塞区間に入るまでに通る予定の場内の線に、
他の列車がないかどうかを表示したもので、
他の列車がある場合は「停止」現示になります。
ただ、場内信号機と出発信号機は、
先の閉塞区間に他の列車がなくても、
安全目的で「注意」とか「警戒」、「停止」現示になることがあります。
これは、更に先の閉塞区間で対向列車が通る可能性がある場合など、
様々な理由があります。
ところで、お子さまは「出発進行!!」と一単語のように言っていますが、
「出発進行」は厳密に言うと、「出発信号機の進行現示」を簡略化したものです。
なので、出発信号機が「注意」現示の場合は「出発進行」ではなく、「出発注意」になります。
一方、駅間の閉塞区間は先に書いた条件によって1〜多数に分割されていて、
複数閉塞区間がある場合は、「第○閉塞区間」と番号が振られています。
閉塞区間の境目には閉塞信号機があり、
通常は「進行」現示なのですが、
先行の列車が走っている閉塞区間に近付くにつれ、
「減速」「注意」・・・と速度制限の低い信号現示になり、
先行列車が寸前の閉塞区間を走っている場合は、
「停止」になって、列車は停止しなければならなくなります。
(停止しないと先行の列車に追突してしまいます。)
こういう状況になりやすいのが優等列車で、
先行の各駅停車に追いついてしまい、
なおかつ、各駅停車が優等列車の通過待ちの出来る駅が無いと、
絶えず信号機が「注意」とか「警戒」とか「停止」になり、ノロノロ運転になってしまいます。
また、先行の列車が何かの原因で遅れている場合もこのような状況になります。
〜〜〜〜〜
単線の場合、場内閉塞区間の考え方は同じなのですが、
駅間の閉塞区間は間に交換所・信号所がない限り、
基本的に1閉塞区間のみになります。
ただし、単線でも続行運転の本数が多い場合は、
複数の閉塞区間に分ける場合があります。
その場合の考え方は複線の閉塞区間と同じになりますが、
上り列車続行の場合下り列車、下り列車続行の場合上り列車は、
反対方向の列車がすべて駅間の閉塞区間から出るまで、
出発信号機は「停止」表示で、駅間の閉塞区間に入る事は出来ません。
単線の閉塞区間は主に正面衝突防止目的で設けられていて、
駅間の閉塞区間を1つにすることによって、
駅間の走行列車を1列車に限定し、
上下線それぞれの列車が同時に同じ区間を走って、
正面衝突することを防止しています。
電車の閉塞区間って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|