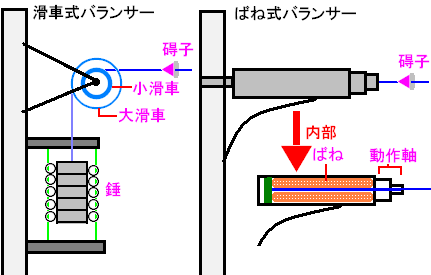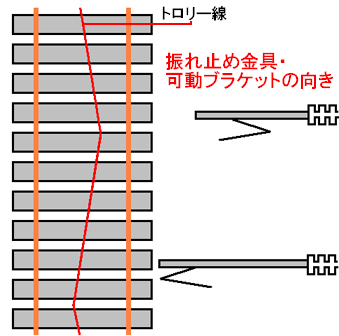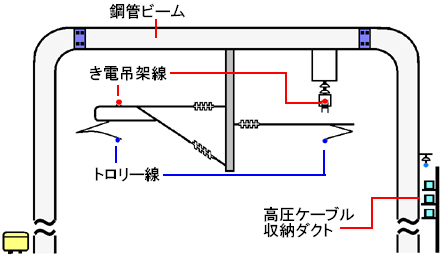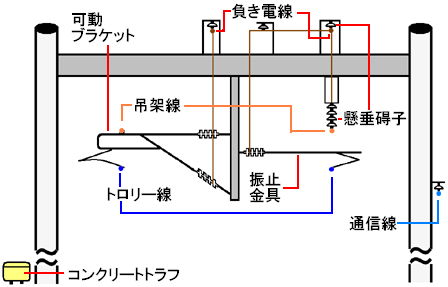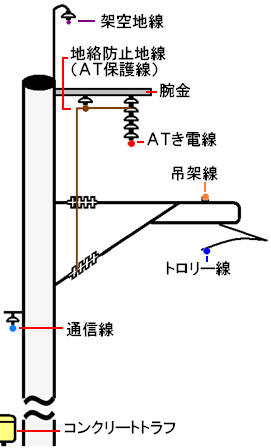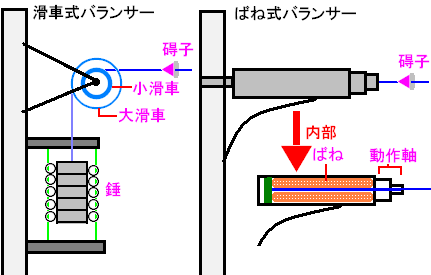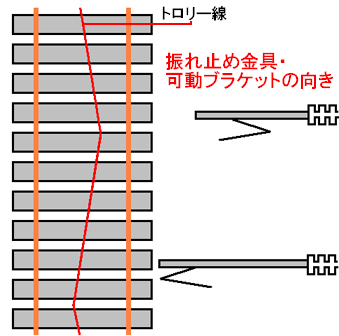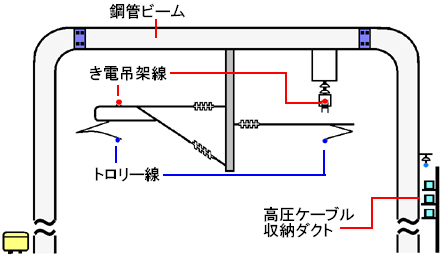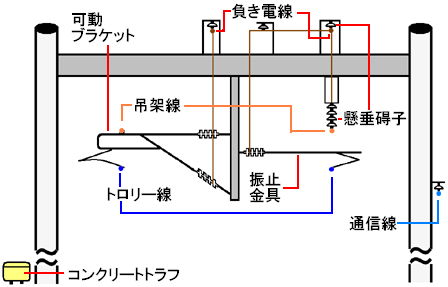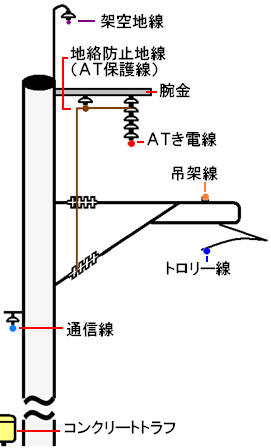電車の架線設備って何!?その3
5、テンションバランサー
架線は寒暖の差で膨張、収縮します。
膨張をほったらかしにするとトロリー線がたるんでしまい、
パンタグラフが通過すると激しいバウンドを起こします。
そうすると、パンタグラフからトロリー線が離れ、せん絡放電が起こり、
パンタグラフやトロリー線を傷めることになります。
逆に収縮をほったらかしにすると、トロリー線が必要以上に緊張してしまい、
ブツっと切れてしまいます。
それらを防止するためにトロリー線を一定の緊張(テンション)に保つよう、
吊架線とトロリー線の終端部分ではテンションバランサーが使われます。
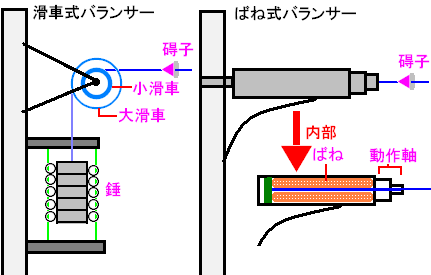
テンションバランサーは滑車式とばね(スプリング)式があります。
滑車式テンションバランサーは小滑車にトロリー線、
大滑車に錘(ウエイト)を吊り下げるワイヤーを取り付けます。
小滑車と大滑車の比率は1:4になっていて、
僅かな錘でも重たいトロリー線を引っ張る事が出来ます。
(トロリー線と錘を吊り下げるワイヤーの滑車を逆にすると、
1回転で多くのトロリー線を巻くことが出来るのですが、
錘はかなり重たくしないといけません。)
滑車式テンションバランサーは構造が簡単なのですが、
錘の重さの調整に手間がかかるので、
ばね式バランサーに交換されつつあります。
ばね式バランサーは文字通りばねの力でトロリー線の緊張を保つものです。
ばね式のばねは二重構造になっていて、
必要以上にテンションバランサーの装置が長くならないようにしています。
滑車式、ばね式何れもテンションバランサー側に張力が働くので、
テンションバランサーを取り付ける架線柱は支線や支柱を設けて、
強度強化をする必要があります。
6、ジグザグ偏位
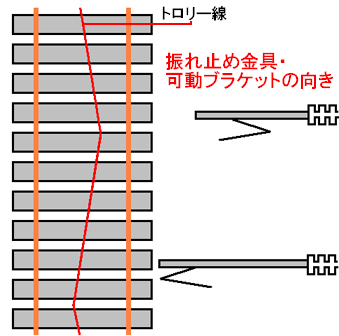
集電装置の所で書きましたが、
パンタグラフの摺り板部分が偏って磨耗しないよう、
トロリー線はジグザグに張られています。
そのジグザグをジグザグ偏位と言います。
上の図は誇張表現していますが、
ジグザグの幅は約200ミリメートルと定められています。
トロリー線をジグザグにするために、
振れ留め金具や可動ブラケットの振れ留めアームは、
ほぼ1本毎に接続部の向きが変わっています。
7、装柱
架線柱にビームややぐらなどの腕金、碍子、
可動ブラケットなどを取り付ける事を装柱と言います。
7−1、直流電化方式の装柱(従来型)

直流電化の場合、吊架線やトロリー線の他にき電線が必要になります。
き電線はビーム上にやぐらと言う四角状に組んだ腕金を設けて、
そこに1〜2連の懸垂碍子を吊り下げて支持したり、
架線柱に腕金を取り付け、それに懸垂碍子を吊り下げて支持したりしています。
き電線は最低1本は必要で、
上下線で電気の流している方向が異なる場合は2本以上あります。
なお、電車の本数が少なく、
そんなに電気を消費しない区間はき電線を設けない場合もあります。
き電線の他にも高圧配電線と言う3相交流3線または単相交流2線、
電圧6600ボルトの線があります。
高圧配電線は駅などの照明や
エスカレータ、エレベータなどの各機器に使う電気や、
信号機などの運転上に必要な機器の電気(これらを付帯電力と言います)を
供給する線です。
ただ、付帯電力を電力会社の配電線から直接受けている場合は、
高圧配電線を設けていません。
図ではやぐらから懸垂碍子2連で吊り下げていますが、
地方の民鉄などは懸垂碍子ではなく、
昔ながらのピン碍子を使っている所があります。
また、最近は落雷対策のため、クランプ碍子を使う所も出ています。
配電線の線は細いため、落雷による断線の危険があります。
そのため、配電線の上に架空地線という線を設け、
その線に雷が落ちるようにしています。
しかし、必ず架空地線に雷が落ちるとは限らないので、
架空地線はお守り程度のものになっています。
なお、高圧配電線はCVTやCVなどの高圧ケーブルにする場合があります。
高圧ケーブルの場合、絶縁を強化するため、
架橋ポリエチレンを多く使っているので、
ケーブル自体のコストがかかってしまいますが、
装柱を単純化出来るので、空間に余裕がない場合は高圧ケーブルを採用しています。
吊架線はビームから吊り下げた下束または架線柱に可動ブラケットを取り付け、
その可動ブラケットに吊架線を取り付ける場合と、
ビームから懸垂碍子を1〜2連吊り下げ、
そこに吊架線を取り付ける場合があります。
可動ブラケットはそれ自体で張力調整が出来る利点の他、
ブラケットが180度動くので(だから「可動」なのですが・・・。)、
架線の架け替えも楽に出来ます。
ただ、ビームを使う場合、ビームの高さが高くなってしまうので、
それに伴って架線柱も高くしなければならない欠点があります。
また、可動ブラケットは重いので、架線柱やビームを強化する必要があります。
なので、ある程度高速運転を考慮している場合は可動ブラケット、
装柱の簡素化を主眼にする場合は懸垂碍子支持を採用するのが一般的です。
可動ブラケットを使った場合のトロリー線接続は、
それに付いている振れ留めアームの先端にします。
一方、懸垂碍子支持の場合、下束に振れ留め金具を取り付け、
それにトロリー線を接続していますが、
直線区間など、トロリー線の振れが小さい場合は、
振れ留め金具を省略している所もあります。
通信線は架線柱に腕金を取り付け、
そこに同軸ケーブルなどのケーブルを取り付ける場合と、
コンクリートトラフと言うコンクリート製の蓋付き側溝の中に収納する場合があります。
架線柱に取り付けるのは主に列車自体の通信(誘導無線)、
コンクリートトラフは保安装置の通信線や
駅同士の通信線を収納していることが多いです。
7−2、直流電化方式の装柱(インテグレート型)
インテグレート(integrate)は日本語にすると、
「統合する」、「まとめる」と言った意味で、
今までバラバラに装柱されていた、
き電線、高圧配電線、吊架線、トロリー線、通信線などを極力まとめて、
景観を良くし、保守の省力化を目指した装柱です。
この装柱は近年採用が増えています。
インテグレート型装柱(インテグレート架線装柱とも言います。)には
以下のガイドラインがあります。
1、今まで別々にあったき電線と吊架線を一体化し、き電吊架線にする。
2、トロリー線をヘビー(重量)化し、極力シンプルカテナリーにする。
3、架空式の高圧配電線をケーブル化し、
地面付近に設けたケーブル収納ダクトや電線管、コンクリートトラフに収める。
4、同じく通信線も光ファイバなどに交換し、コンクリートトラフに収める。
5、ビームや架線柱はトラスではなく、平滑な鋼管を使い、見た目を良くする。
6、高圧配電線の変電設備はキュービクル化する。
交流電化もインテグレート型装柱のコンセプトが採用されていますが、
上記ガイドラインの「1」は出来ません。
交流き電方式の負き電線やATき電線はトロリー線と電圧が異なる他、
電気の流れも逆です。
そのため、短絡しないよう、吊架線とトロリー線を結ぶハンガーには、
沢山の碍子を挟む必要が出てしまいます。
そうすると、かえって設置コストがかかってしまう他、
架線が必要以上に重たくなってしまいます。
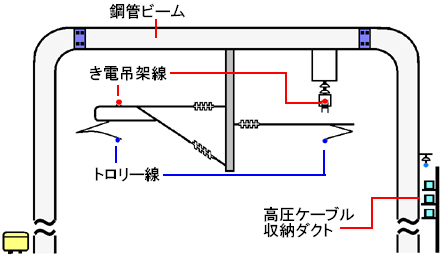
直流電化のインテグレート型装柱の場合、
き電線と吊架線を一体化したき電吊架線(フィーダメッセンジャー)を使います。
そのため、変電所付近を除いて、
き電線を別途支持するやぐらなどを設ける必要はありません。
高圧配電線もケーブル化し、
線路脇の収納ダクトや電線管、コンクリートトラフに収めるので、
それを支持するやぐらなどは同じく必要ありません。
上空部分にき電線と配電線がなくなるので、
すっきりした装柱になります。
ただ、インテグレート型装柱の問題は、高圧配電線が下にあることです。
線路際に高圧配電線のケーブルを収める収納ダクトや電線管を設けてしまうと、
線路横の道路を通っている通行人が偶発的、
または故意に触ってしまう危険があります。
それ以外にも保線作業員が不用意に触れてしまう
(または工事道具をぶつけてしまう)可能性もあります。
そのため、高圧配電線を収める収納ダクトや
電線管の位置は考えなければなりません。
また、先に書いた通り、
き電吊架線は交換時にかえってコストがかかる問題があります。
7−3、BT交流き電方式の装柱
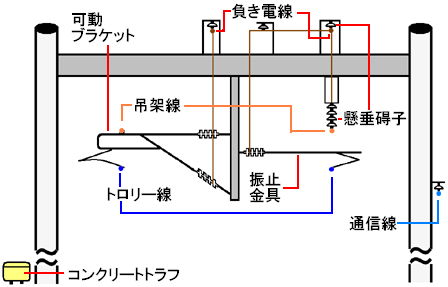
上の図では高圧配電線を省略していますが、
交流電化区間でも高圧配電線を設ける場合があります。
直流装柱と異なるのは、吊架線を懸垂碍子で支持する場合です。
交流電化は電圧が高いため、懸垂碍子を多く繋げる必要があります。
直流電化の場合、懸垂碍子は1〜2連で済むのですが、
交流電化の場合は3〜4連(新幹線は5〜6連)繋ぎます。
また、可動ブラケットや振れ留め金具の長幹碍子は、
直流電化のものより太くて長いものを使います。
一方、BT交流き電方式にある負き電線は電圧が低いため、
懸垂碍子は1個だけで済みます。
負き電線は吊架線を支持する懸垂碍子や、
可動ブラケットなどの長幹碍子にも接続し、
地面に電気が漏れ出る「地絡事故」を防止するようにしています。
7−4、AT交流き電方式の装柱
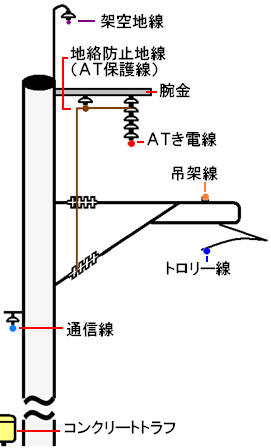
AT交流き電方式にはATき電線があるのですが、
ATき電線は電圧がかなり高いため、
懸垂碍子をいくつも繋げて支持しています。
(東海道新幹線は腕金と碍子が一体化したものを一部で採用。)
直流のき電線は太いので、雷で断線する可能性は低いのですが、
ATき電線は細いので、雷で断線する可能性が高いです。
そのため、AT交流き電方式の場合、架空地線を設けることが多いです。
地絡防止地線はBT交流き電方式で言う、負き電線にあたる線なので、
この線の支持は懸垂碍子1個で済みます。
地絡防止地線は吊架線やトロリー線を支持する可動ブラケットの長幹碍子や懸垂碍子、
ATき電線を支持する懸垂碍子に接続し、
地絡事故を防止しています。
なお、インテグレート型装柱の場合、
この地絡防止地線からの接続線を鋼管柱の中に収めて、
「接続線がだらっと垂れ下がった見苦しい感じ」にならないようにしています。
電車の閉塞区間って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|