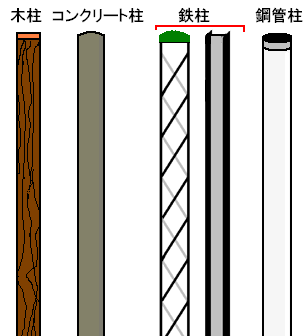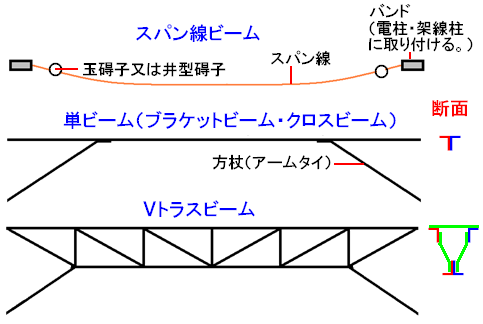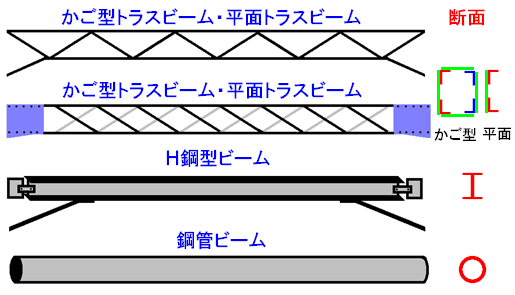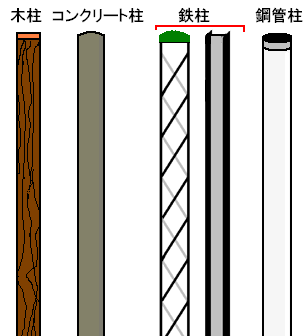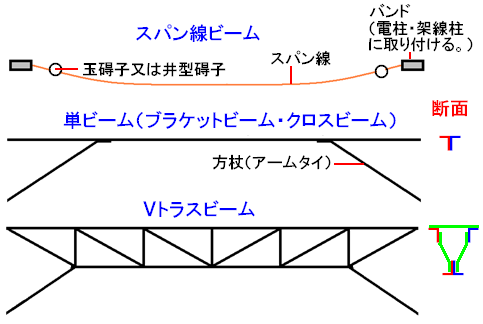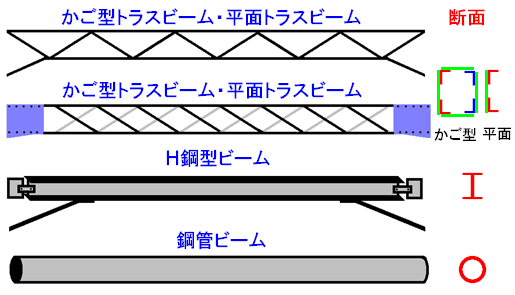電車の架線設備って何!?その1
電車は電線から電気を集電して走らせています。
また、鉄道通信用に通信電線や光ファイバを各所に使っています。
「架線」とはこういった電線や光ファイバなどを設置することを言います。
なお、正しい日本語で言うならば「架線」は、「かせん」と言うのですが、
工事関係者の方は他の用語(線路を架ける架線、河川など)と混乱しないようにするため、
「がせん」とあえて言っています。
鉄道ファンは普通に「かせん」と言っても問題はないのですが、
細かい事に拘る鉄道ファンと話す時は、その会話者に従った方が無難です。
1、鉄道架線柱
電気が流れている電線を地面にボトっと置いておく訳にはいかないので、
何かしらの柱を建てて、それに電線を支持させます。
その柱のことを一般的には電柱と言うのですが、
鉄道の場合、鉄道架線柱(略して単に架線柱とも言う)と言います。
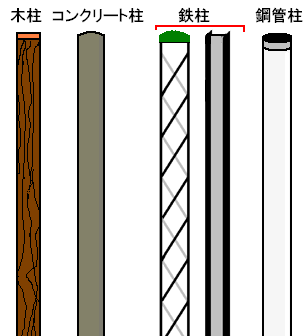
鉄道架線柱は色々あるのですが、
大きく分けて、木柱、コンクリート柱、鉄柱、鋼管柱、鉄塔があります。
木柱は昔からあるもので、
腐らないようにクレオソート(石炭のかすであるコールタールを蒸留したもの)を
しみこませています。
このクレオソートは発がん性物質なので、現在は一般的に使われていませんが、
新規に木柱を建てる所は殆どないので、特に問題はありません。
(まあ、木柱を舐めたり食べたりしなければ大丈夫です。
触った場合は必ず手を洗います。)
既存の木柱もコンクリート柱や鉄柱、鋼管柱に交換されつつあり、
大都市近郊の通勤路線では先ず見ることがないと思います。
そのため、残っているところは地方の民鉄が中心です。
コンクリート柱は鉄道架線柱で最も多く使われているものです。
コンクリート柱は頑丈でコストも安く、長持ちするのですが、
重量が重いため、橋梁など強度が弱いところでは使用出来ません。
なお、コンクリート柱は規格品の円筒基礎の中に建てて、
砕石または、コンクリートを流し込んで設置します。
鉄柱は橋梁や高架橋など、コンクリート柱が建てられない所に主に使います。
鉄柱は手入れさえしっかりやれば、概ねコンクリート柱より長持ちするので、
架線柱をちまちま交換出来ない場所でも使われています。
ただ、鉄柱は錆びるので、定期的に塗装の塗り替えが必要となるため、
保守コストがかかります。
また、鉄柱の設置は基礎をコンクリートで打設する必要があるので、
設置にも手間がかかります。
鋼管柱は字の通り管になっている鉄柱です。
従来の鉄柱に比べ細かいトラスなどの造形がないため、
塗装の手間を削減出来る他、
景観にも優れているので、最近は採用が増えています。
しかし、鋼管柱も錆びるので、定期的な塗装が必要になります。
2、ビーム、ブラケット
ビームは架線柱に取り付けるもので、
電線を支持する碍子(がいし)や可動ブラケット(単独線支持は除く)などは、
そのビームに取り付けます。
ビームを二つ以上の架線柱に橋渡しにすれば、
架線柱の張力による傾きや歪みを防止する事が出来ます。
(ただし、スパン線ビームは除く)
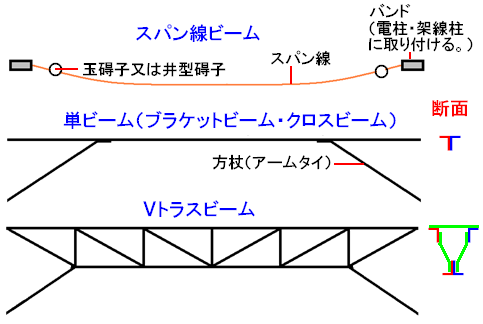
ビームは色々種類があるのですが、
一番単純なビームはスパン線ビームです。
スパン線ビームとは、架線柱または電柱同士をワイヤで結んで、
そのワイヤからトロリー線などを吊るすものです。
ワイヤとトロリー線を繋ぐ金具には絶縁性がないので、
ワイヤの両端や中間に玉碍子や井型碍子などの碍子を挟みます。
(碍子は電線を支持する目的の他、絶縁する目的もあります。
碍子がないと架線柱や電柱をつたって電気が漏電してしまいます。)
スパン線ビームの構造はいたって単純なのですが、
バウンドが強く、風などの影響でグラグラ揺れてしまうので、
パンタグラフがトロリー線から離線してしまう可能性が高くなります。
そのため、高速で運転する箇所には不適です。
スパン線ビームは主に高速で走らない路面電車などで採用されていますが、
スパン線ビームを使うと街の景観がワイヤでごちゃごちゃしてしまうので、
徐々にスパン線ビームからセンターポール式に交換されつつあります。
単ビームは二つの山型鋼材を重ね合わせたシンプルなビームです。
二つ以上の架線柱同士を橋渡しにしない片持ちの場合は、ブラケットビーム、
橋渡しにする場合は、クロスビームと言います。
ブラケットビームで支持出来るのは1線分で、
それ以上の線を支持してしまうとビームが折れたり、
過度な張力で架線柱が歪んだり折れたりしてしまうので、
2線以上支持する場合は(やむを得ない場合を除いて)必ずクロスビームにします。
また、クロスビームにしても、何線分も支持してしまうと、
碍子や吊架線、トロリー線の重みでビームが歪んでしまいます。
また、可動ブラケットは重たいので、クロスビームで支持するのは不適切です。
クロスビームは方杖を設けることである程度強度を強化出来ますが、
普通は多くても3線くらいが限界のようです。
Vトラスビームは(トラスとは三角に組んだ構造物のこと)、
中心に向かってVの字状のトラスで組んだビームです。
山型鋼材三つを三角状に縦材や斜材で結ぶ事により、
強度強化しています。
クロスビームより強度があるので、
複線区間や駅構内で多くの線を支持する場合は、
Vトラスビームを多用しています。
最近のH鋼ビームや鋼管ビームに比べると縦材、斜材のボルト固定箇所が多く、
その部分を中心に腐食しやすいので、
塗装をこまめにしなければならないと言う欠点はありますが、
そこそこの重量で強度が保てるので、
現在でも多くの路線で使われています。
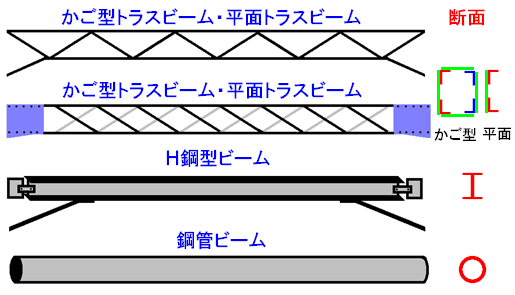
二つの山型鋼材を波状のトラスで結んだビームを平面トラスビームと言います。
平面トラスビームはトラスが細かくなってしまうのですが、
Vトラスビームより上下寸法を小さく出来るので、
上下寸法や架線柱の高さに限界がある場合は、
平面トラスビームを使います。
平面トラスビーム二つを結んで四角形断面にしたビームを
かご型トラスビームと言います。
かご型トラスビームはかなり強度が高いので、
沢山の線を支持することが可能な他、
変電所から出た多くのき電線を支持する場合にも適しています。
ただ、かご型トラスビームは鳥にとっては楽園なのか、
ビームの中に巣を作ってしまうことが多々あります。
鳥が巣を作るとフンや巣に使った金屑などがトロリー線やレールに付着し、
漏電や車輪のスリップと言う事故を招いてしまいます。
また、沿線の住宅にも鳥が飛び交う事になり、
フンや鳴き声などで付近の住民に迷惑をかけてしまうことになります。
そのため、かご型トラスビームに網を被せて
鳥が巣を作らないようにしている所もあります。
H鋼型ビームはH鋼材を使うことによってボルト固定箇所を減らし、
保守省力化を目指したビームです。
最近は更にボルト箇所を減らした鋼管ビームが主流になっているので、
H鋼型ビームの使用は減っているのですが、
簡易的に設置出来る利点があるので、
H鋼架線鉄柱とともに、工事中区間で仮設として使うことがあります。
鋼管ビームは最近主流のビームで、
ボルト固定箇所を大幅に減らし、保守省力と景観向上を目指しています。
鋼管ビームはインテグレート架線区間などで多用しています。
鋼管はそのまま円筒なので、強度も高く、
多くの線を支持することが出来ます。
ただ、欠点として鋼管ビームは重たいので、
設置時に手間がかかる場合があります。
そのため、鋼管ビームの改良型として、
細い鋼管を鋼管トラスで組んだ平面トラスビームが登場し、
多くの線を支持する必要のある場所で使われています。
なお、架線柱とビームを共に鋼管にして一体化した場合、
そのボルト接続面を中心に腐食しやすい欠点があることが分かったため、
コンクリート柱を使える場所はコンクリート柱に鋼管ビーム固定にして、
架線柱とビームを鋼管で一体化するのは、
橋梁や高架などに限定するようにしています。
電車の架線設備って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|