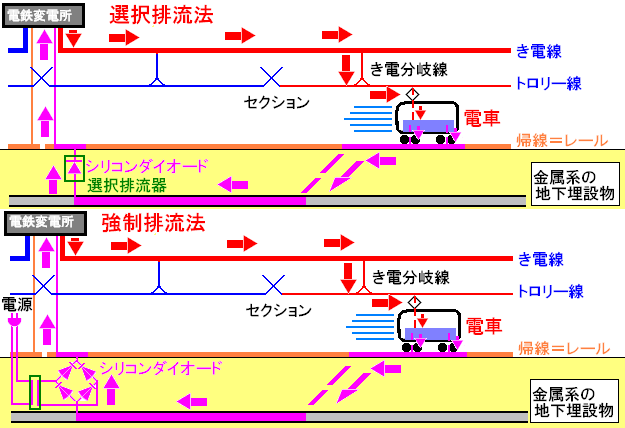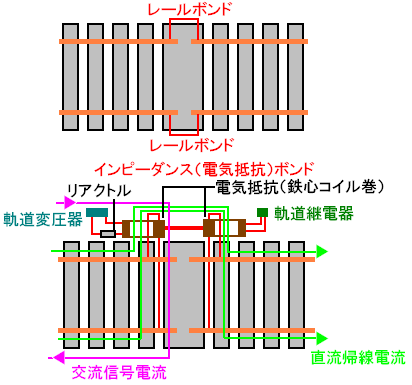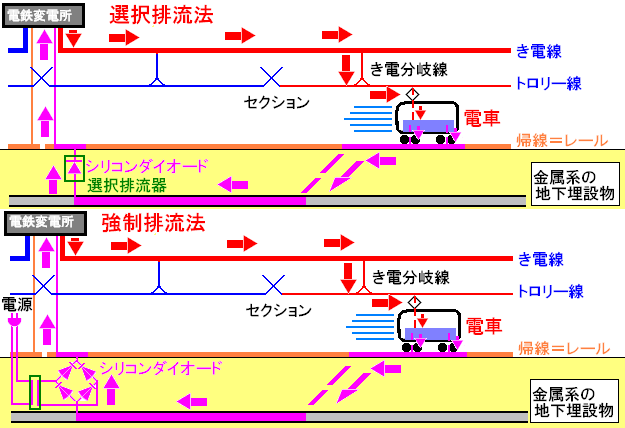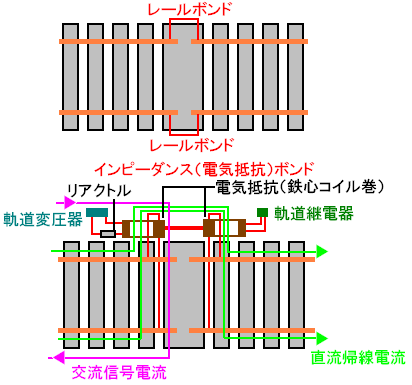電車の電化方式って何!?その3
5、架空地線
落雷対策のため別途架空地線という架線を張る場合があります。
雷は一番高いところに落ちる性質があるので、
架空地線は他のどの電線よりも上に張る必要があります。
ただ、架空地線に絶対雷が落ちるかと言うと、
その確率は低いので、
採用は路線、鉄道会社によってまちまちです。
架空地線は等間隔で接地(地面に接続する事=アース)していて、
そこから落雷電流が地面に放出するようになっています。
6、電食
電気は自分の流れている導体より流れやすい金属物質があると、
そちらの方に流れてしまうと言う性質があります。
しかし、その金属物質は電気を流す事を意図している訳ではないので、
電気が流れる事によって金属物質に錆などの腐食が発生する事があります。
その現象を電食と言います。

帰線電流はレールを伝って電鉄変電所に戻ります。
帰線電流が言う事を聞いてちゃんとレールに流れてくれれば良いのですが、
道床近くの地下により流れやすい
金属系の埋設物(水道管、ガス管、電線管など)があると、
そちらの方に移って流れてしまうことがあります。
そうするとその埋設物が錆びて腐食してしまいます。
また、その埋設物に磁力が発生するので、
その付近の磁気を測定している場合、そのデータが狂ってしまうことがあります。
交流電化の場合はレールに流れた帰線電流を吸い上げてしまうので、
電食が起こる確率は低いのですが、
直流電化の場合はその機能がないため、対策が必要になります。
なお、電食が起こりやすいパターンはレールに抵抗要素が入っている場合が多く、
代表的なものにレールの継目があります。
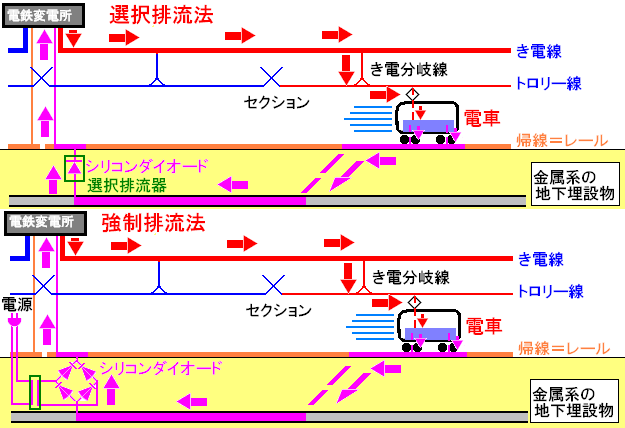
電食を起こさせないようにするには、
道床に絶縁物を挟むと言う方法があります。
道床がコンクリートならレールと地面が完全に絶縁出来ますが、
既存のバラスト軌道でそれを行なうのはあまりにも非現実的です。
それ以外にも、意図的に地中により電気が流れやすい物質を埋めたり、
帰線電流専用の電線を別途設けたり、
電鉄変電所の間隔を短くして
電食のチャンスを減らす(JR内房線など)方法があります。
しかし、それらの方法はコストがかかってしまうので、
一般的には排流器を設ける場合が多いです。
排流方法は直接排流法、選択排流法、強制排流法があるのですが、
そのうち、埋設物とレールを直接結ぶ、直接排流法は電気設備規定で禁止されています。
これは、電食が起こらなかった場合、
逆に帰線電流を埋設物に流してしまうということになってしまう他、
電気の流れる方向が定まっていないので、
埋設物に流れた帰線電流が必ずしもレールに戻ってくるとは限らないからです。
選択排流法は埋設物とレールを結ぶ線の間に排流器と言う機器を挟む方式です。
排流器にはダイオードが入っていて、
ダイオードは一方向にしか電気を流さない性質があるため、
ダイオードの流れる方向をレール方向にすれば、
埋設物に流れた帰線電流をレールに戻す事が出来ます。
強制排流法は強制排流器を挟む方法で、
強制排流器を電源(家庭で言うコンセントにあたるもの)に接続すると、
ダイオード及び、その電源からの電気の流れに乗って、
埋設物に流れた帰線電流が確実にレールに戻ってきます。
ただ、この方法は通信機器に影響があるので、
場合によってはその対策が必要になります。
7、電気的接続
レールにはどうしても継目が必要になります。
レールを帰線にしている場合、その継目で何もされていないと、
先に書きました、電食と言う問題が出てしまいますし、
電食が起こらない場合は、電気自体が流れないと言うことになってしまいます。
そこで継目の所にはボンドと言う電気的接続が必要になります。
「ボンド」とは工作で使うボンドと同じ意味で、
「接着するもの」「接続するもの」と言う意味があります。
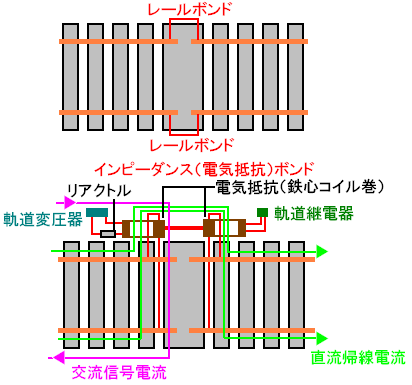
レールの継目は色々な理由で設けられるのですが、
レールの長さの問題やレールの伸縮の問題、
工事区分の関係で設けられる継目はレールボンドが使われます。
レールボンドの構造は簡単で、
それぞれのレールをレールボンドで接続するだけです。
一方、継目の目的が、
レールに流れている信号電流を遮断する目的の絶縁継目の場合、
それを通常のレールボンドで結んでしまうと、
その信号電流もレールボンドを通って流れてしまいます。
そうすると保安装置等が誤作動してしまい、
「進行」の筈なのに、信号が「停止」信号のままで
変わらなくなると言う問題が出てしまいます。
これは絶縁継目に金属製の電車車輪が通り、
それぞれのレールの回路が接続されたかどうかで
電車の通過を判定しているからです。
そのため、レールボンドにより常時回路が接続された状態にしてしまうと、
その継目を電車がずーと途切れることなく通っていると言う判定になってしまいます。
そのため、絶縁継目の所ではレールボンドが使えません。
交流き電方式の場合は、絶縁継目の前に吸い上げ線を設け、
帰線電流を吸い上げてしまえば良いのですが、
(信号の交流電気と運転用の交流電気は周波数が異なるので、
信号の電流は吸い上がらない。)
直流き電方式の場合は、
絶縁継目でも帰線電流を流せるようにする必要があります。
そこで使われるのがインピーダンス(電気抵抗)ボンドと言うものです。
インピーダンスボンドとは、
絶縁継目を挟んだ双方のレール区間の左右のレールを、
電気抵抗を挟んだ回路で結び、
それぞれの電気抵抗の中点同士を接続回路で結ぶと言うものです。
このインピーダンスボンドを設けることによって、
交流の信号電流は遮断され、
直流の帰線電流のみ流れるようになります。
電車の架線設備って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|