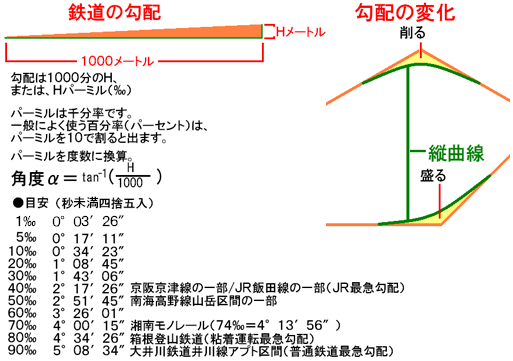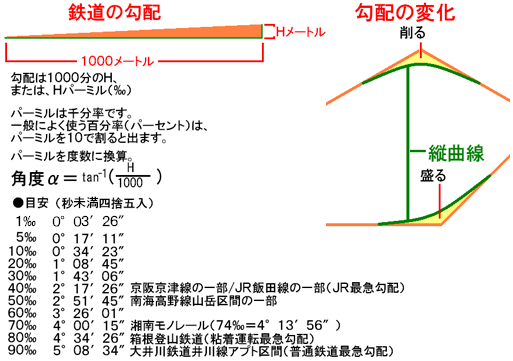電車の線路曲線って何!?
日本は地形的に厳しいところが多く、
そうでないところでも住宅が密集していてなかなか直線の線路を敷くことは困難です。
そのため、どうしても要所要所でカーブが必要になるのですが、
鉄道の車輪は狭いレールの上に乗っているだけなので、
このカーブの設計を誤ると脱線転覆の危険性が出てしまいます。
そのため、線路のカーブ設計には複雑な要素が必要になります。
1、曲線と踏面

普通鉄道の軌道は左右にそれぞれレールがある訳なのですが、
カーブの区間の場合、
カーブ内側のレールよりカーブ外側のレールの方が長くなっています。
これは、外側のレールの方が内側のレールより曲線の半径が大きくなっているためで、
半径が大きくなれば当然直径も大きくなり、カーブの円周も大きくなります。
鉄道の車輪がレールと接触する部分を踏面と言うのですが、
この踏面が平滑で車輪の円周が一定だと、
カーブ外側のレールを走る車輪の方がだんだん遅れていき、
ひいては脱線してしまいます。
これは、自動車のタイヤのようにカーブ外側の車輪がたわまないからです。
しかし、うまい具合にカーブを走るとカーブ外側の方向に遠心力が働くので、
車輪内側(二つのレール内側方向)のフランジに向けて、
だんだん車輪の円周が長くなるように踏面を造ると、
カーブ外側に接する車輪は、
遠心力でフランジよりの円周が長い部分の踏面に接触することになり、
逆にカーブ内側の接する車輪は、
遠心力でフランジから離れた円周が短い部分に接触する事になります。
このことにより、
カーブ外側の車輪の方がカーブ内側の車輪より長くレールに接する事になり、
外側の車輪の遅れが無くなります。
2、カント
鉄道車両で厄介なのは、
自動車などと比べて重心が高いことです(車体の高さが幅に比べて高いため)。
そのため、カーブ区間では遠心力の影響を多く受けて、
カーブ外側に脱線する危険性が高くなります。
これを防止するのがカントと言うものです。

カントとはカーブ外側のレールを高くして、
カーブ内側のレールを低くするものです。
カントが無いと高速で走った場合、若しくは半径の小さいカーブを走った場合、
強い遠心力が働き、
遠心力と重力の合力の方向が軌道の外側に出てしまいます。
そうすると、車両に乗っている乗客はカーブ外側に転倒し、
車両はカーブ外側に引っ張られて脱線してしまいます。
そこで、カーブの外側のレールを高くし、カーブ内側のレールを低くして、
車体をカーブ内側に傾くようにすると遠心力と重力の合力が軌道内に入り、
乗客の転倒や車両の脱線を防ぐ事が出来ます。
そう書くと、「じゃあ、高速列車が走る路線は多くカントをつければ良いのだな!!」とか、
「急カーブは多くカントをつければ良いのだな!!」と言う発想になってしまうのですが、
そう上手くいかないのが世の節理で、
いくら高速で走ると言っても、いくら急カーブだと言っても、
必要以上にカントを付けすぎると、
貨物列車や各駅停車など低速で走る列車、
高速列車でもそこで何かの拍子で(停止信号や緊急停止などで)停車した場合、
逆にカーブの内側に脱線(最悪の場合車体が倒れる)してしまう危険が
増えてしまいます。
脱線しないにしても、乗客は重力でカーブ内側に引っ張られるので、
不快感を感じてしまいます。
そのため、その路線に走る車両の重さ、
優等列車から各駅停車までの走行速度など、
色々な要件からカントの数値を設定する必要があります。
3、スラック
鉄道車両の車輪はレールの曲線に合わせて
左右方向にクニャクニャ変形しないので、
カーブしているレールと車輪は平行になっていません。
そのため、列車がカーブに差し掛かると、
車輪のフランジがレールと接触してしまいます。
そうすると、騒音が発生する他、レールと車輪が必要以上に磨耗してしまいますし、
カーブも円滑に曲がれません。
そこで、カーブ区間にはカントとともにスラックも入れることがあります。

カーブに入ると車輪のフランジとレールが接触してしまいます。
それを防止するために、カーブの区間は少しだけレールの幅を広げます。
(軌間1067ミリメートルなら、1072ミリメートルにするなど。)
そうすると、車輪に若干の余裕幅が出来るため、
フランジがレールと接触しないで済むようになります。
ただし、カントと同じようにスラックを無制限に付けられる訳ではなく、
広げすぎると当然、低速で走った場合、
車輪が双方のレールの間に脱線してしまいます。
脱線しない幅でも、
スラックが大きめだと車輪の左右の余裕幅が必要以上に出来てしまい、
左右方向に車輪が揺れて乗り心地の悪化に繋がってしまいます。
4、単曲線と緩和曲線

単曲線とは一定の半径のカーブの事で、
カーブのメインとなる部分です。
ただ、直線からいきなり単曲線に入ると、
急に遠心力が働いて乗客に不快感を与えてしまう他、
車両にも衝撃がはしり、急カーブだと最悪脱線に繋がってしまいます。
また、カントとスラックはいきなりつく事になり、
急激な段差や車輪の余裕幅の変化で、やはり衝撃を受けたり、
振動が激しくなったりします。
それを防止するために、直線から単曲線に入る間に緩和曲線と言う、
だんだんと半径が短くなる曲線を入れます。
(単曲線から直線になる場合は、だんだんと半径が大きくなる曲線。)
緩和曲線はカーブの半径をだんだんと短くするだけでなく、
その比に乗じてカントとスラックもだんだんと大きくしていきます。
(単曲線から直線になる場合はその反対。)
そうする事で急激な変化をしないようにしています。
道路の場合、
緩和曲線は緩いサインカーブからキツイサインカーブの積み重ね(積分)の、
クロソイド曲線と言うらせんを使うのですが、
鉄道の場合、カントとスラックの値の計算が必要なので、
クロソイド曲線だと計算が複雑になってしまいます。
そのため、緩和曲線は高次放物線を使うことが多いです。
〜〜〜〜〜
なお、単曲線は最初から最後まで同じ半径だとは限らず、
途中で半径が変化、つまり別の半径の単曲線に変わることがあります。
これを複心曲線と言います。
更にカーブの内側と外側が入れ替わる単曲線の組み合わせの場合は、
反向曲線と言います。
これらの切り替えも変化が大きい場合は緩和曲線を挟みます。
5、勾配と縦曲線
近年、急激に鉄道地図とやらの本がブームになっているのですが、
そこで注目する要素が勾配、つまり、坂です。
地形の変化により勾配は各所で必要になるのですが、
鉄道車両の場合、兎に角坂に弱く、
急坂をのぼることは出来ません。
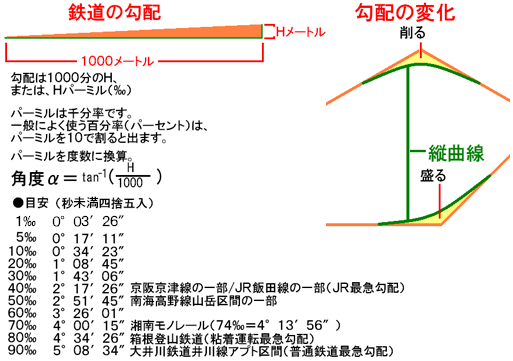
鉄道の勾配はパーミル(パーの1000分の1、つまりパー+ミリ)
と言う千分率で表します。
パーミルは普段の生活では馴染みがなく、
出来ることなら馴染みのある百分率、
つまりパーセント(パーの100分の1、つまりパー+センチ)
を使いたいところなのですが、
鉄道の勾配は緩やかなため、
パーセントにしてしまうと数字が小さくなりすぎてしまいます。
そのため、パーミルと言う単位を使います。
勾配のパーミルは1000メートル進んだ場合の高さの変化量で、
1000メートルで10メートル高さの変化があった場合は10パーミルです。
そう計算すると、
1000パーミル(=100パーセント)は1000メートル進んで、
1000メートルの高さの変化と言う事になります。
勿論、1000メートルずっと同じ勾配と言うところは少ないので、
仮想で1000メートルに勾配を延長させて計算します。
パーミルはパーの1000分の1、パーセントはパーの100分の1なので、
パーミルからパーセントにする場合は、単に10で割れば良いだけです。
10パーミルなら1パーセント、30パーミルだったら3パーセントです。
鉄道ファンの興味心からパーミルを角度に換算したくなる方がいるのですが、
この換算は逆三角関数を使います。
三角関数は高校の数学、
逆三角関数は理数系大学や理数系高等専門学校で習うものなので、
このサイトをご覧になられている小中学生の方々や
文系の方は説明しても分からないし、
計算も出来ないと思います。
なので、上の図には勾配のパーミルとそれに対する角度の表を載せました。
この表から例えば15パーミルなら10パーミルの度数+5パーミルの度数で、
大体の度数が分かるようになっています。
(秒未満を四捨五入しているので、
5パーミルの度数+5パーミルの度数+5パーミルの度数と、
細かく分けて計算すると誤差が大きくなります。また、度以下の単位の分、秒は、
時間の分、秒と同じく60進法なのでご注意ください。)
粘着運転最急勾配の箱根登山鉄道最急勾配区間は80パーミルで、
角度にすると大体4.5度ということになります。
この角度は自動車ならまだまだ余裕でのぼれる角度で、
スキー場においては初心者コースにもならない緩い角度です。
しかし、鉄道の場合はこれでも最悪最急の勾配と言う事になってしまいます。
なお、法律で規定されている鉄道路線の最急勾配は、
高尾登山電鉄(ケーブルカー)の608パーミル(31°17′59″)ですが、
規定外の鉄道も含めると更に急な勾配もあります。
〜〜〜〜〜
坂が上り坂から下り坂、下り坂から上り坂、
または水平(レベル)から坂、坂から水平、
坂の勾配が変化する場所で、
いきなり勾配を変化させると衝撃がはしってしまうので、
路盤を削ったり盛ったりして、徐々に勾配を変化させるようにしています。
この曲線を縦曲線と言います。
電車の電化方式って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|