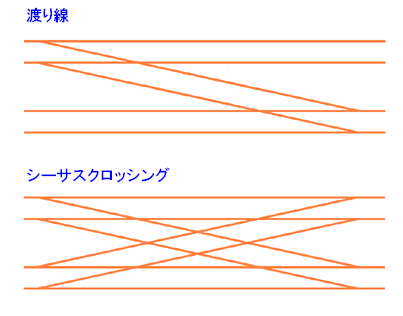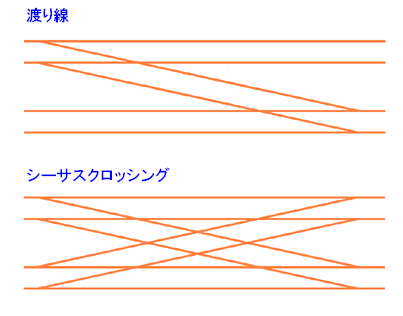電車の分岐装置って何!?その2
3、正位と反位、発条転轍機

分岐部において、通常列車が進入する線を正位と言い、
場合によって進入する線を反位と言います。
CTCや連動装置指令により動かす電動式転轍機などは、
それと連動した信号が赤、黄、緑(鉄道の場合、青信号と言わない)とか表示する事で、
ポイントが正位か反位か分かるのですが、
テコなど手動で動かす転轍機は信号と連動していないところもあるので、
ポイントが正位か反位か分からないことがあります。
そのため、そういった転轍機の上には転轍標識と言う標識を取り付け、
正位か反位か分かるようにしています。
なお、ばねの力により自動的に正位の方向に戻す転轍機を、
発条転轍機(ばね転轍機/スプリングポイント)と言います。
発条転轍機の場合、対向なら特にそのまま正位を通過出来るのですが、
背向の場合は反位になるので、
トングレールを列車の車輪が押してポイントを切り替える事になります。
ポイントは一旦反位に切り替わりますが、
列車通過後、ばねの力で自動的に正位の位置に戻します。
(直ぐにばねの力が作用しないようになっている。)
発条転轍機の場合、進入する方向や線路が限られてしまうのですが、
設備的には簡単で、大掛かりな装置や人を使わないで済むので、
ローカル線ではよく使われています。
発条転轍機もレバー操作により、
一応反位の状態のままにしておくことが出来るのですが、
人を使わないでなんぼのものの転轍機なので、
非常時、工事、臨時列車運転以外はそういう操作はしません。
4、クロッシング
二つの線路が交わっているところをクロッシングと言います。

通常のクロッシングはダイヤモンドクロッシングで、
交差部分がダイヤモンドのような形に見えるのでそう呼ばれています。
しかし、二つの線がほぼ十字に交差して、交差部分がダイヤモンドに見えなくても、
ダイヤモンドクロッシングと言っています。
ダイヤモンドクロッシングは、
通常の分岐装置のリードレール・ウイングレールと
ノーズレールの間の隙間のように、
交差部分にフランジを通過させるための隙間があるため、
その部分を通過する時に騒音と振動を発します。
その振動と騒音は交差が鋭ければ小さく、
交差が十字に近くなると大きくなります。
そのため、新規に十字またはそれに近い交差を設けることは殆ど無く、
かつては十字交差していたところも、改良して解除していることが多いです。
(電化路線で十字交差すると架線の構造も複雑になります。)
一方、「折角交差しているのだから、相手側の線にも転線出来るようにしようぜ。」
としたものがスリップスイッチで、
片側だけにスリップ(渡り)が付いているスリップスイッチを
シングルスリップスイッチと言い、
両側にスリップが付いているスリップスイッチを
ダブルスリップスイッチと言います。
ダブルスリップスイッチの場合、
それぞれどの方向から来ても、二つの方向に行けるようになっています。
スリップスイッチも通常の分岐装置と同様に
トングレールを動かしてポイント切り替えをします。
ダブルスリップスイッチの構造は複雑なのですが、
トングレールのスライド方向は一方向だけでよく、
転轍機1台でうまい具合に切り替わってくれます。
5、渡り線
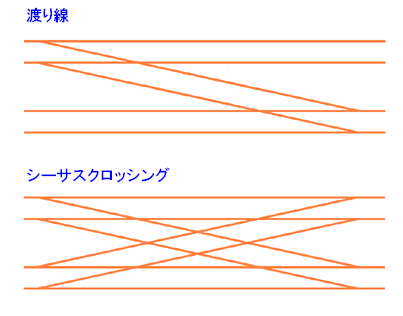
二つの線の間を結ぶ線を渡り線と言います。
左右それぞれの線路が相手側の線路を結ぶ場合、
右から左、左から右と言ったように、
渡り線を2つ交互に配した方が振動や騒音を低減出来るのですが、
駅を出てすぐ急カーブになっていたり、閉塞区間が短かったり、
駅構内の敷地が狭かったり、
地下空間に制約がある地下鉄では渡り線を2つ設ける余裕がないところもあります。
その場合に使われるのがシーサスクロッシングで、
右から左、左から右のわたり線を×印状に交差させて、
渡り線に使う有効長を一つの渡り線分に収めています。
また、一つの転轍機で二つの線の分岐装置のトングレールを
同時に動かすことが可能です。
シーサスクロッシングは二つの渡り線が交差している部分に、
フランジが通過するための隙間があるので、
通常の渡り線より騒音や振動を発する部分が多くなってしまいます。
ただ、シーサスクロッシングの交差角度を鋭くすることで、
騒音や振動を減らすことが出来ます。
6、普通鉄道以外の分岐装置
交走式ケーブルカーのように、
それぞれの車両がそれぞれ進入する線路がいつも同じで、
分岐部においてポイントを切り替える必要がない鉄道や、
トロリーバスのように軌条が無く、道路の分岐となんら変わりないものもあるのですが、
普通鉄道以外の鉄道の分岐装置も基本的な考え方は普通鉄道と同じで、
レールを転轍機でスライドさせることによってポイントを切り替えています。

新交通システム(側方案内式軌条)の場合、
分岐部に設けられている分岐ガイドレール(案内軌条)がスライドします。
車両の下部に取り付けられている案内輪が、
コンクリート壁に取り付けられているガイドレールと、
分岐ガイドレールの間に入り込む事によって、
それぞれの方向に行くことが出来ます。
ただ、新交通システムの車両は案内輪の他に
コンクリート走行路を走行する走行輪があるため、
シーサスクロッシングの場合、
走行輪が通れるよう、交差部分のガイドレールを切らなければならず、
(走行輪がガイドレールに乗り上げてしまうため)
そうすると、案内輪がフリーになってしまい、車両が変な向きの動きに変わってしまい、
コンクリート壁面などに車両をぶつけてしまう可能性があります。
そのため、基本的に新交通システムはシーサスクロッシングを使いません。
(交差を十字に近くすれば場合によっては可能。)
跨座式モノレールや中央案内式軌条の新交通システムや地下鉄等は、
分岐部のレール全体がスライドして切り替わるようになっています。
一応、シーサスクロッシング(モドキ)は出来るのですが、
それぞれの渡りの方向に合わせて、
その都度レールをスライドさせて動かす必要があります。
また、レールのスライドする部分が大きくなるので、
転轍機などの分岐装置が大掛かりになってしまいます。
懸垂式モノレールはガイドがスライドすることによって切り替わります。
電車の線路曲線って何!?へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|