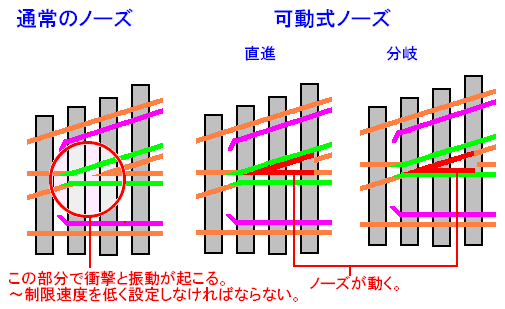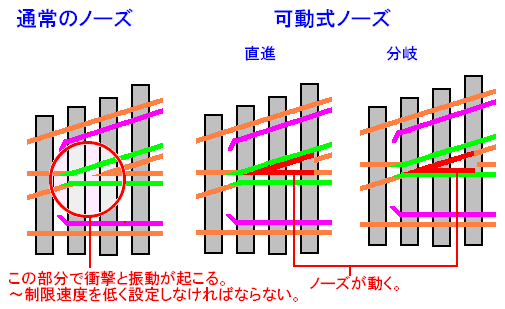電車の分岐装置って何!?その1
鉄道路線が複数の路線、複数の線路で構成されている以上、
どうしてもその所々で線路を分岐させたり、交差させたりする必要が出てきます。
その分岐箇所に使う装置が分岐装置です。
道路の分岐の場合、高速道路などの高規格道路以外は、
単に道が分かれていくだけなので、特に問題は無く単純なのですが、
鉄道の場合は結構厄介で、
複雑な装置や構造物が必要になってきます。
1、分岐の種類
道路にも色々な形態の分岐があるように、
鉄道の線路にも色々な分岐があります。
ここでは代表的なものをご紹介します。

色々な分岐があるのですが、
一番基本的で数も多いのが片開き分岐です。
片開き分岐は分岐側にカーブが入りますが、
直進側にはカーブが入らないので、
スピードを殆ど落とさないで通過することが出来ます。
通常は直進側が本線、分岐側が副本線や側線、枝線になることが多いです。
また、単線の棒線構造の駅を交換可能駅に変えた場合、
従来の線が直進で、付け加えた方の線が分岐側になるのが一般的です。
(従来の線の大きな改良をしなくて済むので。)
三枝分岐は直進と左右両方向の計3方向に分かれている分岐で、
留置線などで同じ長さの編成の電車を3本並列して留置する場合、
片開き分岐を2ヶ所使うよりも効率的で、
歪な線路用地の確保も不要になります。
ただ、片開き分岐に比べると、保守面では面倒になります。
両開き分岐は左右1対1の割合で分岐させる方法です。
左右どちらもカーブが入ってしまうので、
どちらとも速度制限が必要になりますが、
左右の制限速度を比較的緩くかつ、共通化出来るのと、
歪な線路用地の確保が不要になります。
また、駅構内の場合はこの分岐にすることで、
駅前後に分岐に合わせてカーブを入れる必要もありません。
振り分け分岐は両開き分岐と同じく、左右ともカーブが入るのですが、
比率は1対1では無く、
その線路用地や配線などにより決められた比率で分かれる分岐です。
日本の鉄道は綺麗な形で線路用地を確保されている所は少なく、
振り分け分岐を採用せざるを得ない所はかなりあります。
この分岐だと左右両側に速度制限が入る他、
制限速度が統一出来ない欠点もあります。
また、左右どちらか片一方の制限速度はかなり低くなってしまいます。
その他、カーブの途中にある分岐で、
外方分岐と内方分岐があります。
「外方」とか「内方」と言う用語は鉄道やバスなどで使われる業務用語で、
鉄道用語辞典には掲載されているかもしれませんが、
そこそこの国語辞典には掲載されていません。
(パソコンでも一発変換出来ないと思います。)
外方は文字のごとく、外側の方向と言う意味の他、
(一人称から見て)区間(エリア/区域)外と言う意味があります。
内方はその逆で、内側の方向と言う意味と、
(一人称から見て)区間(エリア/区域)内と言う意味があります。
後者の意味は閉塞区間や運賃計算区間などによく使われますが、
ここでは前者の意味で使っています。
外方分岐はカーブの外側に分かれていく分岐で、
内方分岐はカーブの内側に分かれていく分岐です。
カーブ区間には遠心力と重力の合力が軌道内に入るよう、
カーブの半径に合わせてカントと言う左右のレールの高低差があるのですが、
外方分岐や内方分岐はそのカントの調整が難しいので、
望ましい分岐とは言えません。
そのため、やむを得ない場合以外は極力採用しないようにしています。
2、分岐装置の構成

分岐装置は大きく分けて
ポイント部、リード部、クロッシング部に分かれます。
また、ポイント部側から来る場合を対向、
クロッシング部側から来る場合を背向と言います。
ここで鉄道ファンにご注意ですが、
鉄道ファンで無い一般の方が我々鉄道ファンに
「ポイント=分岐全体」の認識で話した場合、
態々「ポイントは分岐の一部分でトングレールが可動する・・・云々〜だからそれは間違いだ。」
とか言う指摘をするのは絶対にやめた方が良いです。
顰蹙をかうだけです。
それが貴方の友人や恋人だったら少なからずその関係に亀裂が入ります。
(鉄道以外に自慢することが無いのか、こういう鉄道ファンが必ずいるんだよなぁ・・・。)
話を戻しまして、
ポイント部は両車輪の基本レールの間に、
左右にスライドするトングレールが入っています。
トングレールは先の線路施設の伸縮継目の項で出ましたが、
先端が先細りしているレールのことです。
このトングレールを左右にスライドさせて、
進入する線路を変える装置を転轍機(器)と言います。
「ポイント」は日本語訳すればそのまま「転轍機」なので、
転轍機を切り替えてトングレールをスライドさせることを
「ポイント切り替え」と言っています。
転轍機を動かす方法は色々あり、
昔はテコと言う重たいレバーを駅員が押したり曳いたりしていたのですが、
現在は圧縮空気や電気で動かすのが一般的です。
電気式転轍機の操作は、
そこそこの規模の駅の駅長室・駅務室などに備え付けられている、
連動装置で操作出来ますが、
現在は中央集中で一鉄道会社の全路線、
または一定のエリアを一括で制御(Centralized Traffic Control、略してCTC)しているので、
通常はCTCの指令により転轍機を動かしています。
リード部はポイント部とクロッシング部の橋渡し的な部分で、
トングレールとウイングレールを結ぶ、
短いリードレールが基本レールの間にあります。
このレールがないと片方の車輪がそのまま道床に落ちて脱線してしまうのは、
まあ、どなたでもお分かりになると思います。
クロッシング部はリードレールに繋がったウイングレールと、
二つの方向のレールが合さって先端が細くなっているノーズレール、
それとガードレールで構成されています。
ここで色々と問題が起きるわけですが、
一つ目の問題は、
リードレール・ウイングレールとノーズレールの間に隙間が必要なことです。
この隙間が無いと、
片方の車輪のフランジ(台車の項参照)がレールに乗り上げて脱線してしまいます。
なので、どうしても隙間が必要になる訳なのですが、
これが分岐部通過の騒音や振動の元になります。
二つ目の問題は、
分岐装置をよくよく見てみると、短い間に急カーブが入っていることです。
分岐装置にいくらカーブが入っても、
通常のカーブのようにカントは付けられないので、
(無理につけようとすると大掛かりな装置になってしまい、建設費用がかかってしまう。)
遠心力と重力の合力が軌道外に出やすくなり、
車体は揺れ、車内にいる乗客もカーブ外側に強く引っ張られ、転倒しそうになります。
それだけならまだ良いのですが、
その揺れや引張りを極力抑えるため、低速で分岐部を通過するため、
車輪がレールに乗り上がって脱線する「乗り上がり脱線」が発生しやすくなります。
そのため、ガードレールやウイングレールで脱線防止をしています。
ただ、前者の問題はノーズレールのノーズを可動式にすることで解決出来ます。
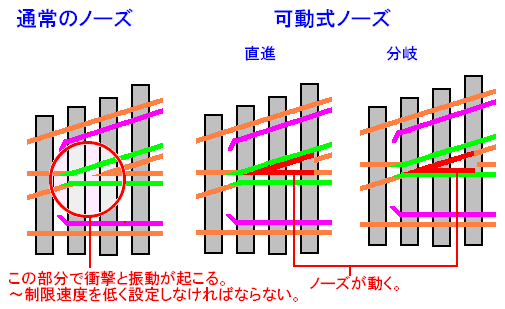
ノーズが動いて、
進入しない側のリードレール・ウイングレールとノーズレールの間の
隙間を埋めることにより、
振動、騒音が低減され、直進側はかなりの高速で通過することが出来ます。
勿論、通常のノーズレールより建設コストや保守コストはかかりますが、
新幹線や高速運転する路線はもはや当たり前に導入されています。
電車の分岐装置って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|