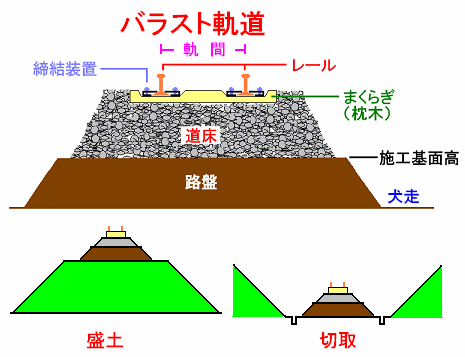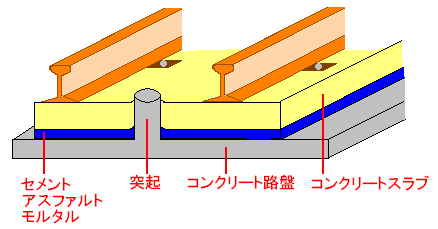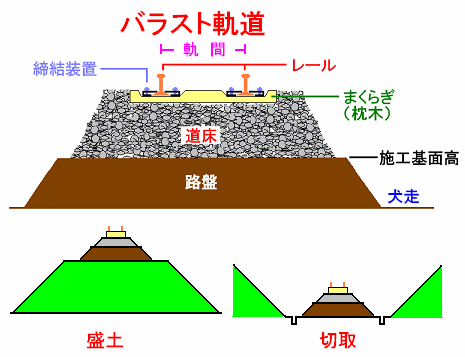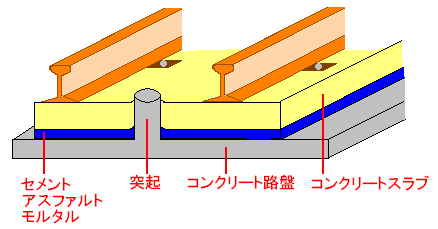電車の線路施設って何!?その2
4、軌間

軌間(ゲージ)とは両側のレールの間の長さのことを言い、
この軌間が広ければ広いほど大量高速輸送が出来ます。
逆に軌間を狭くすると、構造物を小さく出来るので、
建設費を削減することが出来ます。
ただ、路線ごとにバラバラで軌間を決めてしまうと、
直通運転が困難になるので、
一応国際的に1435ミリメートルと言う長さが決められています。
これを国際標準軌と言い、それより広い軌間を広軌、
狭い軌間を狭軌と言います。
日本では地形的に国際標準軌は厳しく、
橋梁やトンネルなどの工費が嵩んでしまうことから、
イギリス人技師が当時イギリスの植民地で採用していた
1067ミリメートルを使うよう勧めました。
そのため、日本の大半の路線の軌間は1067ミリメートルになっています。
この1067ミリメートルが日本で言う標準軌になっています。
日本の普通鉄道は762ミリメートル、1067ミリメートル、
1372ミリメートル、1435ミリメートルの4種類の軌間があります。
762ミリメートルは軽便鉄道で採用された軌間ですが、
現在は大半の路線が廃止か1067ミリメートルなどに改修したため、
現在では四日市あすなろう鉄道内部線・八王子線、
三岐鉄道北勢線、黒部峡谷鉄道の4路線しかありません。
1067ミリメートルは日本標準軌で、JRの大部分の在来線の他、
東武、西武、京王井の頭線、小田急、東急(世田谷線を除く)、相鉄、名鉄、
近鉄南大阪線系統、南海、神鉄、西鉄貝塚線の他、多くの路線で使われています。
1372ミリは特殊軌でこの軌間の採用理由は謎に包まれています。
東京市電(のちに都電)が採用した軌間で、
その市電に乗り入れる予定の路線などがこの軌間を採用しました。
現在は都電荒川線、東急世田谷線、函館市電の他、
かつて路面電車(軌道線)だった京王電鉄の京王線系統、
それに直通する都営新宿線のみがこの軌間になっています。
国際標準軌の1435ミリメートルは大量高速輸送に向いているのですが、
日本では何故か路面電車で多く採用されました。
本格的な大量高速鉄道で採用したのは新幹線で、
あとの路線の大半は路面電車か、路面電車を郊外鉄道線に改良した路線です。
採用路線はJRの新幹線の他、
それに直通する田沢湖線、奥羽本線の一部、
京成とそれに直通する子会社民鉄や
第3セクター、新京成、京急、近鉄の大部分の路線、
京阪、阪急、阪神、山陽、西鉄天神大牟田線系統、
都営浅草線、京都市営地下鉄、大阪市営地下鉄とそれに直通する鉄道線、
神戸市営地下鉄とそれに直通する鉄道線、
箱根登山鉄道、叡電、嵐電、能勢電、阪堺電気軌道、広電、高松琴平電鉄、
筑豊電気軌道、長崎電気軌道、熊本市交通局、鹿児島市交通局、
リニアモーター式地下鉄や第三軌条式地下鉄などで使われています。
なお、新京成電鉄は
600ミリメートル、1067ミリメートル、1372ミリメートル、1435ミリメートルの
4種類の軌間を経験した唯一の鉄道線です。
5、バラスト軌道
鉄道を考えた過去の技術者は偉大なもので、
レールやまくらぎの下に石を敷き詰めると言う方式は、
他のどの軌道よりも乗り心地や防音面で優れていて、
この方式に勝る軌道は今現在でも存在しません。
かつて、敷き詰める石は川の玉砂利を使っていたのですが、
多くの河川で砂利採取が禁止されたため、
現在は山の岩石を砕いた砕石を使うのが一般的になっています。
レールやまくらぎの下の道床に石を敷き詰める方式をバラスト軌道と言います。
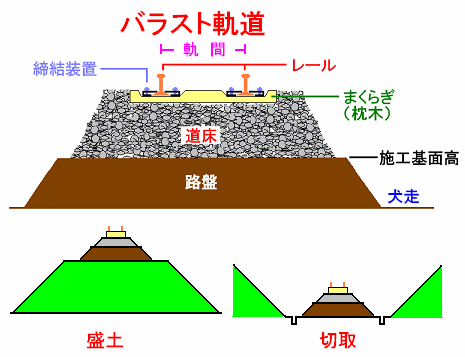
バラスト軌道は土で盛られた路盤の上に砕石を敷き詰め、
その上にまくらぎとレールを敷設します。
路盤までの高さを施工基面高と言い、様々な法的制限の基準になります。
バラスト軌道は道床の砕石がクッションと防音の働きをし、
乗り心地がよく、環境面でも優れています。
また、水はけが良いのも特徴の一つです。
しかし、道床は列車の振動などにより少しずつ崩れてしまいます。
道床を崩れたままにしておくと、レールの高さに歪みが生じ、
乗り心地が悪くなり、最悪の場合は脱線事故に繋がります。
そのため、タイタンパと言うドリル状の工具や、
マルチプルタイタンパと言う保線車両で定期的に道床をついて固めなければなりません。
また、道床の砕石は長く使うと細かくなってしまい、
路盤に埋もれてしまうので、
定期的に入れ替えを行なわなければならないなど、
保守面ではかなり手間がかかります。
現在では極力バラスト軌道は採用しないようにしているのですが、
防音対策が必要な区間は結局バラスト軌道を採用せざるを得なくなります。
〜〜〜〜
地上面より高い所に線路を敷く場合は土を高く盛り、
地上面より低い所に線路を敷く場合は土を掘って谷状にします。
前者を盛土と言い、後者を切取(または切割、切通)と言います。
盛土の土はなるべく切取で出た土を使うのが効率的なので、
路線の経路設定もそれをふまえて決めています。
6、省力化軌道
バラスト軌道は乗り心地、防音面で優れているとは言え、
つき固め作業など手間がかかるため、
何とか手間のかからない軌道の開発に技術者は頭を悩ませました。
現在まで色々な省力化軌道が開発され、
試用または本格採用されています。
6−1、スラブ軌道
スラブ軌道は省力化軌道の中では古い部類に入り、
「もうバラストなんて止めちまって、道床をコンクリートにしちまおう。」と言う、
極端な軌道です。
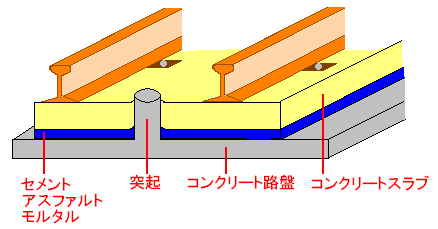
スラブ軌道はコンクリートの路盤に、
緩衝目的のセメントとアスファルトと砂を混ぜたモルタルを挟みます。
(セメントは粘土含有の石灰石を焼いて造ったもの、
アスファルトは石油を絞って出たかす。
ちなみに、コンクリートはセメントに砂や砂利を混ぜたもの。)
その上にコンクリートスラブと言うコンクリート製のプレートを敷き、
それに直にレールを締結します。
スラブ軌道は軌道の設置が簡単で、
保守面においてもつき固めの作業が不要で、
軌道の狂いも少なく、強固で、
雪が降った際、スプリンクラーの水が満遍なく行き、水はけもよいなど、
利点が沢山あります。
しかし、欠点も多く、騒音がとにかくすること、クッション性が低く乗り心地が硬いこと、
コンクリートスラブも長期的に使うと列車の振動や気温の変化による膨張伸縮により、
少しずつ軌道が歪むことが挙げられます。
軌道が歪んだ際、バラスト軌道はつき固めさえ行なえば良いのですが、
スラブ軌道の場合はコンクリートスラブごと交換になるため、
かえって面倒なことになります。
なお、防音対策には消音砕石と言う細かい砕石を敷いたりしています。
スラブ軌道の欠点は意外と多いのですが、
鉄道技術者は何故かこの欠点を挙げようとしない節があります。
どこかで強い力が働いている可能性があるので、
技術者と話す場合は黙っていた方が良さそうです。
とは言え、この欠点自体、技術者は認識しているようで、
更なる省力化軌道の開発を行なっています。
6−2、TC型、E型省力化軌道
TC型、E型省力化軌道は何れも薄くて幅広で扁平な大判まくらぎを使う方法で、
TC型はバラスト軌道の利点を備えつつ省力化した方式、
E型はスラブ軌道の考え方の延長線上にある方式です。

TC型はバラストを安定剤で固定させ、
その上に大判まくらぎを敷く方式です。
大判まくらぎによって列車の振動や重みが道床に伝わる力を分散させることが出来、
バラストも安定剤で固定させているので崩れにくく、
つき固め作業を削減することが出来ます。
E型省力化軌道はコンクリートに直接大判まくらぎを埋め込む方式です。
この方式は保守面で省力化出来るのですが、
スラブ軌道と同様な欠点があり、
クッション性も殆ど無いので、高速で走る路線での採用は不適切です。
6−3、ラダー軌道
バラスト軌道は一つ一つまくらぎを敷く手間があるし、
スラブ軌道は防音や乗り心地に問題があるし・・・と言うことで、
最近開発されたのがラダー軌道です。
ラダーとは梯子(はしご)のことで、まくらぎが梯子状になっています。

ラダー軌道はバラスト・ラダー式とフローリング・ラダー式があります。
バラスト・ラダー式は従来のまくらぎをラダーまくらぎに変えたもので、
一つ一つまくらぎを設置する手間が省ける他、
列車からくる振動や重みを分散させることが出来ます。
そのため、バラストの崩れを抑えることが出来、
つき固め作業の削減が出来ます。
道床をコンクリートにする場合はフローリング・ラダー式を使います。
コンクリート道床に大判まくらぎを埋め込み、更に防振装置を挟んだその上に、
ラダーまくらぎを施設します。
道床はコンクリートですが、防振装置があるため乗り心地が良くなり、
なおかつ、保守省力化が出来るメリットがあります。
ただ、構造が複雑で建設コストはかかります。
電車の分岐装置って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|