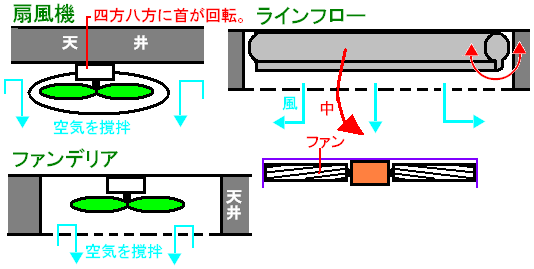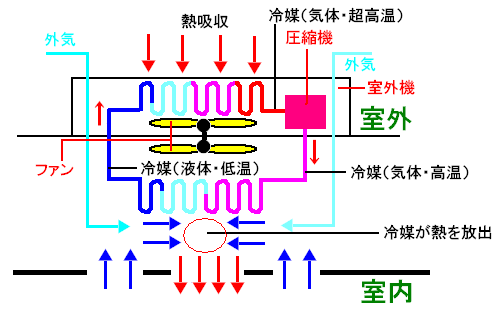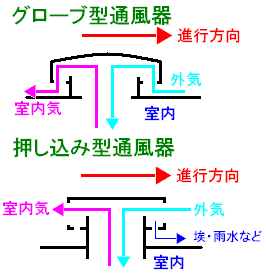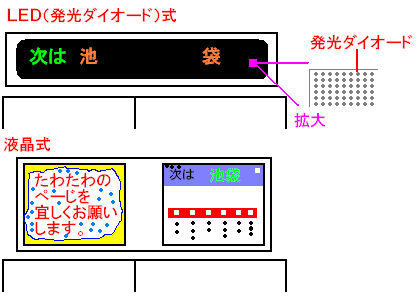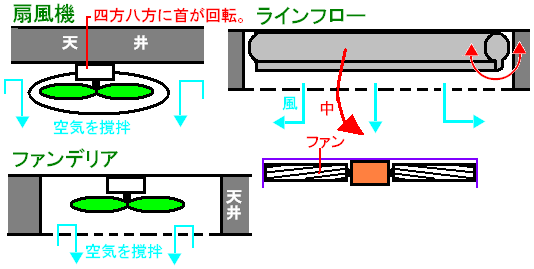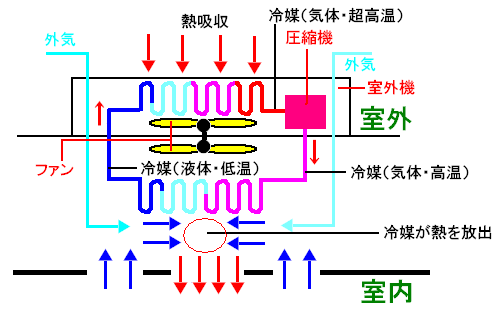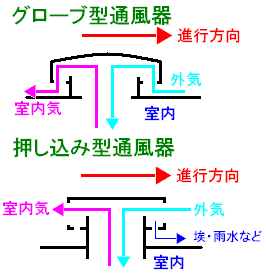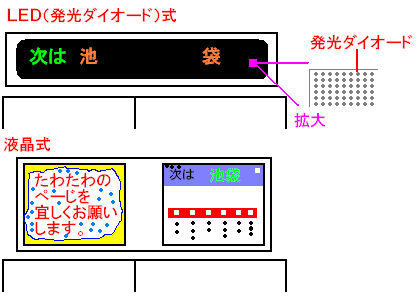電車の車内設備って何!?その2
3、送風機
鉄道車両にクーラーがなかった時代、
暑い夏は窓を開けて外の風を取り入れて暑さを凌いでいました。
しかし、雨天時や畑にこやしなどが撒かれている時期などは、
とても窓を開けることが出来ません。
そこで、窓を開けられなくても暑さが凌げるように、
天井に送風機が取り付けられました。
送風機は車内の空気を撹拌させることによって、
乗客の体温を奪う働きがあります。
鉄道車両の冷房化が当たり前になった現在でも、
冷房の冷たい空気や暖房の暖かい空気を満遍なく行き渡るようにするため、
送風機が取り付けられています。
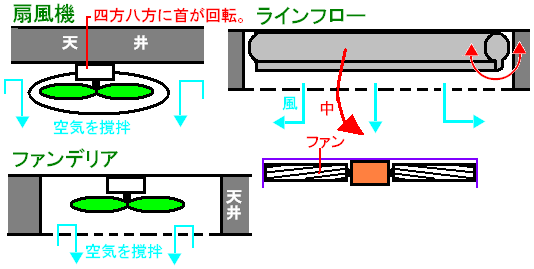
送風機は代表的なものに、
扇風機、ファンデリア、ラインフロー(ラインデリア)があります。
扇風機は言うまでも無いのですが、
羽状のファンをまわすことで空気を撹拌させる装置です。
扇風機の首は四方八方に動き、
車内各所に風が行くようにしています。
ただ、天井が低い車両に扇風機を取り付けると、
背の高い方は扇風機に頭をぶつけてしまう危険性があります。
そのため、天井の低い車両は扇風機の代わりにファンデリアを取り付けています。
「ファンデリア」と言うと何だかお洒落な感じがするのですが、
何てことはなく、
ただ単に「扇風機を天井に埋め込めてみました。」と言うだけです。
ラインフローは三菱電機が開発した送風機です。
(なお、「ラインフロー」と言う用語は商品名なので、
教科書に載せたり、NHKテレビで放送する時は、
「線状送風機」とか言うのかもしれません。)
ラインフローは鉄道車両のような細長い空間には最適な送風機で、
下にライン状の孔が空いた筒の中に棒状のファンをいれ、
そのファンが回転することにより、
孔から風が出て空気を撹拌するものです。
扇風機の場合、一度風が来た所に再び風が来るまで時間がかかるのですが、
ラインフローの場合は左右に振るだけなので、
再び風が来る時間の間隔が短くなります。
しかも、広範囲に風を送ることが出来る利点もあります。
また、送風機を使用しない時期、
扇風機はいちいちカバーを取り付ける手間があるのですが、
ラインフローの場合はその手間が要りません。
欠点は保守点検が面倒になることが挙げられます。
4、クーラー/エアコン
平成っ子の鉄道ファンは、
「鉄道車両にクーラーが付いていて当たり前」だと認識していると思いますが、
実際、鉄道車両にクーラーが付くようになったのは結構最近で、
普通車は昭和50〜60年前後まで、
地下鉄にいたっては平成になるまでクーラーがありませんでした。
地下鉄車両にクーラーを取り付けなかったのは、
クーラーの室外機から出る廃熱でトンネル内に熱が充満し、
トンネル内の温度が上がってしまうおそれがあったからです。
相互直通車両でクーラーのある車両も「地下鉄線内はクーラーを切る」といった、
今では考えられないことが普通に行なわれていました。
地下鉄は頑なに外に室外機が取り付けられるトンネル冷房を導入し、
車両冷房は行なわなかったのですが、
温暖化で乗客が暑さに耐えられなくなったのと、
熱を発する抵抗制御(広義)の車両から、
熱をあまり発しないVVVF制御車両に代わり、
電車自体の熱発生が低減されたため、
今は地下鉄車両にも冷房を取り付けています。

クーラーは冷媒と言うガスを気体にしたり液体にしたりして、
車内の熱を間接的に車外に放出させる装置です。
冷媒はフロンガスまたは環境を考えて代替フロンが使われます。
ここでよくある誤解が、
「クーラーをつけるとフロンガスが放出されてオゾン層が破壊される。
だからクーラーはつけない。」
と言うものです。
クーラーをガンガンつけてもフロンガスは基本的に放出されません。
放出されるとしたら、
冷媒を通る管に孔や亀裂、接続面に隙間などが出来た場合です。
クーラーと温暖化の問題はフロンガスよりもむしろ、
室外機から出る熱及び、クーラーを動かすのに大量の電力が必要になり、
それを火力発電でまかなっている場合、
排煙で温室効果になってしまうことです。
クーラーをつけると冷媒が圧縮機で圧縮され、
高温高圧な気体になります。
それを室外機のファンで放熱し、冷媒を低温な液体にします。
液体になった冷媒は室内機に送られ、
車内の暖かい空気の熱を吸収し、再び気体になります。
車内の空気は冷媒に熱を吸収され、
冷たい空気になります。
それをファンで再び車内に放出させるのがクーラーの仕組みです。
室内機内は冷たいため、水滴が付着します。
その水滴を集めてドレンホースで車外に流すと除湿も出来ます。
基本的に列車のクーラーは関東の場合、普通冷房車で26度、
弱冷房車で28度に設定されています(鉄道会社によって多少前後があります。)。
ただ、小型車の場合、人の占有密度が高くなり、
人の体温で車内が暑くなりやすいので、
それより1度程度低く設定することが多いです。
また、最近のクーラーは車内が混雑すると自動的に温度を1度下げたり、
(混雑度は空気ばねの空気圧で計算されます。)
車外の外気温との格差を縮めるため、
外気温が上がったら1度温度を上げるように制御されています。
なお、現在のクーラーは除湿機能だけの運転(ドライ運転)も可能です。
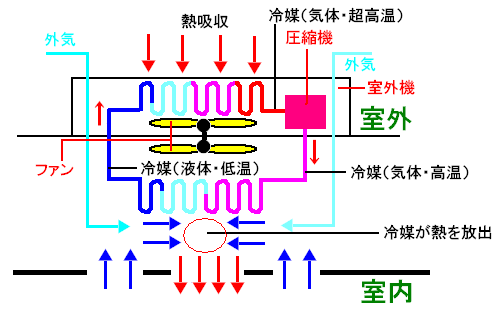
なお、クーラーにエアコン機能が搭載されている場合、
冷媒の循環を逆にすると暖房になります。
外が極端に寒い場合は電気ヒーター程暖かくなりませんが、
鉄道車両は乗客の体温で自然と暖かくなるので、
然程気にする必要はありません。
ただ、寒冷地や閑散線区に使う車両は電気ヒーターの併用が必須です。
なお、路線によっては石炭などのストーブを使っているところがありますが、
基本的にストーブは火災になる危険があるのと、
ストーブの不完全燃焼で一酸化炭素中毒になる危険があるため、
特別な対策をしている車両、及びトンネルなどがない路線など、
あらゆる条件をクリアしないと使えません。
大都市圏の通勤車両のストーブ採用は先ず無理ですし、
今後導入される車両にストーブを取り付けるのは先ず無いと思います。
5、通風器
鉄道車両は駅に停車してドアを開くか、
乗客が窓を開けるかしないと空気の入れ替えが出来ません。
駅の間隔が長く、なかなかドアを開くチャンス無い場合が結構あり、
また、乗客が窓を必ずしも開けてくれるとは限らないので、
列車の屋根には通風器(ベンチレータ)と言う機器を取り付けています。
特急車両などは窓が固定されていて開閉不可能なことが多いので、
通風器は必須になっています。
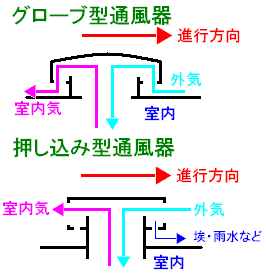
通風器は色々なタイプがあるのですが、
代表的なのはグローブ型と押し込み型があります。
何れも列車が動く(厳密に言うと停車中でもある程度換気可能)と外から風が入り、
それを室内に取り込むことで空気の入れ替えをすることが出来ます。
また、室内の汚れた空気は取り込み方向と逆の方向から排気されます。
6、車内案内表示器
今まで車内の案内は車掌の放送しかなかったのですが、
より細かく情報が流せるよう、また、耳の不自由な方でも情報が得られるよう、
各車両の車内に案内表示器を取り付けている車両が増えてきています。
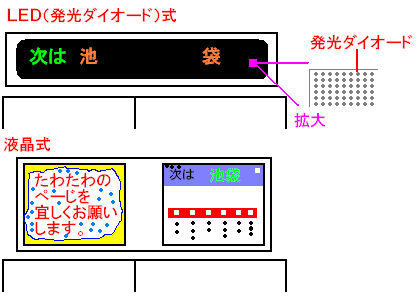
初期の案内表示器は発光ダイオード(LED)によるもので、
青のダイオードが実用化されるまで、
赤、弱い緑、オレンジ(赤+弱い緑)の3色しか色を出せませんでした。
現在は青のダイオードが加わり、フルカラーで表示が出来るようになっています。
発光ダイオードの密度に限界があり、
細かい表現は出来ませんが、
特に色々情報を流す必要が無い路線は、
発光ダイオード式の案内表示器を採用しています。
なお、「まもなく○○駅」と言う表示は、
車両のスピードを計算して出しているため、
運転士が予期しない運転をした場合、
異常に早く表示されたり、遅く表示されたりする欠点があります。
より多くの情報を流したい場合は、
液晶の案内表示器を使います。
この液晶案内表示器は何故か試作搭載しても本採用されない
と言う状態が続いていたのですが、
技術の向上と価格の低下などが進んだため、
液晶式の案内表示器を搭載する列車が増えてきました。
液晶式の場合、2画面採用の所が多く、
1画面に次駅や到着時間、停車駅などの案内を、
もう1画面に鉄道会社及びスポンサーのCM、ニュースなどを流しています。
なお、両方の画面は無線で中継局とやりとりされるため、
「まもなく」表示が遅れることは(無線障害)以外ありません。
注!!お食事中の方はここより下をご覧にならないで下さい!!
お食事中の方用リンク↓
下を見ずに次の電車の車体構造って何!?その1へ直接行きます。
鉄道・なぜなに教室トップへ
7、トイレ
人間は定期的にトイレで排泄物を放出しているわけですが、
列車に乗っている間は我慢しなければなりません。
しかし、長距離乗車する列車ではどうしても、
車内で便意をもよおす可能性が高くなります。
昔は罰金覚悟で窓から用を足していたと言う逸話が残っていますが、
不衛生で汚いし、公序良俗にも反します。
だからと言って乗客に過度の我慢をさせるのは、
サービス面でも良くありませんし、乗客の健康を害することになります。
そのため、長距離走る列車にはトイレが必須になっています。

列車のトイレを水洗にすると、水タンクを搭載しなければなりません。
しかし、列車と言う限られた空間で大型の水タンクを搭載するのは不可能です。
そのため、昔の列車は垂れ流し式が一般的でした。
垂れ流し式は汚物が車外に放出されると、
列車の風圧で飛散、分解され、線路及びその周辺にばら撒くと言うものです。
しかし、駅停車中に汚物を排泄すると、
風圧での分解がされなく、そのまま汚物が線路に落ちてしまいます。
そして、駅構内が排泄物の悪臭で充満してしまいます。
そのため、垂れ流し式のトイレには、
「停車中には使用しないで下さい。」と言う注意書きがあります。
垂れ流し式を改良して一応水洗トイレにしたのが撹拌式です。
撹拌式は汚物を消毒消臭効果のある処理液を混ぜて細かくしてから、
車外に放出する方法です。
垂れ流し式よりは撹拌式の方がマシなのですが、
汚物を車外に排出しているのには変わりがありません。
汚物を車外に放出しないようにしたのが、
循環式で、水洗に使う水を何度も循環させることによって、
水の節約を図るものです。
もちろん、一度汚物を流した水をそのまま使うのは汚く、
洗浄にもならないので、
水には消毒液などを適宜混合させ殺菌、消毒をし、
ろ過装置でろ過してから水を再利用しています。
真空式は殆ど水を使わない方式で、
汚物を流すと排出弁が開き、
圧縮空気と共に真空の汚物タンクに一気に吸い込まれる方式です。
真空式は水の節約が大幅に出来る他、
流す時以外は排出弁が閉じているので、
汚物タンクからの悪臭がトイレや車内に漏れることが少なくなります。
電車の車体構造って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|