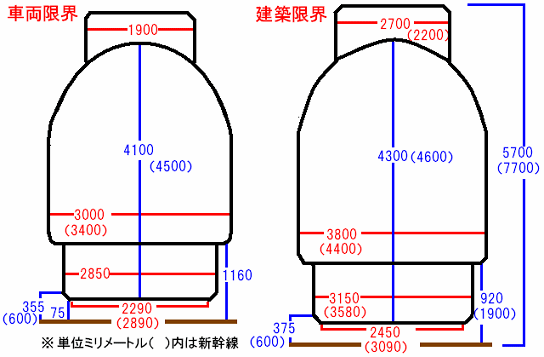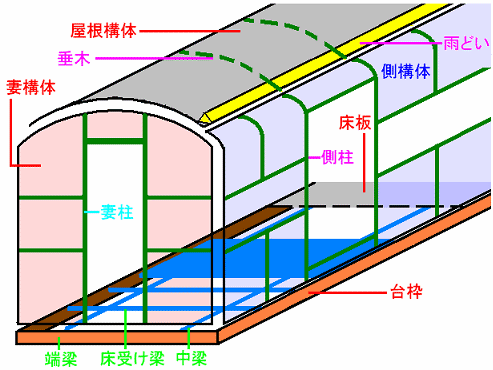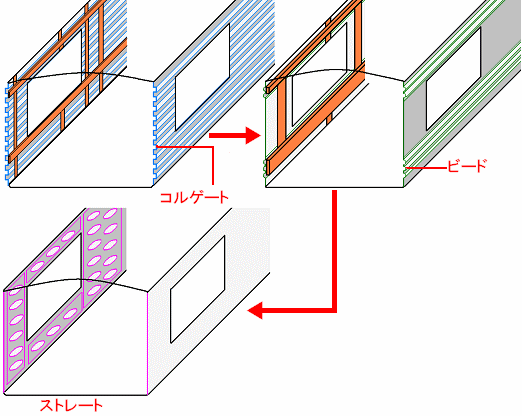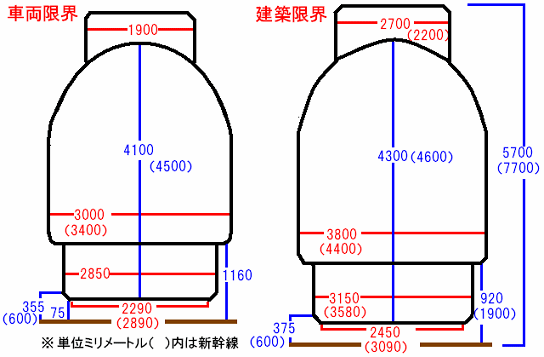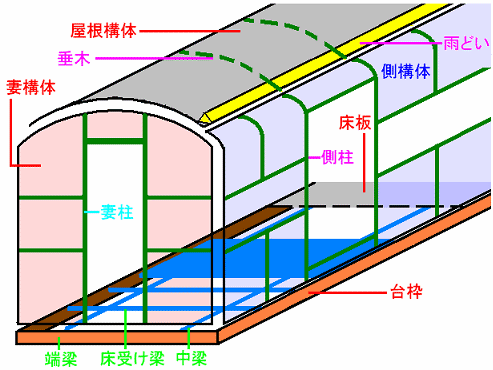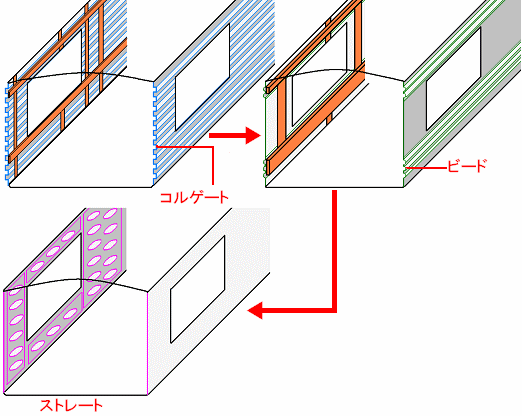電車の車体構造って何!?その1
乗り物と言えば自動車でも飛行機でも船でもボディー、
つまり車体(機体・船体)が重要になります。
何れもいかに省エネルギーでかつ高速で走行(飛行/航行)出来るか、
また、保守が簡略化出来るかが重要になります。
ただ、それぞれの乗り物により、
必ずしも最適なボディーの材質、製造法が一致しているわけではありません。
特に鉄道車両は自動車のように大量生産が出来ず(大量生産しても需要がない)、
飛行機や大型船舶のように一部のメーカーが殆ど市場を独占している訳でもないので、
製造費用を抑えてなるべく安い価格で販売しなければならない
と言う厳しい状況になっています。
しかし、それを追求し過ぎて
安全面や旅客サービスが悪くなっては元も子もないので、
その按配をうまく満たせるような材質や技術を日々研究・開発しています。
1、車両限界と建築限界
当たり前ですが、
鉄道車両は無制限に大きい車体を造るわけにはいきません。
大きな車体を走らせるにはそれなりの線路用地が必要になるばかりでなく、
線路構造物も大きな車体の重量に対応したものにしなければならないからです。
また、車体が大きいと風などの抵抗が大きくなり、
それに比例して走行エネルギー消費も多くなるので、
総じてお金がかかってしまうことになります。
そのため、最大に造れる車両の限度を決める必要があるのですが、
それをメーカー側がバラバラで決めてしまうと、
購入する側の鉄道会社はメーカーの仕様にふりまわされてしまうことになります。
そのため、各路線には共通の約束事として車両限界と言う最大寸法が決められています。
一方、車両の最大寸法が分かったので、
「それを超えれば建物や電柱、ホームなどの建築物を造ることが出来るか」
と言うとそうではありません。
好奇心旺盛な子供は窓から顔を出す可能性が高いし、
車掌はホームの安全確認のため、窓から身を乗り出していることもあります。
そういう場合、車両限界ギリギリに建物や電柱を建築してしまうと、
それに激突してしまう危険性があります。
また、車体が風やカーブなどで傾斜した場合、
車両限界ギリギリだと車体が建築物にこすってしまう可能性もあります。
そのため、車両限界とは別に建築限界と言うものも決められています。
建築物はその限界より外側に造らなければなりません。
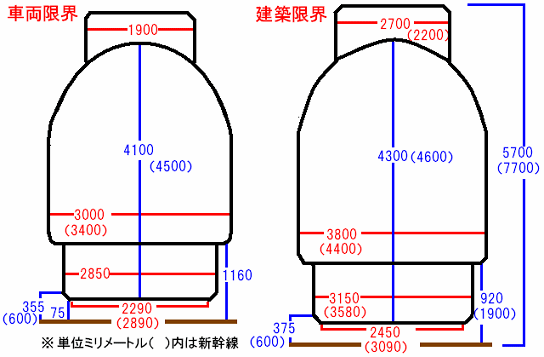
上の寸法はJRのもので、
民鉄は路線状況によりこれより厳しい(小さい)基準のものもあります。
JRの車両でもJRより厳しい車両限界の民鉄に直通する車両は、
民鉄の車両限界に合わせた車両にしなければなりません。
特に地下鉄は建設費を抑えるため建築限界を小さくしています。
そのため、地下鉄に直通する車両は、
一般車両より小さい車両限界内で車両を造る必要があります。
2、車体の構造と材質
鉄道車両は大きく分けて
普通鋼車、ステンレス車、アルミ合金車の3種類に分けられます。
昔は木造車と言うものもあったのですが、
防災や安全面で問題があるので、新規には製造していません。
完全な木造車はさすがにもう無い(遊戯物、特殊鉄道などは除く)のですが、
外装は普通鋼で内装は木で出来た半鋼製車両は一部で残っています。
なお、「阪急電鉄の車両は木目調の内装だ。だから半鋼製車両だ!!」
・・・と、思う方はいないと思いますが、子供はマジで信じてしまう可能性があります。
あれは本当の木ではないですよ!?
2−1、普通鋼車
普通鋼と言うと、「そのまま鉄」と思われる方もいるのですが、
実は鉄以外にも炭素などが微妙に入っていて、100%鉄ではありません。
これは鉄だけだと柔らかいので、強度が弱くなってしまうからです。
なお、車両の普通鋼だけでなく、レールの普通鋼にも炭素などが含まれています。
鉄道ファンが趣味で鉄道に乗りに行ったり、
鉄道車両の写真を撮りに行ったりすることを「鉄分補給」と言っていますが、
実際は「炭素も補給?」していることになります。
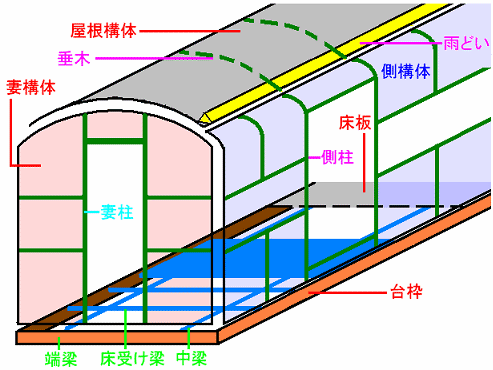
上の図は普通鋼車の車体構成です。
ステンレス車もアルミ合金車も基本的には同じなのですが、
最近はステンレスブロック構造や
アルミ合金ダブルスキン構造(張殻<ちょうかく>構造)など、
必ずしもこの通りの構成ではない車両もあります。
鉄道車両は台枠の上に、
床を構成する床板、
屋根を構成する屋根構体、車両の前後面を構成する妻構体、
車両の側面を構成する側鋼体を組み合わせて造ります。
台枠は縦横に梁が渡してあって、
床受け梁は床板を取り付ける梁になっています。
妻構体や側構体は組み立てられた妻柱や側柱に取り付けます。
住宅で言えば在来工法のようなもので、
一つ一つ熟練した技術者が造り上げるため、
手間がかなりかかります。
〜〜〜〜〜
普通鋼車の利点はとにかく頑丈で、
溶接や細かい造形が容易に出来ることです。
そのため、扉の埋め込みや中間車両の先頭車両化、
窓枠の変更など大胆な改造が出来ます。
同じ車両でも製造した時と、
引退した時で全く姿形が異なっていることもあります。
また、事故で車体が変形してもある程度なら修復出来ます。
欠点はとにかく「錆びる」ことで、
定期的に保守をする必要があります。
塗装をすることで錆の侵食をある程度押さえられるのですが、
その塗装作業にコストがかかってしまいます。
また、錆が侵食しても脆くならないよう、普通鋼の鋼板は厚くしているため、
どうしても車体が重くなってしまいます。
車体が重いと動かすのに大きなエネルギーが必要になるだけでなく、
高速走行も難しくなります。
そのため、最近造られる車両は、
軽量なステンレス車両やアルミ合金車両が殆どで、
普通鋼車は徐々に減ってきています。
何故か鉄道評論家や鉄道ファンの一部にステンレス信仰やアルミ合金崇拝がいて、
「普通鋼車はそのうち無くなるぞ。」と思い切って言ってしまう鉄道評論家もいますが、
実はそうでもありません。
それは逆に「重くないといけない車両」がこの世の中では必要だからです。
一番の例は機関車で、
機関車はそれ自身の車体があまりに軽すぎると、
重い貨車を牽引した場合、粘着力が不足して空転してしまう可能性があります。
そのため、機関車は駆動力を上げるため、
重い普通鋼車にすることが多いです。
極度な急勾配を走る電車なども同様に駆動力を上げるため、
普通鋼車にすることもあります。
また、何よりも「製造費が安い」ので、
地方私鉄で無理して新車を導入する場合は、
安い普通鋼車を選択することが多いです。
2−2、ステンレス車
ステンレスは文字通り、ステン(錆びる)+レス(無い)、
つまり錆びない(厳密に言うと全く錆びない訳ではない)材質で、
鉄にクロムやニッケル、モリブデンなどを合わせた合金です。
ステンレスは錆びにくいので、
錆の侵食を抑える塗装をする必要が無く、
大幅な保守省力化が出来るため、
古くから「なんとかステンレスを車両に導入出来ないか」と色々研究されていました。
昔は柱などの大枠は普通鋼で造り、
それにステンレスの外板を取り付けたセミステンレス車が一般的でしたが、
現在はすべてステンレスのオールステンレス車が一般的になっています。
鉄道関係の書物で言葉が足りないライターが書いた本は、
「ステンレス鋼は普通鋼より丈夫です。」としか書いていないことが多いのですが、
この「ステンレス鋼は普通鋼より丈夫」と言うのは、
同じ厚さで比べた場合の話で、
実際のステンレス車は車両軽量化と製造コスト削減のため、
極限まで薄くしているため、
必ずしも丈夫とは言えません。
なお、ステンレス鋼の略が「SUS」なので、
馬鹿な鉄道ファンが一つ覚え的に「SUS」とかいきなり唱え出す場合があるので、
その時は、「ステンレス鋼車」のことを言っているのだと理解してやってください。
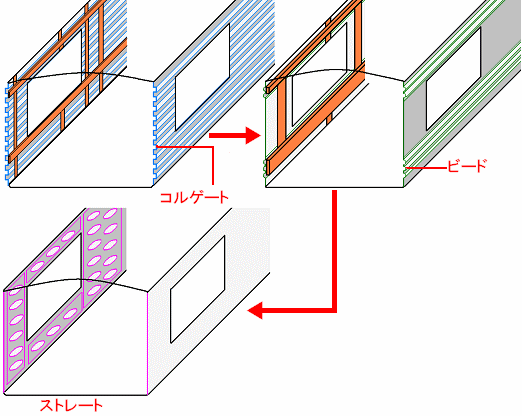
ステンレス車が開発された頃は、
薄いステンレスでの車両製造に四苦八苦しました。
いくら丈夫なステンレスでも薄くすれば強度が弱くなるだけではなく、
溶接の際に歪がでてしまい、
仕上がりの見た目も非常に良くありませんでした。
普通鋼車の場合は歪などが出ても塗装で誤魔化せるのですが、
ステンレス車は「無塗装でなんぼのもの」なので、
いかにこの歪を誤魔化せるかが課題になりました。
そこで考え出されたのがコルゲートという、
外板を凸凹状にする方法です。
コルゲートを付けることで、強度が増し、
歪も誤魔化すことが可能になりました。
しかし、コルゲートは凹凸が多く、車両清掃の際、
凹の部分を中心に洗い残しが出てしまうなど、
別の面での問題が出てきました。
そのため、更に研究が進められ、
ビードと言う円弧状の突起を数本設けることで、
強度強化をし、外見上の見た目も良くすることにしました。
しかし、それでも見た目で見劣りがするのと、
その頃から「ステンレス車の強度不足」が問題視されるようになりました。
ステンレスは細かい造形が難しいので、
先頭車の先頭部分だけは従来通り普通鋼で造ったり、
FRPと言うガラス繊維の強化プラスチックで造っているので、
そこの部分の強度は強いのですが、
側面に関しては何かがぶつかると言うことをあまり想定していなかったので、
脆弱性がありました。
側面の強度を上げるにはステンレス鋼板を厚くするしかないのですが、
そうすると車体が重くなり、製造コストが嵩んでしまいます。
色々考えた結果、構造力学的にステンレス板を加工すれば、
なるべく従来の重量で強度強化が出来ることが分かりました。
また、溶接技術も向上し、溶接の際の歪も無くなってきたので、
現在のステンレス車は側面の凹凸が無く、フラットになっています。
〜〜〜〜〜
ステンレス車の利点は先ず「錆びない」と言うことで、
塗装などの作業を省略出来、
保守省力化が出来ます。
それでいて、普通鋼車より長持ちします。
また、ステンレス鋼板を薄くしているので、
車体が軽く、省エネルギーで列車を走らせることが出来ます。
欠点は無塗装による外板のギラつきです。
アルミ合金に比べてステンレスはギラつきが強く、
旅客目線で見ると寒々しく鋭くきつい感じをどうしても受けてしまいます。
そのため、最近は塗装に変わるアクセントとして使われている
テープ装飾の面積を増やして、
なるべくそのステンレスの表面部分が隠れるようにしたり、
ステンレスの外板の光沢自体を抑える加工をしたりしています。
もう一つの欠点として、
ステンレス車はいくつかのステンレス鋼板(パーツ)を組み合わせて造られているため、
その接合部分が目立ってしまうことがあげられます。
(ステンレス鋼は細かく多彩な造形が出来ないので、
造形ごとに細かく鋼板を造っている。構体毎に分ける場合、ブロック工法と言っている。)
これも気になる鉄道会社はテープ装飾で隠したりして誤魔化しています。
一番の欠点は、事故などで車体が変形した場合、
修復が困難なことです。
製造中の車両なら部品を取り寄せて直すことも出来ますが、
製造中止になった車両は予備部品を確保しておかないと、
直す事が出来なくなります。
地方の私鉄に行った中古車で事故による変形を起こした車体は、
(直せないので)そのままみすぼらしい姿で走らせていることが多いです。
電車の車体構造って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|