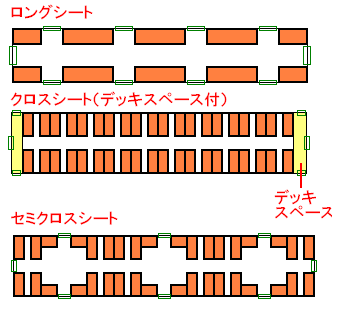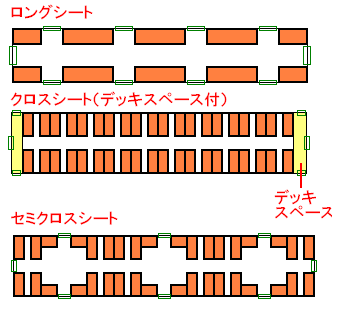電車の車内設備って何!?その1
我々鉄道ファンが鉄道車両を評価する時、
デザインとか車両性能などを重視すると思います。
しかし、一般の乗客にとってはそんなことはどーでもよく、
むしろ、車両の良し悪しの評価は車内設備で決まると言っても過言ではありません。
車内設備は乗客の最大多数が満足出来るように設計しなければならないので、
非常に難しいものがあります。
1、座席
鉄道車両に乗った時、
そのまま立つか座るか(寝台列車は「寝る」もありますが)すると思いますが、
すぐ降りる乗客、立っているのが好きな乗客以外は、
「座席が空いていたら座りたい」と思うのが普通です。
しかし、そう思う乗客をすべて座らせると効率が悪くなり、
かえって混雑の原因になる場合があります。
その時重要になるのが座席配置で、
鉄道車両の場合は一般的に
ロングシート、クロスシート、セミクロスシートが主流になっています。
鉄道アナリストや鉄道ファンはロングシート派、クロスシート派に二分され、
日々大激論が行なわれているのですが、
これは不毛な論争で意味がありません。
実際は使用する路線に適したシート配置にするのが理想的だと言えます。
なお、最近の若い方は「床も座席」と考えているようなのですが、
不特定多数が乗る列車の床に座るのは汚いし、
はっきり言って「邪魔」です。
床は座席でない事を認識した方が良いと思います。
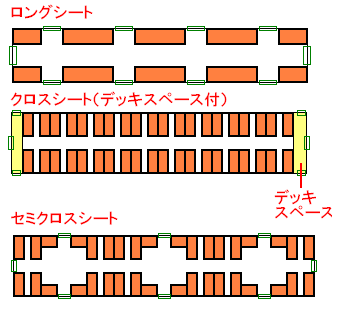
座席配置は大きく分けてロングシートとクロスシートがあるのですが、
ロングシートは車両の壁に沿ってレール方向に長い座席を配する方式です。
ロングシートの利点は床スペースを広くとれるため、
立ち客を多く乗せることが出来る他、
赤の他人が隣に座っても抵抗感が無いこと、
外の景色を見るとき、いちいち首を曲げる必要が無いことが挙げられます。
欠点は座席定員が少なくなること、
昔は良しとされていた足伸ばしや股開きはマナー違反とされ、
窮屈な体制で座らなければならないこと、
前に乗客が立って視界が塞がり、圧迫感を感じることなどが挙げられます。
その利点、欠点を考慮すると、ロングシートは通勤車両に最適だと言えます。
一方、クロスシートは通路を挟んでまくらぎ方向に2〜3人の座席を配する方式です。
そのうち、前後のシートが向きあっている場合は、
ボックスシートまたは見合い式シートと言います。
クロスシートの利点は座席数が多くなるので座れる乗客が増える他、
前に乗客などが立たないので、
グループ客が座る時に気兼ねが要らないこと、
食事や化粧なども場合によっては可能なこと、
ボックスシートで無ければ足が伸ばせることなどが挙げられます。
欠点は床スペースが狭くなり、
立ち客はデッキや通路などの狭い所に立たなければならないこと、
通路が狭く、移動が大変なこと、
窓側の席に座っている人が席を立つ際、
通路側の席に座っている人に配慮しなければならないことが挙げられます。
また、乗客が多いと乗降に時間がかかり、
定時運転が出来なくなると言う欠点もあります。
そのことから考慮すると、
クロスシートは比較的乗客が適正数な長距離の列車に最適だと言えます。
セミクロスシートはロングシートとクロスシートの折衷案で、
入口付近はロングシート、車両中ほどはクロスシートにして、
混雑時も閑散時も対応出来るようにしています。
そのため、セミクロスシートは中距離列車によく使われます。
1−1、ロングシート
ロングシートは足が伸ばせてゆったり座れ、
外の景色をダイナミックに見ることが出来ると言うことで、
一等車両に導入された由緒正しい高貴なシートです。
それがそれが、今ではすっかり通勤車両の代名詞に成り下がってしまいました。
しかし、ただ単にロングシートが設置されているのではなく、
乗客のニーズに合わせて日々様々な改良が行なわれています。

従来のロングシートは座面が平坦で座席下には脚台があり、
この中に電気ヒーターやドア開閉装置などの機器を納めていました。
しかし、このシートだと足を伸ばす乗客が出たり、
一人で二人分の席にゆったり座るという問題が出てきた他、
シート下の空間が狭く、窮屈と言う問題もありました。
また、脚台付近が埃などで汚れ、清潔感も感じられません。
そのため、最近の車両は一人ひとりの座席占有分を明確に分け、
シートにくぼみを付けるバケットシートが採用されています。
このシートにすると、一人で二人分の席に座るということが解消され、
(体型の大きい方は不利ですが。)
背もたれに向かってくぼみを深くすることで、乗客が自然と足を伸ばさなくなります。
従来、バケットシートはそれに対応するばねが無く、
緩衝詰物だけでクッション性を持たせたため、シートが石のように硬くなってしまい、
長時間座るとケツが痛くなると言う問題がありました。
最近はSばねなどが開発され、
バケットシートの問題点も徐々に無くなってきています。
また、座席の支持も
列車の壁や天井に固定されたポールでシートを吊り下げる片持ち式が採用され、
座席下の空間が広くなりました。
ただ、ポールが若干邪魔になるので、
シート幅を従来より広くする必要があります。
1−2、転換クロスシート
従来のクロスシートは背もたれが固定されているボックスシートしかなく、
グループ客以外は赤の他人と無意味に至近距離で向き合わなければならないという、
落ち着かない状態を強いられるだけでなく、
背もたれが垂直に近い状態で長時間座ると疲れてくるという問題がありました。
もう少しリラックスして座れる方法を
色々考え出された結果の一つに転換クロスシートがあります。

転換クロスシートは図のように背もたれの向きが変わるようになっています。
背もたれの向きは背もたれを押すだけで変えられます。
これならば、進行方向に座席の向きを変えられる他、
ボックスシートにするかしないかの選択が自由に出来ます。
また、背もたれにある程度角度が付くのでそこそこリラックスして座ることが出来ます。
欠点は背もたれの角度(リクライニング角度)を自由に調節出来ないことと、
座席背面にテーブルなどを取り付けることが出来ないことなどが挙げられます。
関東ではあまり採用例がなく、
私はこういう座席があることを知りませんでした。
西日本の鉄道に乗った時、
「なんじゃこれ、シートの向きかえられないじゃん。」とぼやいていたら、
おじさんが笑いながら背もたれの向きを変えていました。
あのおじさんの笑顔を一生忘れそうにありません・・・。
1−3、回転リクライニングシート
折角クロスシートにするのなら、
とことんリラックスして座れるように考え出されたのが回転リクライニングシートです。
特急列車や新幹線の車両ではもはや当たり前のシートになっています。

回転リクライニングシートは背もたれの角度を自由に調節することが出来、
ゆったり座ることが出来ます。
座席と座席の間隔をシートピッチと言うのですが、
回転リクライニングシートの場合、ある程度シートピッチを広めにとってあるので、
足を伸ばすことが出来ます。
前のシートの背面、または肘掛には簡易テーブルが付いていて、
それを取り出すことで、小物や飲み物、食べ物などを置くことが出来るので、
飲食なども可能です。
ボックスシートにしたい時は、
シート下の脚台横にある(車両によって場所、形状が異なります)
シート回転ペダルを踏みながら、
中心を軸にするようにシートを押すと、
シートの向きが変わります。
「うちらはボックスシートがええ!!」と言って指定席券を購入したら、
横並びの席になってしまったと言う方たちがいると思いますが、
基本的に指定席でボックスシートを確保したい場合は、
4の倍数人で購入しないと横並びにさせられることが多いです。
(満席に近い時に購入した場合、4の倍数人でもバラバラの席になることがあります。)
これは、2×2人掛けボックスシートに3人のグループが座っている中、
そのグループに無関係の人間一人が座るのには非常に抵抗感があるからです。
座席は極力埋めたいのが鉄道会社の本心なので、
3人のために1座席を犠牲にすることは出来ないのです。
リクライニングシートの欠点と言うか、マナーなのですが、
背もたれを大きく傾ける場合は、
後の座席の方に配慮しなければならないこと、
座席背面のテーブルを出す場合、
前に座っている方に衝撃が加わらないように静かに出さなければならないこと、
テーブルに物を置く場合は静かに置かないと
やはり前に座っている方に衝撃が加わることなどが挙げられます。
老若男女問わず結構このテーブルをバターン!!と倒す族がいて、
ペットボトルなどをドカン!!と置くのですが、
果たして彼らはどういう神経をしているのか知りたいものです。
それと別の欠点として、
シートの回転方法が分かりにくいことが挙げられます。
シートの回転方法がよく分からず、まごつくご年配の方を結構見かけます。
回転リクライニングシートは基本的に進行方向に座席を向けているのですが、
終点に到着した場合、
この座席の向きを変える必要があります。
昔は車内の清掃係の方が一つ一つ座席の向きを変えていたのですが、
現在は乗務員室にあるスイッチで一斉に向きが変えられるようになっています。
2、吊革(吊り手)
惜しくも座れなかった乗客は立つことになるのですが、
何も掴まらないで立っていると、電車が動き出した時や、
ブレーキをかけた時、慣性の法則で転倒してしまいます。
そのため、何かしらに掴まっている必要があるのですが、
その代表的なものに手すり、つかみ棒、吊革などがあります。
その中でも吊革は立ち客がよくお世話になるものだと思います。
吊革は日本固有のもので、
何でも西洋化したがる鉄道技術者は何が何でも吊革を廃止しようと企むのですが、
今の所100%失敗で終わっています。
日本人の体型や日本の風土を考えると吊革は最適なものなので、
それを廃止しようと考える事自体邪道と言えるのですが。

日本の鉄道の黎明(れいめい)期は色々な形の吊革があったのですが、
今は丸型か三角型(おむすび型)の二つが主流になっています。
丸型は長いこと吊革の代表の形になっていたのですが、
握っていると手が痛くなる欠点がありました。
そのため、色々考えた結果、三角型の吊革が理想的だと分かり、
現在は三角型が普及しています。
また、吊革の取り付け方向も、従来はレール方向に取り付けていたのですが、
この場合、手首をひねって掴むことになるため、
手が疲れると言う問題がありました。
そのため、比較的新しい車両はまくらぎ方向に吊革を取り付けています。
また、女性は訳の分からないオヤジの手脂が付着した
吊革を握りたくないと言う方が多いため、
吊革を動かす事で吊革が拭けると言うものが考え出されたのですが、
保守が面倒なのと、長時間使うとかえって汚くなるので、
現在は吊革の素材自体を抗菌仕様にしています。
電車の車内設備って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|