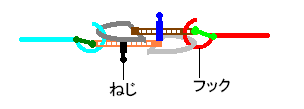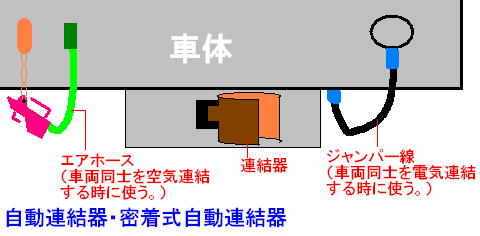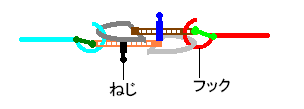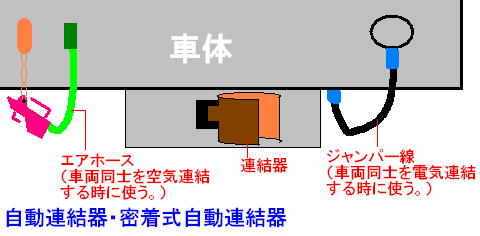電車の連結装置って何!?その1
列車の車体は蛇のようにくねくね曲がります・・・と言う事は無いので、
カーブを円滑に曲がるため、列車の車体長を無制限に長くする事が出来ません。
そのため、旅客の多い路線はいくつかの車両を繋げて運行しています。
また、貨物列車は操車場などで運搬先別に貨車を付け替えたりする必要があるため、
細かく分けられるように貨車の長さをある程度の長さにして、
それらを繋げて運行しています。
そのため、複数の車両同士、貨車同士を繋げる器具が必要になります。
それが連結装置と言うもので、
列車の各車両の前と後に必ず付いています。
1両(単行)で運転する列車も、
故障などで動けなくなった時に別の列車や機関車に牽引してもらうために、
連結装置が必要になります。
1、ねじ・リンク式連結器
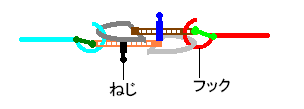
ねじ・リンク式連結器は、
「片方の車両についている輪状の器具を
もう片方の車両のフックに引っ掛ければ良いじゃねえか?」
・・・と言う、普通誰でも考えられるような発想の連結器で、
特に難しいことはありません。
(プラレールの車両の連結器と同じ発想です。)
連結する双方の車両にフックと、
フックに引っ掛ける「リンク」と呼ばれる輪状の器具を取り付け、
相手の車両のフックにリンクを掛け合うことで連結が成立します。
しかし、それだけだとリンクとフックに「遊びの空間」が出来てしまい、
連結器同士がぶつかり合って乗り心地が悪くなってしまいます。
下手すると振動によって連結が外れてしまう事があります。
それを調節するのがねじで、
ねじを巻くとその遊び空間を無くす事が出来、
締め付けをきつくすることが出来ます。
しかし、締め付けをきつくしても、
あくまでも「遊び空間での衝撃」を減らすだけで、
連結器自体にかかる振動を吸収する事は出来ません。
その振動を吸収するために車両の端に
緩衝器と言うクッション性のある器具を取り付けます。
ねじ・リンク式連結器の構造はとても簡単なのですが、
いちいちリンクをフックにかけてねじで締め付ける作業が必要なため、
とても連結に手間がかかり、沢山の作業員が必要になります。
また、連結に時間もかかるため、輸送上無駄な停車時間が多くなってしまいます。
更に、車両の間に作業員が入って連結作業をするため、
連結時に作業員が車両の間に挟まれてしまうと言う危険もあります。
そのため、日本の一般の旅客、貨物列車では現在この連結器は使われていません。
ただ、諸外国は日本みたいに「鉄道は1分でも遅れてはいけない。」とか、
「安全第一」とか言う発想が希薄なので、
今でもこの連結器が躊躇も無く使われています。
2、自動連結器
2−1−1、自動連結器
ねじ・リンク式連結器は手間もかかるし、
連結時に危険が伴うので、
「車両同士を軽く当てただけで連結が出来、
なおかつその時に作業員が車両の間に入らなくて済むような連結器」が発明されました。
それが自動連結器です。
自動連結器はナックルをかみ合わせる方式の連結器です。

自動連結器で連結する場合、
ナックルと言うS字状の器具を動かないよう固定している錠を外します。
そうするとナックルが回転軸(ピン)を中心に動くようになります。
ナックルが少し開いた状態でお互いの車両を近付けさせ、
軽く双方の連結器をぶつけるとお互いのナックルがかみ合います。
あとは錠を再び取り付けてナックルを固定すれば連結完了です。
日本はこの連結器が気に入ったのか、
大正時代早々に全部の車両をこの連結器に取り替えたと言う、
伝説が今もなお語り継がれています。
2−1−2、密着式自動連結器

密着式自動連結器の仕組みは普通の自動連結器と同じです。
ただ、自動連結器はナックルや連結器頭部に遊び空間が出来てしまい、
振動や衝撃が強くなるため、
密着式自動連結器はお互いの頭部同士を差し込ませて密着させ、
遊び空間を無くすようにしています。
貨物列車は「こわれもの」を輸送する貨車以外は多少振動や衝撃があっても良いので、
普通の自動連結器が使われますが、
旅客列車の場合、振動などで乗り心地が悪いと
「お客さまの声(旧・苦情)」に繋がるので、
密着式自動連結器がよく使われます。
2−2、自動連結器・密着式自動連結器の空気連結器と電気連結器
列車は「ただ繋がればおしまいっ!!」
ではなく、空気ブレーキの空気を流す空気管を繋げたり、
乗務員室(運転席や車掌台)から指令した電気的指令を
各車両の機器に伝令するため、
その電線を繋ぐ必要があります。
前者を空気連結器(略して空連)と言い後者を電気連結器(略して電連)と言います。
車両同士を繋げるのも「連結器」、
空気管や電線を繋げるのも「連結器」で名称が若干ややこしいです。
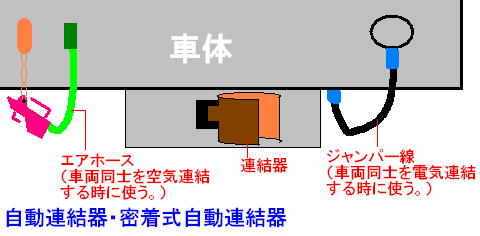
自動連結器や密着式自動連結器の場合、
先頭部車体下部にエアホースとジャンパー線があります。
エアホースは空気を流す管で、ジャンパー線は電気を流す線です。
図ではそれぞれ1本しか描かれていませんが、
電磁直通空気ブレーキなどは元空気ダメ管と直通管の二つ空気管が必要なので、
エアホースが最低2本必要です。
(保安ブレーキなどもあるので大抵2本では済まない。)
ジャンパー線は比較的新しい車両で1本、
古い車両は2本以上あります。
エアホースやジャンパー線は連結完了後、
車両に固定しているチェーンや器具を外し、
相手の車両のエアホースやジャンパー線にそれぞれ繋げます。
電車の連結装置って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|