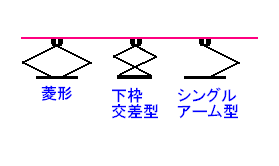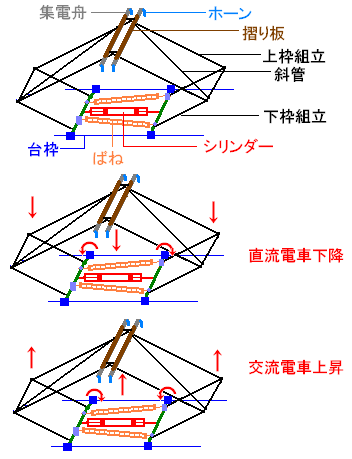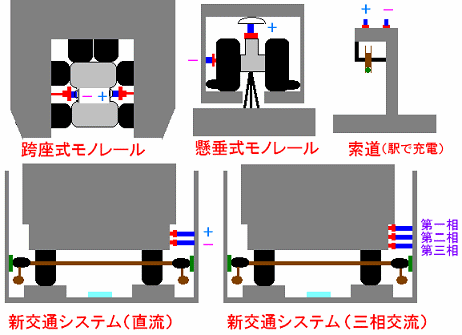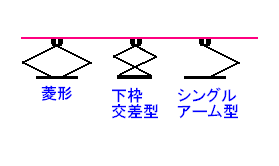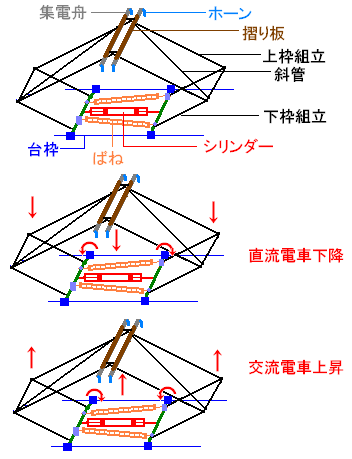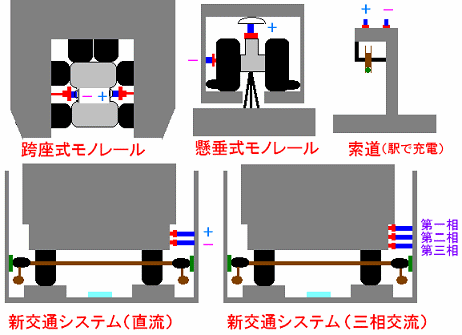電車の集電装置って何!?その2
4、パンタグラフ
パンタグラフは伸び縮みする集電装置のことを言い、
架線集電式の電車ではおなじみの集電装置です。
パンタグラフは通常上がっている状態なので、
使わない時はパンタグラフを下げて折りたたむ必要があります。
昔はひもを引っ張ってパンタグラフを下げていたのですが、
今はシリンダーなどで下げています。
しかし、これは直流電車のお話で、
交流電車の場合、「通常上がっている状態」と言うのは、
高圧の電気が流れているトロリー線に不用意に接触してしまう危険性があるので、
直流電車とは逆に通常下げて折りたたんでいる状態にしています。
なので、電車を動かす時はシリンダーなどでパンタグラフを上げます。
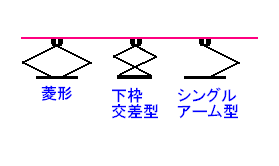
パンタグラフは色々な形があるのですが、
よく使われるのは、菱形、下枠交差型、シングルアーム型です。
その他翼型と言うのもあるのですが、
近い将来絶滅すると思うので説明を割愛します。
下枠交差型は菱形パンタグラフの下枠組立を交差させたもので、
この方式にすると台座の面積を減らすことが出来ます。
屋根上の機器が多く、パンタグラフを設けるスペースが狭い場合や、
新幹線など風除けのパンタグラフカバーをつける車両は、
パンタグラフカバーの設置スペースを捻出するために下枠交差型がよく使われます。
4−1、菱形パンタグラフ
菱形パンタグラフは集電装置の完成版で、
前後に枠組立をしているため、
進行方向を気にする必要がありません。
押し上げる力が強いため、
ビューゲルよりはるかに離線が少なく、
高速運転に適しています。
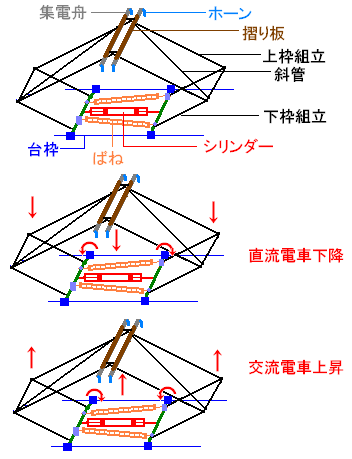
菱形パンタグラフは上のような形になっています。
一番上にあるのが集電舟(しゅうでんしゅう)で、
その集電舟の真ん中に摺り板(すりいた)と言う銅またはカーボンの板が付いています。
この摺り板とトロリー線が接することで電気を集電します。
擦り板とトロリー線の摩擦で摺り板はだんだん磨耗していくので、
この摺り板の部分だけ定期的に交換する必要があります。
なお、摺り板が局地的に磨耗しないように、
トロリー線の架線はジグザグに張って満遍なく
磨耗するようにしています。(ジグザグ偏位)
分岐部でトロリー線が交差している所を通る時、
集電舟の下にトロリー線が入らないようにするため、
集電舟の両端は下に向けています。
この部分をホーンと言います。
パンタグラフの下降(交流電車は上昇)は基本的にシリンダーで行ないます。
パンタグラフを下げるシリンダーを下げシリンダーと言い、
パンタグラフを上げるシリンダーを上げシリンダーと言うのですが、
どちらのシリンダーもシリンダー内のピストンがピストン運動をすることによって、
パンタグラフが下げ(上げ)します。
一方、ばねはパンタグラフの上げた状態(交流電車は下げた状態)を保つためにあります。
4−2、シングルアーム型(式)パンタグラフ
最近の新型電車は殆どシングルアーム型パンタグラフなので、
鉄道ファンの感覚は「菱形を改良したのがシングルアーム型」
のようになっているのですが、
実際は逆で、「シングルアーム型を改良して完全な形になったのが菱形」です。
シングルアーム型はそれ以前のZパンタグラフを改良したものです。
ただ、環境の変化や時代の流れで技術後退を余儀なくされ、
現在はシングルアーム型が主流になっています。

シングルアーム型パンタグラフは、
枠組立に使う腕金(アーム)を上下1つにして部品点数を限りなく減らしています。
部品点数が少ないと言う事は当然保守が省力化出来ると言うメリットがあり、
部品交換コストも下げることが出来ます。
また、パンタグラフと風の接する面が少ないので、
パンタグラフによる風切り音を減らすことが出来、
騒音を低減させることが出来ます。
更にパンタグラフの軽量化も出来、
追従性にも優れているので、高速運転に適しています。
更にまた、架線の高さに合わせて柔軟に動くので、
離線する可能性も殆どありません。
良いこと尽くめのシングルアーム型パンタグラフですが、
欠点はビューゲルのように折り返し時に向きを変えることが出来ないので、
どの進行方向でも風の影響を最小限にする対策や設計が必要であると言うことです。
また、部品点数が少ないと言うことは、
一つの部品にかかる負担が大きいので、
菱形のパンタグラフより老朽化が早いと言う欠点もあります。
それと、シングルアーム型パンタグラフは雪の接着する面が少ないため、
雪に優位とされていますが、雪が大量に台枠積もると、
パンタグラフがたたみ難くなる欠点があります
(パンタグラフに雪が付着しない=その分台枠に雪が積もる)。
5、集電靴(しゅうでんか)
現在、地下鉄の電化は地上線と同じ架空集電式が多いのですが、
リニアモーター式地下鉄が開発される前は、
トンネルの高さを抑えるために、
第三軌条式と言う電化方式を採用した地下鉄路線もあります。
第三軌条式は線路の脇に設置された
第三軌条(サードレール)から集電靴で集電する方式です。

集電靴は台車の両側についています。
集電靴が両側についているのは、
第三軌条が区間によって線路の右だったり左だったりするためです。
第三軌条と帰線であるレールの双方を触ると感電してしまうのですが、
第三軌条と帰線のレールは至近距離にあるため、
人が触れて感電する危険性が極めて高いです。
そのため、基本的に作業員の通路や駅のホームとは反対側に第三軌条を設置します。
作業員の通路や駅のホームは必ずしも同じ側にあるとは限らないので、
第三軌条もそれらに合わせて左右細かく分けて設置されています。
第三軌条式は第三軌条の上面から集電する方式と
下面から集電する方式があるのですが、
今、日本にある第三軌条式の路線はすべて上面から集電する方式になっています。
(かつて碓氷峠に使っていた第三軌条は下面から集電するタイプでした。)
そのため、集電靴は第三軌条の上面に接触して集電しています。
台車と集電靴の間は絶縁されていて、
集電靴で集電した電気が
いきなり車輪を通ってレール(帰線)に流れないようにしています。
第三軌条は碍子で固定されていて、
第三軌条に流れている電気が地面に流れないようにしています。
地面に水道管などの埋設物があると、地面に流れた電気で電食と言う現象が起こり、
水道管などの埋設物が錆びてしまう恐れがあります。
そのため、第三軌条の碍子はかなり大きめして絶縁を強化しています。
第三軌条の上には防護板という板があり、
作業員が転倒などをした時、第三軌条に接触しないようにしています。
6、その他鉄道の集電装置
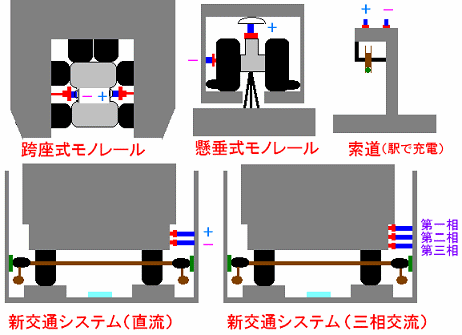
モノレールや新交通システムの集電装置はどうなっているのかと言うと、
上の図のような形で集電しています。
モノレールも新交通システムも問題が一つあり、
軌道がコンクリートになっているため、
車両から変電所に電気を戻す帰線に軌道が使えないと言うことです。
そのため、電気を流す剛体架線は、
変電所から車両に行く電気を流す給電用の正架線と、
車両から変電所に戻る電気を流す帰線用の負架線の2本必要になり、
集電装置も正と負の2つ必要になります。
ただし、札幌市地下鉄や山万ユーカリが丘線などは
中央の案内軌条が鉄製になっているため、
それを帰線に使うことが出来ます。
新交通システムは直流と三相交流の二つがあり、
直流の場合は正と負の2本の剛体架線と2つの集電装置が必要です。
で、少し難しい話で恐縮なのですが、
三相交流の場合は三つそれぞれの相の電気が一定の時間で
変電所と車両の間を行ったり来たりしています。
この「行ったり来たり」は三つの相で時間がずれていて、
三つの相の「行く電気(マイナス)」と「来る電気(プラス)」の流れを合計すると
丁度0になります。
そのため、三相交流の場合帰線は不要になり、剛体架線は3本だけで済みます。
索道(ロープウェイ)の搬器はハンガーの部分に
集電装置があり(場所は搬器によって異なります。)、
駅に停車中の時、電源から電気を集電し、
コンデンサやバッテリーなどに電気を蓄電しています。
電車の連結装置って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|