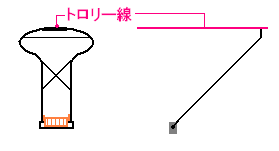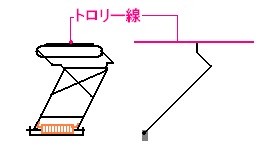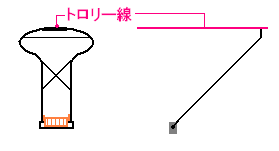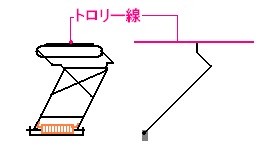電車の集電装置って何!?その1
当たり前ですが電車は電気で走っています。
電気で走るからには電気を何かしらで取り込むか、
電気を蓄えたものを搭載するかしなければなりません。
遊園地の遊戯物の列車などは、
電気を蓄えたバッテリーを搭載するだけでなんとか走れますが、
普通の電車はバッテリーで蓄えた電気だけではとても走らせることが出来ません。
そこで電気の流れた電線から電気を取り入れるのですが、
その電線から電気を取り入れる装置を集電装置と言います。
電車ではおなじみの装置なので、
比較的分かりやすいと思います。
1、トロリーポール
集電装置では一番原始的な装置で、
トロリーホイールと言う溝入りの車輪を棒の先に取り付けた簡単な装置です。

トロリーポールは上の図のような構造になっていて、
トロリーホイールの溝の中に電気が流れているトロリー線を挟んで双方を接触させ、
集電します。
なお、トロリーホイールは回転するので、
その回転により追従性を維持しています。
普段、トロリーポールはばねで上に跳ね上がっている状態なので、
集電しない時(電車を走らせない時)は
ひもを引っ張ってトロリーポールを倒します。
トロリーポールの構造は簡単なのですが、
あまりにも華奢なので
風や電車の振動などによりグラグラ上下左右に揺れてしまいます。
そうすると、トロリー線とトロリーホイールが離れてしまい、
集電出来ないことがしばしば起こります。
それだけならまだマシなのですが、
最悪な時はトロリー線がトロリーホイールから完全に外れてしまうことがあります。
そうなると、運転士はいちいち電車から降りてトロリーポールを操作し、
再びトロリー線をトロリーホイールの溝に入れなければなりません。
トロリー線とトロリーポールが付いたり離れたりするとアークと言う放電が起こり、
トロリー線を傷めてしまいます。
また、トロリーポールも振動などで劣化が激しく長持ちしません。
それ以外にも、終点に到着して折り返し運転をする場合、
ひもでトロリーポールの向きをいちいち変えなければならないと言う手間があります。
「面倒だし、高速運転などとんでもない!!」と言う集電装置なので、
今時こんな集電装置を導入する電車は基本的にありません。・・・が、
ヨーロッパなどではまだまだ現役のトロリーポール搭載電車があるようです。
そんなダメダメ集電装置のトロリーポールなのですが、
実は「最新のシングルアーム型パンタグラフ」より優れている点が
2つ程あったりします。
1つ目は、軌道とトロリー線がある程度ずれていても、
トロリーポールの台座が回転することで追従出来ると言うことです。
トロリーバスなどレールの無い電車(無軌条電車と言うのですが)は、
その時その時でタイヤの通る軌跡が異なります。
そのため、
トロリー線とタイヤの通る軌跡の中心がずれても集電出来るトロリーポールは、
トロリーバスに最適だと言えます。
現在、日本で走っているトロリーバス2路線は何れもトロリーポールを使っています。
(トロリーホイールは回転しないタイプ)
2つ目は、横に2つ並べて集電装置を搭載する場合、
屋根の占有場所がパンタグラフより狭くて済むと言うことです。
モーターや補助電源装置で使った電気を変電所に戻す線(帰線と言います)を
レールにしていない路線は、
トロリー線が給電用(正)と帰線用(負)の2本になり、
集電装置を2台並べて設置しなければならなくなります。
パンタグラフでも2台並べることは可能で、
実際、ケーブルカーなどではそういう車両もあるのですが、
パンタグラフは従来のタイプより小型のものにする必要があります。
その時々で走るところが変わるトロリーバスで小型のパンタグラフを使うと、
トロリー線から離れてしまう恐れがあります。
また、1つのパンタグラフで給電用、帰線用両方のトロリー線に接触してしまうと、
ショートしてしまいます。
(ショート防止に架線交差部はデッドセクションにする。)
トロリーポールの場合、給電用、帰線用それぞれのトロリーポールが、
対になるトロリー線に接触することは無いので、
ショートの危険性はありません。
なので、その点から考慮してもトロリーバスはトロリーポールが最適だと言えます。
2、ビューゲル
トロリーポールはトロリー線から外れてしまうので、
外れないよう鈍足で走らせなければなりません。
しかし、せっかちな乗客は歯がゆい状態になります。
「もうちょっとなんとかならないのか?」
と言うことで登場したのがビューゲルです。
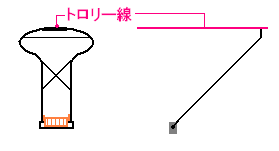
トロリー線の接触面が殆ど点になっているトロリーポールと違い、
ビューゲルは面で接触する形になっています。
そのため、トロリー線が離れる頻度も少なくなります。
また、終点で折り返す場合、
運転士がいちいちビューゲルの向きを変えなくても、
台座の支点を中心に向きが自動的に変わります。
とは言え、トロリーポールより幾分かマシと言う程度の集電装置なので、
高速で走らせるとビューゲルがグラグラ上下に震動してしまい、
トロリー線からビューゲルが離れてしまうことがあります。
トロリー線から離れると言うことは当然アークが発生するので、
トロリー線やビューゲルを傷めてしまうことになります。
なので、高速で走る電車には結局の所使えず、
路面電車などの低速電車で使われるだけです。
そんなビューゲルの一番のお得意様である路面電車も、
徐々にパンタグラフに交換されつつあります。
3、Zパンタグラフ
ビューゲルに起こる問題を改良したのがZパンタグラフです。
細かいことに拘る鉄道ファンや鉄道アナリストは、
「Zパンタグラフはパンタグラフではない!!」と言い出すのですが、
まあ、「視野の狭い可哀そうな人間だなぁ。」と思って、
適当に相槌をうっておけば良いと思います。
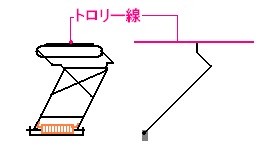
Zパンタグラフは上部を逆方向に折り曲げた形になっています。
上下にグラグラ揺れた時、
台座の支点を中心に動く弧の長さの最大値がビューゲルより若干短くなるので、
トロリー線が離れるリスクが減ります。
また、ビューゲルよりトロリー線を押し上げる力があり、
追従性が良くなっています。
とは言え、あくまでもビューゲルに毛が生えた程度のものなので、
高速で運転すればトロリー線は離れてしまいます。
そのため、Zパンタグラフは高速で走らない路面電車でしか使われていません。
しかし、後期のZパンタグラフはかなり改良され、
折り曲げの位置が真ん中の辺りになり、
追従性が向上し、トロリー線の離線率もかなり減りました。
なお、これを更に改良して進化したのがシングルアーム型パンタグラフです。
電車の集電装置って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|