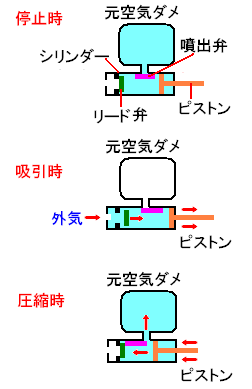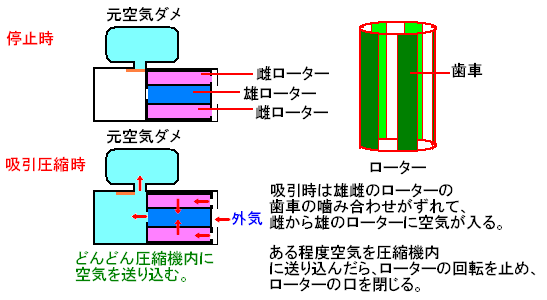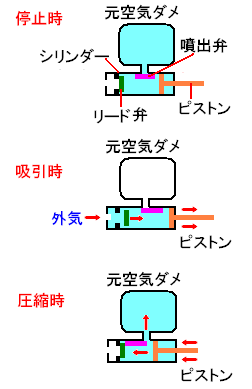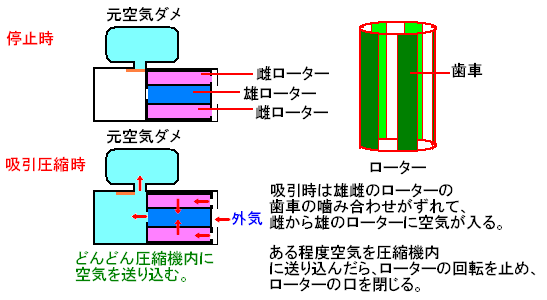電車の補助装置って何!?
電車はただ走らせれば良いと言う訳ではなく、
車内の照明や冷暖房装置、扉の開け閉め、
モニター、通話機器、運転席の各表示灯など、
走らせること以外にも様々な場所で電気や空気を使います。
それを担っている装置が補助装置と言う装置です。
補助装置の主なものに補助電源装置や電動空気圧縮機(コンプレッサー)などがあります。
1、補助電源装置
補助電源装置とは、電車の車内照明、自動扉の開閉モータ、
冷暖房機器、空気圧縮機の作動、車内案内モニター、
運転席の表示灯、運転用モニターなど、
走行以外で使う電気を供給する装置です。
また、走行においても、加速に界磁添加励磁制御を使っている場合や、
回生ブレーキ時に他励磁方式で界磁に電気を流している場合も、
補助電源装置は使われます。
で、厄介なのは、架線の電圧が直流電化で1500ボルト(一部750ボルト、600ボルト)、
交流電化で単相交流2万ボルト(新幹線は2万5千ボルト)になっていることです。
この電気をそのまま各種機器に使うと電圧が高すぎるため、
確実に故障してしまいます。
(それがどういうのか見てみたい方は豆電球をコンセントに差し込んでみてください。
危険なのでお勧めしませんが・・・。)
そのため、架線から取り入れた電圧を下げなければなりません。
交流の場合は変圧器の巻線を変えて電圧を下げれば良いだけなのですが、
直流の場合は簡単に電圧を下げることが出来ません。
昔は電気を使うのが車内照明や運転席の表示灯などに限られていたため、
低電圧の直流電気や低電圧の単相交流電気を使っていましたが、
今は冷房装置、モニター、通信機器など、様々なところで電気を使うため、
三相交流の電源が不可欠になっています。
そのため、直流電化の場合は電圧を下げるとともに、
三相交流にしなければならなくなりました。
また、交流電化であっても、単相交流を三相交流に変換する必要があります。
1−1、電動発電機
知ったかぶりの鉄道ファンがよく「MG、MG・・・」と九官鳥のように言うのですが、
これは、Motor Generatorつまり、電動発電機の略です。
昔はサイリスタなどと言うハイテクノロジーな半導体など無かったため、
直流の電気を直接適切な電圧の交流にすることが出来ませんでした。
そこで、架線から集電した電気でモーターを動かして、
そのモーターの電機子と同軸上で繋がれた発電機を回転させることによって、
適切な電圧の交流電気を発電すると言う回りくどいやり方がとられていました。
ここで発電する電気は単相、または三相交流440ボルトなのですが、
車内の蛍光灯などは家庭用で使われる単相交流100ボルト対応なので、
100ボルトに電圧を下げています。
(三相交流の電気は三相から二相を取り出すと単相になる。)
また、運転台の表示灯は直流の豆電球なので、
電圧を下げた後、更に整流器で直流に変換しています。

この方式だと、直流モーターを使うことになるので、
電車を動かす直流モーターと同じように、
ブラシや整流子などの消耗部品の定期的交換が必要になります。
ただ、利点もあり、デッドセクション(死電区間)などで一瞬架線から電気を集電出来なくなっても、
モーターの電機子は惰性で回転するので、
同軸上で繋がれた発電機の回転子も回転させ続けることが出来ます。
そのため、発電機が発電出来なくなり、
いきなり車内照明等が消えてしまうと言うことはありません。
ただ、その場合、消費する電気が多いと、
発電機の回転が急激に遅くなってしまうため、
(モーターの惰性回転=運動エネルギー=発電機で発電する電気エネルギー)
死電区間(時間)が長い場合は、空調装置など電気の使用が多い機器は自動的に停止させ、
メインの照明は消す場合(補助灯のみにする)があります。
余談ですが、営団地下鉄銀座線(現・東京メトロ銀座線)の第三軌条架線は、
駅の手前にデッドセクションがあるのですが、
当時はこの電動発電機を搭載していなかったので、
駅に入る寸前に停電して暗くなっていました。
電動発電機を搭載したのは、
その後に開通した営団地下鉄丸ノ内線(現・東京メトロ丸ノ内線)からで、
こちらは少し暗くなる程度で真っ暗になることはありませんでした。
1−2、静止型交流変換装置
MGとともに鉄道ファンがよく口にするのが「SIV」です。
これはStatic Inverterつまり静止型交流変換装置の略です。
原理は制御方式で出たVVVFインバータ装置と同じで、
直流電気をインバータ装置で三相交流に変えます。
この変換はやはりサイリスタのON、OFFによって行なわれます。
また、交流電化の場合は、
「装置がインバータ!!」のため、そのままインバータに電気を流せないので、
整流器またはコンバータで直流にしてからインバータ装置に電気を送ります。
なお、VVVFインバータ装置はモーターの回転に合わせて電圧や周波数を変えていますが、
電気機器は50または60ヘルツの周波数対応で、
使う電気の電圧も一定のため、
SIVのインバータ装置は電圧や周波数を常に一定で出力しています。
SIVは電動発電機のように消耗部品がないため保守省力化が出来るとともに、
使用電気の量も少なくすることが出来ます。
欠点は装置の価格が高いことと、
デッドセクションなどで停電した時に対応出来ないことです。
そのため、ある程度の停電に対応できるように、
コンデンサやリアクトルなどの蓄電装置が別途必要になってしまいます。
コンデンサやリアクトルで蓄えられる電気の量は限られているので、
デッドセクション通過時は電気の消費の多い空調装置は
停止させるのが一般的です。
2、電動空気圧縮機
空気圧縮機は横文字で言うと「コンプレッサー」なので、
鉄道ファンたちは好んで「CP、CP・・・。」と鳴いています。
圧縮空気は空気ブレーキで使う他、
自動扉の開け閉めに使います。
しかし、空気圧縮機は動作音がうるさいため、
電力回生ブレーキを停止まで使えるようにしたり、
扉の開閉をリニアモーターなどにしたりして、
圧縮空気を極力使わないような技術を進んで導入しています。
現在の最新の電車の空気圧縮機は殆ど無用の長物化しています。
ただ、連結器が外れた場合の付随車のブレーキや非常時のブレーキ、
電力回生ブレーキが失効した場合(抵抗非搭載)の空気ブレーキなどには
圧縮空気が必要なので、
空気圧縮機を完全に無くすことは出来ません。
なお、「電動」なので、圧縮機を動かすのはモーターで、
このモーターは交流モーターを使います。
空気圧縮機は主なものにピストン式とスクリュー式があります。
何れも空気ブレーキや扉開閉で圧縮空気を使い、
元空気ダメの圧縮空気が少なくなると作動し、
元空気ダメの圧縮空気が満タンになると止まります。
2−1、ピストン式空気圧縮機
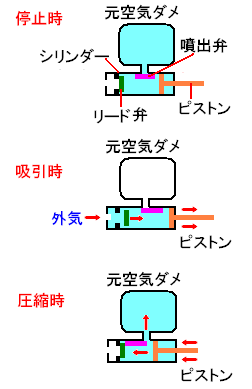
空気を密封容器に入れ、
外から圧力をかけて体積を小さくすると空気は圧縮されます。
これをピストン(注射)運動と言うのですが、
ピストン式はそのピストン運動をピストン(注射)で行なう方式です。
空気圧縮機が停止中の時は外気を取り込むリード弁と、
元空気ダメに圧縮空気を送る噴出弁は閉じています。
吸引時になるとピストンが引かれ、
それに伴いリード弁がスライドして外の空気が取り込まれます。
そして、シリンダー内が空気で満たされたら、
今度はピストンを押します。
そうすると、リード弁が閉じて今度は噴出弁が開きます。
ピストンにより空気は圧縮され、
圧縮空気はシリンダーから元空気ダメに送られます。
ピストン式の空気圧縮機はこれを繰り返して元空気ダメにどんどん圧縮空気を送ります。
ピストン式の空気圧縮機は構造が簡単なのですが、
動作音がうるさいのと、動作音にあわせて振動も激しいので、
最近はあまり導入されません。
動作音は空気圧縮機の製造メーカーにより異なりますが、
「ドンドンドンドン・・・。」とか、
「ミャンミャンミャンミャン・・・。」
「カタカタカタカタ・・・。」と言う音がします。
この繰り返される音1音あたり、1回のピストン運動が行なわれています。
2−2、スクリュー式空気圧縮機
スクリュー式はローターと言う歯車を回転させて空気を圧縮させる方式です。
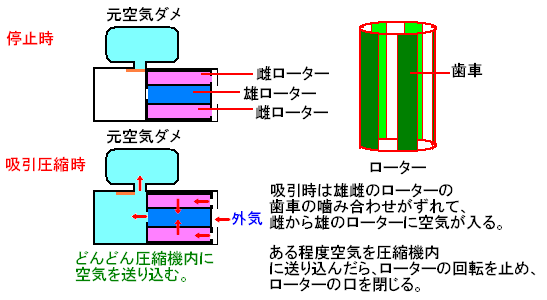
元空気ダメの圧縮空気が少なくなると、
空気圧縮機の中のローターが回転しだします。
ローターは雄ローターと雌ローターがあり、
外の空気は最初、雌ローターに入ります。
回転開始時は雌雄のローターの歯車がお互い噛み合っているので、
雌ローターから雄ローターに空気は行きません。
しかし、回転していく毎にお互いの歯車の噛み合わせがずれていき、
歯車の隙間から空気が通るようになり、
雌ローターから雄ローターに空気が行くようになります。
そして、雄ローターはシリンダーへ空気をどんどん送っていきます。
そして、ある程度シリンダー内に空気が入ったらローターの口を閉じて空気を圧縮し、
元空気ダメに空気を送ります。
ローターの回転を速くするとそれだけ早く圧縮空気が出来ます。
シリンダー等を小型化出来るので、
空気圧縮機自体も縮小化出来ます。
また、ピストン式だとピストンを押している時と引いている時に
空気圧の差が出来てしまうのですが、
スクリュー式は一定の回転数で回せば一定の空気圧に保てます。
スクリュー式はピストン式よりまあまあ作動音が小さいです。
あくまでも「まあまあ」で、やはり「静か」とは言えない状況です。
作動音は「キュルンダダダダダダダ・・・。」とかします。
電車の集電装置って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|