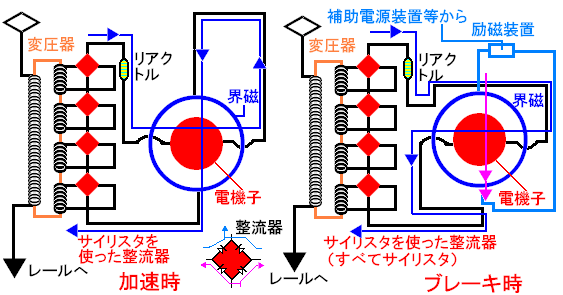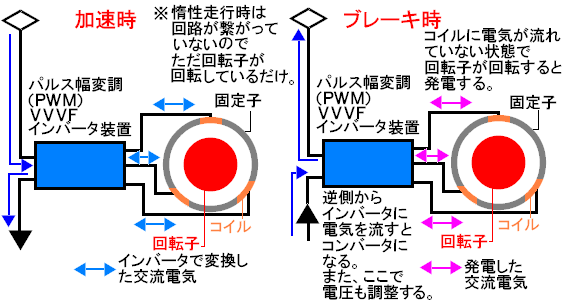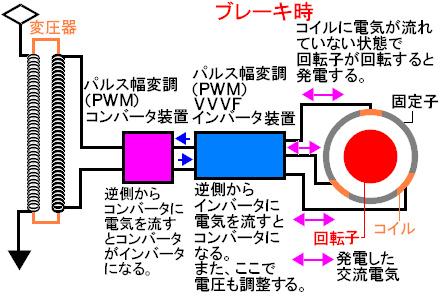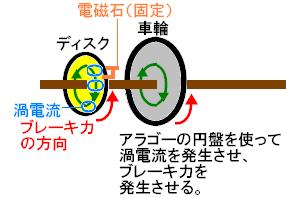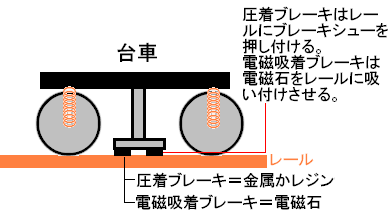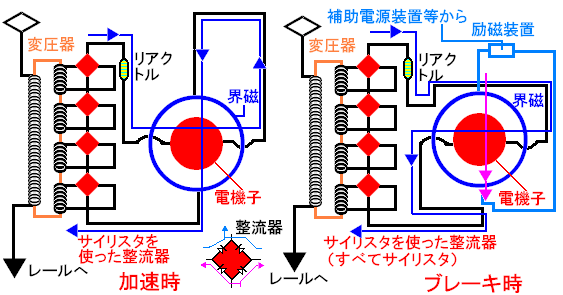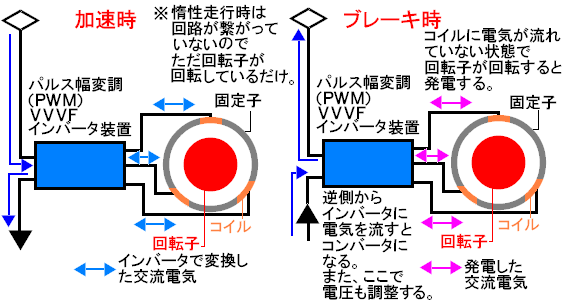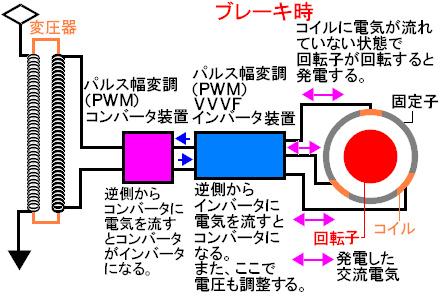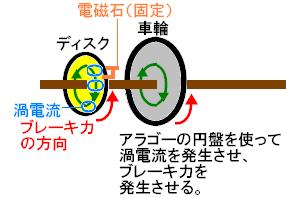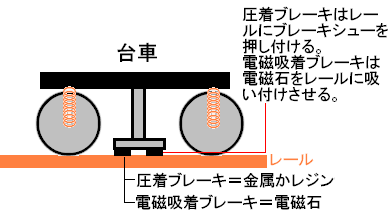電車の電気制動って何!?その2
3−4、加速がサイリスタ位相制御(整流器はすべてサイリスタ)の場合
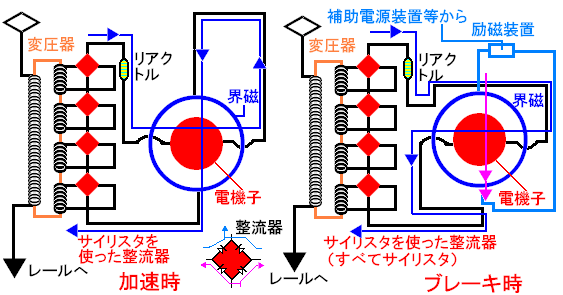
整流器がすべてON、OFF出来るサイリスタで構成されている
(ダイオードが入っていないもの、これをサイリスタ純ブリッジと言います。)
サイリスタ位相制御なら、電力回生ブレーキを使うことが可能です。
採用例が少ないのでなんとも言えないのですが、
今ある電車はブレーキ時に分巻モーターにして、
界磁の電気は補助電源装置などから貰う他励磁方式にしています。
界磁添加励磁制御のように界磁だけを通る閉回路を作り、
そこに電気を流して界磁の磁束を高めます。
(理論的には電機子チョッパ制御と同じような回生ブレーキが出来ると思うのですが・・・。)
発電した電気はサイリスタのある整流器に送られるのですが、
サイリスタはただぼけーっとONにしっぱなしではなく、
ON、OFFを繰り返し、決められた周波数と適切な電圧の交流電気に変換します。
つまり、整流器を真逆のインバータとして使うのです。
整流器から変圧器へ流れる電気の電圧が高ければ、
変圧器は巻線比分電圧を高くすることが出来るので、
架線等に戻す電圧をやや高めにすることが出来ます。
3−5、加速が可変電圧可変周波数制御の場合
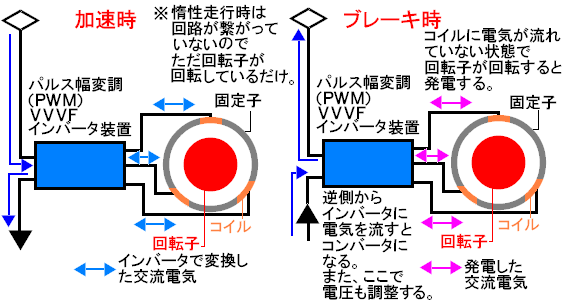
VVVF制御車の場合は一番単純で、
回路が繋がった状態で、
交流モーターのコイルに架線からの電気を流さないようにすると、
回転子の回転で勝手に発電してくれます。
発電した電気はVVVFインバータ装置に送ります。
VVVFインバータ装置は逆側から電気が流れるとコンバータに変身するので、
発電した三相交流の電気は、
VVVFインバータ装置によって適切な電圧の直流電気に変換されます。
あとは、それを架線に戻すだけです。
ブレーキ力はVVVFインバータ装置で調整します。
(サイリスタまたはトランジスタの組み合わせのON、OFFの間隔で。)
VVVF車は回路を全く切り替える必要が無いので、
保守点検が楽になります。
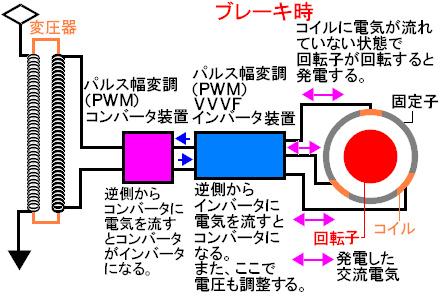
交流電車も殆ど同じで、異なるのは、
VVVFインバータ装置で直流にした適切な電圧の電気を、
コンバータ装置で単相交流に変換します。
コンバータ装置は逆側から電気が流れるとインバータに変身します。
あとは、変圧器で電圧を上げるだけです。
4、渦電流制動
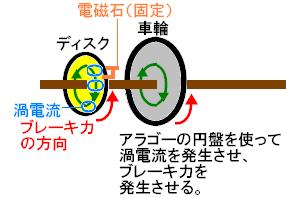
渦(うず)電流ブレーキは、VVVF制御方式の時お話しました、
アラゴーの円盤を利用して電車の速度を落とす方法です。
前回は磁石の方を動かして渦電流を発生させ、
円盤(ディスク)を動かしたのですが、
渦電流ブレーキは逆に車軸に繋がって
回転しているディスクに固定した電磁石を当てます。
そうするとディスクに渦電流が発生し、
回転とは逆側の力が働きます。
これがブレーキ力になり、電車の速度を落とします。
なお、電磁石の電気は発電ブレーキで発電した電気を使います。
付随車で意地でもうるさいコンプレッサーによる空気ブレーキを使いたくない場合、
この渦電流ブレーキを使う場合があります。
5、電磁吸着制動&圧着制動
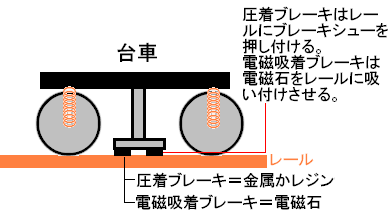
電磁吸着ブレーキは台車に電磁石の付いたブレーキシューを取り付け、
ブレーキ時はブレーキシューに付いた電磁石を
レールに下ろして吸い付けさせることによって、
電車を止めるブレーキです。
圧着ブレーキはブレーキシューが電磁石ではなく、
通常の金属かレジンで、
動作も圧縮空気で行なわれます。
しかし、どちらもレールにブレーキシューを押さえつけて確実に止めるのは同じです。
通常の鉄道路線の車両では使わないブレーキですが、
急勾配のある路線は非常ブレーキとして、
この電磁吸着ブレーキか圧着ブレーキが使われます。
6、電気制動の応用
電気ブレーキを使った、
色々な応用ブレーキがあります。
その中でもよく使われるのは抑速(よくそく)ブレーキです。
長い下り坂が続く路線は、
「スピードが上がったらブレーキをかける」
と言う動作を何度も行なわなければならず、
運転士にとっては非常に面倒くさく、
ブレーキタイミングを誤ったら必要以上に速度が上がって大事故に繋がるので、
そういう路線を走らせる電車には抑速ブレーキが付いています。
抑速ブレーキは主幹制御器など(ハンドル)を所定の位置に合わせると投入され、
惰性走行時、必要以上にスピードが上がった場合、
自動的にブレーキ回路を組んで、発電ブレーキまたは電力回生ブレーキをかけます。
そして、スピードがある程度落ちたらブレーキ回路を切って、
また惰性走行に戻ると言うことを行ないます。
電車の台車構造って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|