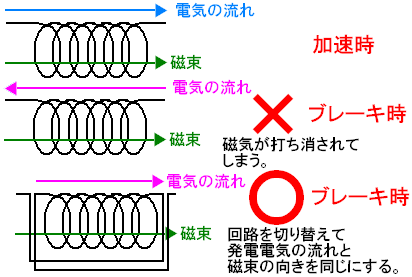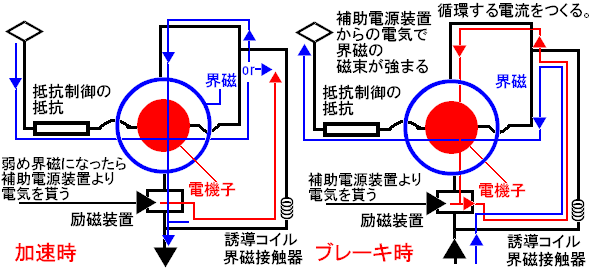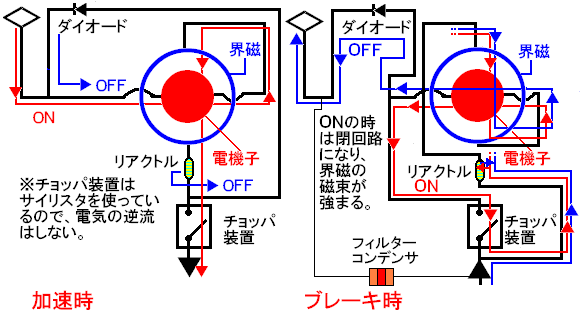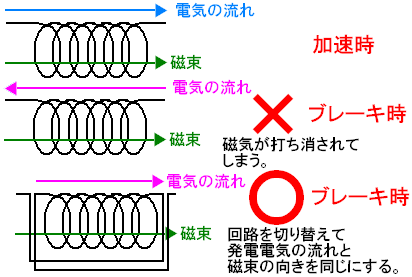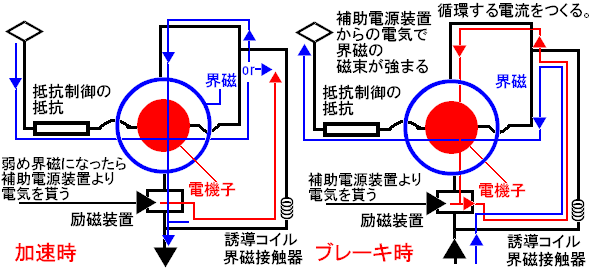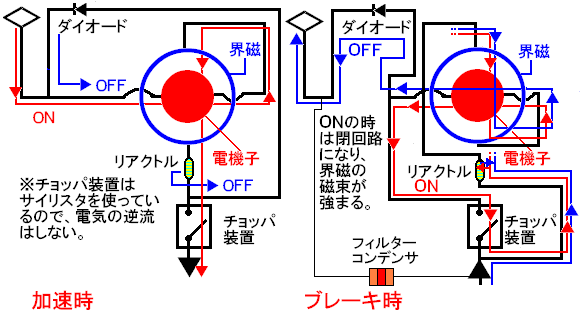電車の電気制動って何!?その1
電車は空気ブレーキの他に電気ブレーキも使えます。
電気ブレーキは電気の特性を利用してかけるブレーキで、
代表的なのにモーターを発電機として利用し、
ブレーキ力を得るものがあります。
1、発電制動と電力回生制動とは
発電ブレーキと電力回生ブレーキは共にモーターを発電機にして、
ブレーキ力を得るものです。
・・・と言っても、ピンと来ないと思います。
身近なもので考えるならば、
自転車のライトが良いと思います。
自転車のライトはダイナモと言う発電機の発電電気で点いています。
ダイナモはタイヤに押し付けてローラーを回転させることによって、
発電しています。(「勝手にライト自転車」や電池のライトは除く)
しかし、最近無灯火の自転車が増えている理由として、
「ダイナモをタイヤに押し付けるとペダルが重くなる!!」と言うのがあります。
これは、ダイナモが発電することによって、
運動エネルギー(ペダルをこぐ力)が電気エネルギーに変わっているからです。
発電ブレーキと電力回生ブレーキはこれと全く同じで、
モーターが発電機として発電することにより、
運動エネルギーが電気エネルギーに変わり、
運動エネルギーの量がだんだん減ってくるため、
ブレーキ力が発生するのです。

これは発電機の図です。
「制御方式の時と同じ直流モーター図じゃないか?」と思われた方もいらっしゃると思いますが、
よく見ると電気の流れる方向が違います。
モーターの場合、フレミングの左手の法則を使うのですが、
発電機の場合は、フレミングの右手の法則を使います。
モーターの界磁は加速時に磁気を帯びるのですが、
その磁気はしばらく残っています。
そこで、その界磁に残っている磁気の中(磁界)で、
電機子を車輪の回転力で回転させると電気を発電します。
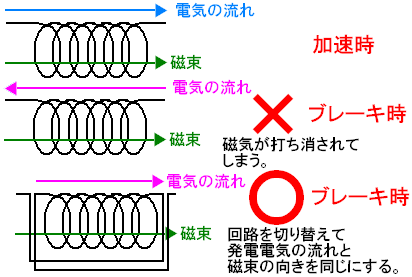
ただ、気をつけなければならないのが、
電気の流れる方向で、
電車の界磁は電磁石を使っているため、
加速と同じ回路構成だとブレーキ時に界磁のN極とS極が逆転してしまいます。
そうすると、残っている磁力に対して反対の磁力が発生してしまい、
双方で打ち消しあって磁気が無くなり、発電出来なくなってしまいます。
電力回生ブレーキの場合は発電出来なくなると、
架線から電気を集電してしまい、モーターになってしまいます。
そこで、発電ブレーキや電力回生ブレーキを使う場合は、
電機子または界磁の回路を繋ぎ変える必要があります。
(直流モーターの場合のみ)
なお、先のページで書いたとおり、
発電ブレーキや電力回生ブレーキなどの電気ブレーキは速度を落とすブレーキで、
確実に止めるブレーキではありません。
また、モーターの無い付随車では勿論使えません。
付随車はモーターのある電動車と連結器で繋がっているので、
ある程度の速度までは電動車の速度低下でカバー出来るのですが、
停止寸前は止めようとする大きな力が必要になるため、
電動車のブレーキ力だけではカバー出来なくなります。
そのため、停止寸前の付随車は従来通り空気ブレーキなどを使うことが多いです。
また、連結器が外れると、付随車は全くブレーキがかけられなくなるので、
保安ブレーキも空気ブレーキなど、他の系統のブレーキを使います。
また、発電ブレーキや電力回生ブレーキは
速度が低くなるとブレーキの利きが悪くなります。
(最新のVVVF制御車は除く)
低速域では電動車も空気ブレーキを使うのが一般的ですが、
ブレーキ回路のままほんの気持ちだけ架線から電気を集電すると、
電機子に逆回転しようとする力が働くので、
結果的にブレーキになります。
これを純電気ブレーキと言います。
勿論、「ほんの気持ちだけの集電」と言うのがポイントで、
集電しすぎるとマジで電機子が逆回転して、
電車を止めるどころかバックしてしまうと言う
シャレにならないことが起こってしまいます。
2、発電制動
発電ブレーキは、モーターで発電した電気エネルギーを、
抵抗で熱エネルギーに変えることによって、
ブレーキ力を得るものです。
ラッキーなことに抵抗制御(広義)は加速時に使う抵抗を持っているので、
それを発電ブレーキに使う抵抗に流用出来ます。
発電ブレーキは、車輪の回転力=運動エネルギーを電気エネルギーに変え、
更に熱エネルギーに変えるというエネルギーのたらいまわしを行なっています。
発電ブレーキは抵抗制御(広義)の他、
回生ブレーキが使えない交流電車のタップ制御、
サイリスタ位相制御(整流器にダイオードがある場合)にも使われています。
そのため、タップ制御やサイリスタ位相制御は
発電ブレーキ用の抵抗を搭載しています。

発電ブレーキはブレーキ時になったら、回路を繋ぎます。
先ほど書きましたように、界磁のN極とS極を加速時と揃えるため、
界磁または電機子の回路を繋ぎ変えます。
回路の間に抵抗を挟み、その抵抗が熱を発することによって、
ブレーキ力が発生します。
なお、抵抗は制御方式で使っているものと同じものなので、
抵抗の値(インピーダンス)を変えることによって、
ブレーキ力を変えることが出来ます。
発電ブレーキ車は抵抗から熱を発するので、
電車の床下がポカポカして暖房代わりになります。
寒い雪の日に発電ブレーキ(抵抗制御)車が来るとほっとします。
しかし・・・、夏は床下から熱風が容赦なく吹き上げ、
灼熱地獄になります。
夏、走らせることを考えると、
かなりエネルギーのロスになっているのがこのブレーキの欠点です。
3、電力回生制動
発電ブレーキは折角発電した電気を
使い道の無い熱エネルギーに変えてしまいます。
「このエネルギーもったいねーじゃねーか。この電気を有効利用しようぜっ!!」
と、言うことで考え出されたのが電力回生ブレーキです。
電力回生ブレーキはモーターで発電した電気を架線に戻すことによって、
電気の有効利用が出来るブレーキです。
がっ!!電気を架線に戻すのは結構大変だったりします。
●まず1に、直流電化の場合、
発電した電気を使ってくれる他の電車(加速中)が無いとブレーキが利きません。
これを「回生失効」と言います。
まあ、大都市圏の電車の本数の多い通勤路線は問題ないと思います。
ただ、本数が少ないローカル線で電力回生ブレーキを使うと失効することが多くなります。
この場合、とるべき方法は以下のものがあります。
A,諦めて空気ブレーキに切り替えると言う王道な方法。
B,こんな時のために抵抗を搭載し、発電ブレーキに切り替えると言う方法。
C,「意地でも回生ブレーキで止めてやるっ!」と、
変電所または電車に、発電した電気をプールしておける蓄電装置を設けたり、
電車の加速以外のもので電気を消費させると言う方法。
ただ、大体ローカル線は赤字路線が多いわけで、
Cのようなお金のかかる方法を取るのは、
一部のお金持ち鉄道会社のローカル線くらいです。
●2に、発電した電気を架線に戻すには、
架線の電圧よりやや高めにしないといけません。
でないと、発電どころかパンタグラフから架線の電気を集電してしまい、
モーターが発電機でなく、そのままモーターになってしまいます。
しかも、電力回生ブレーキのため界磁の回路を切り替えた場合は最悪で、
前進している電車がいきなりバックすると言うスリリングなことになってしまいます。
そのため、電力回生ブレーキが使えるのは、電圧を高くしたり、
架線からの電気を通さないような仕組みがある制御方式の電車のみです。
(電圧を高くするには界磁の磁束をなんらかで強めなければなりませんし、
架線からの電気を流さないようにするためにはダイオードなどが必要です。)
抵抗制御(広義)の場合、電圧を低くすることは出来ても高くすることが出来ないので、
電力回生ブレーキは使えません。
●3に、交流電化の場合、周波数を架線の電気と揃えないといけないのですが、
タップ制御やサイリスタ位相制御(整流器にダイオードがある場合)は、
発電した直流電気を決まった周波数(東50ヘルツ、西60ヘルツ)の交流に出来ません。
そのため、両制御方式は電力回生ブレーキが使えません。
で、電力回生ブレーキなのですが、
これが制御方式によって方法がバラバラで説明しにくかったりします・・・。
3−1、加速が界磁添加励磁制御の場合
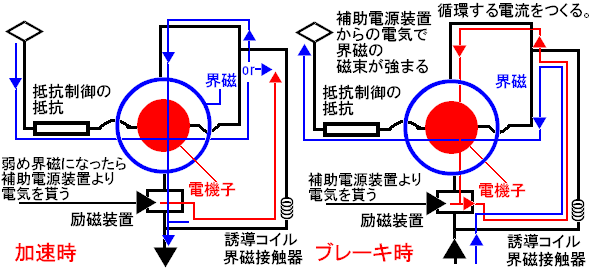
界磁添加励磁制御の回路は抵抗制御(広義)と殆ど変わらないのですが、
弱め界磁制御の時に使う励磁装置で補助電源装置から電気を貰うことが出来るので、
これを界磁のみに流れる閉回路(電気が循環する回路)に流すことによって、
界磁の磁束を強めることが出来ます。
界磁の磁束が強まれば、発電電気の電圧を上げることが出来ます。
ブレーキ力は誘導コイルや界磁接触器、
抵抗制御(狭義)の抵抗によって調節することが出来ます。
界磁添加励磁制御の場合、
回路を複雑に組み替えなくても電力回生ブレーキが使えるのですが、
この回路だと純電気ブレーキが使えないので、
純電気ブレーキを使おうと思う場合は回路を切り替えなければなりません。
(界磁添加励磁制御の純ブレーキ車っておそらく無かったと思いますが・・・。)
3−2、加速が界磁チョッパ制御の場合

電力回生ブレーキを使うためには界磁の磁束を強めれば良いのですが、
残念ながら電車のモーターは、
電機子と界磁が一緒の回路で繋がっている直巻モーターが多く、
界磁の磁束を強めるために架線から電気を集電してしまうと、
電機子にも電気が流れてしまい、
結果としてモーターになってしまいます。
そのため、電機子チョッパ制御や界磁添加励磁制御が開発されるまで、
電力回生ブレーキが使えるのは、複巻モーターの制御のみでした。
幸か不幸か界磁チョッパ制御は電機子と回路が繋がっている界磁と、
繋がっていない界磁とに分かれている複巻モーターを使うので、
電力回生ブレーキが容易に使える利点があります。
ブレーキをかけたとき、架線から電気を集電して、
電機子を通らない界磁の方に電気を流します。
そうすると、界磁だけ電気が流れることになるので、
界磁の磁束が強まります。
ブレーキ力はチョッパ装置のON、OFFで調節することが出来、
ブレーキを強くしたい場合はチョッパ装置のONの時間を長くし、
界磁のみの回路に電気を多く流して界磁の磁束を強めます。
複巻モーターは保守が大変なのですが、
電力回生ブレーキが使えるのは魅力的なので、
一時期大手民鉄がこぞって界磁チョッパ制御を採用しました。
そのため、大手民鉄は比較的界磁チョッパ制御車が多くなっています。
3−3、加速が電機子チョッパ制御の場合
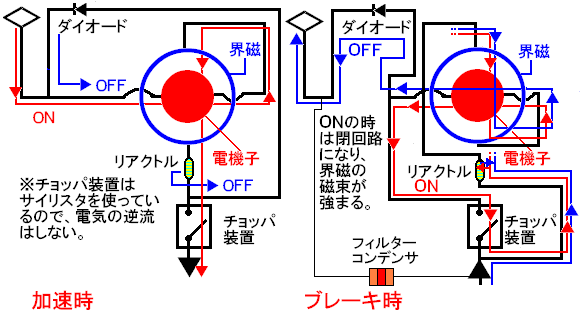
電機子チョッパ制御の場合、とりあえず加速時の界磁の残留磁気で発電します。
しかし、それだけではたいした電気を発電していないので、
電圧も低い状態です。
そのため、途中にチョッパ装置とリアクトルのある閉回路を作り、
発電電気をリアクトルに蓄えておきます。
リアクトルは発電電気すべてを蓄えることが出来ないので、
リアクトルに蓄えられなかった電気は界磁に流れ、
界磁の磁束を強める役割を行ないます。
リアクトルにある程度電気が貯まり適切な電圧になった時、
チョッパ装置をOFFにして閉回路を遮断して架線に電気を戻します。
ブレーキ力はチョッパ装置のON、OFFで調節することが出来、
ブレーキ力を強めたい時はチョッパ装置のONの時間を長くし、
界磁の磁束を強めつつ、リアクトルに電気を蓄えます。
電機子チョッパ制御の電車が、
減速時もチョッパ装置から「ビー」と言う音がするのはこのためです。
ただ、架線に戻る電気は、
チョッパ装置で色々な周波数(ON、OFFの間隔)の電気が
ごちゃごちゃ混ざっている状態で、
一部の周波数の電気は通信機器に悪影響を及ぼしてしまいます。
これを架線に戻さないようにするためにフィルターコンデンサを使い、
不適切な周波数の電気はコンデンサに吸い付けて除去し、
特定の周波数の電気だけ架線に戻すようにします。
電機子チョッパ制御は加速時に使うダイオードやチョッパ装置、
リアクトルなどを効率よくブレーキに転用しているのですが、
そのためにぐちゃぐちゃ訳の分からない
複雑な回路の切り替えをしなければならないのが欠点で、
回路の切り替えが多くなると、故障が多くなり、
保守点検も面倒になります。
電車の電気制動って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|