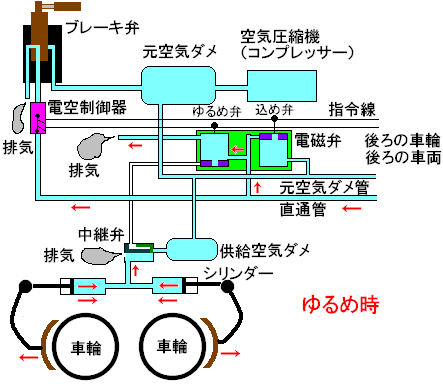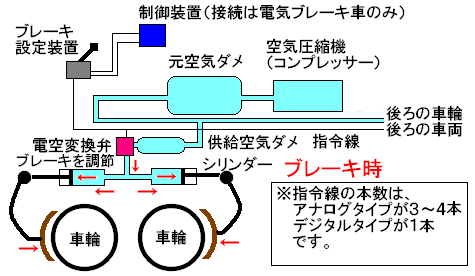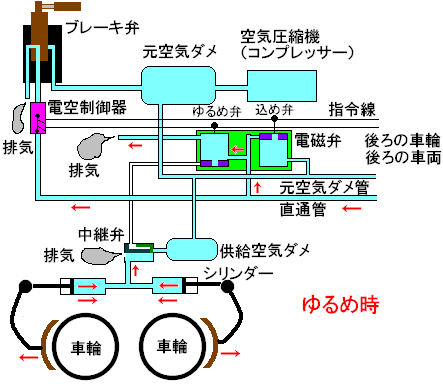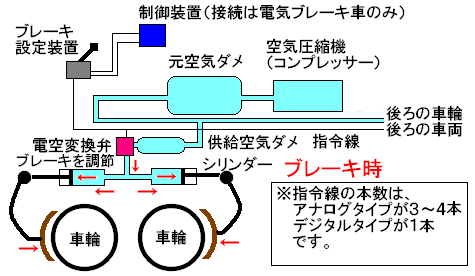電車の空気制動って何!?その2
4、電磁直通空気制動
「直通空気ブレーキや自動空気ブレーキは運転が煩わしく、
所定の位置に止めるのは難しいし、
後ろの車両に行くほど応答が悪いし・・・。」
と、不満が爆発したので、
抜本的にブレーキ装置を見直してメカニック調にしたのが、
電磁直通空気ブレーキです。
「電磁なんちゃら〜」と言う場合、
大抵、電磁石と磁気を帯びる物質(鉄など)の吸引、反発を使う仕組みになっていて、
この電磁直通空気ブレーキも電磁石と物質の吸引、反発を利用しています。

電磁直通空気ブレーキの場合、
元空気ダメからの空気は元空気ダメ管に送られるのですが、
ブレーキ弁をブレーキに投入すると、
電空制御器の方にも圧縮空気が送られます。
電空制御器は直通管からの圧縮空気と元空気ダメからの圧縮空気の気圧差で、
指令線へのスイッチが切り替わるような仕組みになっています。
ブレーキ時の直通空気管からの圧縮空気と元空気ダメからの圧縮空気を比較すると、
元空気ダメからの圧縮空気の方が空気圧が高いので、
そのときはスイッチが入るようになっています。
電空制御器のスイッチに繋がっている指令線は2本あり、
1本は込め弁用、もう1本はゆるめ弁用になっています。
両方の指令線のスイッチが入ると、
各車両にある電磁弁の込め弁がON、ゆるめ弁がOFFになり、
電磁弁から中継弁に圧縮空気が送られるようになります。
なお、電磁弁の込め弁、ゆるめ弁のON、OFFは、
電磁石の吸引、反発で切り替わる仕組みになっています。
電磁弁から中継弁に圧縮空気を送ると、
注射運動により元空気ダメ管に繋がっている、供給空気ダメの口が開き、
ブレーキシリンダーに圧縮空気が送られます。
車両間の電磁弁操作は指令線で行なわれるので、
ブレーキの応答が速くなり、
後ろの車両もすぐにブレーキがかかります。

ブレーキをかけ続けると、電磁弁から直通管へ圧縮空気がどんどん送られ、
直通管の空気圧が高くなり、
元空気ダメからの圧縮空気との気圧差が少なくなります。
そうすると、電空制御器の込め弁の指令線のスイッチが切れ、
ゆるめ弁の指令線のみスイッチが入ることになります。
そうすると、込め弁、ゆるめ弁ともに電磁弁ではOFFになり、
元空気ダメ管から直通管に圧縮空気が行かなくなるので、
電磁弁から中継弁への圧縮空気も一定になります。
そうすると、中継弁では供給空気ダメの口がふさがり、
元空気ダメからの圧縮空気は全くシリンダーに行かなくなるので、
シリンダー内は一定空気圧を持続出来ることになります。
つまり、電磁直通空気ブレーキは、
自動的にブレーキ位置から重なり位置に切り替えてくれるのです。
そのため、いちいちブレーキハンドルをいちいちブレーキ位置、
重なり位置に細かく動かさなくても、
一定の目盛に投入すれば、それに応じたブレーキ力が発生することになるのです。
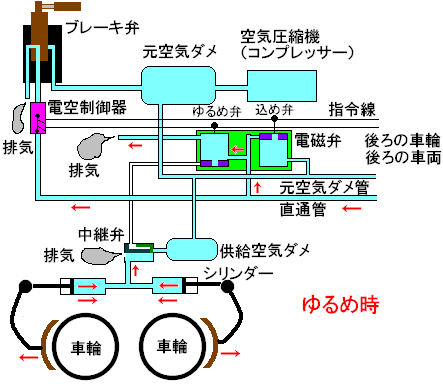
ゆるめ時は直通管の圧縮空気が排気され、
空気圧が下がります。
そうすると、電空制御弁は込め弁、ゆるめ弁ともに指令線へのスイッチは切れます。
そうすると、電磁弁の込め弁はOFF、ゆるめ弁はONになり、
電磁弁からも圧縮空気が排気されます。
電磁弁から中継弁に圧縮空気が行かなくなるので、
シリンダーの圧縮空気が中継弁に逆流し、
注射運動によりピストンが押し上げられ、
中継弁の排気口が開き、圧縮空気が排気され、
シリンダーのピストンは元に戻るようになります。
中継弁の供給空気ダメの口は閉じているので、
シリンダーには全く圧縮空気が行きません。
電磁直通空気ブレーキはこういった仕組みなのですが、
多分、「配管や機器がぐちゃぐちゃでよくわからねぇ。」と思ったと思います。
それが、この電磁直通空気ブレーキの欠点で、
配管が複雑になり、電空制御器や電磁弁などの機器が増えるので、
保守はかなり大変になります。
それと、
「これって、ブレーキ管が外れたり、指令線が切れたりしたらやべぇんじゃねぇ?」
と、思った方もいらっしゃると思います。
確かにかなりやばいです。
指令線が切れると電磁弁は全く機能しなくなりますし、
ブレーキ管が外れると直通空気ブレーキと同じ目に会います。
つまり、連結器が外れて、ブレーキ管や指令線が外れたり切れたりすると、
ブレーキが全くかからなくなるのです。
そのため、電磁直通空気ブレーキを使う場合は、
保安ブレーキと言う、
別系統の非常電磁弁からブレーキシリンダーに圧縮空気を送るブレーキを
併用しなければなりません。
保安ブレーキは非常電磁弁に電気が流れなくなると、
弁が開き、シリンダーに圧縮空気が行く仕組みになっています。
また、ブレーキ管の空気圧が急激に弱まった場合も、
同様に非常電磁弁からシリンダーに圧縮空気が送られます。
非常ブレーキをかけるとき(またはブレーキ弁からブレーキ幹を外す場合)、
「バーン」と言う激しい空気が漏れる音がする電車の場合、
態とブレーキ管の空気圧を下げて、
非常電磁弁からシリンダーに空気を送る仕組みになっています。
5、電気指令式空気制動
電磁直通空気ブレーキの登場で、電車の運転はかなり楽になり、
乗り心地も向上したのですが、
そのうち、整備担当からは「配管が複雑で大変だ!!」と言う不満が増え、
運転士側も、「ブレーキ弁がでかくて足元が狭い。もっと運転台をスリムに出来ないか!?
出来れば、主幹制御器(マスコン)とブレーキ弁を一体化したワンハンドルが良いなあ。」
と言う要望も出てきました。
そこで、登場したのが電気指令式空気ブレーキです。
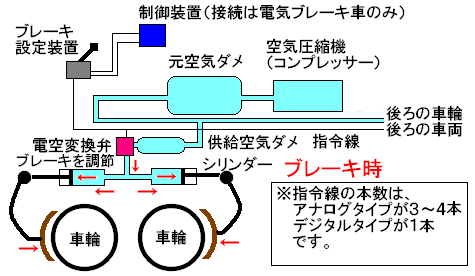
電気指令式空気ブレーキの場合、
運転台には全く圧縮空気を送りません。
そのため、ブレーキ弁はなくなり、
変わりにブレーキ力を設定するブレーキ設定装置
(まあ、ブレーキハンドルに変わりないのですが・・・。
くだらないことに拘る鉄道ファンと話す時はそう言った方が無難です。)
が設けられています。
ブレーキ設定装置を操作することにより、指令線にその情報が伝達されます。
指令線は各車両にある電空変換弁に接続されていて、
その電空変換弁で、
指令線の信号に合った圧縮空気の込め、ゆるめ、重なりが自動的に行なわれます。
なお、電気指令式空気ブレーキの指令線はアナログタイプとデジタルタイプがあります。
アナログタイプは3〜4本の指令線が必要で、
各指令線の信号のON、OFFの組み合わせで、
電空変換弁を制御します。
デジタルタイプはアナログタイプのON、OFFを
0と1の組み合わせ信号に変えたもので、
指令線は1本で済みます。

上の図はアナログタイプの中継弁の構造です。
それぞれの電磁弁(電空変換弁)がON、OFFの電気指令により、
中継弁に空気を送ったり送らなかったりすることによって、
(「電磁」・・・つまり電磁石の吸着と反発を利用しているわけです。)
中継弁の供給弁がスライドし、
シリンダーに送る空気を調整することが出来ます。
ブレーキ力はそれぞれの電磁弁のON、OFFの組み合わせで調節します。
なお、電磁直通ブレーキと電気指令式ブレーキの電車は、
発電ブレーキや回生ブレーキなどの電気ブレーキを併用している電車が多く、
高速域は電気ブレーキ、停車寸前または付随車は空気ブレーキと使い分けています。
そのため、電気ブレーキから空気ブレーキに円滑に切り替わるよう、
ブレーキ装置と制御装置間で信号のやりとりを行なっています。
そういったやりとりを電空協調制御と言います。
電気指令式空気ブレーキは電磁直通空気ブレーキと同じく、
ブレーキ管や指令線が外れたり切れたりするとブレーキがかからなくなるので、
保安ブレーキを併用しています。
電車の電気制動って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|