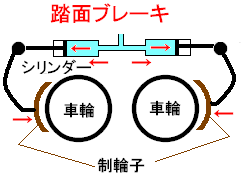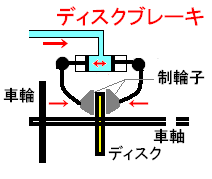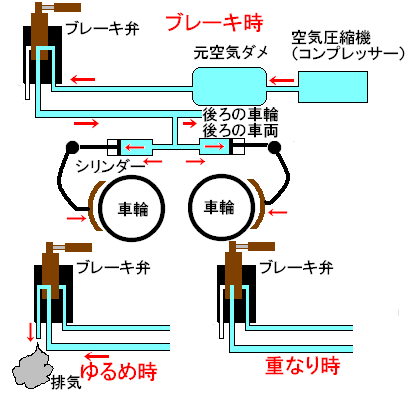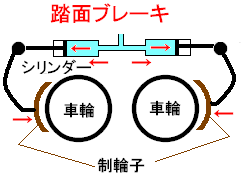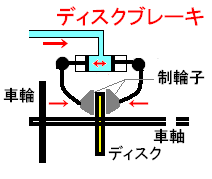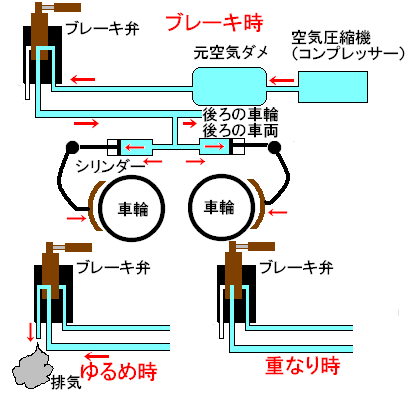電車の空気制動って何!?その1
電車を止めるときは制動(ブレーキ)をかけます。
と言うと、「バーカ!!当たり前だろ!?」と言われてしまいそうですが、
電車のブレーキは結構奥が深かったりするため、
実際の仕組みは余程の玄人鉄道ファンでないと分からない場合が多いです。
電車のブレーキは空気ブレーキ、電気ブレーキ、その他ブレーキの3種類と、
それを応用したブレーキがあります。
そのうち、空気ブレーキは電車や気動車の基本のブレーキとなるため、
基礎ブレーキと呼ばれています。
また、機械的に止めるため、機械ブレーキとも言われています。
最近の電車は電気ブレーキで殆ど止めてしまうため、
空気ブレーキの存在は薄くなりつつあるのですが、
電気ブレーキは「速度を落とすブレーキ」で、
「動かないように止めておく、確実に止めるブレーキ」ではないので、
空気ブレーキまたは、
その他ブレーキ(電磁吸着ブレーキなど)は必須となっています。
1、踏面ブレーキとディスクブレーキ
空気ブレーキは大きく分けて2種類のブレーキ方法があり、
一つは制輪子(ブレーキパッド)を
車輪の踏面(レールに接する部分)に当てるタイプと、
もう一つは車輪の内側または外側にディスク(円盤)を取り付け、
そのディスクの両側面を制輪子で挟みこむタイプがあります。
制輪子は昔、金属製だったのですが、
今はレジン制輪子が一般的になっています。
レジンは合成樹脂や鉛、油など混ぜて加工したものです。
金属製の制輪子はキキキーッっとブレーキ音がうるさく、
雨の日は摩擦力が弱まるためブレーキがききにくくなります。
更に、磨耗が激しく茶色い鉄粉が飛散すると言う欠点もあります。
しかし、レジン制輪子はその欠点を克服しています。
ただ、レジン制輪子にも欠点があり、強いブレーキをかけると、
摩擦熱でレジンの一部が溶けてとてもくさい臭いを発します。
レジン制輪子を知らない一般の乗客は、
「毒ガスでも撒かれた??」と思ってしまうかもしれません。
また、レジンの一部成分にアスベスト(石綿)を使っていた時期もあるので、
古い電車はあまり制輪子に近づかない方が良さそうです。
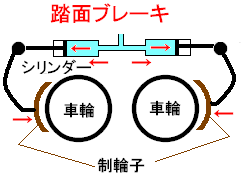
上の図は踏面ブレーキです。
図では片側だけ制輪子を当てていますが、
両側から挟みこむタイプもあります。
踏面ブレーキの構造は単純で、ブレーキ自体の保守は楽なのですが、
車輪の踏面に制輪子を当てるので、
次第に踏面が摩擦で磨耗し、デコボコになってしまいます。
そのため、定期的に車輪の踏面を研磨しないと、
乗り心地がとても悪くなり、走行音もうるさくなります。
走行中、「ダンダンダンダンダン・・・。」と言う音がする場合は、
踏面が磨耗している証拠です。
ただ、最近の回生ブレーキの電車は止まる寸前まで空気ブレーキは使わないので、
踏面研磨の手間も減りつつあります。
また、別の欠点として、
踏面が汚れているとブレーキの効きが悪くなると言うことが挙げられます。
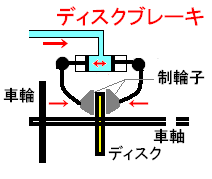
ディスクブレーキは車輪の内側、または外側にディスクと言う独立した円盤を設け、
それを制輪子で挟みこむことによって電車を止めます。
車輪の踏面は(空気ブレーキの原因による)磨耗をしないので、
研磨の手間が減り、
乗り心地も悪くなることはないのですが、
ディスクと言う部品が増えてしまうため、
保守などは逆に大変になってしまいます。
また、電動車はモーターのスペースもあるので、
車輪内側に付けにくいという欠点もあります。
そのため、踏面ブレーキとディスクブレーキは、
各鉄道会社の考え方でそれぞれ使い分けています。
なお、この後の図は全部踏面ブレーキで書かれていますが、
ディスクブレーキも仕組みは同じです。
2、直通空気制動
直通空気ブレーキは空気ブレーキの中で一番古いタイプで、
空気圧縮機で圧縮した空気圧の高い圧縮空気を、
直接シリンダーに送るブレーキ装置です。
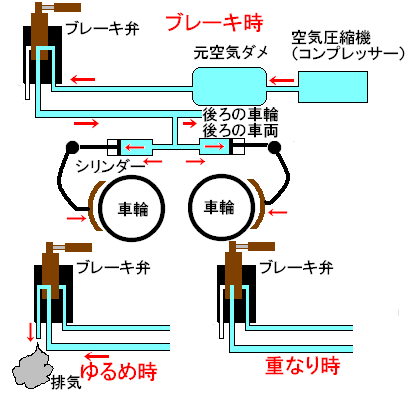
直通空気ブレーキはブレーキをかけるとき、
ブレーキ弁(ブレーキハンドル)を動かし、
元空気ダメの空気をシリンダーに送ります。
そうすると、シリンダー内のピストンが注射(ピストン)運動を起こし、押されます。
ピストンが押されると、それに接続された制輪子も押されて動くわけです。
一応、直通空気ブレーキは
2両以上の車両にブレーキをかけることが出来るのですが、
後ろの車両に行くほどブレーキの応答が悪くなり、
車両同士が押し合い引き合いし、ブレーキ時の乗り心地はかなり悪いです。
更に、連結器などが外れてブレーキ管も外れた場合、
圧縮空気がドンドン外に漏れてしまい、
ブレーキがかからなくなると言う最悪の事態になってしまいます。
そのため、原則2両以上繋げる電車には使わないブレーキで、
仮に単行で運転する場合も、予備系統のブレーキが必要になります。
ところでっ!!電車運転シミュレーションゲームの旧型電車運転は、
「ブレーキが8段階あり、それぞれの数字でブレーキのかかり具合が異なる。」
・・・と言う設定が多いのですが、これは嘘です!!
ブレーキに目盛があり、その目盛ごとにブレーキのかかり具合が変わるのは、
電磁直通空気ブレーキ以降のブレーキです。
直通空気ブレーキとこのあとの自動空気ブレーキはそんな目盛はなく、
ブレーキ位置、ゆるめ位置、重なり位置しかありません。
そのため、ブレーキ力を調整するのには、直通空気ブレーキの場合、
ブレーキ位置にハンドルを合わせ、一定のブレーキ力になった後、
重なり位置にしてそのブレーキ力(シリンダー内の圧力)を維持します。
そして、ブレーキ力を弱くしたい時は、
ゆるめ位置に持っていってシリンダー内の圧縮空気を排気して、
圧力を下げた後、また重なり位置に戻します。
そのため、停車するまで何度もブレーキハンドルをブレーキ位置、ゆるめ位置、
重なり位置に合わせなければならず、
所定の位置にピッタリ止めるのは職人芸的になってしまいます。
当然、高速運転の列車では不向きなブレーキなので使われてなく、
路面電車などあまり速く走らない電車の旧型電車に使っている程度です。
3、自動空気制動
「直通空気ブレーキはブレーキ管が外れた場合あぶねぇ!!」
と、言うことで登場したのが、
自動空気ブレーキです。

直通空気ブレーキはブレーキ位置にすると、
元空気ダメの空気がシリンダーに送られるのですが、
自動空気ブレーキは逆で、ブレーキ位置にすると、
ブレーキ管の圧縮空気が排気され、ブレーキ管内の空気圧が下がります。
そうすると、制御弁内のピストンが補助空気ダメの空気圧でスライドして、
同空気ダメの空気がシリンダーに送られます。
そして、シリンダー内のピストンが注射運動・・・(以下直通空気ブレーキと同じ)。
直通空気ブレーキと異なり、
ブレーキ管の圧縮空気を抜くことでブレーキをかけるシステムなので、
万が一連結器が外れ、ブレーキ管も外れた場合は、
ブレーキ管内の圧縮空気が排気され、
補助空気ダメの空気がシリンダーに送られるので、
外れた車両にもブレーキがかかります。
そのため、直通空気ブレーキより安全性が高くなります。
ただ、後ろに行くほどブレーキの応答性が悪いのと、
ブレーキ操作が難しいのは相変わらずです。

で、自動空気ブレーキのゆるめ位置と重なり位置なのですが、
ゆるめ位置の場合、元空気ダメから制御弁に圧縮空気が送られます。
制御弁では元空気ダメからの圧縮空気により、
ピストンが補助空気ダメの方向にスライドし、
圧縮空気が補助空気ダメに送られます。
一方、シリンダー内の圧縮空気は制御弁の排気口から排気され、
ブレーキが緩みます。
重なり位置はブレーキ弁の排気も制御弁の排気もされず、
制御弁内のピストンはブレーキ管側、シリンダー側両方の口を塞ぐので、
シリンダー内の空気圧は一定になり、
一定のブレーキ力が持続できます。
ブレーキのききが悪い時は補助空気ダメの圧縮空気が少ないと言うことなので、
一度ゆるめ位置に戻す必要があります。
電車の空気制動って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|