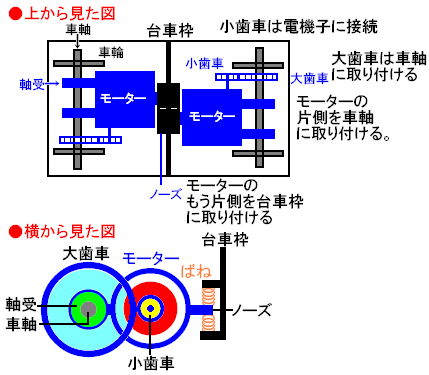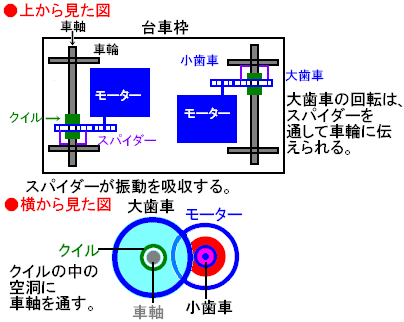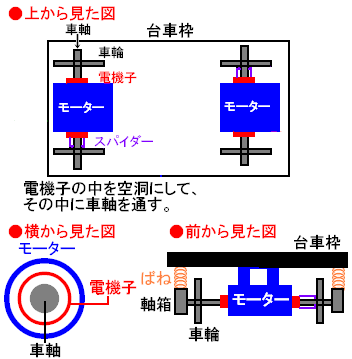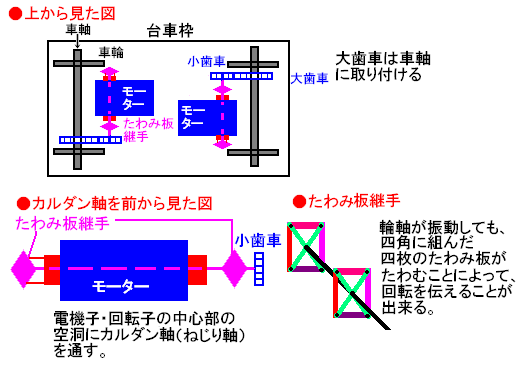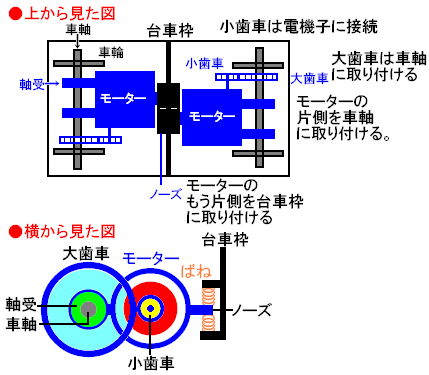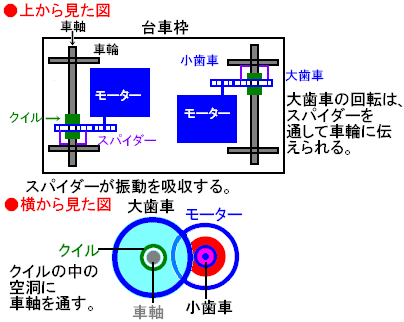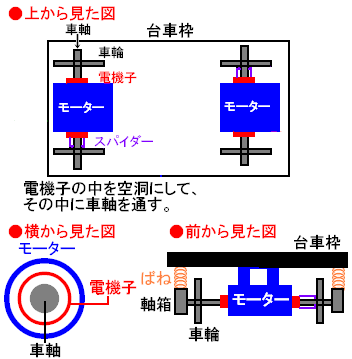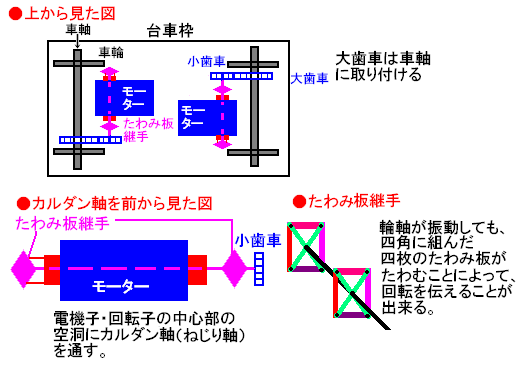電車の駆動装置って何!?
制御方式を使い、
直流モーターの電機子や交流モーターの回転子を回転させたら、
その回転を車軸に伝えます。
一般的発想だと、「単に電機子や回転子に付けた歯車と、
車軸に付けた歯車を噛み合わせれば良いだけだろ!?」と思ってしまうのですが、
そうは問屋が卸さないわけで、
それだけだと間違いなく歯車がぶっ壊れます。
それを防止するためにあるのが駆動装置と言うわけです。
1、駆動装置とは

何で駆動装置が必要なのかと言うと、
モーターと車輪の取り付け位置に問題があるからです。
モーターは台車枠に直接取り付けるのに対し、
車輪はレールの凹凸やレールの幅の変形による衝撃を吸収するため、
台車枠と車輪の間にばねを挟んで取り付けています。
レールのつなぎ目などで車輪が衝撃を受け振動が起きると、
当然車軸も振動が起きます。
それに対し、モーターはばねで振動を吸収した台車枠に取り付けているので、
あまり振動しません。
・・・と、言うことは、あまり振動しないモーターの歯車と、
振動する車軸の歯車を噛み合わせると・・・!!
バキーン!!と歯車が壊れてしまうわけです。
じゃあ、どうすれば良いのかと言うと、
二つの方法があります。
1、「モーターも輪軸(車輪と車軸のこと)と一緒に振動させてしまえ!!」
と言う暴挙に出ること。
2、「輪軸が振動しても何かその振動を吸収するものをモーターと歯車の間に挟もう。」
と言う紳士的な方法をとること。
昔は1しか方法がなかったのですが、
今は2の方法が一般的に使われています。
※なお、小歯車と大歯車の比率を歯車比と言います。
小歯車と大歯車の比率が近くなるほど高速域の伸びが良くなり、
大歯車の比率が大きくなるほど高加減速(トルク大)になります。
2、吊掛駆動方式(つりかけくどうほうしき)
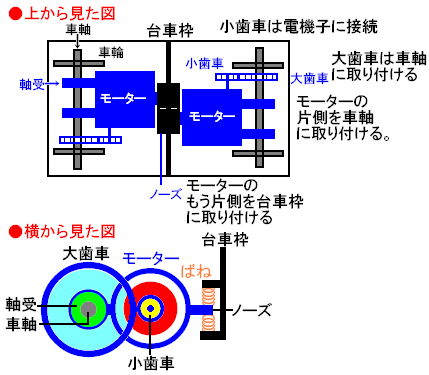
人によって「吊り掛け駆動」とか「釣り掛け駆動」とか書き方が異なりますが、
同じ方式です。
文字通りモーターを吊って掛ける方式なのですが、
この方式は先ほどの1の方式で、
モーターの片側を台車枠に、もう片側を車軸に取り付け、
輪軸の振動を共有して歯車を噛み合わせます。
吊掛駆動方式は余計な器具がないので、
構造が単純で保守点検は楽なのですが、
モーターの片側を軸受を使い、
車軸に取り付ける(端的に言うとモーターの重さの約半分を車軸に載せてしまう)
と言うのは、
良いわけ無いわけで、車軸にはモーターの重みがのしかかるので、
摩擦が生じ、高速運転が出来ないだけでなく、
車輪にもモーターの重みがかかるので、
レールを傷めてしまうという欠点があります。
モーター側も車軸と共に振動するので、
歯車やモーター自体が壊れやすくなり、
乗り心地も良くなく、騒音も大きいと言う欠点があります。
しかし、昔はこの方式しかなかったので、
一般的に使われていました。
現在は殆ど採用してなく、
残っているのは古い車両か、
古い車両の台車に新しい車体を載せ変えた車両くらいしかありません。
ただ、電気機関車は駆動力を重視するため、今も吊掛駆動方式を採用する事があります。
3、クイル駆動方式
吊掛駆動方式じゃああんまりだ!と言うことで登場したのがクイル駆動方式です。
クイルとは中空軸のことです・・・と書くと、
「中空軸ってなんだ!?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、
中空軸とは物体の中心部に穴を開けて貫通させ、
空洞にしたものを言います。
まあ、筒とか管とかを想像すると分かりやすいと思います。
クイル駆動方式はカルダン駆動方式が登場するまでの過渡的な駆動方式なので、
細かく見ると様々な種類があるのですが、
大雑把に分けると歯車有タイプと歯車無タイプの2種類に分けられます。
3−1、クイル駆動方式(歯車有)
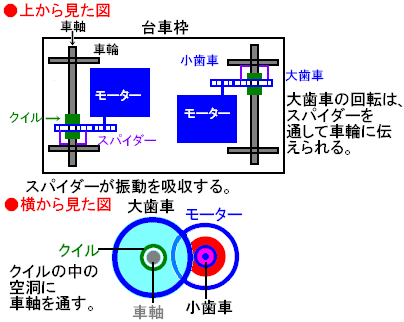
クイル駆動方式歯車有タイプは、
大歯車を車軸にべったり取り付けるのではなく、
大歯車の中心に穴を開けてクイルの管を入れ、
そのクイルの中の空洞に車軸を通します。
そうすることによって、車軸の振動が直接大歯車に伝わらなくなります。
しかし、そうするためには、
大歯車を車軸から浮き上がった状態(クイルが車軸に接していない状態)
にする必要があるので、
スパイダーと言うばねのような器具を大歯車と車輪に繋げます。
スパイダーは大歯車を浮き上がらせ、
回転を車輪に伝える役目があるのと同時に、
振動を吸収する役目があります。
スパイダーは完全に振動を吸収することが出来ませんが、
吊掛駆動方式に比べれば、モーターや歯車、レールへの負担が減り、
乗り心地も良くなります。
なお、モーターの取り付けは台車枠だけに取り付けるタイプや、
「片側台車、片側クイル」に取り付けるタイプなど色々あります。
3−2、クイル駆動方式(歯車無)
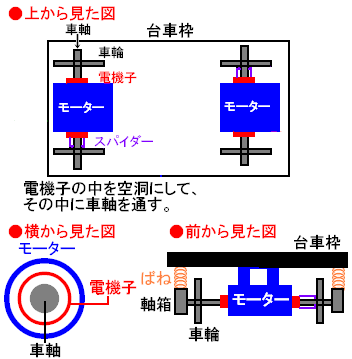
クイル駆動方式の歯車無タイプは、
モーターの中の電機子の中心を空洞にして、
その中に車軸を通します。
モーターは台車枠に取り付けられているため、
電機子と車軸は接触しません。
そのため、車軸の振動は電機子に直接伝わりません。
で、電機子の回転はやはりスパイダーなどのばね器具で伝えます。
輪軸の振動はスパイダーがある程度吸収するので、
モーターに振動が伝わりにくくなります。
4、中空軸平行カルダン駆動方式
クイル駆動方式はある程度振動を吸収出来るのですが、
「もっと抜本的に振動を吸収する方式はねぇか??」と言うことで、
考えられたのがカルダン駆動方式です。
「カルダンってなんじゃい!?」と思われると思いますが、
カルダンとは、電機子または交流モーターの回転子と継手(つぎて)、
継手と小歯車を結ぶ一連の回転軸(カルダン軸)のことを言います。
カルダン駆動方式の場合、モーターは完全に台車枠取付で、
輪軸の振動が直にモーターに伝わることはありません。
そのため、乗り心地は格段に良くなるばかりでなく、
高速運転も出来るようになります。
平行カルダン駆動方式はカルダン軸が車軸に平行してある方式で、
一般的には電機子や回転子の中心を空洞にした、
中空軸平行カルダン駆動方式が使われます。
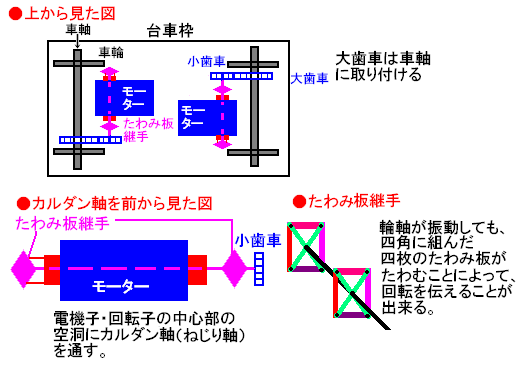
中空軸平行カルダン駆動方式の場合、
電機子の回転を小歯車とは反対側のたわみ板継手に伝えます。
たわみ板継手とは、たわみ板を四角に組んだもので、
輪軸が振動してもたわみ板継手がたわんで振動を吸収することによって、
回転を確実に伝達することが出来る器具です。
そして、回転を伝えられたたわみ板継手は、
電機子や回転子の中の空洞に通しているカルダン軸(ねじり軸)を通して、
もう一つのたわみ板継手に回転を伝えます。
もう一つのたわみ板継手は小歯車に回転を伝えます。
しかし、そう説明すると、
「なんで、電機子や回転子の回転を
一旦小歯車と反対側のたわみ板継手に伝えるんだ??
小歯車側に2つのたわみ板継手をつければ
電機子などを中空軸にする必要ないじゃないか!!」
・・・と言う疑問を感じると思います。
これは、ある程度の振動を吸収するには
カルダン軸(ねじり軸)を長くする必要があるのですが、
実際、モーターやカルダン軸に使えるスペースは狭軌で1067ミリ未満、
標準軌でも1435ミリ未満しかないので、
スペースが足らなさ過ぎるのです。
仮に無理矢理やると、モーターが台車枠からはみ出てしまうと言うことになります。
そのため、こんな複雑な回転伝達構造になってしまうのです。
5、直角カルダン駆動方式
中空軸平行カルダン方式も良いけど、
ちょっと構造が複雑だな・・・、
と言うわけで登場したのが直角カルダン駆動方式で、
「2つの車輪間のスペースが狭いなら、2つの車軸間のスペースを使おう」
と言う発想の転換をしています。
名前の通り、カルダン軸は車軸に対して直角になります。

直角カルダン駆動方式の場合は、
モーターをレールの向きにし、
電機子や回転子に取り付けたカルダン軸(回転軸)を
2つの自在継手を通して歯車に伝えます。
自在継手はたわみ板継手と同じく、
輪軸が振動しても確実に回転を伝えられるもので、
輪軸の振動はヨークに挟まれたスパイダーと言うばねのような器具で吸収します。
しかし、一つ問題なのは回転軸の方向が車軸と90度異なることで、
これを修正するために傘歯車と言う特殊な歯車を使います。
直角カルダン駆動は、中空軸平行カルダン駆動方式より構造が単純なのですが、
傘歯車の特殊性が問題なのか、
意外と同駆動方式の電車は少ないようです。
6、歯車形軸継手平行カルダン駆動方式
やっぱ、カルダン駆動方式は直角より平行の方が良いや・・・。
でも、中空軸は構造が複雑になるしなぁ・・・。
と言うことで考え出されたのが歯車形軸継手平行カルダン駆動方式です。
同方式は名称が長すぎるので、一般的にはWN継手駆動方式と言われています。

構造はかなり簡単になり、
モーターの電機子や回転子に取り付けたカルダン軸(回転軸)と
歯車の間にWN継手を挟むだけです。
WN継手は今までの継手と同じように輪軸が振動しても回転を伝えることが出来ます。
WN継手は2個挟む必要が無く、カルダン軸を長くする必要もないので、
電機子や回転子を空洞にして(中空軸)カルダン軸を通す必要はありません。
WN継手は今までの継手より大型のため、
スペース上、使うためにはモーターを小型化しなければならないと言う欠点があったのですが、
最近のVVVF制御の交流モーターはだいぶ小型化されているので、
現在はWN継手駆動方式が駆動方式の主流となっています。
7、平板形たわみ板継手平行カルダン駆動方式
人間の欲望とはきりが無いもので、
WN継手方式では満足出来なくなり、
今度は「もっと継手を小型化出来ないか!?」
と言う新たな欲が出てきました。
そこで出てきたのが平板形たわみ板継手平行カルダン駆動方式で、
この駆動方式も名称が長いので、東京ディズニー・・・じゃなくて、
TD継手駆動方式と一般的に言われています。

構造的にはWN継手駆動方式と殆ど変わりなく、
WN継手の変わりにTD継手を使っているという違いだけです。
TD継手は間に平板形たわみ板を挟むことによって、
衝撃を吸収し、回転を伝えています。
TD継手はWN継手より継手面積、体積が小さくなり、
省スペース化が出来ると同時に若干軽量化/保守省力化も出来ます。
電車の空気制動って何!?その1へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|