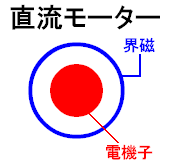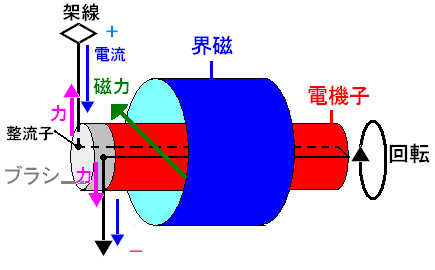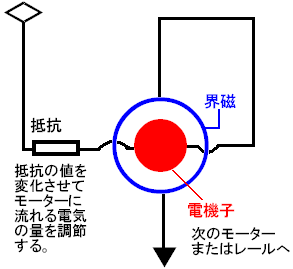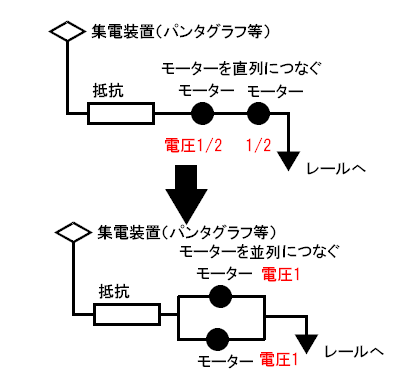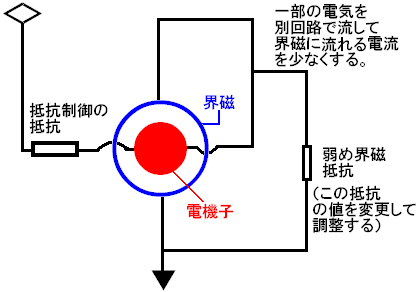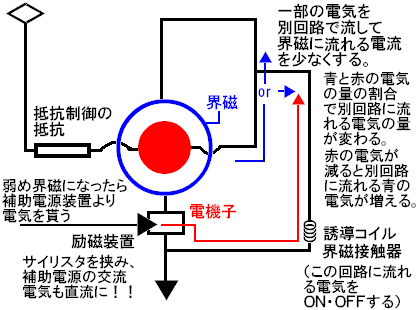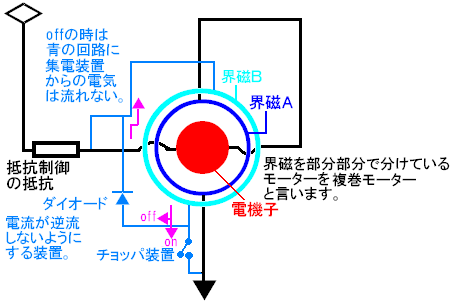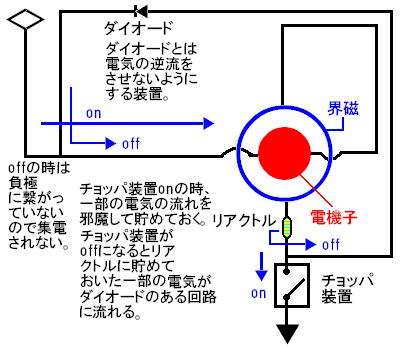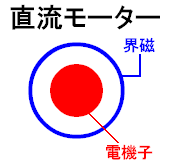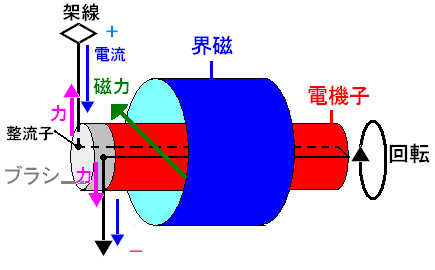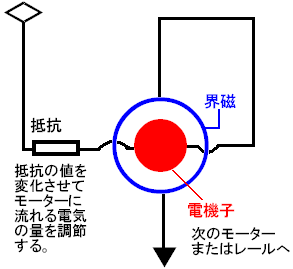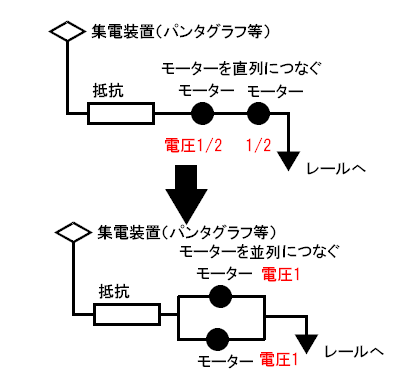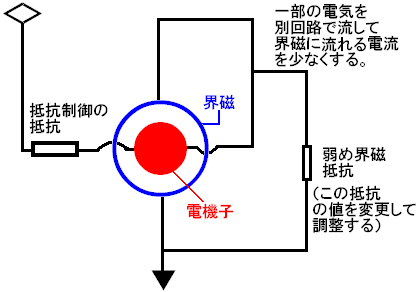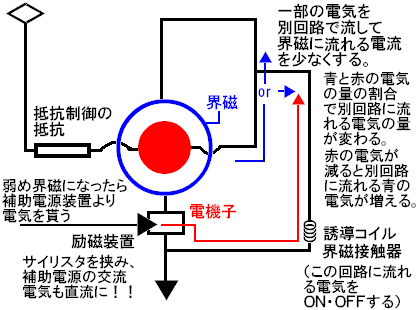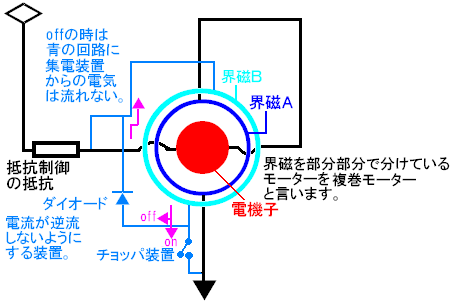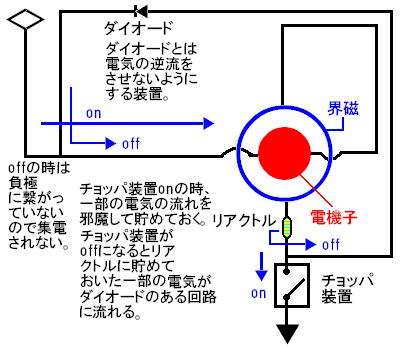電車の制御方式って何!?その1
鉄道雑誌や本を見ると、
「抵抗制御」とか「VVVF制御」とかの記述をよく見かけると思います。
また、鉄道ファンたちの会話の中でもよくその言葉が出ると思います。
しかし!!
そもそもこの「制御(コントロール)方式」とは何なのか
分かっている鉄道ファンは少ないと思います。
知っていても電車の走行音で「これは抵抗制御だ」、
「これはVVVFだ」と区別が出来る程度だと思います。
私も最近まで用語だけで各制御方式の内容は知りませんでした。
ここではこの制御方式を無駄な説明を省きまくって簡潔に解説します。
1、制御方式とは
電車は架線から取り入れた電気をモーターに送るのですが、
そのままモーターに電気を送ると電気が多すぎて壊れてしまいます。
また、モーター自体は電気の量をコントロール出来ないので、
一定の電流が流れている場合は一定の回転しかしません。
「制御」とはこのモーターに送る電気の量を調整するものです。
2、直流モータとは
今のところVVVF制御以外は全部直流モーターを使います。
で、直流モーターは下の図のようになっています。
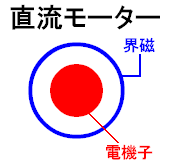
「なめているのか!?おいっ!!」と言う声が聞こえそうですが、
余計なものを省きまくると大体直流モーターなんてこんなもんですよ、はい。
外の「界磁」と言うのはばねのように電線をグルグルまいたコイルで、
電気を流すと磁石になります(電磁石)。
中の「電機子」は電気を流すとグルグル回転するものです。
まあ、電機子の回転が歯車や駆動装置(後述予定)を通り、
車軸(左右両車輪同士を結ぶ棒)に伝わるわけです。
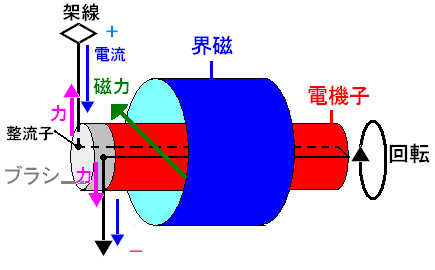
直流モーターを横から見るとこんな感じです。
電機子と電気回路を繋ぐ接点部分をブラシと言い、
ここは電機子が回転すればするほど磨り減る消耗品です。
界磁に磁力を発生させるとフレミングの左手の法則により、
上と下の力が電機子にかかります。
その力がお互い作用し合い、回転する仕組みになっています。
なお、界磁のパワーが強い時は馬力(まあ、トルクとか言うのですが)が凄く出ます。
逆に電機子のパワーが強い時は回転速度が速くなります。
発車時は馬力が必要で、高速走行時は高速回転が必要です。
そのため、双方に流れる電気を調節することで、
マニュアル自動車みたいにいちいちギアチェンジをしなくても
加速から高速走行まで出来るのです。
また、界磁に磁石の力が残っている(少しでも界磁に電気が流れている)時に、
電機子が車輪の回転を使い回転すると、
何と!!電気を発電するのです!!
(但し、何かしら電気を消費するものがないとダメ。)
この電気を昔は抵抗器で発熱して捨てると言うもったいないことをしていたのですが、
現在は架線に戻してエネルギー効率を高めています。
当たり前ですが、直流モーターを使うには直流電気でないと駄目です。
まあ、直流電化の路線は問題ないでしょう。
しかーしっ!!交流電化を走る電車は変圧器で電気を降圧したあと、
整流器などで直流にしなければなりません。
余談ですが、界磁と電機子を平べったくするとリニアモーターになります。
3、抵抗制御
抵抗制御・・・、この言葉は厄介で広義の意味と狭義の意味があります。嫌ですねぇ・・・。
一般に鉄道ファンが会話で使っているのは「広義の抵抗制御」だと思います。
まず、狭義の「抵抗制御」の解説をします。
3−1−1、抵抗制御(狭義)
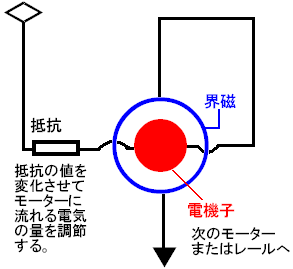
抵抗制御は電気の流れを悪くする
電気抵抗の値(気取った人は「インピーダンス」と言いますが)
を変えることにより、モーターに流れる電気の量を調整します。
電車の発進時は抵抗を大きくしてあまり電気を流さないようにし、
速度が上がるごとにだんだん抵抗を小さくしていきます。
ただしっ!!
この電気抵抗は熱を発するので、
冷却時間を考慮しなければなりません。
そのため、発進から低速域までしか使えません。
3−1−2、直並列制御
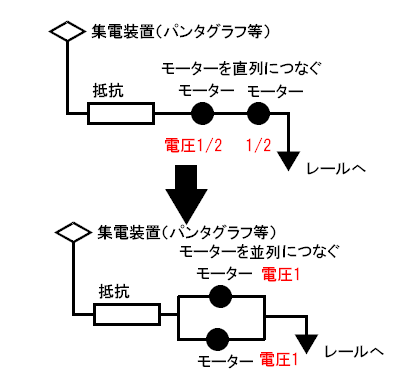
抵抗制御(狭義)が一段落すると直並列制御が行なわれます。
最初モーターを直列つなぎ(図では2個のモーターですが、2個とは限りません)にします。
そして、速度が上がったら並列つなぎにつなぎ変えます。
直列つなぎの場合、
モーターにかかる電圧がモーターの数ごとに減ってしまいます(電圧=集電電圧÷モーター数)。
しかし、並列つなぎの場合、
それぞれのモーターが異なる回路だったらモーターにかかる電圧はそのままです
(電圧=集電電圧÷回路にあるモーター数)。
つまり、電圧は直列つなぎ<並列つなぎになるので、
直列つなぎより並列つなぎの方がモーターの回転が速くなるのです。
3−1−3、弱め界磁制御
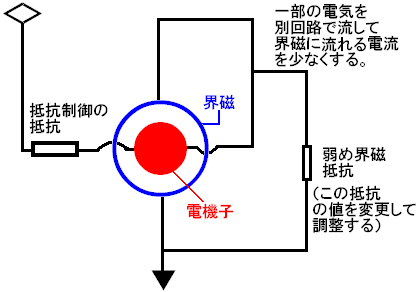
抵抗制御(狭義)や直並列制御には限度があります。
じゃあ、更に高速で走らせたい場合はどうするかと言うと、
弱め界磁制御を使います。
速度が速くなり弱め界磁制御に移行したとき、
界磁を通らない別回路を開放させます。
界磁に流れるはずの電気の一部を別回路に流して、
界磁に流れる電流を少なくするものです。
そうすると、界磁の磁石としてのパワーが減り、
電機子は「うるせー界磁の拘束力が弱まったぜ!!」と喜び、
回転が速くなるわけです。
つまり、界磁より電機子の方をストロング(?)にさせると言うのが
「弱め界磁制御」なのです!!
なお、界磁に流れる電気と界磁に流れない別回路の電気の調整は、
別回路にある弱め界磁抵抗の抵抗の値を変えて調整します。
で、上のように界磁に電気が流れる前に別回路に電気を流せるようにしたのを、
「分路界磁式」と言い、
界磁の途中から別回路に流すようにしたのを「部分界磁式」と言うのですが、
殆どは分路界磁式なので、余計な分類は覚えない方がよいでしょう!?
3−2、抵抗制御(広義)
で、広義の抵抗制御は何だと言うと、
この抵抗制御(狭義)と直並列制御と弱め界磁制御(無いのもある)を
単純に組み合わせたものを言います。
決して、「弱め界磁になったら補助電源装置等から電気を貰おう」とか、
「界磁の一部に流れる電気回路を切ったり入れたりしてみよう」とか言う、
おかしなマネを起こさないことが前提です。
〜抵抗制御の走行音〜
抵抗制御の走行音はモーター音だけで、
その他の異音はありません。
モーター音は重低音で速度が速くなると爆音になります。
4、界磁添加励磁制御(かいじてんかれいじせいぎょ)
まあ、鉄道雑誌や本はすごーく親切で、
「界磁添加励磁制御」と書いても「かな」なんてふりません。
「馬鹿なおめーらに漢字の勉強させてやってるんだぞ!!」
と言う執筆者の声が聞こえてきます。
私はそんな執筆者のありがたい忠告のおかげで、
最近までこの漢字が読めませんでした。
・・・で、読めても意味が全然分かりません。
もっと分かりやすいネーミングが出来なかったのでしょうか?
で、界磁添加励磁制御とは何だと言うと、
「抵抗制御(広義)」に少し毛を生やしたものです。
抵抗制御(狭義)と直並列制御に関しては抵抗制御(広義)と変わりません。
違うのは弱め界磁になったときです。
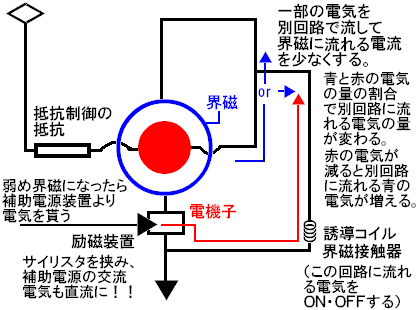
弱め界磁になったら、補助電源装置等から電気の一部分を貰います。
残念ながら補助電源装置の電気は三相交流なので、
サイリスタを使って直流にします。
で、この電気を界磁を通らない別回路に逆向きで流します。
別回路に流れる逆向きの電気が強いうちは、
架線からの電気はしぶしぶ界磁に流れなければならないのですが、
逆向きの電気を徐々に弱くすると、
界磁に流れるはずの電気の一部分がだんだん別回路から流れるようになるのです。
そうすると界磁のパワーが弱まり電機子の「電気の添加による天下」になるのです。
なお、ブレーキの時、補助電源装置から界磁に電気を流すことが出来るので、
回生ブレーキも使えると言うお徳なおまけもあります。
つまり!界磁添加励磁制御は抵抗制御(広義)に近い単純な構成で、
省エネルギーが出来ると言うメリットがあるのです。
〜界磁添加励磁制御の走行音〜
抵抗制御との違いは弱め界磁の時だけなので、
走行音で区別するのは難しいです。
ただ、回生ブレーキが使える関係か、
ブレーキ解除音が同系の抵抗制御車と比べると異なります。
5、界磁チョッパ制御
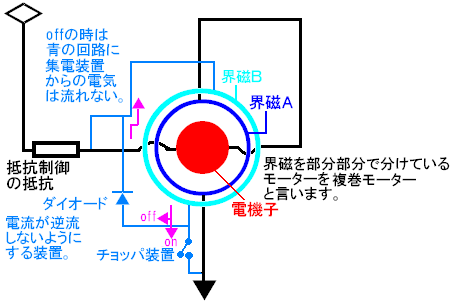
界磁チョッパ制御も殆ど抵抗制御(広義)と同じで、
起動からある程度の速度までは抵抗制御(狭義)と直並列制御を使います。
違うのは高速域で、
一部の界磁に流れる電気をチョッパ装置でON、OFFすることによって、
界磁のパワーをだんだん弱くしていきます。
つまり、最初はONの時間を長くし、
だんだんとOFFの時間を長くするのです。
当然、界磁が弱くなれば電機子は「やったー!!」と喜んで速く回転するのです。
ただ、界磁を部分部分に分けた複巻モーターと言う構造上、
ちょっと機器が複雑になると言う欠点はあります。
〜界磁チョッパ制御の走行音〜
複巻モーターは普通の直巻モーターの音よりかん高い音なので、
聴きなれると区別が出来ます。
6、電機子チョッパ制御
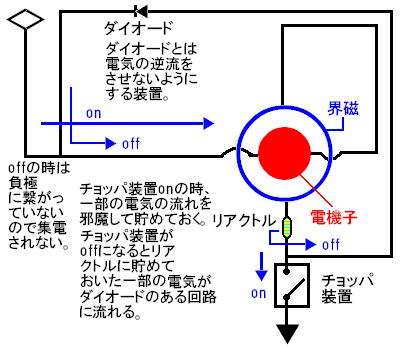
電機子チョッパ制御とは、
チョッパ装置と言うスイッチを超スピードでON、OFFすることで、
流れる電気の量を調整する制御です。
最初はOFFの時間を長くし、あまり電気が流れないようにします。
だんだん速度があがったらONの時間を長くし、
モーターに流れる電気の量を増やします。
ただ、それだけだとモーターに流れる電気が瞬間的に止まったり流れたりするため、
モーターの回転が粗雑になり、
ひいては乗り心地悪化やモーターの早期寿命に繋がるので、
回路にリアクトルを挟みます。
リアクトルとはまあ「電気の障害物(川のダムのようなもの)」のようなもので、
ONの時一部の電気を障害してそれを蓄えておきます。
そして、OFFになったとき、蓄えておいた電気をダイオードのある回路に流し、
電機子や界磁に電気を送ります。
そうすると、モーターに流れる電気が完全に途切れることがなくなるため、
滑らかな回転になるのです。
電機子チョッパ制御方式は抵抗を排除することが出来る究極の省エネ車両なのですが、
チョッパ制御装置に大電流をON、OFF出来るサイリスタと言う半導体が必要で、
開発当時はそのサイリスタのお値段が高かったため、
電機子チョッパ制御はあまり普及しませんでした。
もし、VVVF制御が開発されなかったら、
今頃電機子チョッパ制御の天下になっていたかもしれません。
〜電機子チョッパ制御の走行音〜
チョッパ装置の「ビー」と言う音がとにかく目立つので、
すぐに分かります。
特にモーター音があまり出ていない低速域でよく分かります。
電車の制御方式って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|