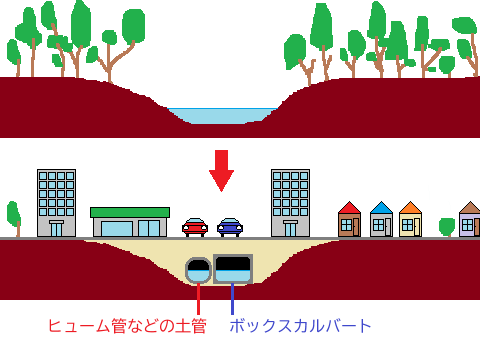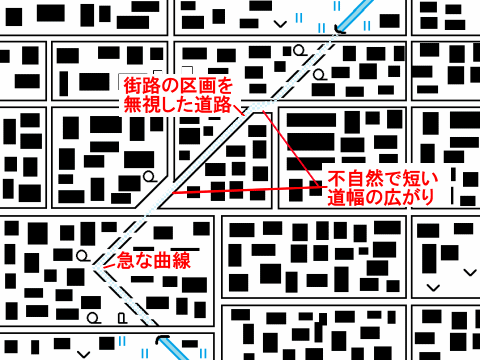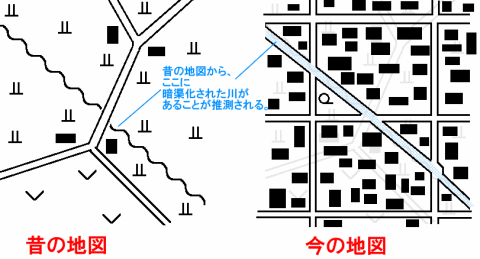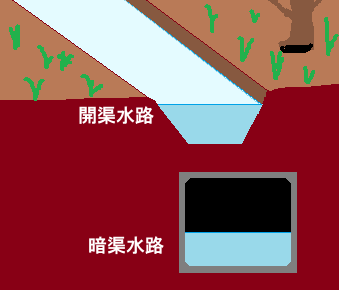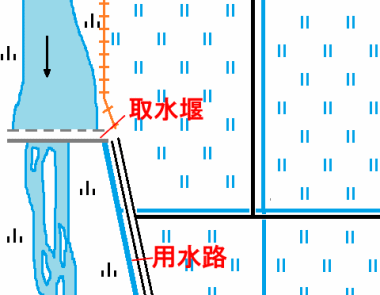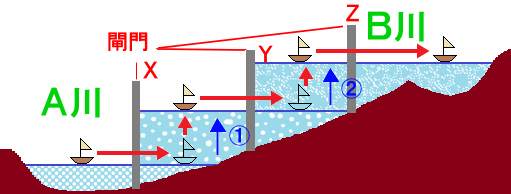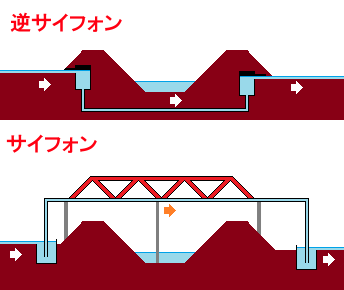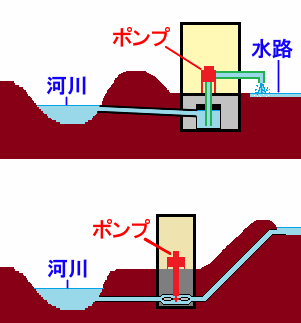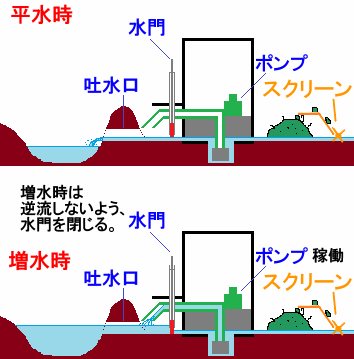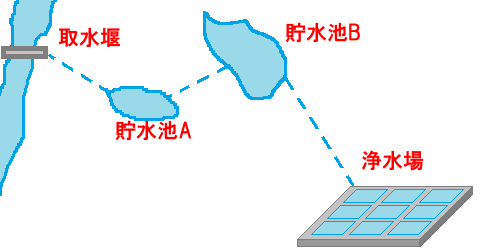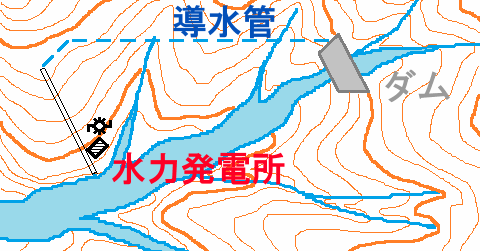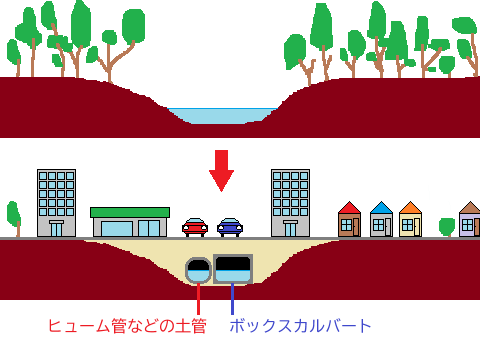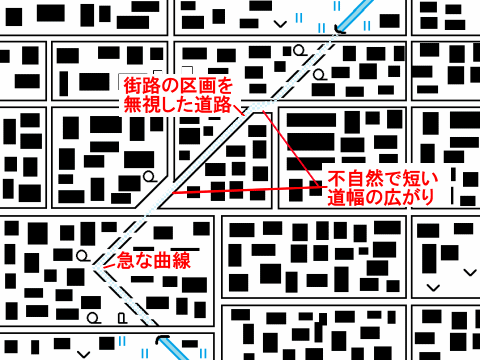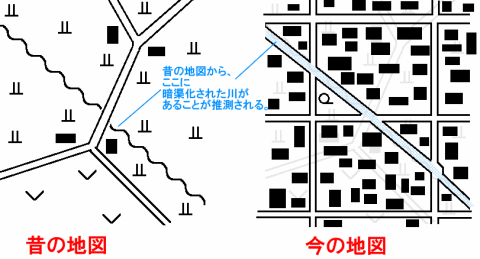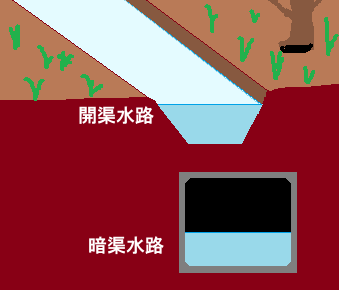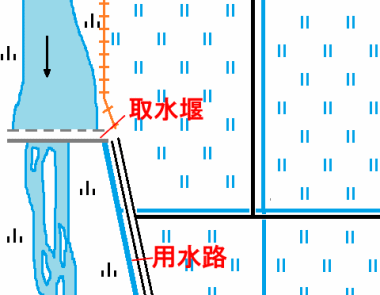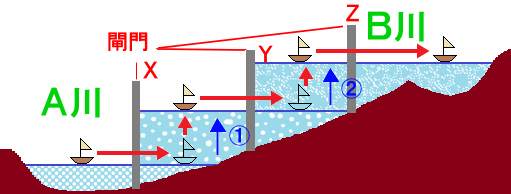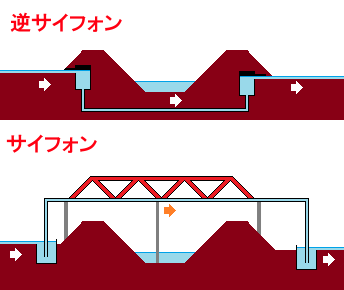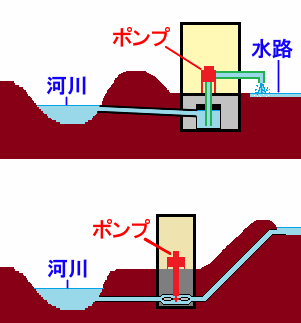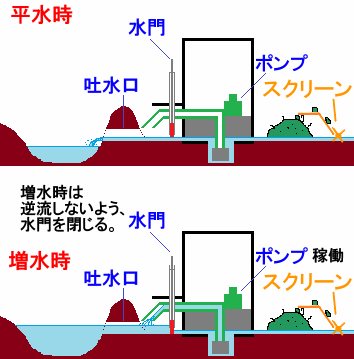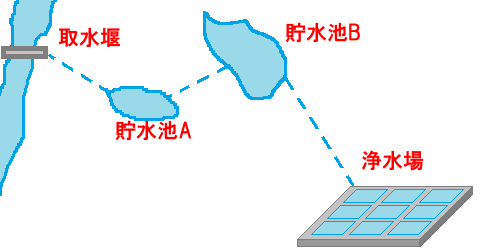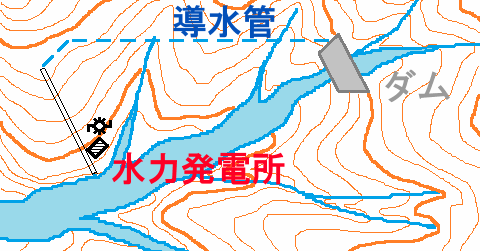人工河川・人工河川構造物1
河川にも色々な人工河川、人工構造物があります。
ここでは地図読図で必要な主なものを挙げます。
1、暗渠と開渠
1−1、暗渠
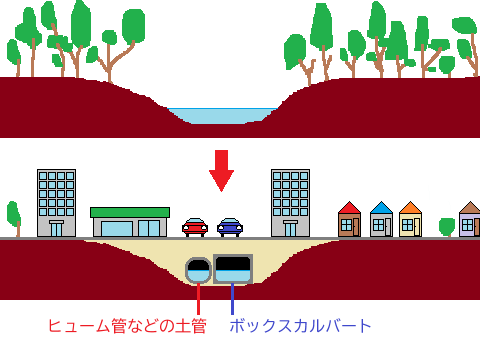
暗渠(あんきょ)とは河川や用水路に蓋をして覆った場所や、
土管(鉄管、ヒューム【鉄筋コンクリート】管、陶管等)や、
ボックスカルバート<以下「土管等」>で、
地下水路化した場所を言います。
暗渠化する理由は用地の有効利用や、
河川や用水路に落ちて溺れるなどの危険性を除去するためです。
デメリットは増水したときに対応できないことです。
土管やボックスカルバートはある程度余裕のある大きさのものを使いますが、
想定外の水量になったとき、溢れてマンホールの蓋を飛ばしたり、
土管等の破壊で上の地盤が崩落することがあります。
建設時に推定して計算した水量が、
将来的にも通用するとは限らず、
近年は温暖化によるゲリラ豪雨で水量が急速に増えることもあります。
そのため、限界になりそうな場合は土管等を増設したり、
開渠化する必要があります。
なお、大きな河川を暗渠化するのには莫大な予算が必要なだけでなく、
上記のような増水があるため、基本的に暗渠化しません。

暗渠は実際に現場に行ってみると、推定が可能です。
谷筋のはずなのに川が見られないこと、
何となく暗渠化された所の部分が川筋のように見えること、
各家が暗渠化された方に正面出入口がないことなどで推定できます。
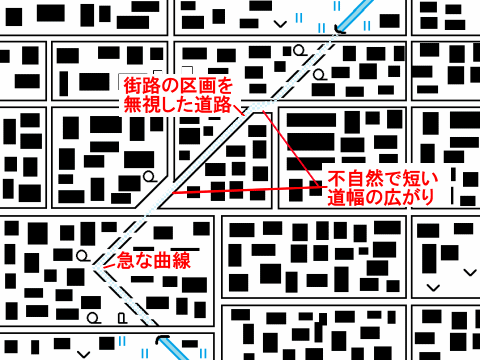
一方、地図の読図で暗渠を推定するのはかなり難しいです。
これは、暗渠化されているのは大体都市部で、
等高線が分かりにくいこと、
地下水路のように実際の暗渠部の川筋の地図記号がなく、
何も地図上に表示されないからです。
それでも、以下のことでなんとなく推定することはできます。
●一部の道路が短い区間だけ道幅が広がる。
●街路の区画を無視した道路。
(例として碁盤目状の区画に斜めに通る道など)
●川らしい曲線。
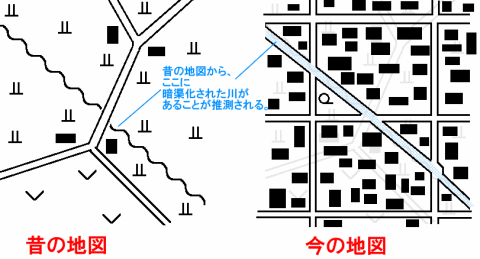
もっと正確に分かるためには、昔の空中写真や地図を比較参照にするのが良いです。
勿論、流路変更により、河川の位置が変わっている可能性もあるのですが、
昔の地図で川だった場所と同じ場所を通る道路や庭園路などは、
暗渠化された河川が流れている可能性が高いです。
あと、鉄道の廃線跡と暗渠化された河川の部分が似ているのですが、
違いとして、
●暗渠の部分は急な曲線部分がある。
●幅が線路跡に対して狭すぎるor広すぎる。
●駅跡らしき痕跡が見られない。
●等高線で判断して勾配が急な場合は暗渠である可能性がある。
(鉄道は急勾配を走ることは出来ない。)
1−2、開渠
暗渠と異なり、蓋をしたり、
土管・陶管で地下を通していない水路を開渠(かいきょ)と言います。
基本的に開渠は子供が立ち入って溺れたり、
増水した水路の様子を見に行った高齢者が流されたり、
ゴミなどが入って流路が閉ざされたりするデメリットがあるため、
市街地や道路に近いところは基本的に暗渠化するところが多いのですが、
暗渠よりも建設費が低いことや、
保守がしやすいこと、急激な増水にある程度対応出来るため、
開渠で用水路を造るところもあります。
平成時代には、暗渠化した河川や水路を態と全部、
あるいは一部分開渠化したところもあります。
これは、昭和後期のコンクリート化により自然が減り、
水や木々などの自然とのふれあいが希薄になったため、
環境悪化対策で緑地化と共に河川や水路の開渠化が行われました。
ただ、令和に入った今は再び都市のコンクリート化が進んでおり、
開渠化するところは減っています。
理由は緑地化や開渠化したところの手入れや保守が、
少子高齢化で困難になっていること、
大量の落ち葉の処理問題や虫の発生、
木々が増えることで死角が増え、
犯罪が増えていることが理由に挙げられます。
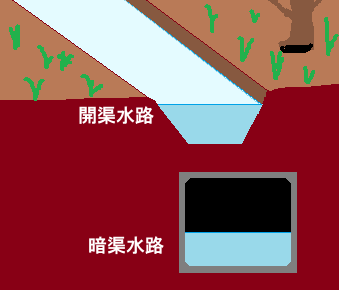
河川や用水路によって、暗渠と開渠の両方が2層になっている所もあります。
一番の理由は、開渠側の河川幅を宅地化などで広げることができず、
増水時に対応できないためです。
二層化河川は暗渠を造って水の流れを二分化し、
増水時は暗渠側に水を流して開渠側が氾濫しないようにしています。
2、用水路、排水路(悪水路)
2−1、用水路
用水路とは何かの用途で使う水を流す水路のことを言い、
正式には「●●用水路」と、●●には用途名が入ります。
主なのには農業用水路、工業用水路、発電用水路
水道用水路、船舶用水路(運河)などがあります。
農業用水路は文字通り農業に使う用水路で、
主に水田に水を張る目的や、
畑の作物に水をやる目的に使います。
一方、工業用水路は工業機器や製品の洗浄や冷却などに使う用水路です。
発電所用水路は主に水力発電所に流す水をながす用水路ですが、
実は火力発電所や原子力発電所でも蒸気の冷却に水を使うので、
それらの発電所に流す用水路もあります。
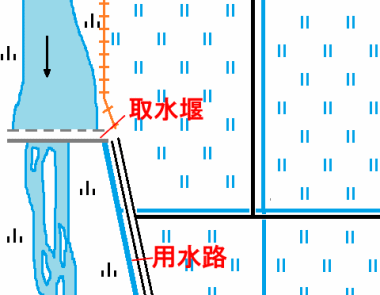
用水路は用途に限らず、
川にある取水堰から水を取り込むことが多いです。
取水堰を設ける理由は、
自然に流れる川だと流路が経年変化で移動し、
取水口に水が流れなくなるようになったり、
取水口の付近の水量が少なくて、
使用する量の水が取水できない可能性があるためです。
基本的に取水堰には水門があり、
水を使わない時期は水門を閉め、水が流れないようにしています。
なお、川から水を引き込んだ場合、水は使いたい放題な訳ではありません。
水には水利権があるため、取水量などが制限されています。
そのため、水門付近には水利権を示す表示板があることが多いです。
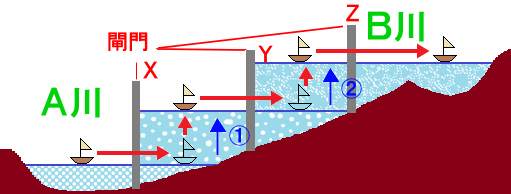
船舶用水路(運河)は船を通すための水路です。
船は必ず2点間同じ高さの川の間を通るとは限らないので、
閘門(こうもん〜水門)を複数設け区画を区切り、
水の水位を調整しながら高低差のある河川間を船が行き来出来るようにしています。
図の例だと、
標高が低い所を流れているA川から高い所を流れているB川に船が向かう場合、
先ず、A川から水門X-Y間に船を進めます、
そして、閘門X-Y間の水位をA川と同じ高さから上昇させます。
更に、閘門Y-Z間に船を進めて、
今度は閘門Y-Z間の水位をB川と同じ水位に上昇させます。
その後、船をB川に移動させて、A川からB川に移動が完了します。
こういった船舶用水路(運河)を閘門式運河、
古い言い方だと通船堀と言います。
なお、こういった閘門式運河を造ることが困難な場所には、
船を引き上げるインクラインという急勾配線路を設けることがあります。
2−2、排水路(悪水路)
用水路と逆で使用済みの水を流す水路を排水路と言います。
今は下水道などが整備されているため、
排水路と言えば水田に流した水を排水する農業用排水路が殆どです。
しかし、昔は生活排水や工業用排水も排水路に流していました。
そのため、
昭和時代の高度経済成長期は、
それによる河川の水質汚染が問題になっていました。
2−3、サイフォン、逆サイフォン
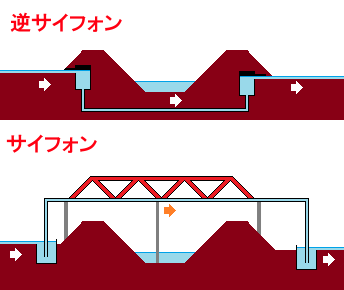
用水路は河川より後に人工的に造られるものなので、
他の河川や道路、鉄道線路などと交差する場合があります。
この交差物を避けるために造られるのが逆サイフォンとサイフォンです。
逆サイフォンは、
高い所水槽と低い水槽をU字状の管で結ぶと、
高い水槽から低い水槽へ
高い水槽側の水圧によりU字状の管を通って流れる性質を利用したものです。
サイフォンは逆サイフォンのU字状の管を∩字状の管にしたもので、
原理は同じです。
この逆サイフォンとサイフォンを使えば、
用水路より水位の低い河川の下(上)を、
ポンプなどの機械を使わずに流して立体交差させることができます。
なお、逆サイフォンやサイフォンを使う場合は、
必ず高い水槽と低い水槽を結ぶ必要があります。
逆だと逆流してしまいます。
なので、水を高い位置に汲み上げる必要がある場所では使えず、
次に挙げる揚水機場が必要になります。
3、揚水機場と排水機場
3−1、揚水機場
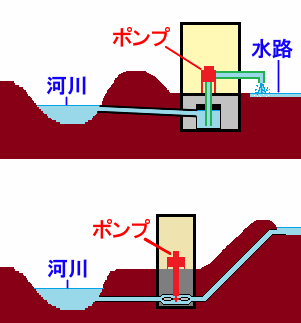
揚水機とは平たく言えばポンプのことなので、
揚水機場をポンプ場と言うこともあります。
揚水機場が設けられる場合は、
取水する河川より流す用水路の方が高い位置にある場合に設けられます。
揚水機場では取水した水を揚水機で汲み上げ、
高い位置の水路に流しています。
なお、揚水式発電所は発電をしない時間帯に、
発電機に繋がるランナ(水車)を逆回転させ、
下池の水を上池に水を汲み上げ、
電気を多く使う時間帯に発電するための水を確保しています。
3−2、排水機場
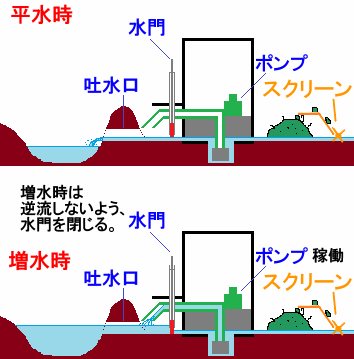
排水機場は排水路の水を河川に流す施設を言います。
一見、排水路の水をそのまま河川に合流させれば良いように考えてしまうのですが、
そのようにはいきません。
先ず、排水路と言うことで、ゴミなどの不純物が沢山流れているため、
それらをスクリーンで取り除く必要があります。
もう一つは流す河川と排水路との水位差です。
排水路の方が水位が高い場合は特に問題ないのですが、
豪雨などで河川の水が増水すると、
排水路より河川の方が水位が高くなってしまいます。
そうすると、河川の水が排水路に遡上してしまいます。
元々排水路は流す水のキャパシティが大きいわけでは無いので、
大量の河川の水が遡上してしまうと氾濫を起こしてしまいます。
そのため、
河川への吐水口の所に水門を設け、
河川の水位上昇時は水門を閉じて水が遡上しないようにします。
その一方で、排水路の水は増水時でも河川に流さなければならないので、
ポンプを使い水を汲み上げ、
河川の水位より高いところから流すようにします。
4、送水路(送水管)、導水路(導水管)
2拠点間を水圧鉄管、PC管、RC管などで水を送る水路を送水路(送水管)、
導水路(導水管)と言います。
で、専門家も結構勘違いしているのですが、
「水圧鉄管」は水を流す管の材質を示す用語であり、
水を管を使って送水すること自体を言う場合は、
送水路(送水管)、導水路(導水管)と言うのが正しいです。
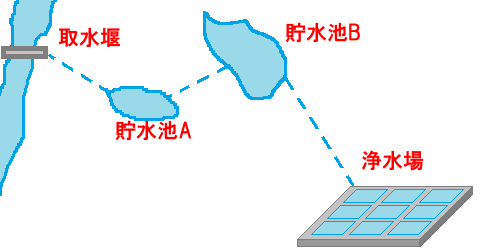
送水路、導水路でよくあるのが、上水道と水力発電所です。
浄水場は基本、河川から直接水を引き込むことが多いのですが、
引き込む河川の上流の貯水量が少なかったり、
引き込み側の浄水場の水を利用する住民や工場、ビルディングなどが多い場合は、
安定供給のため、複数のダム湖や貯水池を経由することがあります。
その経由地を結んでいるのが、送水路、導水路です。
東京の東村山、境、和田堀の各浄水場は多摩川から取水しています。
しかし、多摩川の上流にある小河内ダムは上流に大きな河川が無いため、
夏の水不足などで放流してしまうと1週間ほどで貯水率が0%になってしまいます。
そのため、山口貯水池(狭山湖)、
村山貯水池(多摩湖)を経由して各浄水場に配水しています。
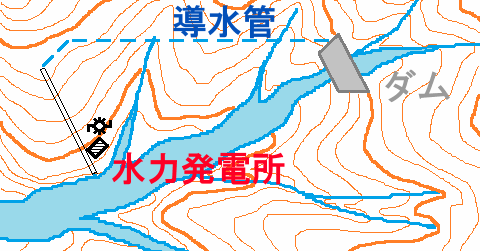
一方、水力発電所も送水路、導水路で発電用水を流しています。
水力発電所は高低差のある所に水を流してその水流で水車(ランナ)を回し、
水車に繋がった発電機で発電する仕組みです。
そのため、水車に流す水は発電所より高い位置から流す必要があります。
水は発電所よりかなり上流にある取水堰やダムから取水し、
緩い勾配の導水路で発電所近くまで送水し、
斜面の導水管(水圧鉄管)で一気に水を河川に向けて流します。
なお、発電機が止まると水車も回らなくなり、
導水管を流す水で管に圧力がかかってしまうため、
取水部から発電所までの導水路が長い場合は、
サージタンクという一時的に水を貯水するタンクを設ける場合があります。
人工河川・人工河川構造物2へ
川柳五七の地図のページ8へ戻る
川柳五七の地図のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|