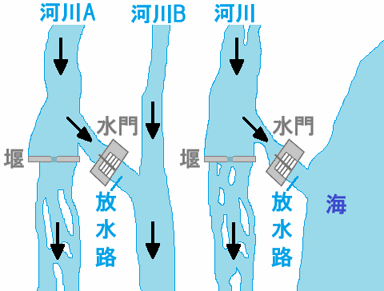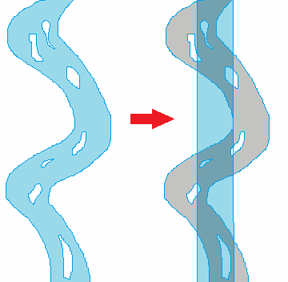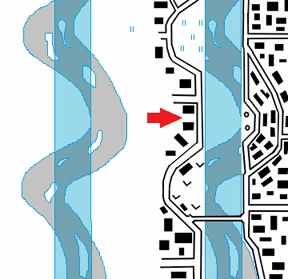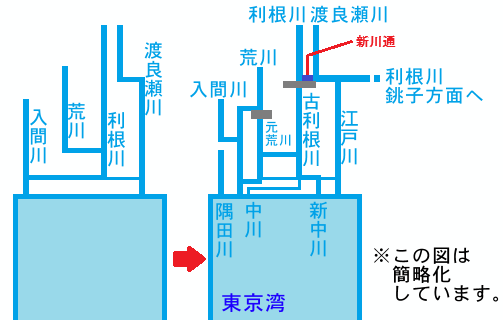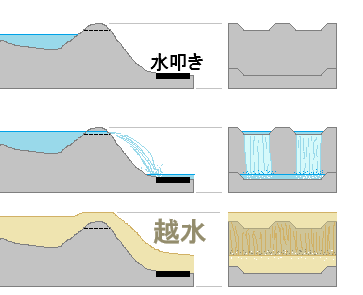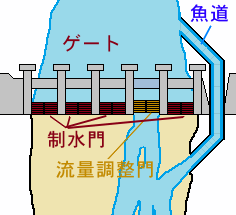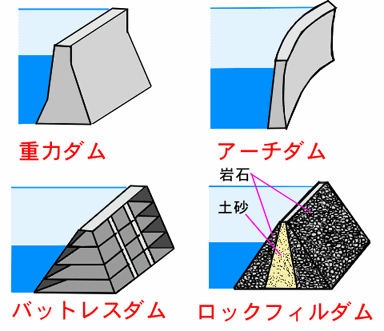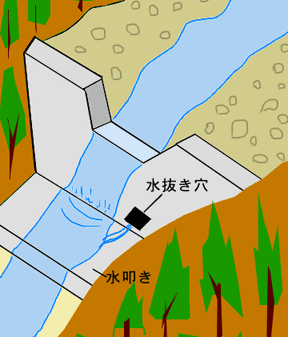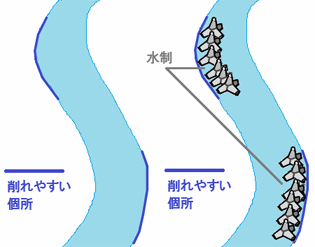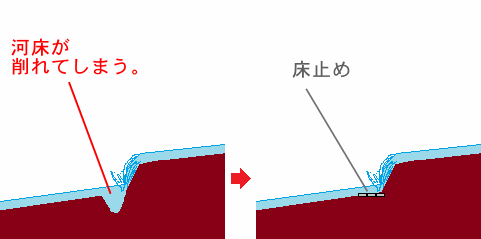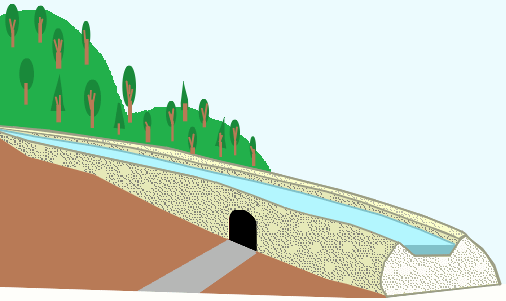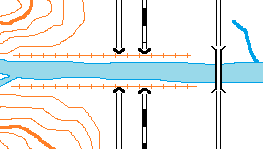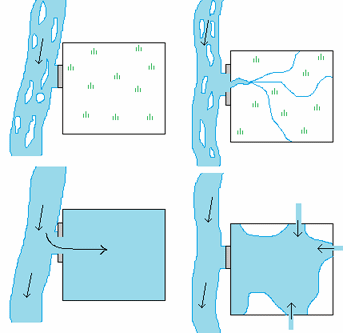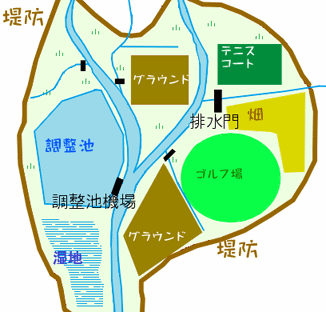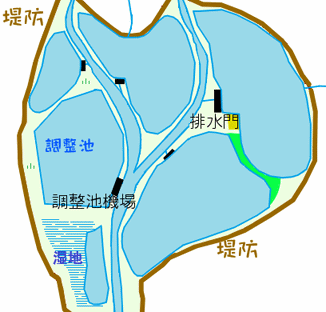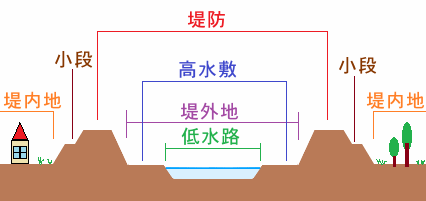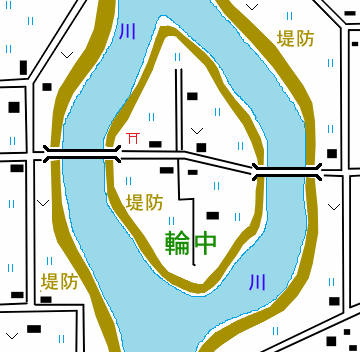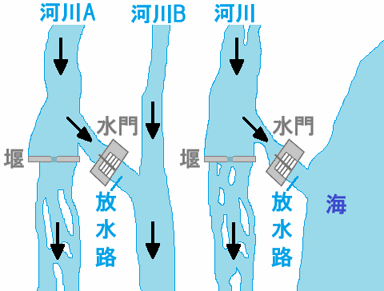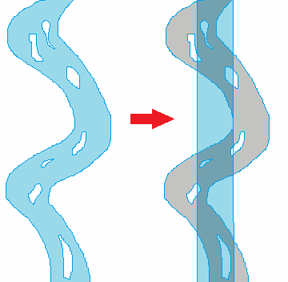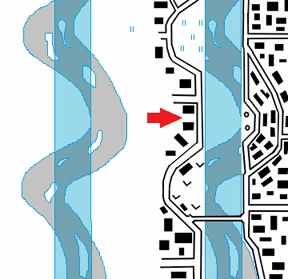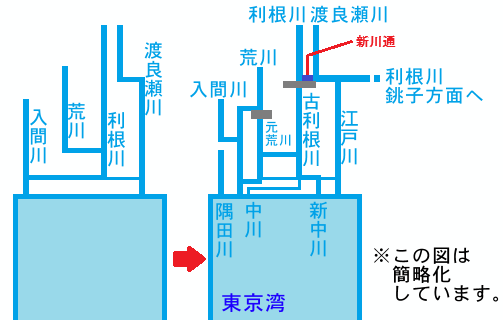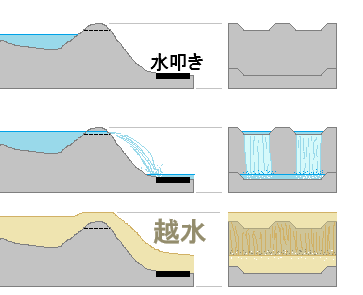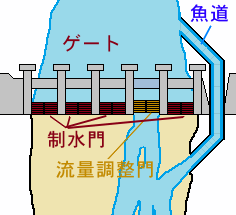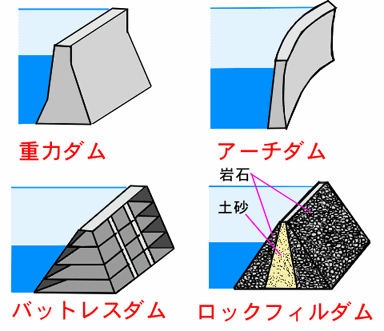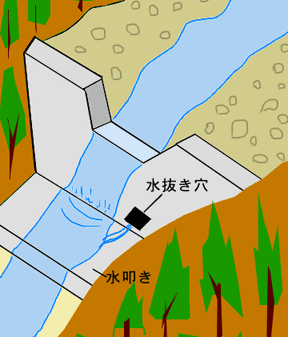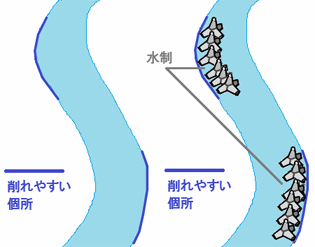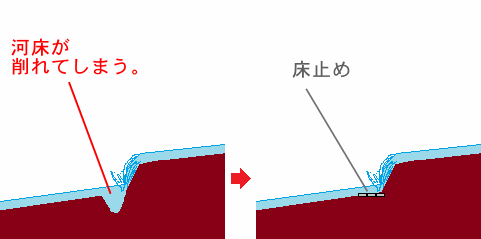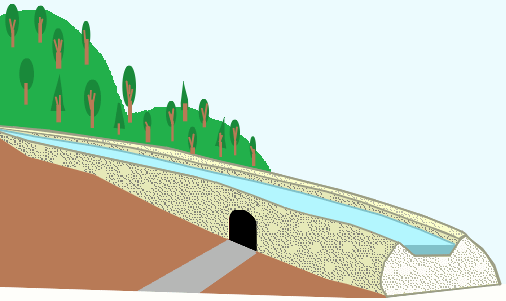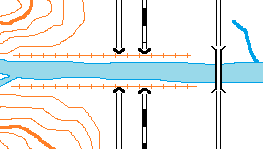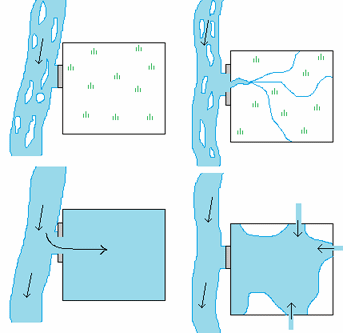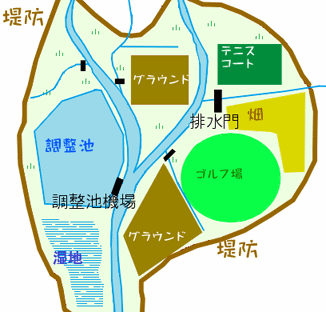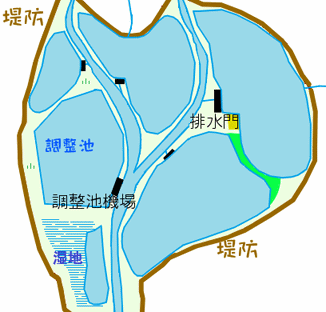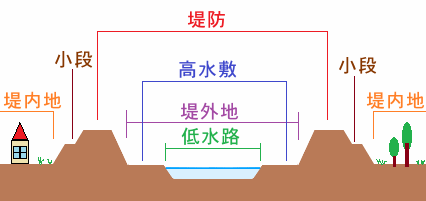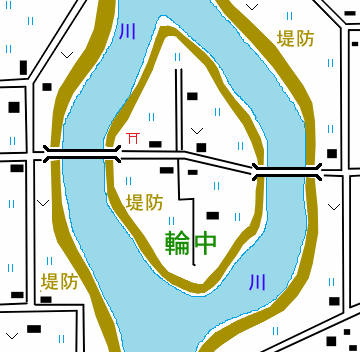人工河川・人工河川構造物2
1、放水路
放水路(分水路ともいう)とは
洪水防止や灌漑(かんがい/農業用水のこと)用水確保のために、
水を引き込んで流す水路や河川を言います。
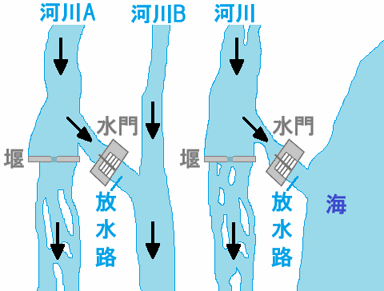
放水路は用水路に比べて幅が広く、流量が多いのが特徴です。
河川が洪水で氾濫するのを防ぐ方法はいくつかあり、
河川幅を拡げること、大きな堤防(スーパー堤防)を造ること、
後述する調整池や遊水池を造ることなどがあります。
しかし、河川の下流域はだいたい市街地化が進んでおり、
それらの用地を確保するのが困難な場合が多いです。
そのため、河川の流量が増えたとき、比較的余裕のある河川に流したり、
そのまま放水路で海に放流するようにして、
在来河川の流量が一定以上増えないようにしています。
なお、放水路は地上とは限らず、
埼玉県春日部市の首都圏外郭放水路のような地下放水路もあります。
地下放水路の場合、一河川の放水だけでなく、
複数の河川の放水をする場合があります。
首都圏外郭放水路の場合、
大落古利根川、幸松川、倉松川、中川などの河川の水を江戸川に放水しています。
2、河川改修
河川は川の流れで形成された流路のまま流すのが自然の摂理なのですが、
そうすると、降雨による増水で氾濫などをしたり、
各地から排水が集まって河川の流下能力を越えてしまったりするだけでなく、
無駄な蛇行で土地の有効利用も出来ない面もあります。
これを改修することを河川改修といいます。
河川改修は流路変更、放水路や調整池の建設、
河川幅の拡大(引堤)、河道の掘削、
堤防建設、堤防嵩上げ等があります。
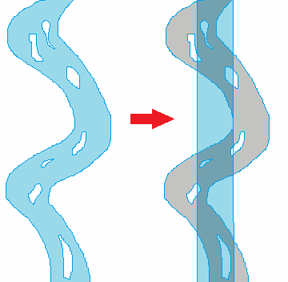
河川が蛇行していると、蛇行部分の円弧外側に水圧がかかってしまいます。
そうすると、その部分の堤防が崩れて氾濫することがあります。
それを防止するため、
河川の流路を緩やかなカーブや直線に造り直すことがあります。
また、場合によっては河川の流れを別河川に付け替える場合もあります。
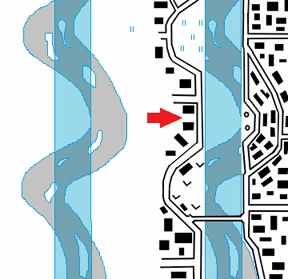
河川改修をした場所は現在、
全く痕跡のないところもありますが、
道路の形状、植生などで判別できるところも多いです。
なお、流路変更後、整地をあまりしなかった場合、
自然の流路変更と同じように、後背湿地や三日月湖ができる場合もあります。
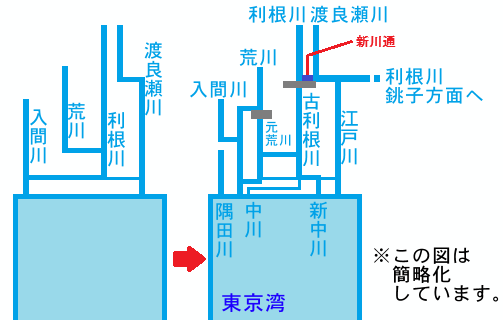
河川の流路変更や付け替えは全国的に行われており、
昔と大きく異なる所もあります。
この「昔」は「江戸時代の頃」もありますが、
昭和時代初期と比べても現在と大きく異なる場合があります。
東京湾北側に注ぐ河川も、
江戸時代と比べると現在は大きく異なっています。
3、堰・ダム
3−1、堰(せき)
堰は水を一時的に蓄えて取水したり、
河川の流量調節をするために設けられます。
堰は大きく分けて堰堤(えんてい)などの固定堰、
水門などで水量を調節する可動堰があります。
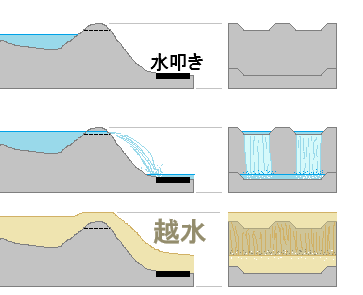
固定堰は堰堤など色々な種類があります。
基本、円滑に取水口から取水できるよう、一定水まで貯水するようにしており、
ある程度水量が貯まると、水通しから水が下流に流れるようになります。
更に降雨で増水すると堰を越流して自然放流するようになっています。
なお、堰の下流側には水叩きというコンクリート構造物が敷かれることが多いです。
水叩きは落差による水圧で河床が削れてしまうのを防止する目的があります。
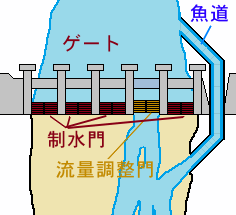
可動堰はいくつかのゲート(門)に区画されており、
制水門と流量調整門の二つで構成されています。
制水門は平水時には閉じている場合が多く、
降雨により増水した際に門を開けて水を流します。
制水門の開ける門数は増水量によって変わります。
なお、平水時でも取水をしない時期や、
河床の洗浄目的に流量を多くする場合、
制水門を開ける場合もあります。
一方、流量調整門は基本常時開けてあるのですが、
流す流量によって門の開け具合を調整しています。
〜〜〜〜〜
堰は固定、可動にかかわらず、堰の横に魚道が設けられる場合があります。
この魚道は遡上する魚類が遡上しやすいように設けられます。
ここは魚が多く通るため、ここで釣りをすると魚が釣れやすいです。
しかし、そうすると、乱獲により生態系が崩れてしまうため、
魚道で釣りをするのはルール違反になる個所が多いです。
3−2、ダム
ダムは水を堰き止めて水を蓄える構造物で、
堰より多くの水が蓄えることができます。
蓄える水量は時期や降雨などで細かく調整され、
貯水量が一定以上になると、
放水門や放水口で放水をして水を下流に流します。
その他、貯水量が一定以上にならなくても、
下流の流量確保や河川洗浄のために放水することがあります。
ダムの貯水目的は
利水確保(水力発電、上水道確保、農業用水確保、工業用水確保)や、
洪水調整などの流量調整などです。
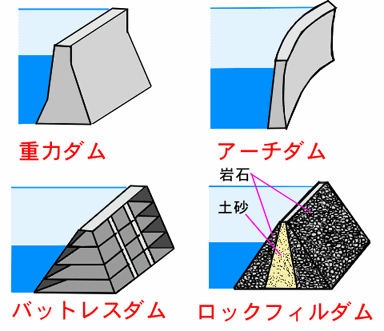
ダムの種類は多くあり、
それだけで趣味サイトや趣味SNSが出来てしまうのですが、
このサイトは地図趣味、地図地理職業者用サイトなので簡潔に述べます。
日本のダムでよく使われるのは、
重力ダム、アーチダム、ロックフィルダムです。
重力ダムはダム躯体の重さ自体で貯水した水の水圧を抑えるダムで、
基本、このダムが採用されます。
アーチダムは円弧状になったダムで、
両岸の岩盤でダムを支えて固定し、
貯水した水の水圧を抑えます。
アーチダムは円弧状にして強化するため、
躯体を薄くすることができます。
そのため、重力ダムより工費を抑えることができるのですが、
両岸の岩盤が強固でない所では、採用できません。
ロックフィルダムはコンクリートに代わって岩石で造られたダムです。
ただ、岩石を積み上げただけだと水が隙間を透過してしまうため、
中央部に水を通さない土砂などで構成されているコア部分を設けます。
重力ダムなどはコンクリートの打設のため、大がかりな工事になるのですが、
ロックフィルダムは比較的工事規模を縮小することが出来ます。
また、重力ダムのように重いコンクリートを打設するための強固な地盤が必要でなく、
アーチダムのように両岸の強固な岩盤も必要ないため、
比較的地盤や岩盤が良くないところでも採用できます。
ただ、躯体下辺面積を使うため、
ある程度ダムを建設できる用地が必要になります。
バットレスダムは薄いコンクリート板(遮水壁)を、
格子状で組んだコンクリート製のバットレスで抑える形状のダムです。
遮水壁を薄くすることができ、それぞれのパーツをモジュール化できるのですが、
複雑な構造になってしまうと言う欠点があるため、
日本では採用例が少ないです。
3−3、砂防ダム
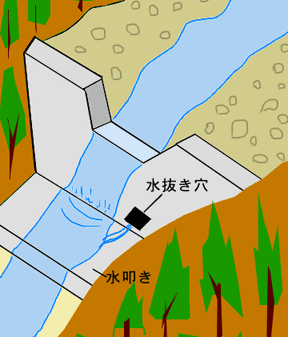
砂防ダム(治山ダム)は河川の上流部に設置されることが多いです。
土砂が下流に流されてしまい、
河床低下や地盤低下をすることを防止するために設けられます。
また、土砂が降雨により大量に流れる土石流を防止するためにも設けられます。
砂防ダムは1個所だけでなく、一定間隔で沢山設けらている河川が多いです。
3−4、水制、床止め
川の流れは緩やかとは限らず、
場所によっては急流だったりします。
しかし、急流区間をそのまま急流で流すと
護岸や堤防を削って破壊してしまうこともあります。
そのために設けられるのが水制です。
水制は様々なコンクリートブロックが使われるのですが、
多いのは消波ブロック(テトラポッド)です。
一方、川に段差があると、段差の下流側の河床が削れてしまいます。
それを防止するのが床止めです。
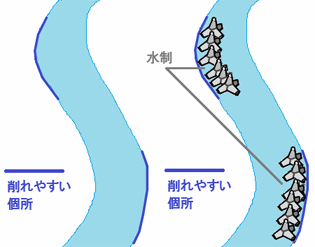
河川の曲線区間は円の外側に水圧かかります。
そうなると、その部分は削られてしまうため、
消波ブロックを集中的に置きます。
そうすると、消波ブロックにより水圧が緩和され、
護岸等の保護に繋がります。
なお、地震などで転倒、倒壊したり、
人が水制に乗った際、滑り落ちて怪我などをする場合があるため、
周辺環境に応じて消波ブロックではなく、
別のブロックが使われることがあります。
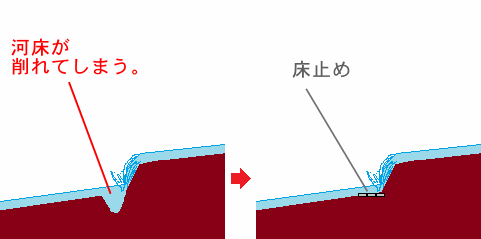
川に段差がある場合、
その落差で落ちた水の水圧が河床を削ってしまいます。
そうすると河床低下が起こってしまいます。
河床低下が起こると、
護岸や橋梁の橋脚が不安定になって倒壊する恐れが出ること、
水位が下がって取水が困難になることなど様々な問題が発生するため、
河床が削れる部分に床止めを敷きます。
床止めに使われるブロックは様々な種類があり、
単にジグソーパズルのように並べて敷くものから、
本格的に打設するものなどがあります。
4、天井川
天井川は上流から運ばれた土砂が堆積して、
周囲の高さより高くなった河川を言います。
基本、天井川は自然に生成されるのですが、
上記で紹介した砂防ダムを設けることにより、
天井川の生成を抑制することができます。
天井川が形成されやすい個所は上流に砂礫層が多い山岳地の麓でかつ、
山岳地からいきなり平地に切り替わってしまうような場所です。
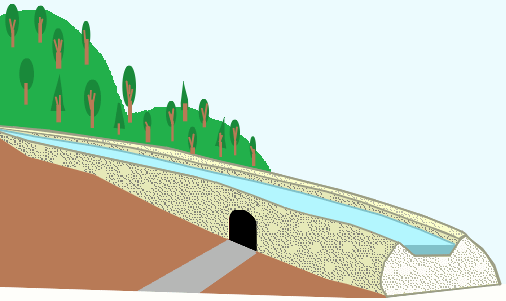
天井川は上流から運ばれる土砂が堆積して、
周囲より高い位置に流れるようになってしまった川を言います。
しかし、天井川は大きな堤防を造ったり、河川拡幅などをすることが困難な上、
天井川と交差する道路や鉄道はトンネルを掘削する必要が出てしまいます。
天井川は自然堤防を形成することが多いのですがその堤防の高さは低く、
氾濫すると多大な被害を受けてしまうため、
なるべく天井川が形成されないよう、
砂防ダムなどで抑制することが多いです。
または、神戸市内の湊川のように流路自体を変更して、
天井川区間を無くしている河川もあります。
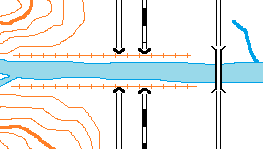
河川と道路、鉄道の交差は普通、橋梁になるのですが、
それがトンネルで交差している場合はほぼ天井川だと言えます。
天井川はずっと天井川な訳ではなく、
下流域になると、普通の高さの河川になります。
そのため、上流において道路等がトンネル交差になっている河川も、
下流は橋梁交差になっているところが多いです。
5、調整池・遊水池
5−1、調整池
調整池は河川の水量を調整して、
洪水や氾濫を防止する目的で設けられます。
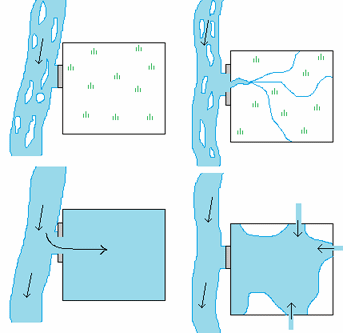
調整池は増水すると門を開いて調整池に水を引き込み、
一時的に貯水して、流量を減らすものと、
逆に増水すると門を閉じて、
雨水などの排水を増水した川に流さないようにするのもの、
流量などの状況により、両方の機能があるものとがあります。
基本的に河川改修が困難な河川で、
河川沿いにある程度の用地が確保される場所に設けられる場合が多いです。
また、コンクリート地盤が多いニュータウンなどは、
降雨時に雨水が一気に河川に流れてしまうため、
一定規模の開発地では必ず調整池を設けることとしています。
なお、調整池として使っていない時は、
テニスコート等として開放している場所もあります。
5−2、遊水池
遊水池は堤外地(後述)内の高水敷(後述)に設けられるもので、
普段はグラウンド、ゴルフ場、テニス場、サッカー場、軟式野球場、公園、
荒れ地、畑、湿地等になっているのですが、
河川が増水した場合、
これらの場所に水が貯まって滞留することで河川の増水を防ぎ、
堤防決壊や堤防越水による洪水被害を防ぐ機能があります。
遊水池は中下流域のある程度流量の多い河川では設けられることが多いです。
遊水池は日本各地にあるのですが、
有名かつ大規模なものは埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県に渡って存在している、
渡良瀬遊水池です。
渡良瀬遊水池は元々渡良瀬川の氾濫で
足尾銅山から流れる鉱毒が広まらないようにする目的で造られましたが、
現在は専ら洪水調整と自然環境保護目的になっています。
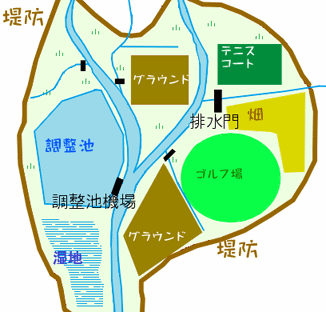
遊水池は堤外地内に設けられ、
通常はグラウンド等になっています。
また、遊水池内に調整池が設けられることもあります。
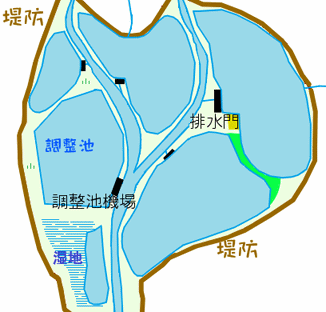
河川が増水すると、これらグラウンド等に水を引き込んで冠水させ、
一時的に水を滞留させます。
そのことで河川の増水を防ぎ、
堤防決壊や堤防越水による氾濫を防ぐことが出来ます。
6、堤防
堤防は河川の水が増水したとき、
周囲の住宅や農地に水が流れ込んで氾濫することを防止する目的で
河川に沿って設けられる構造物です。
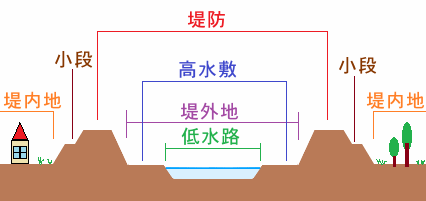
堤防は基本、堤外地の外側に設けられます。
(紛らわしいのですが、堤外地は両岸の堤防の間(内側部分)を言います。)
通常は堤外地内には高水敷と低水路があり、
普段は高水敷より低い低水路に水が流れています。
しかし、水が増水すると高水敷にまで水が冠水します。
高水敷と周囲の住宅地や農地の高さはさほど変わらない場合が多く、
高水敷が冠水してしまうと、住宅地や農地まで水が冠水してしまいます。
そうすると、住宅破壊や農作物が駄目になるなど、多大な被害を受けるため、
堤外地と堤内地の境目に堤防が設けられます。
高水敷は狭い所、広いところ色々あり、
流域面積が大きい川は低水路から堤防までかなり離れている場合があります。
基本、高水敷内は荒れ地や農地、グラウンド等になっているのですが、
都市形成2で挙げた一部集落や、
河川改修で高水敷拡幅する前からあった集落が、
堤外地内に住宅を形成している場合があります。
ただ、現在は堤外地に恒久的な住宅を建設することは法律上出来ないため、
こういった堤外地内の集落は移転等でだんだん減っています。
〜〜〜〜〜
なお、高水敷ではゴミの不法投棄や残土などの産業廃棄物投棄、
浮浪者の住み着き、
飼育に必要な免許や許可、登録を得ていない動物の飼育施設設置など、
様々な問題がある場所があります。
(私は高水敷内で放し飼いされている野犬数十匹に襲われそうになりました。)
基本、ちゃんと整備が行き届いていない高水敷内には
無闇に立ち入らない方が良いと言えます。
7、輪中
輪中とは堤防で囲まれた地域のことを言います。
河川が網の目のように張り巡らされている場所でかつ、
土地の高さが河川と同程度もしくはそれ以下の場所に造られます。
輪中で有名な場所は濃尾平野ですが、
河川改修や埋め立てなどで、従来の輪中は減りつつあります。
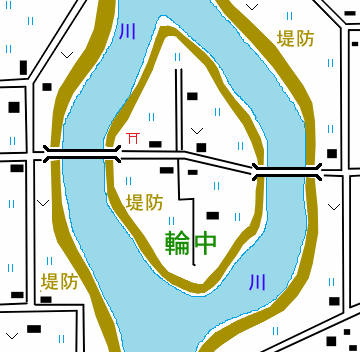
輪中は周囲が河川で囲まれた地域に見られます。
土地の高さが河川と同程度、またはそれ以下のため、
河川が増水した場合は水害に遭ってしまいます。
そのため、堤防で周囲をくるんで水害から守っています。
堤防は輪中の周囲を巡らしていますが、
基本的に河川の流れによる水圧を受けやすい上流側の堤防を高くし、
下流側の堤防は低めにしています。
輪中内は耕作地及び、集落があるのが特徴で、
それらがない場合は輪中と言わず、
単なる中洲になります。
川柳五七の地図のページ8へ戻る
川柳五七の地図のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|