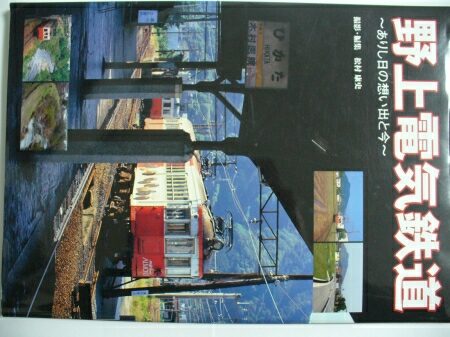 |
| 書名・野上電気鉄道〜ありし日の想い出と今〜 出版社・タクシー日本新聞社(注・在庫確認要) 著者・松村康史 定価・3150円(税込み) 頁・94ページ |
| 東の銚子電気鉄道、西の野上電気鉄道と、 超ローカル民鉄電化路線の代表中の代表2社のうち、 平成6年、惜しくも廃止となってしまった、 野上電気鉄道の写真集です。 実は私、この路線にすごく乗りたかったのですが、 結局乗れませんでした。 「あと10年廃止が延びていたら・・・。」と後悔のしっぱなしです。 現役当時の野上電気鉄道を扱った本がないかなと、 大型書店で探していたところ、この本を発見しました。 値段は少し高かったのですが、躊躇せず購入しました。 サビだらけの電車、傾いた木製架線柱、ヨロヨロの線路、 タイムスリップしたような木造駅舎・・・。 この写真集は現役当時の野上電気鉄道の魅力を余すことなく 写真に収めています。 一昔前の鉄道路線の雰囲気が味わえる、 いい写真集だと思います。 それだからこそ、後半の廃線跡の写真は胸を痛くします。 「ああ、今も現役で残っていたら・・・。」と感じずにはいられません。 この本は3分の2がカラーで、残りが白黒になっています。 カラー部分が写真集、 白黒部分が車両紹介や、現状紹介になっています。 |
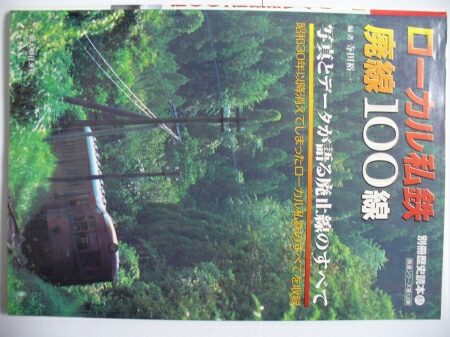 |
| 書名・ローカル私鉄廃線100線 出版社・新人物往来社(注・在庫確認要) 著者・寺田祐一 定価・2400円+税 頁・157ページ |
| 高度経済成長期以降、モータリゼーションで消えてしまった 鉄道路線100線の写真とデータを載せている本です。 この頃に廃線された路線は結構魅力的な路線が多く、 この本を見ると、興味深い路線が沢山出てくると思います。 写真だけでなく、現役当時の沿革や経営状況、路線図、 在籍車両などを詳しく載せているので、 廃線路線の現役時代を調べたい方にお勧めの本です。 本は前半部がカラーと白黒が交互になっていて、 後半部は白黒のみになっています。 なお、前半部に廃線が比較的新しい路線、 後半部に廃線が比較的古い路線を載せています。 これは、廃線の古い路線は白黒写真しかないからだと思います。 この本は大手出版社から出ている本ではないので、 誤記、脱字、ページの差し違えのミスが目立ちます。 そこのところは了承しておいた方が良いです。 また、元々別冊本の更にそのシリーズの本なので、 絶版になっている可能性があります。 書店で見当たらない場合は、出版社にお問い合わせください。 |
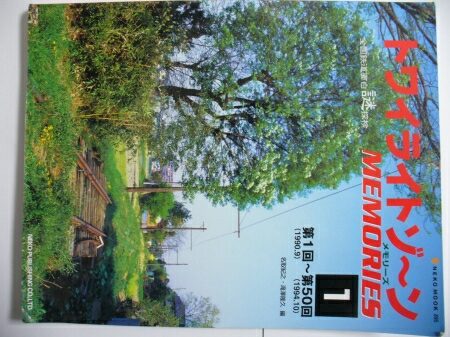 |
| 書名・トワイライトゾ〜ンMEMORIES(1)(注・要取り寄せ) 出版社・ネコ・パブリッシング 著者・名取紀之/滝澤隆久 定価・2800円(税込み) 頁・354ページ |
| 「トワイライトゾ〜ン」は、 ネコ・パブリッシングで発売している鉄道雑誌、 「レイル・マガジン」の1コーナーです。 このコーナーは、鉄道趣味で光の当たらない部分 (廃路線、貨物支線、貨物車両、廃車体、変わった鉄道) にスポットに当てた、異色のコーナーです。 「レイル・マガジン」であまりに人気コーナーとなったので、 特別編集と、特別コーナーを付した総集編、 「トワイライトゾ〜ン・マニュアル」を1年に1回出していたのですが、 「トワイライトゾ〜ン・マニュアル」は 10巻以上になってしまったこと、 初期の巻が絶版になってしまったこと、 更なるまとめた本が欲しいと言うファンの要望に応えて、 この本が発売されました。 とりあえず「トワイライトゾ〜ン・メモリーズ」の1巻として、 1990年9月から1994年10月までの、 4年分の同コーナーをまとめています。 もう普通の鉄道に食あたり気味になった鉄道ファン向けで、 更なる鉄分補給が必要になった人なら楽しめる本です。 もちろん、弊サイト作者も食あたり気味だったので、 この本が出たとき、「ヤッホー!!」と感激し、即購入しました。 残念ながら全部白黒ですが(本コーナーも白黒でしたが)、 載せている情報量は沢山あり、何度読んでも飽きない内容です。 本が分厚くて大版なので、 寝ながら読むことが出来ないのが欠点です。 なお、表紙の写真は弊サイトでも特集している、 「西武安比奈線」です。 |
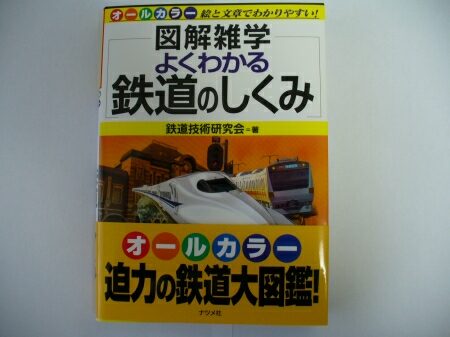 |
| 書名・図解雑学/よくわかる鉄道のしくみ 出版社・ナツメ社 著者・鉄道技術研究会 定価・1500円+税 頁・223ページ |
| 鉄道工学・鉄道技術の分野で、初心者鉄道ファン、 女性鉄道ファン向けの易しい本です。 下の「鉄道車両を知りつくす」より説明を簡潔にしているので、 こっちの方が初心者入門書だと言えます。 また、オールカラーで図や写真も多いので分かりやすいです。 ただ、この本は簡単にしすぎて問題もあり、 解説イラストの間違い、定義の間違い、 用語の使い間違いが結構ありますので、 あらかじめご承知ください。 (初心者鉄道ファンにはあまり支障はないと思いますが・・・。) あと、この本は「図解雑学/電車のしくみ」に似ているので、 誤購入にお気をつけ下さい。 間違えて買うと初心者鉄道ファンは頭が痛くなります。 |
 |
| 書名・鉄道車両を知りつくす 出版社・学研 著者・川辺謙一 定価・1900円+税 頁・145ページ |
| この分野の本では一番広く浅く扱っているのがこの本です。 特に、この本は蒸気機関車と気動車の仕組みも扱っているので、 鉄道入門者でなくても、買っておきたい本です。 ただ、下に「入門者必読!!」とか書いてあり、 鉄道ファンの入門者は「読まなくちゃ!!」 とか思ってしまうかもしれませんが、 はっきり言って入門者はまだ読まないほうが良いと思います。 入門者にとっては少し内容が難しいです。 入門者は先ず、鉄道車両に乗ったり、写真を撮ったりして、 鉄道に慣れ親しむのが先決です。 慣れるうちに「電車ってどうして動くのだろう」 とか疑問が出てくると思います。 その時初めてこの本を読む価値があるのです。 本は緑とオレンジの2色刷りが基本で、 図も多いので、かなり分かりやすい内容となっています。 ただ、各項目が基本的なことしか書いていないので、 熟練した鉄道ファンには物足りないかもしれません。 |
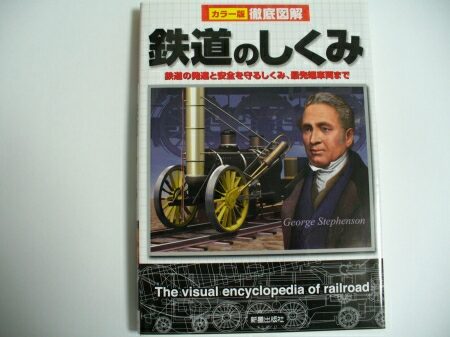 |
| 書名・鉄道のしくみ 出版社・新星出版社 著者・宮田道一/他 定価・1400円+税 頁・223ページ |
| 上の本から更に一歩踏み出したのがこの本です。 全ページカラーで、図や写真も積極的に載せているので、 かなり見やすく、分かりやすいです。 上の本は車両中心に扱っていますが、 この本はダイヤや保安装置、 鉄道施設についても詳しく取り扱っています。 一般的鉄道ファン向けで、 まあ、普通の鉄道ファンならこの本程度の知識があれば、 十分対応できます。(弊サイトはこの本のレベルで作っています。) ただ、電車の車両自体の扱いが小さいので、 電車についてもっと深く知りたい方は、 次に紹介する本も一緒に購入すると良いかと思います。 |
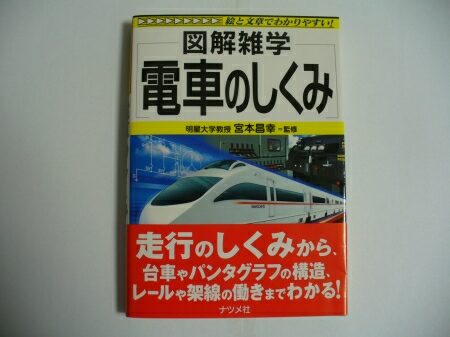 |
| 書名・図解雑学/電車のしくみ 出版社・ナツメ社 著者・宮本昌幸 定価・1350円+税 頁・223ページ |
| 鉄道工学・鉄道技術の分野で、 鉄道ファン向けに作った最初の本です。 この本が出たとき、私は「こういう本が欲しかった!!」と、 感激しました。 そう思ったのは弊サイト作者だけではないと思います。 ですので、上下の本が続けざまに発売されたのだと思います。 ただ、この本の取り扱っているのは「電車」だけで、 蒸気機関車や気動車、新交通システムなどは載っていません。 (新交通システムはコラムで載せています。) しかし、電車の構造、走るしくみ、レール、架線のことを、 図を用いてここまで簡潔に分かりやすく説明した本は 今までなかったので、宮本昌幸氏がこの本を作ったのは、 我々鉄道ファンの知識を更に飛躍させることになりました。 また、鉄道技術・工学の苦手な鉄道ファンでも、 難しい鉄道技術を知ることが出来るようになったと言う面でも、 画期的な本だと思います。 ある程度の鉄道ファンなら絶対必携すべき本だと思います。 本自体は黒と青の2色刷りで、1ページは文章、もう1ページは図 と言う構成になっています。 ですので、さほど読むのに時間はかからないと思います。 |
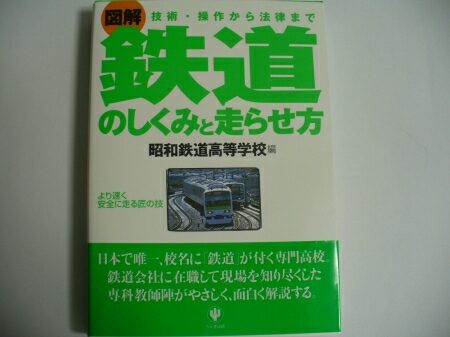 |
| 書名・図解/鉄道のしくみと走らせ方 出版社・かんき出版 著者・昭和鉄道高等学校/所澤秀樹編集 定価・2200円+税 頁・334ページ |
| 私の鉄道ファン仲間が行った高校、 昭和鉄道高等学校の講師の先生方が編集した本です。 今のところ、 この分野のファン向け本では一番内容が充実しています。 内容は、上の「図解雑学/電車のしくみ」に肉付けした感じで、 上の本を読んでもっと知りたくなった人が読むのに最適な本です。 本は「図解雑学/電車のしくみ」を意識したのか、 黒と青の2色刷りでだいたい3分の2が文章、 あと、3分の1が図などになっています。 分量が多いので、 読み終わるのに結構時間がかかると思いますが、 ある程度の鉄道ファンなら苦もなく読めると思います。 |