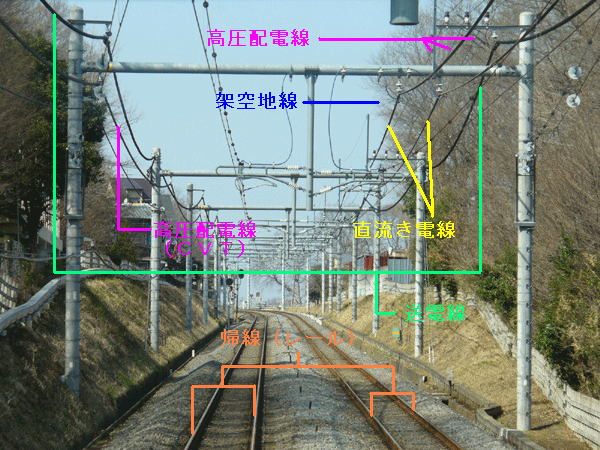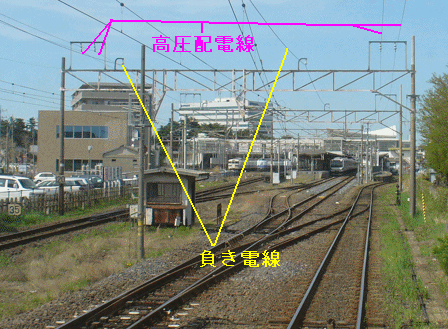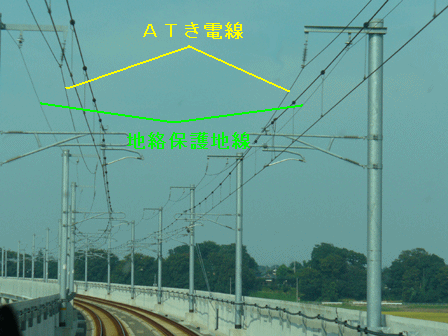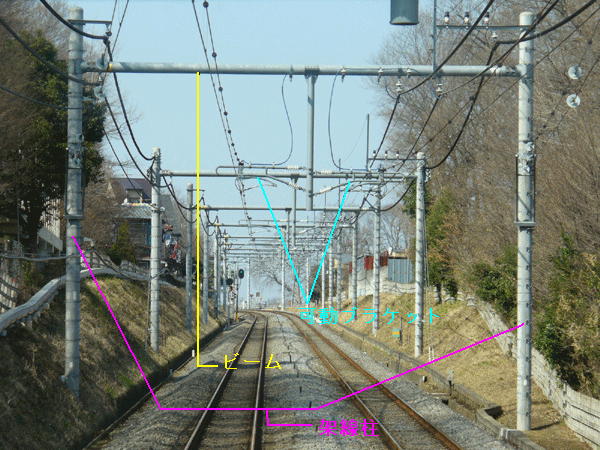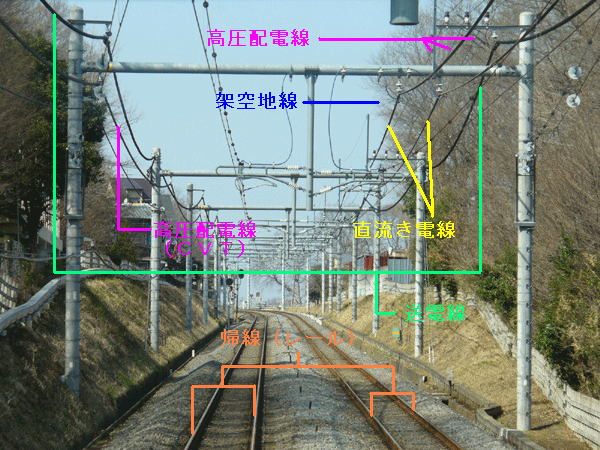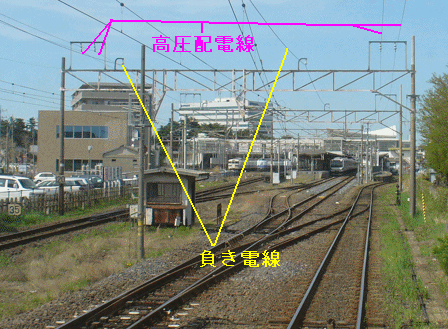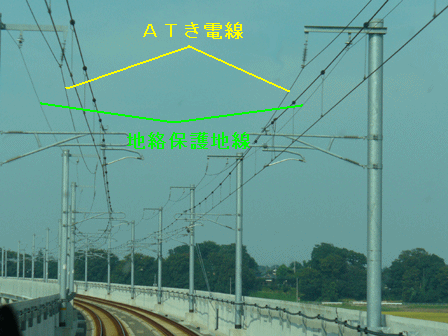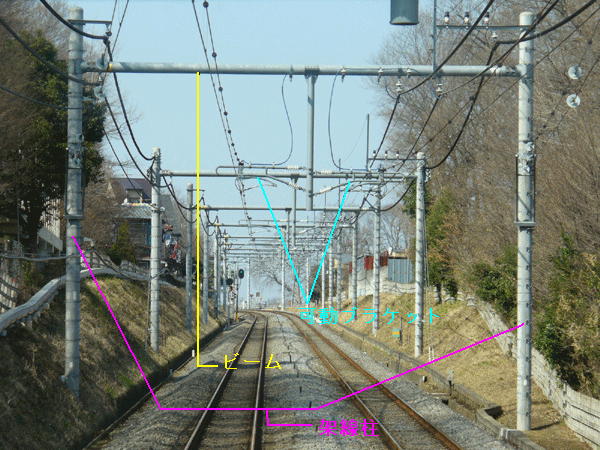鉄道架線案内2
次に各電化種類の装柱例を挙げてみます。
〜装柱架線名称〜
1、直流電化方式
直流電化方式は昔からの電化方式で、新幹線や北海道、九州、東北、北陸のJR線等、
新交通システムの一部などを除くと、殆どが直流電化方式です。
長所は電車の製造コストが安くなるので、電車の大量生産が出来ます。
なので、本数の多い大都市部にむいている方式です。
欠点は、高圧の電気を流せないことで、
変電所を多く設けなければならないと言うことが挙げられます。
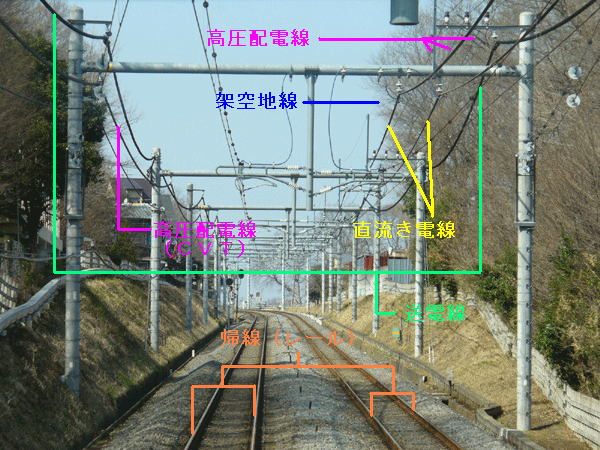
(写真・西武池袋線)
なんだかごちゃごちゃしていますが、上から見てみます。
A,架空地線(グランドワイヤ)
落雷から高圧線などの電線を守るためにある線です。
ただ、架空地線はお守りくらいの効果で、
架空地線に実際雷が落ちる確率は低いとされています。
そのため、架空地線の採用は各社、各路線まちまちです。
関東の大手民鉄では比較的西武鉄道が早く導入し、
続いて東武鉄道が全線で導入しています。
最近は京王電鉄と京成電鉄が新設工事をやっています。
一部では架空地線を光ファイバ兼用にしているところもあります。
B,高圧配電線
駅などの照明やエレベータ、エスカレータなどで使う電気や、
信号や踏み切りなどで使う電気が流れています。
比較的電化の古い路線に採用が多く、
最近の非電化を電化にした方式では、
電力会社の配電線から直接電気を供給しているので、ないところもあります。
また、インテグレート架線は、高圧配電線を地中埋め込みにしたり、
線路脇のパイプでまとめるところもあります。
電圧は6600Vが一般的で、
単相交流2線方式と三相交流3線方式があります。
大手民鉄は三相交流3線2回線が多く、
1回線が落雷などでダメになっても、
もう1回線でカバー出来るようにしています。
また、1回線を架空配電線式(3本の電線が独立している線)に、
1回線をCVTケーブル(3本の電線をまとめてねじった線)にする方式が多いです。
これは、両方の特性を生かしたためだと言えます。
この方式は東武、西武、京王、東急で採用されています。
小田急は2回線化が早かったので、2回線とも架空配電線式、
京急は2回線ともCVTケーブルになっています。
なお、相鉄と京成(一部を除く)はまだ2回線化されていません。
なお、架空配電線式高圧線の支持は懸垂碍子が多いのですが、
写真の西武のように、
東京電力タイプのクランプ碍子(雷で断線しにくい碍子)を使うこともあり、
東武や小田急の一部で使われています。
C,送電線
変電所の近くに電力会社の送電線がない場合に、
近隣変電所から社内送電線をひく場合があります。
最近は地中化されて、都市部では見られなくなりつつあります。
写真はCVTケーブル2回線ですが、
架空送電線式もあり、1回線のところもあります。
D,直流き電線(フィーダ)
1500Vの直流電気が流れていますが、
ローカル線や地下鉄などは、750Vや600Vの所があります。
直流電化の場合、トロリー線に流した電気だけでは足りないことが多いので、
(無理矢理やるとトロリー線が太くなり、電線の揺れが大きくなる)
大抵、トロリー線に併設されてこの線があり、
一定間隔で直流き電線からトロリー線に電気を供給しています(き電分岐線)。
最近のインテグレート架線は、
直流き電線と吊架線を一体化したものになっています。
直流き電線は大抵、複線が2本以上、単線が1本以上になっています。
E,帰線(レール)
電車で使用した電気を変電所に戻す電気(マイナス電気)を流す線を帰線と言います。
直流電化の場合、レールがその役目をします。
レールに電気が流れていると「感電する!!」
とかお思いになる方もいらっしゃるかと思いますが、
き電線やトロリー線などのプラス電気に触れなければ大丈夫です。
しかし、第三軌条式はプラス電気(第三軌条)とマイナス電気(レール)が近いので、
両方触れて感電する恐れがあります。
そのため、電圧が高く出来ない欠点があります。
新交通システムやモノレールなどレールがコンクリートのものは、
帰線に出来ないので、
別に負き電線を設ける必要があります。
2、BT交流電化方式
交流電化方式は、AT方式とBT方式があります。
交流電化の古い線はBT方式で電化されています。
東海道新幹線も開業当初はBT方式でした(今はAT方式)。
BTとはブースタートランスの略で、
レールに流したマイナス電気を吸い上げる変圧器のことを言います。
設備は簡単で、トロリー線で超高圧き電線も兼ねるので、変電所の数も減らせます。
しかし、約4KMごとにあるBTのところにはセクションが必要で、
その区間は惰性運転しなければならない欠点があります。
あと、これはAT方式と共通欠点として、
電車に変圧器と整流器(コンバータ)を搭載しなければならないので、
車両製造費が高くなります。
(交流モーターを使うVVVFインバータ制御も、
単相交流を変圧器で電圧を落として、整流器で直流化し、
それでVVVFインバータ制御で三相交流にするというややこしい状態になっています。)
なお、交流電化は在来線が20KV、新幹線が25KVの2種類の電圧があるだけでなく、
富士川を境に東は50ヘルツ、西は60ヘルツと2種類の周波数があります。
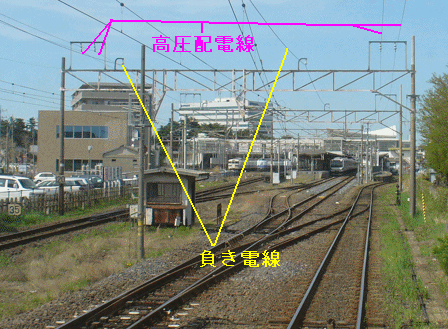
(写真・JR常磐線)
BT交流電化方式の特徴として、
負き電線があることです。
普通マイナスの電気はレールに流すのですが、
それだけだと通信誘導障害が起きてしまいます。
通信誘導障害を減らすには、プラスの電気、
つまりトロリー線にマイナス電気を近づける必要があります。
そのマイナスの電気を流す電線を負き電線(ネガティブフィーダ)と言います。
電車からのマイナスの電気は一旦レールに流されますが、
BTで吸い上げられ、負き電線に流れます。
3、AT交流電化方式
BT電化方式は約4KMごとにセクションが必要なだけでなく、
直流電化より少ないとは言え、ある程度の変電所が必要です。
その欠点を解消したのがAT交流電化方式です。
ATとはオートトランスの略です。
ATはコイルが一つでATき電線とトロリー線を結んでいます。
そのコイルの中間点にレールからの帰線を接続する形になっています。
ATき電線とトロリー線は電気の流れる方向が逆になっているので、
通信誘導障害は起きません。
ATは約10KMごとに設置され、ATのところにセクションは必要ありません。
ただ、変電所間のセクションは必要(位相差が出るため)なので、
全くセクションがなくなるわけではありません。
ATの存在で2倍の電圧が使用でき、
ATの間隔も長いので、変電所の間隔を広げることが出来ます。
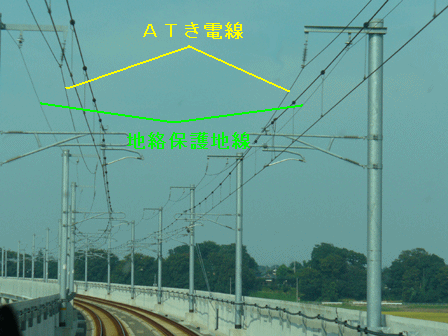
(写真・つくばエクスプレス線)
A,ATき電線
トロリー線と逆方向の電気が流れている線。
超高圧線なので、支持する懸垂碍子の数が多いという特徴があります。
B,地絡保護地線
予期せぬ事故により、
ATき電線やトロリー線の電気が大地上に流れてしまう事故を防ぐ線です。
AT交流電化方式は超高圧の電気なので、
電気が地上に流れてしまうと大地上にいる人や家畜が感電してしまいます。
それを防ぐために設けられています。
つくばエクスプレス線の例だと分かりにくいのですが、
地絡保護地線は、
ATき電線の碍子やトロリー線を吊る碍子、可動ブラケットに接続されています。
〜装柱例〜
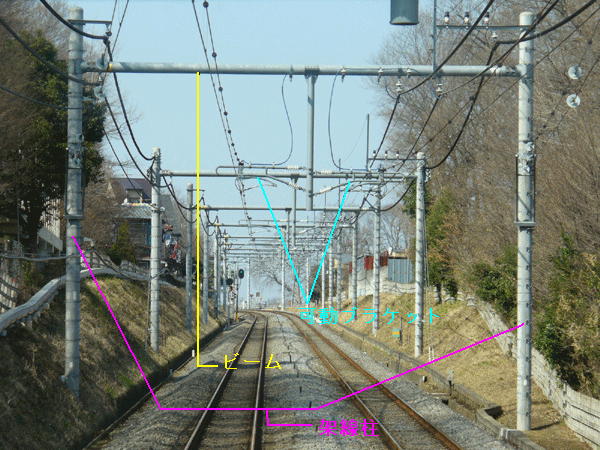
西武池袋線のこの地点の場合、
両側の架線柱はビームで結ばれています。
ビームは架線柱の安定化を図るだけでなく、
吊架線を吊る碍子や可動ブラケット(可動ビーム)を吊り下げることが出来ます。
ビームはV型、かご型、H鋼型などがありますが、
最近は写真のように管型が多くなっています。
可動ブラケットは、通常枕木方向を向いていますが、
180度回転することができます。
そのため、架線の張替えが楽にできます。
また、温度変化による架線の張力調整も出来る利点もあります。
〜テンションバランサー〜
テンションバランサーとは、
気温の変化などで伸び縮みする架線(吊架線・トロリー線)の張力を一定にする装置のことです。
テンションバランサーは2種類あります。
1、滑車式
滑車から錘を下げて、その錘で架線の張力を一定にさせる方式です。

2、ばね式
ばねの力で架線の張力を一定にさせる方式です。
滑車式のように錘の調整が不要で、
コストも安いので、今はこちらが主流になっています。

鉄道話題・一覧表へ戻る
川柳五七の新電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|