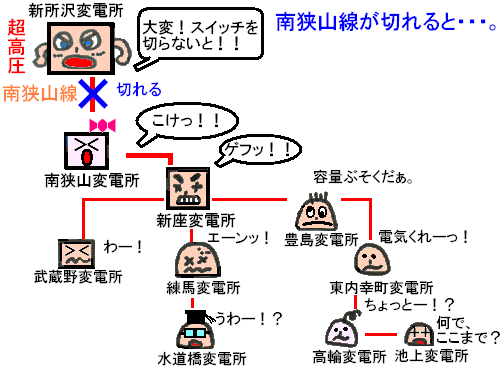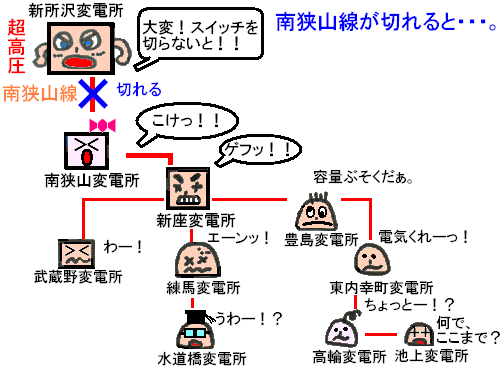|

南川越変電所と南狭山変電所5

大部分の変圧器は騒音防止の塀に囲まれていて見ることが出来ません。

水野線の各線の先には脇田線と日高線が接続されています。

上の回線の脇田線は新座線の鉄塔の下に入ります。
日高線は先ほど書きましたように、
南狭山線の鉄塔から来ています。

脇田線と新座線の合流部分です。
ここから新座線は狭山線と脇田線を併架します。

随分前に流行っただんご三兄弟ならぬ、
送電線三兄弟です。
一番上の4導体2回線の新座線は新座変電所に繋がっています。
真ん中の単導体2回線の狭山線は先の南川越変電所から来ています。
一番下の脇田線は川越線と合流します。
コラム・南狭山線が切れたとき・・・。
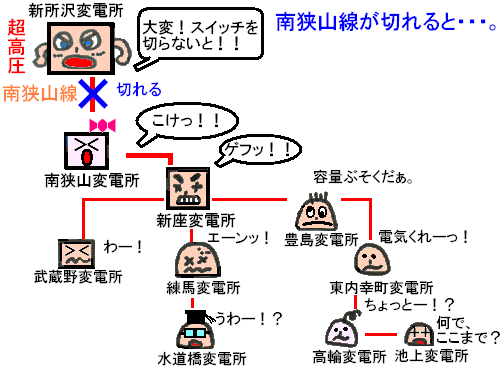
もうかなり前になるのですが、
平成11年に南狭山線に自衛隊機が衝突し、
埼玉県のみならず、東京23区の大部分で停電が起こったのですが、
「何で埼玉県の1送電線路が切れると東京の都心部が停電するのか」
不思議に思われた方もいらっしゃるかと思います。
送電線にあまり興味のない方は「電気は東京湾の火力発電所から都心を通り、
埼玉などの関東北部に向かっている」と思っているようですが、実際は逆です。
何でこのような不思議なことになっているのかと言うと、
かつての発電の主体は水力発電所だったことが起因しています。
元々超高圧変電所の新所沢変電所(埼玉県鶴ヶ島)は、
容量が限界に達していた中東京変電所(埼玉県日高)を増強する形で造られました。
中東京変電所は中東京幹線や奥秩父線など、
信濃川や安曇の水力発電所から来た送電線を引き込んでいます。
しかし、時代は流れ、発電の主体が火力発電所になると、
発電の場所は北の山々から東京湾沿岸などになりました。
とは言え、従来の送電線路網大幅に変更すると、
新規送電線路のための土地買収、建設に莫大な費用がかかってしまいます。
そこでとった措置は、従来の送電線路を改良して使うことでした。
極力中東京変電所から都心部に向かっていた送電線路を変更せずに
新所沢変電所に振り分けました。
そこで問題になるのは火力発電所から新所沢変電所に来る線なのですが、
これは、東京湾の各火力発電所からJパワーの西東京変電所(東京都町田)と、
新多摩変電所(東京都八王子)を経由し、
新所沢変電所に電気を送っています。
つまり、火力発電所からの電気は首都圏を半周してから都心部に向かうと言う、
大迂回を行なっているのです。
更に現在は原子力発電所が加わっているのですが、
原子力発電所の発電量は大きく、
従来の送電線路の改良だけで
柏崎刈羽原子力発電所から新所沢変電所に電気を送ることは出来ません。
そのため、西群馬幹線など100万V設計の送電線で、
柏崎刈羽から一気に新富士変電所(静岡県小山)に送られ、
新秦野変電所、新多摩変電所を経由し、
新所沢変電所に向かうと言うコースを通っています。
新潟の柏崎刈羽原子力発電所の電気が東京都心部に来るのに、
何と静岡県を通っているのです。
そう考えると、新所沢変電所は超重要な変電所だと分かります。
送電ファンがなんで埼玉の片田舎にある新所沢変電所に興味を持つのかと言うと、
この変電所がトラブルると東京都心部の機能が麻痺してしまうほど重要な変電所だからです。
特に、新所沢変電所から出ている南狭山線は、
東京都心部に間接的に関与する路線なので、
この線にトラブルが起こると、
東京都大田区の池上変電所までの区間がダメージを受けてしまいます。
そして、一次変電所がコケるとそこから繋がっている配電用変電所もコケ、
被害が広範囲に及んでしまうのです。
南狭山線は新所沢変電所から出ているので、
新所沢変電所が安全装置を働かせてスイッチを切ってしまうと、
南狭山変電所の機能が停止してしまいます。
そして、そこから新座線で繋がっている新座変電所も機能停止します。
そして、豊島変電所(以下、地中変電所)、東内幸町変電所、高輪変電所、
とドミノ倒し的に停止してしまい、最終的には池上変電所まで機能停止するのです。
もちろん、各一次変電所は別の系統からの送電線も引き込んでいるのですが、
超高圧変電所がスイッチを切ってしまうと、
それ以下の一次変電所、
配電用変電所も安全のためスイッチが一時的に切れてしまいます。
「たかが1路線が切れただけで・・・。」と、当時各マスコミは東京電力を叩いていましたが、
新所沢変電所や南狭山線は歴史上苦肉の策で出来た路線なので、
仕方ない面もあるのです。
川柳五七の電線のページ3Wへ戻る
川柳五七の電線のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|