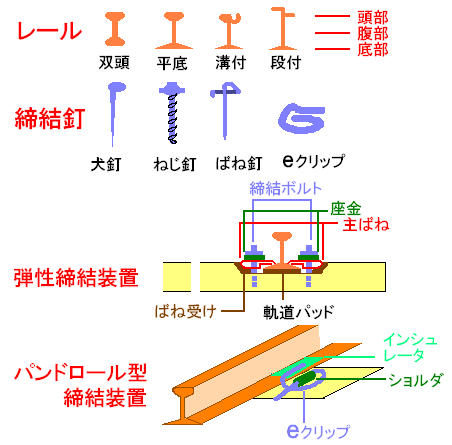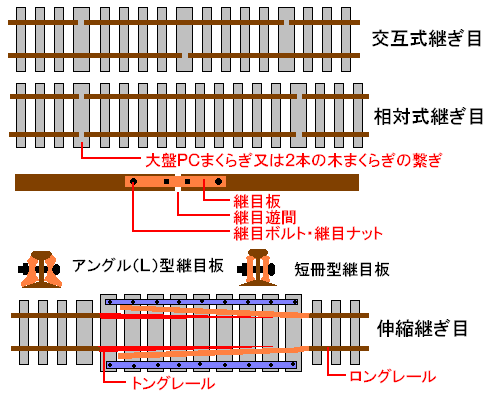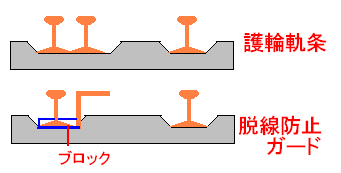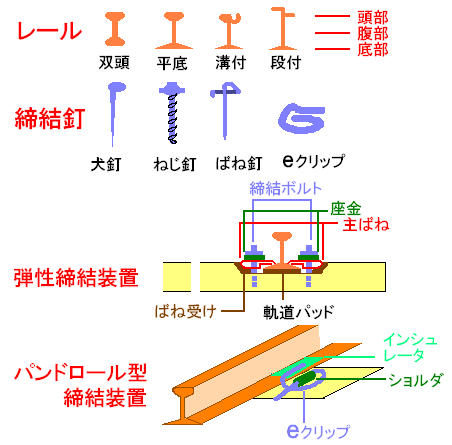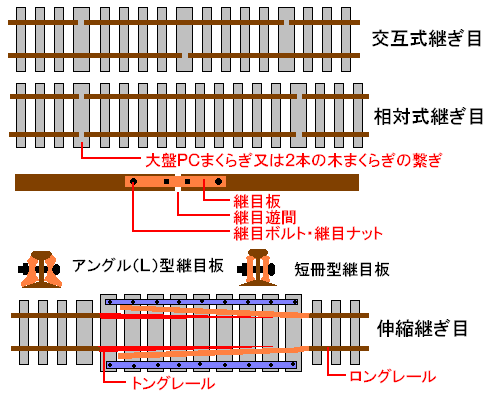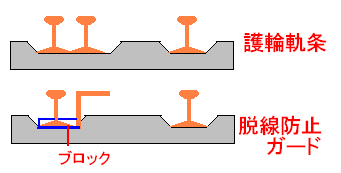電車の線路施設って何!?その1
一般的には「線路=軌道」と認識していると思いますが、
専門的な定義では、
「線路=レール、まくらぎ、道床、路盤、側溝、犬走、盛土、切取等、
列車が走る施設全体」を指しています。
そのうち、レール、まくらぎ、道床で構成される構造物を軌道と言います。
鉄道は必ずしも軌道のレールが鉄製ではなく、
新交通システムや日本跨座式モノレール、
リニアモーターカーなど軌道がコンクリートのものや、
トロリーバスなど軌道がないものもあります。
これらすべて説明すると説明が長くなってしまうので、
ここでは鉄道の原点である普通鉄道の線路について述べたいと思います。
1、レールとまくらぎ
軌道と言えば真っ先に思いつくのがレールとまくらぎです。
レールは日本語として言うには「レール」で間違いないのですが、
英語読みに拘る場合は「レイル」と言っています。
鉄道雑誌でも「Rail Magazine」だけは何故か「レイル」と言う表記に拘っています。
レールは鉄に炭素を混ぜた普通鋼が使われ、
レールの単位は1メートルあたりの重さで決められています。
レールは30キログラムから60キログラムまで使われていて、
大量かつ高速輸送を行なう場合は、重いレールを使います。
改良型のレールはNとかTとかの記号が付いています。
NはNEWの頭文字で、通常のレールより高くなっています。
一方、Tは東海道新幹線の頭文字で、頭部の形状を丈夫にしたものです。
レールの長さは20メートルから50メートルの長尺レールを基本とし、
それ以上の長さにする場合は、長尺レールを溶接して長くします。
この長くしたレールをロングレールと言います。
ロングレールは継目が減り、乗り心地の向上が出来るのですが、
寒暖による膨張伸縮が大きく、
急カーブや木まくらぎの区間で採用するとまくらぎや締結装置が破損するため、
ロングレールには出来ません。
なお、中途半端な長さにもレールが敷設出来るよう、
5メートル程度の短尺レールもあります。
一方、まくらぎはレールの下に敷くもので、
レールとの接続は締結釘または締結装置と言う器具を使います。
まくらぎは漢字で書くと「枕木」なのですが、
「枕」と言う字が常用漢字外漢字なのと、
現在はPCまくらぎや合成まくらぎなど木を使わないまくらぎが多いので、
平仮名またはカタカナで表記することが多くなっています。
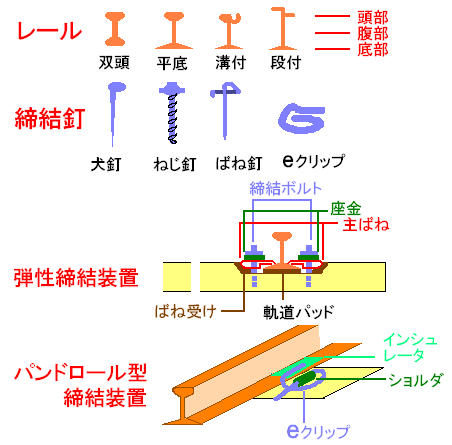
レールは形状によって色々種類があります。
日本の鉄道の黎明期は双頭レールが主に使われました。
双頭レールは上下面とも頭面に出来るので、
片面が磨り減って磨耗しても、
ひっくりかえして使うことが出来ると言う利点があります。
しかし、高速運転では安定感に不安があるため、
現在は平底レールが使われています。
溝付レールや段付レールは路面電車で採用されたレールです。
かつての路面電車は未舗装道路の路面区間も多く、
レールが泥や石などで埋まってしまい、
走行時に砂埃が舞うだけでなく、脱線の危険性が増すため、
車輪のフランジに泥や石が当たらないよう、
これらのレールが採用されました。
現在はほぼ舗装道路になったため、
新規に採用する例はあまりなく、日本では既に製造中止になっています。
レールとまくらぎを接続する締結釘はかつては犬釘が使われていました。
犬釘は釘の頭をレールの底部上面に当たるように向けて、
ハンマーでまくらぎに打ち込んで固定させるものです。
現在でも木まくらぎが残っている区間で散見されますが、
犬釘は列車の振動でだんだん抜けてしまうので、
定期的に打ち込んだり、まくらぎごと交換する必要があります。
ねじ釘は下部に螺旋状の溝を付け、ねじ状にしたもので、
犬釘より抜けにくい特性があります。
ばね釘はレールの振動を若干吸収出来ます。
PCまくらぎが主体の現在は弾性締結装置の採用が多いです。、
弾性締結装置はレールとまくらぎの間に
軌道パットと言うゴム製のクッションを挟み、
更に主ばねをレールの底部上面に当てて、
それを締結ボルトでまくらぎに接続する方法です。
レールの振動は主ばねと軌道パット両方で吸収されるため、
乗り心地が非常に良くなります。
また、最近はパンドロール型締結装置の採用も多くなりました。
パンドロール型締結装置はショルダにeクリップを専用器具で差し込んで、
その先端の平面をインシュレータを挟んでレールの底部上面に当てることにより、
レールを固定させています。
専用器具で簡単に取り付け出来る利点があり、
逆に専用器具でないと取り外しも出来ないので、
悪戯などで取り外される心配もありません。
また、eクリップはばねの働きがある他、
インシュレータはクッションの役割があるため、
乗り心地も安定しています。

まくらぎは元々は木のまくらぎが主体だったのですが、
現在はPCまくらぎ又は合成まくらぎが主体になっています。
PCまくらぎのPCは、プレストレストコンクリートの略で、
コンクリートの中に入れる鋼材の圧力でまくらぎ全体が圧縮され、
強度が保たれています。
PCまくらぎの製造方法はプレテンション方式とポストテンション方式があり、
前者はPCワイヤを引っ張って緊張力を加えた後、
コンクリートを流し込む方法で、
後者はPC鋼棒にコンクリートを流し込んで、
コンクリートが固まった後、PC鋼棒を引っ張って緊張力を与え、
更にPC鋼棒のボルトを締めてコンクリートを圧縮する方法です。
PCまくらぎは丈夫で長持ちするのですが、
規格品なのと、重たいので、
色々な長さのまくらぎが必要な分岐部や、
強度に限界のある橋梁区間では使えません。
そこで使うのが合成まくらぎです。
合成まくらぎは硬質発泡ウレタンとガラス繊維で作られたもので、
この素材は植木鉢やレンガなどにも使われています。
合成まくらぎの利点は、
切断が容易に出来るため、用途に合わせて長さを調整出来ること、
締結ボルトの孔を任意の場所に開けられること、
PCまくらぎより軽いので橋梁にも使用出来ることなどが挙げられます。
2、継目
レールの長さには限りがあるので、
レール同士を結ぶ所が必要になります。
そのレール同士を結んだところを一般大衆的に繋目(つなぎめ)と言うのですが、
工事上、難しい漢字は避けたいので、
専門的には継目(つぎめ)と言っています。
継目は必ず必要なもので、
ロングレールでもあまりに長くしすぎると工事の際に手間がかかること、
レールの端の膨張が大きくなりすぎてしまうこと、
線形や駅構内、勾配変動等軌道の区分が明確に分けられないこと、
レールに流す信号の切れ目が出来ないことなどから、
一定の距離で継目を設けています。
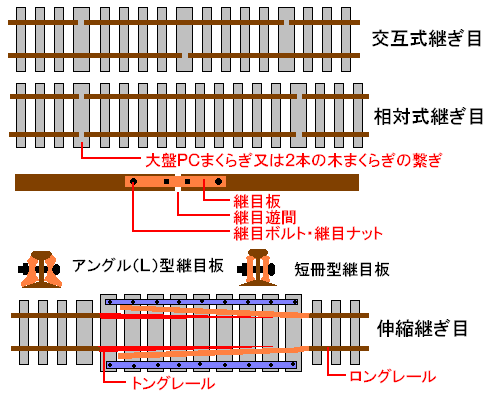
基本的にはレールは継目板で結びます。
継目は左右両側のレールで交互に継目を設ける交互式継ぎ目と、
同じ位置で継目を設ける相対式継ぎ目があります。
継目の部分は継目用のまくらぎが必要なのと、
騒音を発する部分を減らしたいので、
基本的には相対式継ぎ目が採用されます。
しかし、カーブの区間など、一方のレールに偏って負担がくるような区間の場合、
継目の位置を揃えてしまうと、継目部分の負担がそこに集中してしまうため、
場合によっては交互式継目を採用する場合があります。
レール同士は継目板という金具でボルト固定されています。
そのため、レールの端は最初からボルト孔が開けられています。
この孔はレール同士の隙間が出来るように計算して開けられています。
レール同士の隙間は継目遊間と言い、
レールが寒さで収縮、暑さで膨張しても
レール同士が接触して破損しないようにしています。
ただ、この継目遊間があの「ガタンゴトン」と言う騒音を発する元になっています。
また、継目板にはアングル型と短冊型があるのですが、
これは鉄道会社や路線によって採用が分かれています。
ロングレールの場合、膨張収縮が大きく、
継目板での継目では継目遊間が足りません。
そのため、伸縮継目という特殊な継目を使います。
この継目はロングレールの先に先細りになっているトングレールを設け、
徐々に次のロングレールに移行するようになっています。
そのため、膨張出来る長さに余裕を持たせることが出来ます。
また、この継目方式は斜めの継目と言うことになるので、
「ガタンゴトン」と言う騒音を発することが無いと言う利点もあります。
継目はこの他、
レールに流れている信号の電気を絶縁する目的の絶縁継目があり、
この継目は絶縁性のある樹脂でレールが結ばれています。
列車の車輪が絶縁継目を通った時だけ、
信号の電気が車輪を経由して双方のレールに流れるので、
その区間に列車が通っていると言う信号を送ることが出来ます。
ただ、絶縁継目は列車から変電所に戻る
帰線電流(鉄道架線の項で後述)も遮断してしまうため、
帰線電流だけ流れるよう、
インピーダンス(電気抵抗)ボンドと言う複雑な配線をする必要があります。
3、護輪軌条と脱線防止ガード
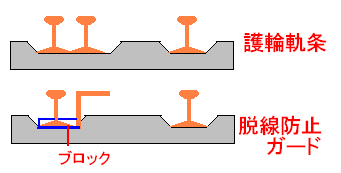
列車は急カーブを低速で走るとカーブの外側に乗り上がって脱線したり、
橋梁や高い盛土区間など、横風の影響で脱線したりする危険があります。
その脱線を防止(・・・と言うか被害を最小限に止める)するのが、
護輪軌条と脱線防止ガードです。
護輪軌条はレールで、
脱線防止ガードは本レールに取り付けるアングル材になっています。
最近は取り付けやすさやPCまくらぎが多くなった関係で後者の方が多く使われます。
急カーブでは乗り上がり脱線を防ぐためにカーブ内側の本レールの内側に、
橋梁や盛土は左右どちらの横風でも対応出来る様に
両側の本レールの内側に取り付けます。
ただ、カーブ内側に脱線する可能性のある急カーブは、
両側の本レールの内側に取り付けています。
何れも列車の車輪が脱線しそうになると、
車輪のフランジが護輪軌条や脱線防止ガードにひっかかり、
脱線を防止することが出来ます。
仮に脱線しても、車輪が本レールと護輪軌条・脱線防止ガードに入るため、
大きな脱線を防ぐことが出来ます。
兎角、事故があるとこれらを設置したかしなかったかが問題になるのですが、
実はカーブ区間のスピードオーバーによる車輪浮き上がりの脱線では全く無意味です。
(車輪が護輪軌条や脱線防止ガードさえも乗り越えてしまうため)
基本的にこれらは万が一のお守り程度のものなので、
脱線対策はスピードオーバーしないような
保安装置などの整備の方が重要になってきます。
電車の線路施設って何!?その2へ
鉄道・なぜなに教室トップへ
川柳五七の電車のページトップへ
たわたわのぺーじトップへ

|